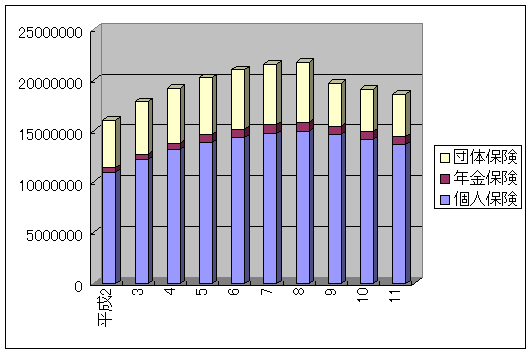
経営管理(MGM704)4クレジット
保険会社におけるコンプライアンスと今後の経営方針への提言
Rushmore University
Global Distance Learning DBA
大國 亨
このコースワークを提出するにあたって、ここに記述されている文章/アイデアは、引用の表記がない限り、私の作品であります。また、私がこのコースの研究を手がけるまでは、このコースワークは存在しなかったことを確認します。
金融商品販売法、消費者契約法も本年4月に施行され、金融機関においてもようやく役職員の間に理解が生まれてきた。また、金融行政もこれまでの護送船団方式と呼ばれた金融機関が横並びで事業を行っていればリスクを取らなくてすんだ事前認可体制から一変して、公表された検査マニュアルに基づく検査を受ける事後検査体制へと大きく変貌した。
金融庁の検査マニュアルにおいても、コンプライアンス態勢の確立が強く求められている。
コンプライアンス態勢とはどのようなものであるべきかを金融庁の検査マニュアルその他に基づいて確認する。
そして、保険会社を例にして、コンプライアンスに係る問題が実は、役職員の単なる個人的な資質の問題ではなく、現在の日本における保険会社の販売構造によって引き起こされている可能性が高いことを、統計資料を用いて検証する。
最終的に、どのようなコンプライアンス態勢が好ましいか、どのようにすればコンプライアンス環境を整えられるか、提案する。
保険会社におけるコンプライアンスの問題については現在私自身が業務上具体的に係っている関係もあり、一般に公開された資料、裁判等によって公開された事例を除いて、正確な数字、事例の具体的情報を明かすことができない。たとえ個別の事例を取上げたように思われる場合でも、特定の事例を前提とせず、一般的事例として取り扱っていることをお断りしておく。
目次
1.はじめに
2.生命保険の現状
2.1生命保険の加入状況
2.2生命保険会社の営業体制
2.2.1転換制度とは
2.2.2営業職員とは
2.2.3営業職員の成績評価制度
2.3成績第一主義の弊害
3.今後望まれる営業姿勢−コンプライアンス
3.1コンプライアンスとは何か
3.2ベスト・アドバイスとは
3.3なぜコンプライアンスは必要なのか
4.金融庁検査マニュアル
4.1コンプライアンスと取締の役割
4.2望ましいコンプライアンス態勢
4.2.1内部監査とは
4.2.2コンプライアンスを有効に機能させるための方策
5.生命保険会社への提言
6.結び
資料1三菱自動車リコール隠し事件
資料2雪印乳業集団食中毒事件
資料3大和銀行 大阪地裁判決
参考文献
1.はじめに
昨今の生命保険会社の相次ぐ破綻により、生命保険会社の経営には大変厳しい目がむけられている。その為、生命保険業界全体で保有する生命保険の件数、金額ともに減少する、生命保険会社にとっては逆風とも言える状況が続いている。また、義理・人情・プレゼントを中心とした販売手法は、厳しい批判にさらされている。
各種生命保険の加入率は91.8%にも達している成熟商品である。これに対して、営業職員だけでも30万人に達する人員を投入してローラー販売を行う手法を生命保険各社は採用している。
また、昨今の金融業政は、グローバライゼーションを前提として事前承認・調整型から事後検査型へと大きく変化した。そして、その一環として、生命保険各社にもコンプライアンス体制の確保が要求されることとなった。
本論文においては、人員を投入した販売方法が無理な販売に繋がっている可能性が高いこと、コンプライアンス重視を打ち出した金融行政のもとでは、従来のような営業方針を維持することは難しいこと、それだけでなく、信頼を失った生命保険業界の信頼を取り戻し、再び国民の福利厚生に役立つ生命保険業界を確立するためにも、従来型のローラー販売体制を維持し続けるわけには行かないことを論証する。
2.生命保険の現状
2.1生命保険の加入状況
我が国における生命保険の加入状況は下記のとおりである。ただし、表1の「生命保険に関する実態調査」は全数調査ではなく、平成12年に生命保険文化センターによって行われた6,500世帯を対象としたサンプル調査である。
表1 生命保険に関する実態調査
|
|
項目 |
全生保 |
民保 |
簡保 |
JA |
|||||
|
世帯員の生命保険加入状況 (個人年金を含む) |
世帯主 |
加入率 |
87.9% |
73.2 |
29.7 |
10.7 |
||||
|
加入件数 |
1.9件 |
1.6 |
1.4 |
1.4 |
||||||
|
*満期保険金等 |
709万円 |
679 |
349 |
367 |
||||||
|
普通死亡保険金 |
2,524万円 |
2,561 |
548 |
1,631 |
||||||
|
疾病入院給付金日額 |
9.8千円 |
8.5 |
6.5 |
7.3 |
||||||
|
妻 妻 |
加入率 |
76.6% |
55.5 |
33.7 |
8.8 |
|||||
|
加入件数 |
1.7件 |
1.3 |
1.4 |
1.2 |
||||||
|
*満期保険金等 |
448万円 |
422 |
294 |
276 |
||||||
|
普通死亡保険金 |
1,131万円 |
1,079 |
446 |
1,182 |
||||||
|
疾病入院給付金日額 |
7.6千円 |
6.5 |
5.4 |
5.9 |
||||||
|
子 |
加入率 |
58.1% |
31.5 |
30.6 |
3.9 |
|||||
|
世帯の生命保険加入状況 (個人年金を含む) |
加入率 |
91.8% |
79.0 |
52.0 |
15.7 |
|||||
|
加入件数 |
4.6件 |
3.1 |
2.7 |
2.4 |
||||||
|
*満期保険金等 |
1,234万円 |
1,017 |
553 |
590 |
||||||
|
不通死亡保険金 |
4,141万円 |
3,781 |
878 |
2,690 |
||||||
|
疾病入院給付金日額 |
20.4千円 |
16.1 |
10.0 |
12.3 |
||||||
|
払込保険料 |
61.0万円 |
43.3 |
34.3 |
30.0 |
||||||
|
年金型商品の世帯加入率 |
32.5% |
個人年金保険の世帯加入率 |
29.0% |
|||||||
|
世帯の生活保障意識 |
世帯主に万一のことがあった場合の家族の必要生活資金 |
|||||||||
|
年間必要額 |
必要年数 |
総額 |
総額/世帯平均年収 |
|||||||
|
413万円 |
17.2年間 |
7,126万円 |
10.3年分 |
|||||||
|
世帯主が入院した場合の必要資金(月額) |
31.7万円 |
|||||||||
|
夫婦の老後の必要生活資金(月額) |
27.8万円 |
|||||||||
|
世帯主または配偶者が要介護状態となった場合の必要資金(月額) |
743万円 |
|||||||||
加入状況の各項目は、加入率を除きすべて加入一世帯あたり(加入一人あたり)の平均である。
*満期保険金等には、満期保険金の他に生存給付金や一時金を含む。
「子」は「子ども(未婚・不就労)」の数値である。「子」の加入率の定義は、
[(生命保険に加入している子ども(未婚・不就労)の総数)/(本調査に回答した子ども(未婚・不就労)がいる世帯での子ども(未婚・不就労)の総数)]x100
「年金型商品」と「個人年金保険」の定義は、
[(年金型商品(個人年金保険)のいずれかに加入している世帯の数)/(全回答世帯の数)]x100
必要生活資金は、生命保険未加入世帯を含む全回答世帯一世帯あたりの平均である
(出典 (財)生命保険文化センター(2000)「生命保険に関する全国実態調査<概要>」)
図1 保有契約及び構成比の推移 金額 億円
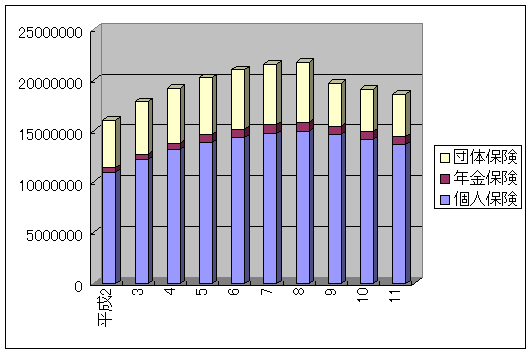
平成11年度保有件数ベースでは、個人保険1億1,587万件、個人年金保険1,403万件、団体保険の名寄せ被保険者数7,824万人に達している。
(出典(財)生命保険文化センター『2000年版生命保険ファクトブック』)
1999年の段階で、保険契約者は全人口の91.8%に達している。この数字そのものは、平成6年度の調査での95.0%をピークに減少している。しかし、それでも依然として消費者のほとんどが保険に加入しているという実態に変わりはない。また、このことは、個人保険の加入件数が1億を超えていることからも裏付けられる(図1参照。ただし、この場合重複加入もありうる。)。
ただし、世帯主に万一のことがあった場合の経済的備えについては、「少し不安である」(39.8%)、「非常に不安である」(33.0%)((財)生命保険文化センター、同前)と、依然として不十分であるとの認識されている。このような調査結果を基に、生命保険会社は、まだまだ顧客ニーズはあるとして販売促進を図っている。
それでは、現実的にはどの程度の金額が必要とされるのであろうか。
ここで、35歳男性、妻33歳、子ども7歳と5歳の家庭をモデルケースに、世帯主が死亡した場合の必要保障額を試算してみる。
試算1
<生活資金>
家族の生活資金(月25万円x17年間) 5,100万円(1)
配偶所の生活資金(月18万円x34年間)
7,344万円(2)
合計 12,444万円
その他将来予測される支出
教育費 1,376万円/4,279万円(3)
結婚資金 277万円(4)
最終整理資金
371万円/554万円(5)
合計 2,024万円/5,110万円
総計 14,446万円/17,554万円
<収入その他>
公的年金(遺族年金) 4,896万円
公的年金(老齢年金) 1,527万円
配偶所の収入(月10万円x27年間)
3,240万円
合計
9,663万円
差額 4,783万円/7,891万円
(1) 末子大学卒業まで。従ってこの試算は子どもが大学まで行くことを前提としている。
(2) 子どもが大学卒業と同時に独立した場合。
(3) 幼稚園から、一貫して公立小中高校に進み、大学は国立大学に自宅から通った場合と、幼稚園から高校まで私立、大学も私立大学理科系に進み、下宿した場合。高校までであれば、一人あたりそれぞれ188万円と943万円。(東海銀行 子どもの教育費 平成12年6月)
(4) 結婚資金のうち、親からの援助に頼る金額夫126.7万円、妻150.7万円の合計。(平成10年三和銀行調べ)
(5) 葬儀費用の全国平均229万円(日本消費者協会調べ 平成11年)とお墓関連の費用142万円から325万円(メモリアルアートの大野資料 平成10年)の合計
(出典(株)近代セールス社 FINANCIAL PLANNER’S DIARY 2001)
この他にも、住宅ローンなども加えてある例も見かけるが、ローンの借主が死亡した場合には通常団体信用保険でカバーされるため、上記の例では省いた。また、緊急予備費などの名目で支出額を加算する場合もある。
生活資金の総計と収入その他の合計の差額が生命保険でカバーすることが求められる額ということになる。最も少ない見積もりでも、4,783万円が必要であり、それに対して世帯主の平均生命保険加入額が2,524万円であるから、2,200万円ほど不足していることになる。
ところで、上記の試算はかなり融通が利く。例えば夫死亡後の収入額を20万円にしただけでも、不足額は埋まってしまう。10万円と20万円というのはかなりの差ではあるが、非現実的な数字ではない。また、現在所有している預貯金、試算などは全く考慮していない。
また、上記設例では夫がかなり若く死亡することを前提としているが、夫が長生きした場合はどうであろうか。
上記の家族、年齢がそれぞれ15才年上の場合の試算
試算2
<生活資金>
家族の生活資金(月25万円x2年間) 600万円
配偶所の生活資金(月18万円x34年間)
7,344万円
合計 7,944万円
その他将来予測される支出
教育費 232万円/522万円
結婚資金 277万円
最終整理資金
371万円/554万円
合計 880万円/1,353万円
総計 8,824万円/9,297万円
<収入その他>
公的年金(中高齢寡婦) 1,025万円
公的年金(老齢年金) 1,527万円
配偶所の収入(月10万円x12年間)
1,440万円
合計
3,992万円
差額 4,832万円/5,305万円
(出典、注意書きなどは試算1と同じ)
夫が若くして死亡した場合とあまり変わらない金額が必要とされることが分かる。ただし、ここでも資産状況などは全く勘案していない。世帯主の年齢が高くなれば、ある程度資産も拡大しているはずである。また、年齢が異なる場合には、資金が必要とされる時期も異なる。若年の保険加入者に対しては、万一の場合の死亡保障と長期的な財産形成が重視されるのに対して、高年齢の場合には、老後の保障と安全な資金運用が重視されるようになる。
確かに老後の面倒を国が見てくれることが期待できなくなった今、必要補償額が2千万円も不足しているとの資料を目にすると、現在の生命保険による保障が充分とは言いがたいのかも知れない。
ただし、金額ベースでは不足しているとしても、全く生命保険に加入していない世帯が非常に少ないわけであるから、現在の保険契約の実態が他社、もしくは自社の契約から乗り換える形でしか販売ができないことが裏付けられる。
この件に関しては、以下の資料が参考になると思われる。
表2 解約・失効率の推移 (万件)
|
年度 |
個人保険 |
個人年金保険 |
団体保険 |
合計 % |
||||||||||||
|
年始保有 |
解約 |
失効 |
復活 |
% |
年始保有 |
解約 |
失効 |
復活 |
% |
年始保有 |
解約 |
失効 |
復活 |
% |
||
|
平成2 |
11,579.70 |
417 |
235.4 |
12.9 |
5.5 |
580.3 |
26 |
14.8 |
0.7 |
6.9 |
201,916 |
8,831 |
3,733 |
188 |
6.1 |
6.1 |
|
3 |
11,792.10 |
453.5 |
226.4 |
12.1 |
5.7 |
751.6 |
35.5 |
26.3 |
1.1 |
8.1 |
216,893 |
10,398 |
4,315 |
125 |
6.7 |
6.7 |
|
4 |
11,997.10 |
497.8 |
229.8 |
11.8 |
6.0 |
922.7 |
49.2 |
33 |
1.3 |
8.8 |
226,344 |
12,320 |
5,378 |
190 |
7.7 |
7.7 |
|
5 |
12,281.70 |
529.8 |
238.3 |
13.1 |
6.1 |
1,102.10 |
59 |
34.5 |
1.5 |
8.3 |
228,252 |
12,839 |
5,518 |
194 |
8.0 |
7.9 |
|
6 |
12,618.50 |
543.2 |
248.6 |
15.3 |
6.2 |
1,285.80 |
65.1 |
35.2 |
1.7 |
7.7 |
226,844 |
13,828 |
5,160 |
135 |
8.3 |
8.2 |
|
7 |
12,873.50 |
579.4 |
267.3 |
19.7 |
6.4 |
1,367.50 |
76 |
32 |
1.5 |
7.8 |
223,757 |
13,815 |
4,383 |
109 |
8.1 |
8.0 |
|
8 |
13,125.80 |
584.7 |
279.3 |
16.4 |
6.5 |
1,448.00 |
73.3 |
30.4 |
1.4 |
7.1 |
221,660 |
14,815 |
4,118 |
106 |
8.5 |
8.4 |
|
9 |
13,003.40 |
800.1 |
293.4 |
15.9 |
8.3 |
1,471.20 |
132.5 |
24.9 |
1.1 |
10.6 |
213,973 |
25,869 |
5,428 |
101 |
14.6 |
14.2 |
|
10 |
12,431.80 |
692.9 |
261.7 |
20.7 |
7.5 |
1,429.60 |
92.9 |
19.3 |
1 |
7.8 |
170,004 |
15,346 |
3,114 |
96 |
10.8 |
10.6 |
|
11 |
12,012.90 |
682.9 |
306.6 |
41 |
7.9 |
1,439.40 |
87.9 |
22.3 |
1.9 |
7.5 |
149,181 |
11,237 |
2,276 |
340 |
8.8 |
8.7 |
(出典 (財)生命保険文化センター(2001)『2000年版生命保険ファクトブック』)
まず、解約・失効率がかなり高率になっていること、年始保有件数がむしろ減少傾向であることが注目される。現状では、年間、実に保有生命保険の10件に1件近くが解約されていることを示すとともに、年始保有件数が増えていないということは、新規契約が失効・解約数を下回っていることを示している。ここ数年は不況であるため解約件数が減少しているという面ももちろん否定できないであろうが、現在では新契約は既存契約を解約あるいは下取りして獲得していることが示されている。
2.2生命保険会社の営業体制
表3 年度末登録営業職員数の推移
|
年度 |
営業職員数(人) |
|
平成2 |
444,691 |
|
3 |
443,397 |
|
4 |
427,859 |
|
5 |
421,362 |
|
6 |
399,665 |
|
7 |
395,392 |
|
8 |
389,875 |
|
9 |
353,903 |
|
10 |
341,605 |
|
11 |
329,779* |
* 内訳
新規登録営業職員数 : 135,267人
業務廃止営業職員数 : 146,012人
その他増減営業職員数 : −1,081人
営業職員純増加数 : −11,826人
(出典(財)生命保険文化センター(2001)『2000年版生命保険ファクトブック』)
現状約30万人の営業職員(一般に、○○保険のおばちゃんなどといわれている職員。後述するように、一般的には内勤職員とは全く異なる職務体系をとる。)が存在する。人口1億2千万人として、なんと400人に1人の割合で営業職員が存在することになる。しかも、これは一般の民間生命保険だけの数字である。この他、いわゆる代理店といわれる、生命保険だけを取り扱っているわけではない販売経路(平成11年度末で187,949店)、さらに簡保、JAなどの共済もある。あまりにも多くの人数で限られたパイの奪い合いをしているように思えるがいかがであろうか。
生命保険は同一人物に毎年売れる商品ではない。しかもすでに90%以上の消費者が何らかの生命保険に加入しているのである。そこで販売方法もGNPなどと揶揄される義理・人情・プレゼントに頼った強引な販売が目立つようになるのである。
この件に関しては、生命保険文化センター調査が参考になる数字を提供している。
表4 解約・失効の理由(複数回答) %
|
|
昭和六十三年調査(昭和六十〜六十三年解約) |
平成三年調査(昭和六十三〜平成三年解約) |
平成六年調査(平成三〜六年解約) |
平成九年調査(平成六〜九年解約) |
平成十二年調査(平成九〜十二年解約) |
|
掛金を支払う余裕がなくなったから |
19.3 |
13.2 |
22.3 |
29.5 |
36.2 |
|
他の生命保険に切替えたので |
33.8 |
33.2 |
28.3 |
37.4 |
33.7 |
|
まとまったお金が必要となって |
19.0 |
19.2 |
25.5 |
25.4 |
20.7 |
|
義理で入ったものなので |
24.2 |
25.2 |
23.5 |
18.7 |
18.8 |
|
加入後のアフターサービスが不満だったので |
− |
− |
6.6 |
3.0 |
8.0 |
|
掛金が更新によって高くなってしまったから |
− |
− |
− |
3.5 |
7.4 |
|
高額な保障が必要なくなったから |
− |
− |
− |
4.1 |
6.0 |
|
期間が長すぎるのでいやになった |
10.3 |
7.6 |
6.9 |
3.2 |
4.0 |
|
イメージしていた商品内容と異なるため |
4.9 |
5.8 |
6.0 |
4.6 |
3.8 |
|
少額すぎて生命保険として役に立たないので |
11.9 |
11.4 |
10.4 |
5.4 |
3.0 |
|
生命保険はインフレに対応できないと考えて |
5.4 |
5.0 |
4.7 |
2.5 |
2.8 |
|
他に有利な貯蓄手段があったので |
− |
6.2 |
4.9 |
2.7 |
2.6 |
(出典(財)生命保険文化センター「平成12年度生命保険に関する全国実態調査<概要>」)
上記表4からも分るとおり、経済的な理由で失効・解約したものが半数以上を占めている(「掛金を支払う余裕がなくなったから」、及び「まとまったお金が必要となって」)。特に、近年この項目の比率が高まっているのは、昨今の不況の実態を鑑みれば、妥当な理由であるとも思える。しかしながら、無理な営業の結果と思われる「義理で入ったものなので」が時期にもよるが、四分の一近くを占めている。また、転換制度(後述)のところでも触れるとおり、「他の生命保険に切り替えたので」という理由も三分の一を占めている。加入後のアフターサービスへの不満、保障内容が高額すぎる、あるいは少額すぎる、あるいは加入時の説明不足が原因と思われる更新によって掛金が高くなったといった理由も挙げられてはいるものの、多数を占めるまでには到っていない。
しかしながら、保険金額が高額すぎる、少額すぎるとの不満は、保険契約時の保険金額設定に疑問を抱かせる。また、掛金が更新後高くなった(加入時より年齢が上がるため、更新型では掛金が高くなるのが普通である)、あるいはイメージと違う商品であったといった不満は、保険加入時の説明不足が原因とも思われる。また、アフターサービスが不十分という不満は、いかに生命保険商品が売りっぱなし商品であるかを示している。本来保険商品は、一定の期間が経過したら見直しをかけるべき商品なのである。時間の経過とともに、資産内容、家族構成、経済の見通し、投資スタンスなどに変化が生まれるのが当然なのである。
ところが、見直しの結果不要となった部分の保険契約を解除する、などということを生命保険会社としては好まない。また、営業職員としても、新規契約獲得のインセンティブ(報酬)が最も高いことから新規契約の獲得には熱心であるが、既存契約の見直しといった手間がかかる割には実際の契約に結び付かない場合も多い(従ってインセンティブに結び付かない。見直しによって契約を一部解除したりする場合には、逆にインセンティブの戻入として会社に支払わなくてはならない場合もある。)既存契約のメンテナンスに積極的に取組もうとはしない。
しかし、生命保険各社も最近ではいわゆるユニバーサル型と呼ばれる、転換契約等をせずに保険契約の内容を見直せる生命保険を取扱うようになってきた。この保険契約の場合、自社で取扱っている各種特約を付加えたり、外したりすることによって、保険契約の性格(貯蓄を目的とするか、いざというときの保障を中心とするか)まで見直しが可能になる。この場合、ある顧客から契約を取った場合、一生涯保険契約のメンテナンスをすることが必要になる。各保険会社とも、ユニバーサル型(保険契約締結後も契約内容の変更がフレキシブルにできる)の取扱を始めるとともに、販売に際してコンサルティングを重視する方針を打ち出してはいる。歓迎すべきことではあるが、実際の販売体制が同じままで、どの程度の効果があるのであろうか。
2.2.1転換制度とは
保険契約の諸悪の根源であるかのような言い方をされることもある転換制度であるが、その歴史は意外と新しく、昭和50年に導入された。その導入の経緯も、意外なことに、業界主導ではなく、消費者団体等の要望を基に導入されたのである。
実は、保険契約も、昔から同じような商品(現在では定期付終身など、死亡保険が商品構成のメインになっている)を販売していたわけでなく、昭和30-40年代においては、どちらかというと貯蓄目的の養老保険が主流であった。ところが、消費者側でも死亡保障を求める声が強くなってきた。その場合、従前の保険を解約して新しい保険に変更するわけであるが、この当時の制度では、従前の保険を解約してしまうと、特別配当(通常の配当では清算しきれない含み益などの剰余金を満期・死亡などによって消滅したときに最終的に清算する。従って、長期間保有したほうが有利。短期で解約、もう一度新たに入りなおすと、期間の計算がゼロからスタートすることになってしまう。)を受け取る権利がなくなってしまう。そこで、経過年数を通算することによって特別配当を受け取る権利を転換前契約から転換後契約に引き継ぐことができる転換制度が、同じ保険種類のまま死亡保障を増額する中途増額制度とともに採用されたのである。
当初はこのように消費者のために考えられた制度であったが、この制度を逆手に取った消費者保護にかける転換が続出した。そのひとつの例が、バブル崩壊後の低金利(予定利率の引き下げ)時代に、バブル以前の高い予定利率を引きずっている既存契約を新しい予定利率の低い商品に乗り換えさせることによって逆ざや解消を狙ったかのような転換契約が相次いだことである。従来の保険商品は金融商品になぞらえて言えば、固定金利の商品が主流であった。保険料を割り引く際に用いる金利のことを予定利率という。支払う保険料などを計算する際に、事前に約束した高い予定利率を用いて計算するのである。バブル崩壊後、低金利が長く続き、株価、地価の下落などとともに生命保険会社の資産内容が大いに傷ついたことから、逆ざやも大きくクローズアップされることになった。このような転換には、当時の大蔵省からも注意が発せられた。
2.2.2営業職員とは
営業職員とは前述のように、一般に○○保険のおばちゃんなどといわれている人々である。日系の生命保険会社では営業職員が販売の主力を担い、一般に内勤職員と呼ばれる本社勤務の職員とは全く異なる勤務体系を採っている(外資系生命保険会社、あるいは最近設立された生命保険会社の場合には、異なる場合もある)。ここでは、従来の日系生命保険会社を前提として論を進める。営業職員と内勤職員の大きな違いは、給与の決定方法と雇用形態である。営業職員の給与は、固定給部分が非常に小さく、歩合給の占める割合が大きい。これに対して、内勤職員は一般のサラリーマンと同じく固定給である。
また、営業職員はいわばパート職員のようなものであり、(現在では日系の企業といえども保障されているわけではないが)終身雇用制ではない。営業職員には、営業職員になったときから一定の成績を上げることを義務付けられており、成績の要求水準を満たせない場合には契約が延長されない。そして、この見直し期間は大体3ヶ月程度のようである。3ヶ月間成績を上げられなければクビ、なのである。
従って、営業職員の勤続年数はきわめて短い。平成11年度において、上記表3「年度末登録営業職員数の推移」の末尾にも記したとおり、年度末に登録している営業職員33万人に対して、実に4割にあたる13万5千人が新規登録を受けた職員であり、14万6千人が年度中に退職しているのである。もちろん、いくつもの生命保険会社を転々とする営業職員もいるといわれているが、いずれにしても定着率が高いとは言い難いのである。営業職員の採用に関しては、金融庁検査マニュアルにも、「保険募集人の採用、委託に当たって、その適格性を審査するための審査基準(保険募集に関する法令、保険契約に関する知識、保険募集の業務遂行能力、本来業務の事業内容、事業目的等)が整備されているか」を問うている。
2.2.3営業職員の成績評価制度
本論で記述する営業職員の評価制度は、会社毎にそれぞれ多少の違いはあるものの、日系の生命保険会社においては基本的には同様の雇用形態を採っている。ただし、例え日系の生命保険会社といえども、下記のシステムとは明確に異なった体制を採用、成功を収めている会社もあることここに明記しておく。
営業職員の給与は、基本的な手当、契約獲得に応じた歩合給、その他に別れる。
この中で、金額的に最も多いのが契約獲得に応じた歩合給である。また、その他に含まれる賞与なども、基本的には獲得実績が反映される。従って、非常に小額の基本的な手当(月額数万円程度)を除くと、殆どが歩合給で構成されていることになる(ただし、法定の最低賃金は支払われる)。
歩合給の決定の仕方は、概ね以下のようになる。基本的には、生命保険の金額、あるいは1年間に支払われる保険料のある一定のパーセンテージが営業職員に支払われることになる。ところが、生命保険契約は通常長期にわたる契約である。従って、保険契約が残存している期間ずっと歩合給を支払うことにすると、1月当りの金額は1件当りでは極端に少ない金額になってしまう。特に新入社員には酷な制度になってしまう。そこで、新契約を獲得した場合、特に初年度に厚く配分され、2年以降にも獲得契約に応じた歩合給は支払われるものの、その比率はぐっと小さくなる配分方式が採られている。
従って、営業職員にとっては、新契約を取り続けることが給与を維持する絶対条件になるのである。
生命保険会社の営業職員の成績評価は、ほぼ100%営業成績で決まる。そして、新入社員として入社後、実に3ヶ月毎にその成績が見直され、その期間に一定の成績を上げないとクビになってしまうといわれている。また、職級を上がるためにも(職級が上がると、インセンティブの比率が上がったり、営業所全体の成績の一部が給与に反映されたりするようになる)一定以上の成績を上げることが必要になる。従って、営業職員の定着率は決して誉められたものではなく、100人入社しても、1年後には半数以下、2年後には1から2割程度まで減ってしまうそうである。
金融庁の検査マニュアルにおいても、「業績評価、人事考課等にあたって、保険募集に関する法令等の遵守に係る取組み状況を、業務推進より優先させるなど、適確に反映しうるための方策を講じているか」という項目がある。成績を第一にした考課システムは、とかく事故を招き易いものであり、コンプライアンスを確保するには、余り好ましくない制度であるといえるだろう。
2.3成績第一主義の弊害
成績第一主義の弊害は、前述の営業職員の定着率の低さといったことのほかに、具体的な契約内容にも現れる。
義理・人情・プレゼントに頼った営業が行われていることは前述のとおりであるが、単に強引なセールスが行われているだけでなく、不適正契約と呼ばれる不正な契約が結ばれることがある。具体的には、以下に挙げるような契約が結ばれることがある。
まず、契約が取れないことから、架空名義、借名などによる作成契約が結ばれることがある。これらの契約は金融検査マニュアルなどを持ち出さなくても、当然に禁止されているものである。しかし、あと一件取れなければ、などという場合に、自腹を切って作ってしまう場合が後を断たないという。
また、作成契約とまでは行かずとも、知り合いに無理に保険に入ってもらうため、契約者の代りに申請書や告知書を代筆してしまうこともまま見受けられる。これも当然禁止行為である。
また、とにかく契約を取るために、あまり細かいことはいわず、医師の審査を省き、告知書扱い(病歴、健康状態などを自己申告する)とするケースも多い。この場合、契約者本人に面接をしないため、実際の病歴を申告せずに保険に加入することが容易になる。極端な場合には、入院している人間を保険に加入させてしまうといった例まである。ただし、病歴や健康状態を偽って保険給付を受けたことが発覚すると、当然保険金は支払われないし、場合によっては刑事責任まで追求されることもありうる。
いずれにしても、上記のような保険契約は生命保険会社にとっても歓迎すべきものではない。短期失効・解約が増えるばかりでなく、保険金の不正請求の温床ともなるからである。
作成契約の場合には、作成した営業職員がずっと保険料を支払い続けられるわけもなく、ある一定期間を超過して、例えば1年を経過してインセンティブが低くなったら失効させてしまう、などということが起きる。もちろん、不正が発覚する、あるいは退社してしまうなどの場合も当然に失効する。生命保険会社にとっては、短期失効・解約契約は、営業職員への経費の前払効果(将来受取るべき保険料に含まれる営業職員への歩合給を前倒しで支払ってしまうことから生じる)を勘案すると、赤字であるといわれている。
また、告知義務違反による医療給付請求の増大は、保険設計上採用した統計上妥当とされる額を超えて請求(不正請求)が来ることになり、当然生命保険会社にとっては損失となる。
また、知り合いに無理を言って入ってもらった契約の場合には、とにかく解約等が多い(表4参照)。解約理由の4分の1から5分の1が「義理で入ったものなので」となっていることが、生命保険文化センターの資料からも読み取れる。
不適正契約ばかりが原因とは言えないとしても、保険契約の短期失効・解約は、生命保険会社にとっては大きな損失である。保険金の運用は長期契約を前提として行われている。しかし、失効・解約による運用資産の減少、現金の流出などが多い場合には、その分長期運用の比率を減らし、現金準備を高めなくてはならない。このことは、保険会社にとって運用機会を失うことを意味する。そもそも、顧客がその必要性を納得して保険契約を結んだのであれば、そうそう簡単に失効させることはあり得ないはずである。
生命保険自体がかなり成熟した商品であり(加入率91.8%は前述のとおり)、自社、もしくは他社の保険契約からの乗り換えを主体として保険の営業が成り立っていることも前述のとおりである。
営業職員を中心とする生命保険の営業システムそのものが、上記のような不良契約を招いているのではないだろうか。
どのくらいの保険金額が必要かをシミュレーションした個所でも述べたとおり、個々の世帯にとってどれだけの保険金が必要であるかを決定するには、かなり時間をかけた調査、検討が必要になる。ところが、よくあるケースだと思われるが、アンケート等と称する用紙に生年月日と家族構成を記入しただけで、生命保険の設計書が送られて来たりする。まさに安易な営業姿勢を示している。
しかし、このような営業姿勢を、営業職員の資質のみに帰するわけには行かないのではないだろうか。最盛期よりは減っているとはいえ、直近の統計でも30万人近い営業職員と20万近い代理店を抱えているのである。しかも、これらの営業関係の職員の給与が実績主義に基づいている。加入率が低く、顧客に喜んで生命保険に加入してもらえた時代はいざ知らず、現在ではとにかく無理を言ってでも保険に入ってもらわなくてはならない。そこで、既存保険契約の解約を前提とした営業がまかり通ることになる。自社が契約を獲得するだけであればそれでも構わないのかも知れないが、通常は自社の契約が他社の契約に乗り換えるため解約されることを覚悟しなくてはならない。前述のように、短期失効・解約は生命保険会社にとっては好ましいことではないのである。
これは、営業職員だけの問題ではない。これらの職員の給与体系が実績主義に基づくものであるとはいえ、固定給の支払、研修体制の確保など生命保険会社の負担はかなりのものである。今後業績面でも、新規参入により従来とは異なった営業チャンネルを開拓した生命保険会社と、営業職員に頼った旧来型の生命保険会社とでは、かなりの格差が生じてしまうのではないだろうか。
また、コンプライアンスに触れる不適性契約の存在は、会社収益の悪化だけでなく、社会における生命保険会社のイメージを決定的に危うくし、会社の存亡に関わる影響を及ぼすであろう。
3.今後望まれる営業姿勢−コンプライアンス
以下において、金融機関、本論文においては特に生命保険会社にとって、コンプライアンス態勢の確立が前述の問題に対して解決策を提供してくれることを示すとともに、いかにすればコンプライアンス態勢を構築できるかを、コンプライアンス体制を整える場合に欠くことのできない条件となった金融庁の検査マニュアルを基に検証する。
3.1コンプライアンスとは何か
コンプライアンスは、通常法令遵守などと訳されることが多い。しかしながら、本論文におけるコンプライアンスの意味は、単なる法令遵守にとどまるものではない。むしろ、倫理基準といったほうが適切であろう。単なる法令遵守であれば、法令違反を摘発して処分を下せばよいのであろうが、倫理基準となると、そのように明解な取扱が常に可能となるわけではない。
コンプライアンスは、よく車のブレーキに喩えられる。ブレーキのない車には危険で乗っていられないと。しかし、コンプライアンスが問題になるのは、もう少し微妙な場合である。
車を運転して交差点に差し掛かったとき、黄色い信号に変わることがある。そんな場合に、アクセルを吹かして通りぬけてしまう人と、ブレーキを踏んで止まる人といる。通り抜けてしまうことは、現実にはよくあることで、必ずしも法令違反として責められることではないだろう。コンプライアンスでも同じことである。赤信号の交差点に突っ込んでいくことは、明白な法令違反で、コンプライアンス云々以前の問題であろう。黄色信号に突っ込んでも、今回は大丈夫かもしれない。しかし、習慣化して違反を繰り返している内に、事故が起きるのではないだろうか。
黄色信号の交差点を発見したとき、もし突っ込んでしまえば、自分が危険に晒されるだけでなく、同乗者や、他の交通機関、歩行者などをも危険に巻込む可能性があることに思いを致せば、ブレーキに足が掛るのではないか。コンプライアンスでも同じことで、コンプライアンス違反は自分だけでなく、会社や業界はもとより、顧客にまで損失をもたらすことに気付けば、違反を繰り返す前にやめることができるのである。
また、コンプライアンスを確立するためには、法令等を遵守するのみならず、その責任体制を明確にしなくてはならない。単なる法令違反であれば、違反者とその管理責任者を処分すればよいことになるが、倫理基準の場合には、難しい問題が出てくる。
顧客に例えば保険商品を勧める場合、様々な商品の組み合わせ(勧めないことも含めて)が可能なはずである。その場合に具体的にどのような商品を勧めるかという基準は、顧客にとって何がベストの商品であるかという以外にはあり得ないのである。このような義務のことを「ベスト・アドバイス義務」とも呼ばれている。しかし、何をもってベストというのであろうか。
3.2ベスト・アドバイスとは
保険商品を含む金融商品・投資商品を販売する場合に顧客にとってベストな商品を勧めることは精神としては理解できるにしても、法的に強制することは難しい。なぜならば、何がベストなアドバイスであったかを、事後的な結果を基に判断するわけにはいかないないからである。もし、事後的な結果をもってベスト・アドバイスであるかないかを判断するとすれば、投資家・消費者は投資の選択・実行に関して何ら自己責任を負わず、投資が失敗した場合にはベスト・アドバイス義務違反を問えることになってしまうからである。
それでは、何をもってベスト・アドバイスというのであろうか。保険商品を販売する場合を例にとると、以下のようになる。
まず、商品販売の前提となる顧客に関する基本的条件を確認しなくてはならない。一般的な顧客に関する事実(家族構成・資産内容など)はもとより、保険商品も金融商品として投資の一部であるという性格を持っているのであるから、顧客の投資スタンス、リスク許容度なども関しても、販売する側と顧客側で共通の理解がなくてはならない。
以上のような基本的な顧客に係る情報を入手した後、ベストな保険商品の設計にかかる。そして、次に、保険商品の勧誘が行われることになる。この時、生命保険会社、勧誘を行う営業職員は、保険商品について顧客が理解するようベストを尽さなくてはならない。特に、顧客に対して不利益となる事項に関しては、確実に顧客の理解を得なくてはならない。前述の転換制度などに関して、「保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込をさせ、又は新たな保険契約の申込をさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為」(保険業法300条第1項第4号)は法的にも禁止されている。
今後、変額保険などの市場リスクを含む保険商品の販売が急速に拡大していくと思われるので、以上のようなベスト・アドバイスに関する原則はますます重要度を増していくと思われる。
また、現在でも重要事項の説明に関しては、説明を受け、理解をしたことの証左として記名捺印を求めることになっている(説明義務に関しては、金融商品販売法、消費者契約法はもとより、保険業法300条第1項第1条にも規定されている)。生命保険会社、販売を行う営業職員には、記名捺印を求めるだけの形式に流れることなく、説明義務を果すことが求められているのである。
ベスト・アドバイスとはこのように、法令で一義的には定め難い倫理的な部分を多分に含んでいるため、法令で義務づけることはなされていない。「金融サービス・マーケットが信頼されるためには、ベスト・アドバイスが必然的になされるルールが必要である。しかし、先に述べたように、ベスト・アドバイスを法令で義務づけることは、金融サービス・マーケットにへの副作用が大きく、現実には難しい。そのため、マーケット・メカニズムの自浄作用を活用したコンプライアンスに期待が寄せられるのである」(牛越 博文『日本版金融サービス法』p181)。
それでは、コンプライアンスに欠け、金融サービス・マーケットが信頼を失った場合、どのような事態が予想されるのであろうか。
3.3なぜコンプライアンスは必要なのか
なぜコンプライアンスは必要なのか。端的に言えば、リスク管理の一端として必要なのである。もちろん、法令違反、コンプライアンス違反がない超したことはない。しかし、人間とは過ちを犯すものであり、その人間が構成する組織に完璧に法令違反をなくすことを求めた場合、どうなるであろうか。厳罰主義をもって望めば、違反件数を減らすことはできるかもしれない。しかし、違反をなくすのはまず不可能であろう。その場合に、違反を違反として公表することも可能ではあろうが、多くの場合、違反を隠そうとするインセンティブが働くのではないか。
このことについては、本論文の取上げている業務分野ではないが、広く知られている例として、雪印乳業の食中毒事件と三菱自動車のリコール隠し事件を取上げてみたい。両事件の経緯については、資料1、2において報道機関による発表を引用しておいたので、事実関係については参照されたい。
いずれの事件も、事件の端緒に、明確な法令違反が存在したことは間違いない。しかし、さらに問題を大きくしたのは、事件が発覚した後も、責任の所在がはっきりしないばかりか、事実関係すらはっきりしなかったことである。両社とも、記者会見の場において社長が記者会見中に、その場に居合わせた担当者が社長の会見内容とは異なる事実を発表するという失態を演じた。しかも、その内容は重要な事実であるにも関わらず、社長には知らされていなかったのである。記者会見の場で大失態が演じられ、報道機関を通じて白日の下に晒されてしまったのである。その結果、新聞報道などにおける両社の発表が二転三転する結果となり、消費者の信頼をいたく裏切ることになった。
前述のように、人間の組織から間違いを完全に排除することはできない。問題となるのは、間違いが起こったときに、いかに対処するかである。両社とも、問題が起こった場合のマニュアルがはっきりせず、どのように情報を伝えるかが明確にされていなかった。その結果、最高首脳陣に正確な情報が伝わらず、社内的な混乱を招き、発表が二転三転するという不手際を招いた。このことが消費者の怒りを増幅し、両社の業績をも直撃したのである。
端緒となった法令違反は違反として、発覚後の対処方法にも問題があったと思われる。社内のコンプライアンス体制がしっかりしていれば、あれほどの問題とはならなかったのではないだろうか。そもそも、コンプライアンス体制がしっかりしていれば、問題そのものも早期に解消されていたのではないだろうか。
従来、ともすれば、コンプライアンスはいわゆる営業部門の御目付け役的な役割を担わされてきた。従って、「コンプライアンスを四角四面に守っていたら、営業なんかできない」といった反応を引き起こしがちであった。しかし、上記の例は、そのような誤った評価がいかに危険であるかを示している。コンプライアンスを軽視することは、実に会社の存亡をも左右するのである。
4.金融庁検査マニュアル
「金融検査については、平成10年に「新しい金融検査に関する基本事項について」(蔵検第140号)を定め、自己責任原則の徹底と市場規律を基軸に、明確なルールを前提とした透明性の高い行政への転換を図ってきているところである。平成11年には「預金当受入金融機関に係る検査マニュアル」、平成12年には「保険会社に係る検査マニュアル」を定め、これにより、監督当局の検査監督機能の向上及び透明な行政の確立のみならず、金融機関等の自己責任に基づく経営を促し、もって金融業性全体に対する信頼の確立を図っているところである。」(金融庁「証券会社に係る検査マニュアルについて」金検第170号)さらに、平成13年には「証券会社に係る検査マニュアル」も制定された。その後も細かな変更・改訂が加えられ、金融庁検査の際の運用基準となっている。
金融庁検査マニュアルの位置付けは、あくまでも検査官が金融機関を検査する際に用いる手引書であるとされており、検査マニュアルの項目を一字一句過たずに実行することが求められているわけではない。逆に、それぞれの金融機関が自己責任の原則の下、それぞれの規模・特性に応じた独自のマニュアルを作成することが求められている。検査にあたっても、検査マニュアルを機械的・画一的に適用することがないように配慮することが求められている。ただし、チェック項目の語尾が「しているか」または「なっているか」とあるのは、特にことわりのない限りすべての金融機関にミニマム・スタンダードとして求められる項目であるとされている。実際のチェックリストを一覧すれば分かるとおり、実はほとんどの項目が上記のような語尾で終わっている。もちろん、そのような対応がなされていない場合でも、金融機関の業務の健全性や適切性確保の観点から見て、各金融機関の対応が合理的であり、その規模・特性・業務内容から見て充分に効果をあげていれば必ずしも不適切な対応として非難されるわけではないとされてはいるが、かなり厳しく金融機関の行動を縛っているものであることは間違いない。
4.1コンプライアンスと取締役の役割
金融庁の検査マニュアルでは、取締役及び取締役会の役割が大変重視されている。これは、BISレポート(Bank for International Settlement , Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations)を受けて決定されたものであるが、当初は違和感をもって受取られた。
日本においては、取締役会はかなり形骸化しており、取締役といえども経営陣の一員というよりは、単なる高級サラリーマンである場合が多く、実質的な経営権は常務会等のより高度な経営機関が握っている場合が多かった。
しかしながら、法律上、経営者といいうるものは取締役以外にはいないのであり、コンプライアンスの問題に関しては、取締役の役割が強調されている。ただし、経営形態に合わせて、執行役員や、その他の取締役に相当するものが担当することも認められている。
金融庁の検査マニュアルの「取締役の意識」の確認という項目において、
l 「コンプライアンスに関しては、取締役が誠実かつ率先垂範して取組んでいるか。また、取締役会は、高い職業倫理観を滋養し、あらゆ職階における職員及び保険募集人に対してない部管理の重要性を強調・明示する風土を組織内に醸成する責任を果しているか。」
l 「代表取締役は、年頭所感や拠点長会議等、可能な機会をとらえ、法令等遵守に対する取組み姿勢を示しているか。」
l 「取締役はコンプライアンス担当部門を営業部門と同様に位置付け、適切な人材と規模を確保し、関心をもって管理するとともに業績評価、人事考課において適切な評価を与えているか。」
l 「取締役自身が、社内外のコンプライアンスの問題に対し、規則に基づき、公平、公正に断固とした姿勢で対応しているか。」(金融庁「保険会社に係る検査マニュアル」)
といった点が強調されている。
このことは、最近の大和銀行事件における大阪地方裁判所の判決にも現れている(資料3参照)。この事件では、その830億円という巨額の損害賠償額が話題となり、株主代表訴訟に関する商法改正まで話題となった。ただし、この判決については原告、被告双方が控訴しているため、現段階では確定判決ではない。
しかし、判決の中で、取締役の注意義務と忠実義務については、大変厳しく求めており、その基準に適合しない場合には、取締役個人への損害賠償を認める(金額は別として)方向にあることは間違いないと思われる。
判決の中で、「取締役は、みずから法令を遵守するだけでは充分でなく、従業員が会社の業務を遂行する際に違法な行為に及ぶことを未然に防止し、会社全体として法令遵守経営を実現しなければならない。」「取締役は、従業員が職務を遂行する際違法な行為に及ぶことを未然に防止する法令遵守体制を確立する義務があり、これもまた、取締役の善管注意義務及び忠実義務の内容をなすもの」であるとしている。また、「取締役会上程事項以外の事項についても、監視義務を負うのであり、リスク管理体制の構築についても、それが適正に行われているか監視する義務がある」と、取締役は業務全般に責任を負うとしている。
それだけでなく、自らの判断を下さず、大蔵省の要望を漫然と受入れ、米国当局に報告しなかったことについても、「そのような判断は大きな誤りであり、米国当局の厳しい処分を受ける事態を招いた」と厳しく指弾している。(以上引用は、大阪地裁第10民事部平成12年9月20日判決 旬刊商事法務1573号)
従来、ともすれば不祥事は個人の責任、個人的犯罪と捉えられがちであった。これに対して、金融庁や裁判所の姿勢は、真っ向から取締役の責任を問うている。それだけでなく、従来であればコンプライアンス関係の責任は法務担当役員が責任を持ち、例えば営業担当役員は営業成績にしか責任を持たないといった良く言えば分業主義、悪く言えば無責任体制が取られていた。これに対しても鋭く警鐘を鳴らしている。
後述の望ましいコンプライアンス態勢のパートでも触れるとおり、コンプライアンスは決して法務担当部門が管理体制を敷くことによって確立される訳ではない。コンプライアンスはコンプライアンスを普遍的、全社的な価値観として全役員・職員に共有されて初めて機能するのである。そのため、代表取締役には、折に触れてコンプライアンスの重要性に関するメッセージを役職員に対して発信するとともに、取締役ともども実践することが求められているのである。
4.2望ましいコンプライアンス態勢
実際のコンプライアンス態勢、あるいはコンプライアンス部門の構築には、実は幾通りものやり方、方法が考えられる(実際には企業毎に異なっているのかもしれない)。金融庁の検査マニュアルもコンプライアンス・オフィサーの設置を求めてはいるが、具体的にどの部門に配置せよ、といった点には言及していない。
とはいえ、コンプライアンス担当部門の設置方法は大別すれば、概ね次の二つの方法に分類されるのではないかと思われる。
まず第一が、取締役など上級管理者の中からチーフ・コンプライアンス・オフィサーを任命し、実際の手足となって動く実働部隊は検査部などが兼任、またコンプライアンス・オフィサーも各部署に所属する人間の中から任命する(内部任命方式とする)方法である。
これに対して、取締役など上級管理者の中からチーフ・コンプライアンス・オフィサーを任命することは同じであるが、そのものの下に従来の検査部を発展、拡大させた内部監査部(英語ではInternal Audit Department。日本の検査部に相当するが、より独立性が高く、監査の内容も高度なものを含む。詳しくは後述。)を設置し、各部署におけるコンプライアンス・オフィサーも内部監査部所属にする方法も考えられる(外部設置方法とする)。
いずれの方法もメリット、デメリットがあり、優劣はつけがたい。
表5内部設置方式と外部設置方式のメリット、デメリット
|
|
内部設置方法 |
外部設置方法 |
|
メリット |
既に人員が確保されており、当該業務への習熟度も高い。 追加的な人員が必要ないため、コスト的に有利。 |
コンプライアンス業務に習熟することができる。 指揮系統が明確。 |
|
デメリット |
コンプライアンス・オフィサーは業務上はラインの管理を受け、コンプライアンスに関してはコンプライアンス部門の管理を受けるという指揮系統の煩雑性。 業務推進をコンプライアンスに優先させるという不安。 コンプライアンスに関する専門性に疑問。 コンプライアンス評価に当該部門の担当者が関与することによる評価の恣意性。 |
当該業務に精通しているとは限らない。 設置に追加的なコストがかかる。特に、小さな部門、組織の場合には、設置そのものができない場合がある。 新たにコンプライアンス専門の人員を育成しなくてはならない。 コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンスだけに責任を持つ場合には、評価が過度に慎重になり、自己防衛的な形式主義に陥る可能性がある。 |
実際には、内部設置方式と外部設置方式を組織の大小や性格によって、同一企業内でも混在させる例が多いようである。問題は、コンプライアンス・オフィサーや内部監査部の設置ではなく、いかにコンプライアンス態勢を確立していくかにあり、形式ではない。
表5を見ても分るとおり、内部設置方式のメリットは外部設置方式のデメリットになり、内部設置方式のデメリットは外部設置方式のメリットになってしまう。各部門の中にいるコンプライアンス・オフィサー等も被雇用者である従業員であり、一従業員に会社全体を見渡した経営判断を求めるのは不可能である。もしその判断を求めるとすれば、従業員が経営責任を負うことになってしまう。そのような体制は当然不合理である。会社全体を見渡して責任を負うのは当然取締役であるべきであり、従って取締役は自己の担当分野を超えて責任を負うという前述の判決理由にも結び付くわけである。
4.2.1内部監査とは
金融庁の検査マニュアルにおいて、設定当初は企業が自らに対して行う検査も、金融庁の行う検査と同じ「検査」という言葉が使われていた。しかし、2001年4月の改訂において、「検査」を「内部監査」という言葉に置きかえることによって、金融庁の検査とは異なった意味合いで内部監査を実行すべきことを示した。
内部監査とは、「「内部監査」とは、各業務部門等の本部部門及び営業店等(以下、「被監査部門等」という。)から独立した内部監査部門(検査部、業務監査部等)が、被監査部門等における内部管理態勢(リスク管理態勢を含む)等の適切性、有効性を検証するプロセスである。このプロセスは、被監査部門等における内部事務処理等の問題点の発見・指摘にとどまらず、内部管理態勢等の評価及び問題点の改善方法の提言等まで行うものであり、原則として、内部管理の一環として被監査部門等が実施する検査等を含まない。」(金融庁「保険会社に係る検査マニュアル」)と規定している。
従来の事務的な手順に関する検査に対して、経営の内部に関する事項に踏み込んだ監査が求められていることが分る。このような要求に従うためには、従来の検査部以上の権限が与えられる必要がある(従来の検査部が、経営判断に属する管理体制の評価、改善方法の提言などを行うことは考えられなかった)。
4.2.2コンプライアンスを有効に機能させるための方策
繰返しになるが、コンプライアンスを機能させる魔法のような方法がある訳ではない。しかし、企業のコンプライアンスを崩壊させることは簡単である。コンプライアンス違反を無視すればよいのである。それ自体が発覚して企業が糾弾されるリスクは小さいかもしれないが、コンプライアンス違反が放置される現状を目の当たりにした従業員は、自らも同じことを繰り返して行く。遠からずして企業のコンプライアンス態勢はずたずたになるであろう。
コンプライアンス違反に結び付く芽をひとつずつ地道に潰していくしかないのである。
しかしながら、コンプライアンスを守り易い体制を作ることは可能なのではないだろうか。コンプライアンス違反に結び付く芽を潰すといったが、コンプライアンス違反を誘発するような体制をそのままにしておいたのでは、コンプライアンスの確立はできない。一方で、業務推進、営業成績アップを至上目的としながら、コンプライアンスの確立を叫ぶのは、長期的にはともかく、短期的にはアクセルとブレーキを同時に踏みっぱなしにしているようなものではないだろうか。そのようなことをすれば、エンジンかブレーキか(あるいは他の部品か)が壊れてしまう。しかし、ブレーキのない車でアクセルを踏みっぱなしにすることは単なる危険行為であるし、アクセルのない車でブレーキを踏んでいれば、動かない。車を運転するには、アクセルとブレーキを必要に応じて適切に使い分ける必要がある。
生命保険会社においては、前述のように短期的な営業成績を基準に営業職員を評価しながら、同時にコンプライアンスを求めている。これは、コンプライアンス違反を誘発する土壌の中でコンプライアンスの確立を求めているようなものなのではないだろうか。
もし、そうであるとすれば、どのような方策がコンプライアンスを確保しながら業績を伸ばせる方法として考えられるのであろうか。
5.生命保険会社への提言
取締役の忠実義務等を果すことは最低限必要なことであるが、それ以上に、従来からの営業方針を改めることが要求されていると思われる。従来から、生命保険は人海戦術を駆使した販売方法が主流であった。しかし、生命保険の加入率が一巡し、これからは生命保険の内容見直しの時代に入っているのである。従来の人海戦術を中心とした販売戦略は機能しなくなっている。
その場合、どのような販売戦略が考えられるのであろうか。現在でも、新しい保険は開発されており、そのような商品へのニーズがなくなった訳ではない。むしろ、顧客に適応した木目の細かいサービス・商品を提供することによる顧客の囲い込みの時代に入ったのである。前述のように顧客の生命保険に対するニーズは時間の経過とともに変化するのが当然なのである。そうであるとすれば、それに応えることが生命保険会社にとって、新たな付加価値を生み出すことになるのである。どのようなサービス・商品を提供するのか。その選択を行う際にコンプライアンスが重要になってくるのである。顧客との付合いが一生であると思えば、あるいは一生嫌われずに付合っていただかなくてはいけないと思えば、短期的な損得を抜きにしてベスト・アドバイスを提供できるのではないか。
そのためにも、営業職員の評価制度は改められなくてはならない。人的資源として、営業職員は今後とも生命保険各社にとってなくてはならないものであろうが、その活用方法には変革が必要である。コンプライアンスを確立しつつ営業成績を上げていくためには、1年で4割も退職していく(あるいはさせていく)制度は改められなくてはならない。
しかも、人的資産としての営業職員は既に確保しているのである。営業職員を単なる営業を行うセールスマンではなく、生命保険のコンサルタント(現在既にそのような名称を採用している会社もある。ここでは、営業優先ではなく、顧客に適合した商品を適切に販売する相談と合意に基づいて行う販売員という意味で用いた。)として育てていく人事政策が要求されるであろう。
営業職員は長期的に保険のコンサルタントとして育てていくとして、どのように顧客を開拓していけばよいのであろうか。
企業にとっての財産は顧客だといわれている。保険会社にとっても、まさにその通りである。生命保険の販売において、既存顧客が財産であるとは、生命保険会社が用いる営業職員の教育用パンフレットにも書いてあることで、それ自体は目新しいことではない。しかし、この財産は適正に生かされていなかったのではないか。契約に入るまではあれほど足繁く通ってきた営業職員が加入した途端にパタッと現れなくなったという経験は誰しもあるのではないか。久しぶりに現れたと思ったら、どなたかお知り合いをご紹介ください、では、この貴重な財産を浪費しているといわれても仕方がないだろう。
例え契約時にベスト・アドバイスに基づいて生命保険に加入したとしても、時間の経過とともに必要な保険が変化していくことは前述の通りである。また、生命保険に加入して頂く場合に、家族構成はもとより、他社生命保険加入の状態などもかなり詳しく聴取しているはずである。このような情報は、生命保険の整理、見直しには絶対に必要な資料であり、保険に加入して頂いたのでなければ、入手困難な貴重な情報である。
既に営業している生命保険会社は、そのような膨大なデータを既に保有しているのである。しかし、新規契約に偏重したインセンティブ・システムがそのような情報の活用を妨げているのである。いま一度、自らの保有する財産の活用方法を考えるべきではないだろうか。
また、営業職員のルートとは別に、代理店を通した販売ルートがあることに簡単に触れた。この代理店を通した販売も、複数の会社の保険の取扱が可能になることによって、大きく変化しつつある。複数の生命保険を代理店(保険専門に複数の生命保険会社・損害保険会社の商品を扱うスーパーマーケットのような代理店も現れている)で見比べ、特定の保険会社に属さない専門の保険アドバイザーによるアドバイスを受け、保険商品を選ぶ時代が始まろうとしている。その場合、要求されるのは、他社に見劣りしない(別の言葉で言えば、他社と同じ)商品構成より、独自性のある(他社とは差別化した)商品開発力であろう。ただし、商品開発に関しては、コンプライアンスを中心とした本論文の趣旨とは外れるので、これ以上の言及は避けるものとする。
しかし、上記スーパーマーケットのような特別な代理店は別として、通常の代理店は生命保険販売以外の正業を持っているのが普通であり、その分顧客との接点が多様化している。代理店ルートも生命保険会社の財産であり、前述と同じように、財産の活用を考えるべきであろう。
6.結び
以上から、今までの営業形態が時代にはそぐわなくなっていること、生命保険会社の人海戦術に基づいた営業形態がコンプライアンスを実現する妨げになっていること、さらに、今後生命保険会社が営業を続けていくにはコンプライアンスの確保が条件となっていることが明かになった。
コンプライアンスを確保しつつ営業を推進するためには、従来とは異なった体制が社内的にも求められるのである。そして、その変革の資源は、実は社内に活用されないまま死蔵されてきたのである。
死蔵されてきた資源が適正に活用されれば、現在は危機的な状況にある生命保険会社も再び立ち上がることができるのではないだろうか。なぜならば、自己責任で自分の資産形成を行わなくてはならない現在に生きる我々にとって、保険商品は我々の厚生に欠くことのできないものだからである。
以上の提言をもって、本論文の締めくくりとする。
<資料1>三菱自動車リコール隠し事件
「「リコール隠し」4部門幹部が決定
=三菱自動車、全社的に隠ぺい工作(8月28日配信)
三菱自動車工業(本社東京都港区)のクレーム情報、リコール(回収・無償修理)隠ぺい事件で、欠陥を運輸省に届け出ず、勝手に販売店に指示してひそかに修理する「リコール隠し」の方針が、品質保証部、サービス、設計、製造の計4部門の幹部が出席した会議で決まっていたことが、28日、警視庁交通捜査課や運輸省の調べで分かった。会議で決定した方針に基づき、設計、製造部門などが「やみ修理」の実施方針を立てていた。
同課は、隠ぺい工作がクレーム情報隠ぺいの中心となった品質保証部だけでなく、全社的な規模で行われていたことを裏付けるとみて、今後、会議に出席した幹部から事情聴取する。
調べによると、同社ではユーザーからのクレーム情報は、本社の品質保証部に集められる。同部内で安全性にかかわると判断された情報は、同部長をヘッドとして、販売店との窓口となるサービス部門、設計、製造各部門の次長、課長クラスが加わった「クレーム対策会議」で議論。そこでリコールなどの対応が必要とされた案件については、部長クラスで構成する「リコール・改善対策検討会」に諮り、方針が決まる。
捜査対象となった1998年以降、乗用車「デボネア」や大型トラック、大型バス、小型バスの4件でリコール隠しが行われた。
この4件については、いずれもクレーム対策会議か、同対策会議と同じメンバーによる会議で、安全上問題があると判断された。しかし、会議ではリコールせずに、やみで修理することが決められた。
会議の決定を受けて、設計、製造部門が、やみ修理のやり方などの対応策を検討。サービス部門から販売店に回収や修理の指示を文書で伝達した。文書には「極秘扱い」「取り扱い注意」などと書かれた上、外部への情報漏れを防ぐ趣旨の注意書きが書いてあり、隠ぺいの徹底が図られた。」
(時事通信2000年8月28日配信http://www.jiji.co.jp/edit/topics/data2000/200008/0827mitsubishi/0828n4.html (09/11/2001))
<資料2>雪印乳業集団食中毒事件
「雪印乳業食中毒事件
約一万五千人が被害を訴え、戦後最大規模となった雪印乳業の集団食中毒事件。製品回収の遅れや度重なる対応の不手際で信用を失った同社は「顧客第一主義」を掲げて再出発した。しかし、事件から半年近くたった今も被害者との補償交渉は続き、売り上げも激減したままで、信頼回復への道は険しい。
▽食中毒の後遺症
「裁判しても勝てませんよ」。大阪府内の女性(30)は、雪印が提示した示談条件を拒むと交渉担当の社員にこう言われたという。「こっちが被害者なのに、まるで悪者扱いされた」。八月、慰謝料など約四十万円の支払いを求め大阪簡裁に調停を申し立てた。
女性は六月下旬、スーパーで買った雪印低脂肪乳を飲み、激しい下痢や吐き気に襲われ四日間入院した。“後遺症”で今も牛乳類は飲めないという。
雪印は事件後、約百人態勢の「お客さまケアセンター」を設置、補償交渉に当たった。広報部は「五千件あった交渉は約百件を残すだけになった」と被害者対応の順調さを強調する。
しかし、雪印の交渉態度に対する不満の声は多い。多くの被害者から話を聞いた田中厚弁護士は「統一した補償基準もなく、治療費以外は被害者の出方によって変えている」と批判。「場当たり的な対応で、事件発生当時の姿勢と変わらない」と手厳しい。
「社会とずれがあった」(西紘平新社長)との反省から、外部の有識者から提言を受けるために設けた「経営諮問委員会」も、座長に身内とも言える顧問弁護士を据えた。国民生活センターの島野康相談部長は「雪印はなにが一番の問題だったか、まだ理解していないようだ」とあきれる。
▽トップから転落
経営面でも雪印の前途は多難だ。事件の影響で売り上げが激減。九月中間決算では二百四十三億円の経常損失を出し、業界トップの座を明治乳業に明け渡した。
雪印製品はほとんどのスーパーの店頭に戻ったが、消費者は戻らない。十一月の牛乳などの売り上げも前年同月比五四%減の見通しで、安全性を軽視した代償はあまりにも大きい。
雪印乳業食中毒事件 雪印乳業大阪工場が製造した低脂肪乳などを飲んだ約一万五千人が下痢や吐き気などを訴え、飲み残しから黄色ブドウ球菌の毒素が検出された。その後、原料になった北海道・大樹工場製の脱脂粉乳の汚染が判明。大阪府警は同社幹部らを近く業務上過失致傷容廃で書類送検する方針。(共同通信)」
(京都新聞2000年12月19日 http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2000dec/19/16.html (09/11/2001))
<資料3>大和銀行 大阪地裁判決
「2000年9月20日
株主代表訴訟:大和銀旧経営陣に830億円賠償命令 大阪地裁
1995年に米司法当局に訴追された大和銀行ニューヨーク支店の元嘱託行員による債券取引を巡る巨額損失事件で、同行の個人株主2人と法人株主1社が「適切な管理、監督の措置をとらなかったため、銀行が損害をこうむった」として、85年〜95年に同行の取締役と監査役だった49人を相手取り、計14億5000万ドル(約1450億円)を同行に支払うよう求めた株主代表訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。池田光宏裁判長は「取締役の善管注意義務に違反した」などとしてニューヨーク支店長だった安井健二被告、事件発覚時の頭取だった藤田彬被告ら計11被告に計約7億7500万ドル(約830億円)を支払うよう命じた。株主代表訴訟としては、前例のない巨額の損害賠償。予期しない社員の犯罪で企業が損失を受けた場合にも、経営陣の監督責任があると判断しており、企業の経営責任を従来以上に重視した画期的な判決と言える。今後、企業経営に大きな影響を与えるのは必至だ。
事件は、同支店の元嘱託行員が84年から11年間で、米国債などの無断売買を約3万回も繰り返し、約11億ドル(約1100億円)の損失を出した。元嘱託行員は帳簿類を偽造して損失を隠していたが、95年7月に頭取に手紙で告白した。銀行側は、米国の連邦銀行法などに反して、米金融当局に2カ月間、事実を報告せず、同年9月、米司法当局に訴追された。同行は96年2月、約3億4000万ドル(約350億円)の罰金を支払った。
訴訟では、兵庫県と東京都の個人株主2人と、東京都の法人株主1社が、元嘱託行員の無断取引による損失と、同行が支払った罰金との合計額を返還するよう請求していた。「11年も不正取引を発見できず、損失を拡大させたのは、取締役と監査役の重大な職務怠慢」であり、「事実の把握後、米金融当局に速やかに報告しなかったために銀行が訴追され、多額の罰金を支払う結果を招いた」と主張した。
一方、被告側は「元嘱託行員による個人的な犯罪で、銀行は被害者。検査体制に不備はなかった。米金融当局に報告が遅れたのは、実態解明と原因究明を優先し、加えて、不確実な内容を報告すべきでないとする大蔵省の意向だった」と反論していた。 【和泉かよ子】」
(毎日新聞2000年9月20日http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200009/20/0920e051-401.html (09/13/2001))
参考文献
Bank for International Settlement (1998), Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations, http://www.bis.org/publ/bcbs40.htm (09/05/2001)
勝月 裕爾(2000)『改訂 金融コンプライアンスと法令ポイント』経済法令研究会
木村 剛(2001)『新しい金融監査と内部監査』経済法令研究会
金融庁「証券会社に係る検査マニュアル」http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/shouken.pdf (08/30/2001)
金融庁「保険会社に係る検査マニュアル」http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/hoken.pdf (08/30/2001)
金融庁「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/yokin.pdf (08/30/2001)
金融庁「証券会社に係る検査マニュアルについて」金検第170号http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/shouken.pdf (08/30/2001)
高 巌編著(2001)『ECS2000 このように倫理法令遵守マネジメント・システムを構築する』日科技連出版社
高 巌・國廣 正(1999)『金融機関のコンプライアンス・プログラム』経済法令研究会
大阪地裁第10民事部平成12年9月20日判決 旬刊商事法務1573号 (社)商事法務研究会
(財)生命保険文化センター(2000)「平成12年度生命保険に関する全国実態調査<概要>」http://www.jili.or.jp/PBx/f_res.html (09/04/2001)
(財)生命保険文化センター(2001)『2000年版生命保険ファクトブック』(財)生命保険文化センター
牛越 博文(2000)『日本版金融サービス法』日本経済新聞社