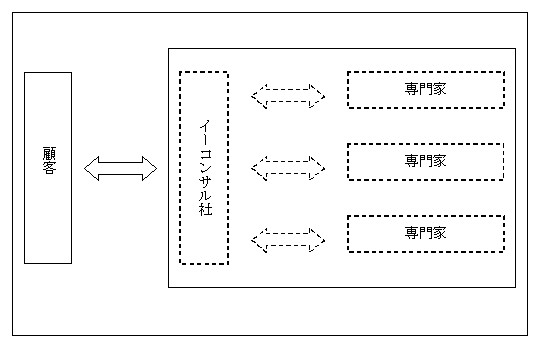
経営管理(MGM703)4クレジット
eビジネス時代のコンサルティング・ビジネス、イーコンサル社におけるビジネスモデル
Rushmore University
Global Distance Learning DBA
大國
亨
このコースワークを提出するにあたって、ここに記述されている文章/アイデアは、引用の表記がない限り、私の作品であります。また、私がこのコースの研究を手がけるまでは、このコースワークは存在しなかったことを確認します。
eビジネス時代のコンサルティング会社のあり方を考えるにあたって、イーコンサル社という架空のコンサルティング会社を題材として取り上げる。このイーコンサル社を題材として、このグループがいかなるコンセプトあるいはアイデアに立脚したものであり、どのような理念を中心としてまとまったグループであるかを検証し、今後どのような理念に基づくビジネス戦略を採用していくべきであるかを探る。
目次
1.はじめに
2.eビジネスの発展段階の類型
2.1第一段階 ドットコムの時代
2.2第二段階 eクリスマス
3.独占的知的サービス業の現状とイーコンサル社のコンセプト
3.1独占的知的サービス業
3.1.1独占的知的サービス業の現状
3.1.2相続問題に必要とされる知的専門家
3.2イーコンサル社
3.2.1イーコンサル社の組織
3.2.2イーコンサル社の理想とする組織
3.2.3イーコンサル社の実際の組成
3.2.4イーコンサル社 顧客との法的契約関係
4.eビジネスの将来
4.1現代のeビジネスの目指す方向
4.2ソリューション・プロバイダー
5.ビジネスモデル特許
5.1特許とは
5.2イーコンサル社のビジネスモデル特許
6.提言
6.1イーコンサル社の法人化
6.2イーコンサル社が行う事業
6.2.1アウトソーシング
6.2.2イーコンサル社が行う事業
6.3顧客ベースの拡大
6.3.1ウェッブベースの宣伝活動
6.3.2リレーションシップ・マネジャーとしての役割
7.結論
資料1税理士法の改正
資料2日本におけるビジネスモデル特許
参考文献
1.はじめに
eビジネスの時代といわれて入るが、その具体的な導入となると、業種、企業規模、経営方針などによって、千差万別の状態にある。本論文においては、ネットを使った知的サービスを提供するコンサルティング・ビジネスの新しいビジネスモデルを提示するものである。
なお、本論分においては、イーコンサル社という架空の企業を立ち上げることを前提として論文を書き進めてある。実際の事業化・企業化を目指して準備中であるが、諸般の事情により正式な名称は伏せてあることをお断りしておく。
2.eビジネスの発展段階の類型
eビジネスの時代といわれて久しいが、その本質についての議論は1、2年でやっと深まってきた。初期のころは、インターネットを使ったビジネスであれば何でもeビジネスであり、ホームページを開設さえすれば企業のIT化は完成したかの認識があった。また、インターネット上でショッピングができるようにすれば、顧客を安価に獲得でき、商機が広まるとの思われてきた。しかしながら、本格的にeビジネスに参入しようとすれば、膨大な初期投資を必要とすることから安価でもなく、顧客の獲得もホームページ開設により自動的にできるわけでもない。さらに、ネット・ショッピングといえども商品の配送や在庫・顧客管理が存在して初めて機能することが分かってきた。
これらの経験を踏まえて、現在は新しいeビジネスモデルが生まれようとしているのである。
2.1第一段階 ドットコムの時代
eビジネスの第一段階においては、各企業が競ってホームページを作り、そのホームページから企業が提供するサービスや商品の購入を可能にすることに力が注がれた。そして、企業のCI活動の一環として、IT化を誇示するため、会社名に.comを付け加えた名称が大流行したものである。
この段階でまず問題となったのは、企業がホームページを作ったとしても、必ずしもその出来栄えとヒット回数が関連しないことであった。例え検索機能を使った場合でも、ずらっと出てきたページの中から顧客がどのような優先順位で選択するかというと、やはり知名度があり、安心できる企業名から選択し勝ちであった。この場合における知名度のある企業とは、従来からのビジネスによって顧客に親しみのあるブランドのことである。顧客は新規さや値段だけを選好基準とするのではなく、企業規模に基づく安心感や、従来からの取引も選好基準としているのである。従って、苦労して作ったホームページの出来が顧客アピールに直接関連するわけでもなかったのである。また、一時流行となった.comにしても、現在ではその神通力も失われてしまったといってよいのではないだろうか。
この段階で明らかになったのは、eビジネスを立ち上げた新興企業が、企業のアイデンティティーをウェッブ上で表現、構築していくことが如何に困難であるかということであろう。
2.2第2段階 eクリスマス
次の段階でもうひとつeビジネスにとって大きな落とし穴となったのが、1999年の米国クリスマス商戦における大量の遅配事件であった。1999年において、米国においてはすでにインターネットでの買い物は一般化していた。しかもアメリカ経済は空前の好景気を謳歌していた。米国の消費者も、冬の寒空の下、混んだデパートへ買い出しに行ってレジで待たされたり、欠品に悩まされていらいらしたりするよりはインターネットのショッピング・モールで買い物をしたほうがはるかにスマートで快適であると思ったのであろうか、大量の注文が舞い込んだ。「11〜12月にネット・ショッピングを利用した人は2500万人、支出額は前年比2.25倍の70億ドルに達したという」(渡辺 邦昭『eマーケット経営革命』p29)。その結果、トイザらスのような大手までもが欠配・遅配のトラブルが相次いだそうである(渡辺 邦昭、同前p31)。
eビジネスの別の一面は、経営の効率性の追求にある。効率的な経営をするために、在庫を削減するのは有効な方法のひとつである。eビジネスのひとつの側面であるネットワークの活用により、以前より少ない在庫で経営が成り立つ。その代表例がトヨタのカンバン方式である。トヨタと部品業者の密接で綿密な関係によって成立したこのシステムを小売業のような従来型ビジネスにそのまま当てはめたことが問題を引き起こしたのである。いずれにしても、eビジネスと言ったところで、従来のビジネスにおいて必要とされる要件を欠いていたのでは、成功はおぼつかないことが分かるであろう。
在庫をどのように管理するかという問題に対するアプローチには2通りあるようである。eビジネスが本来持つ特性をより生かす方向を志向する場合には、徹底したアウトソーシングが要請される。この場合において、業務を依頼するアウトソース先は当然ながらその分野において秀でた機能を持つ企業でなくてはならない。上記ロジスティックス分野においては、例えばUPSが優れたサービスを提供していることで名高い。プロ用ギターの生産で有名なフェンダー社は、ロジスティックスにおいても高い評価を得ている。ところが、同社の内部にはそのような機能はない。「その秘密はユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)との電子的なリンクにある。かつては楽器が配達された後の重要なプロセスであったチューニングにいたるまで、あらゆる業務をUPSが処理している」(Peter
Keen and Mark McDonald, THE ePROCESS EDGE, (沢崎 冬日訳『バリュー・ネットワーク戦略』p11)。UPSは、顧客のビジネスを改革する、優れたロジスティックスに関する知識、アイデア、経験を顧客に提供することによって、従来のロジスティックス担当の企業が行い得なかったロジスティックスに係る周辺業務を取り込むことに成功したのである。
逆に、ロジスティックス業務をわざわざ内部に取り込むことにしたのがアマゾン・ドット・コムである。アマゾンはオンライン書店として、大規模な在庫を持たないことが売り物であった。ところが、現在では世界各地に大規模な倉庫を構えるにいたっている。倉庫のような現物資産に対して投資をすることは、当然同社の財務的な観点からは好ましいことではない。しかし、同社は財務的観点より、顧客を満足させることを選択したのである。同社はeクリスマスの影響を受けなかったという(Peter
Keen and Mark McDonald, ditto,p11)。
3.独占的独占的知的サービス業の現状とイーコンサル社のコンセプト
本章においては、独占的知的サービス業の現状と問題点を探り、そこから導き出される、現状の欠点を修正した、将来性のあるイーコンサル社のビジネスモデルを提示する。
3.1独占的知的サービス業
以下において、いわゆる士族、あるいは先生と呼ばれる独占的知的サービス業の現状が、サービスを提供している側は、独占を許容されている代わりに数多くの規制を受け、いわば自縄自縛の状態になっている。その経営形態は社会的地位の高さとは裏腹にほとんど個人経営である。
逆に、サービスを受ける側にとっては、専門家との日常的な接触は少なく、ましていくつかの事務所の専門を調べた上で見積もりを取って仕事を依頼する、などということは事実上不可能である。
サービスを提供する側にとっても、サービスの提供を受ける側にとっても実に不満足であり、改革が必要であるかを示す。
3.1.1独占的知的サービス業の現状
弁護士、公認会計士、税理士などの国家資格保有者を中心としてかたちづくられる独占的知的サービス業の実態は、いかなるものであるだろうか。これら独占的知的サービス業は、法によって与えられた独占権を享受していると同時に、独占権を与えられた範囲の業務を行い得ないという制約を持っている。このことは、それら知的専門家に対して自分の専門とする業務に関して、同業者以外の参入を阻止できるという特権を与えると同時に、そのような独占的知的サービス業に従事するものにとっては、他業種の業務については顧客からの需要があったとしても、その資格を保有していない限り応えられないという制約を与えることになる。現状では、重複する分野について部分的な相互参入は図られているものの、独占的知的サービス業に対する法規制が緩和されることは考えにくい。恒常的に企業と接している会計・税務等関連事務所や社会保険・労働保険等関連事務所にとっては、顧客からの法務相談などは多数寄せられるものの、専門外の相談に対して対応することは、例えその相談が回答し得るものであったとしても、法的に禁止されている場合も多いことから難しく、知り合いの事務所を紹介するといった俗人的な対応に留まっていた。
会計事務所などにとっては、顧客から寄せられる専門外の要望に効率よく応えることによって顧客満足を高める必要がある。逆に、法律事務所などは、いわゆる広告宣伝活動が許されていないため、極めて新規顧客を獲得することが難しく、自己の専門性を生かした、効率的な顧客開拓を行うことが課題となっている。
また、法律事務所、司法書士事務所などは、個人に対して国家から免許を受けるという形式をとっているため個人事務所が多く、それら事務所経営の実態は、その社会的地位の高さに反して、限りなく個人商店に近いものである。
逆に、顧客の側から見た不都合には以下のようなことがあげられるであろう。現在では、法律面からの規制により、法律問題は弁護士事務所もしくは司法書士事務所、会計や税務は会計事務所や税理士事務所と個別の契約を結ばなくてはならない。多数の事務所と顧問契約を結ぶだけの余裕と規模を備えた大企業はともかく、中小企業にとっては、税務・会計といった恒常的に関係を持つことが必要な事務所との契約はともかく、係争事件など法律問題については個別に契約を結ぶしか方法がなく、日常的な業務についてのリーガル・オピニオンをとることはかなりの出費と時間を取られることになり、活発には行われてこなかった。また、何か依頼したい事項があっても、そもそも弁護士などは敷居が高くてなかなか聞きづらいといった問題がある。いつ降りかかってくるか分からない訴訟事件などを考えれば弁護士などと顧問契約を結ぶことが望ましいことはいうまでもないであろうが、大企業でない限りその費用負担を正当化するのは難しいであろう。
顧客から見て選択肢が極めて限られてしまうことも問題である。現実には、税理士など恒常的に付き合いのある専門家のところに紹介の依頼がくることが多いようである。しかし、税理士などがその他の専門家を紹介するにしても、どうしても自身の知り合いを紹介するに留まり、その案件に見合った専門家を紹介するといったシステムにはなっていない。また、国家資格を与えられた独占的知的サービス業はその宣伝広告などに厳しい制限が加えられており、どのような分野の事件を専門にしているのか、以前にどのような係争事件を抱えていたのかなどを、事前にチェックすることは極めて難しいのが現状である。
3.1.2相続問題に必要とされる知的専門家
このことは、極めて総合的な案件である相続を取り扱う場合を例に考えれば分かりやすいであろう。大手の法人などでない限り、相続問題は起こる。相続は個人にとっても、小規模なオーナー会社などにとっても重大事であるが、当然ながら何度も経験することではない。
相続財産の内容にもよるが、相続問題解決に必要な専門家は、遺言などの取扱いについては弁護士、相続税の申告などについては税理士、相続財産に土地などが含まれていれば、その測量・評価に不動産鑑定士、土地家屋調査士、相続に関する登記に司法書士、個人が死亡した場合の生命保険その他の金融資産に関しては、金融の専門家などの協力が必要になる。
相続財産の分割が相続人の話し合いによってすんなりと決まるのであれば問題ないが、紛争が起きた場合などには、さらに相続人個人個人が弁護士などを立てる必要がある。また、弁護士といえども相続財産の処分などに関しては専門家とはいえないであろうから、これら専門家の間をコーディネートする人間も必要になる。
個別の問題に関しては、個別の専門家を依頼すれば済むことである。しかし、相続人の間に立って、公平に遺産を分割してくれる専門家は存在するのであろうか。実際には、相続を専門に取り扱う税理士、ファイナンシャル・プランナーもいるが、一般的に税理士やファイナンシャル・プランナーが相続を専門に取り扱っているわけではない。もし、相続人が個別に上記のような専門家に依頼した場合には、相続人本人がコーディネート役を務めなくてはならない。ファイナンシャル・プランナーなどがこのコーディネート役を勤めることが期待されるが、現状では認知度も低く、あまり活用されていない。被相続人の死亡という精神的なダメージを抱えながらそのような役回りをすることは大変である。
逆に、専門家側から見た場合に相続問題はどのような意味を持っているのであろうか。冒頭にも記したとおり、相続は顧客に何度も起きることではない。通常の数の顧客を抱える個人税理士事務所(通常10から20社くらい)であっても、相続は数年に一度ぐらいしか起こらないそうである。従って、税理士などでも、相続関係の税金に精通しているわけではない場合もあるそうである。また、相続は極めて個別的な問題で、すべての相続が異なっている。定型的な処理が難しいため、処理に時間がかかる。しかも、一回だけの仕事で、継続性がない。顧客サービスの観点を除けば、以後のビジネスに結び付けにくい。また、上記のように、相続財産の種類によっては、極めて多くの専門家の協力を仰がなくてはならない。個人的に、それだけのネットワークを作ることは難しい。また、依頼先の専門家が相続に関して詳しいかどうかは必ずしも明らかではない。そして、遺産分割に関して何の障害もなく話が進むのであればともかく、相続人間で紛争が生じている場合には、さらに手間と時間がかかる。一般的に相続は手数料の取れる案件ではあるが、継続性がなく、正直なところあまり係り合いたくないと思っている専門家も多いのである。
このように双方にニーズがありながらお互いに満たされていない現状を打破すべく、イーコンサル社を立ち上げることとなったのである。
3.2イーコンサル社
上記のような独占的知的サービス業の現状を踏まえ、その欠点を克服するために考えらたビジネスモデルがイーコンサル社である。イーコンサル社のコンセプトは、企業にたいして、法律、会計、その他知的サービスをワンストップ型店舗において顧客に提供することを基本的理念としている。
3.2.1イーコンサル社の組織
イーコンサル社はワンストップ型店舗を理念としているが、法制面などからの制限により、必ずしも理想的な組織がかたちづくれるわけではない。実際にはウェッブ上のバーチャルな組織としてはワンストップ型店舗を目指しているが、現実には会員事務所の連合体組織となっている。
3.2.2イーコンサル社の理想とする組織
イーコンサル社の理想とする組織形態は、図1に示したとおりである。顧客に対しては、イーコンサル社はあくまでもひとつの組織体として、あらゆる知的サービスを提供する。顧客から見ると、イーコンサル社はあらゆる種類の専門家を内部にそろえた知的サービスの百貨店となるのである。
顧客はイーコンサル社との契約を結ぶだけで、法律、会計、税務、金融、不動産など専門性の高い問題に対して、専門家からのアドバイスを得られるようになる。また、顧客は案件の内容をイーコンサル社に伝えるだけで、イーコンサル社側がその案件に見合った専門家を、もしくは複数の分野にまたがる案件の場合には複数の分野の専門家からなるチームを組成して処理にあたらせる。その場合に発生する中間的な事務(各事務所との連絡、調整など)はすべてイーコンサル社の内部において処理される。
図1 イーコンサル社 顧客との理念的な関係
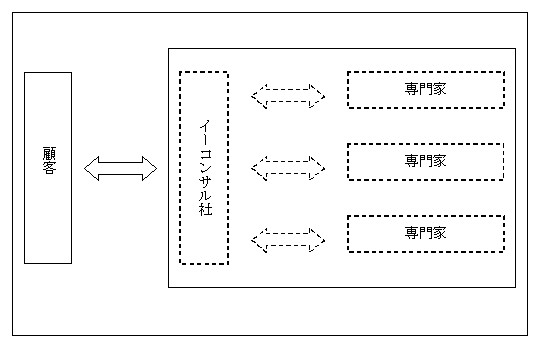
3.2.3イーコンサル社の実際の組成
イーコンサル社の実際の組成は、図2に見るとおり、独立した法律、会計事務所などの連合体である(イーコンサル社自体も、法的には法人組織をとっている)。これは、各種専門家を規制する業法の規制により、図1の組織を現実の企業としては作ることができないためである。
図2 イーコンサル社 実際の組織
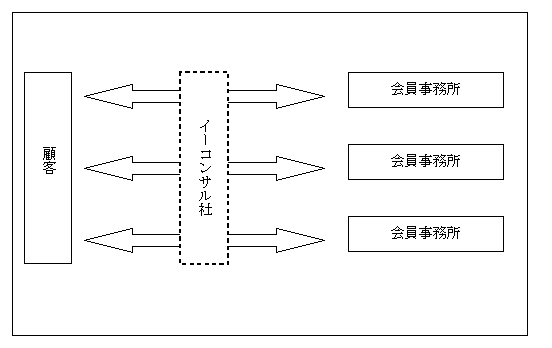
イーコンサル社に所属するそれぞれの会員事務所は国家資格保有者を中心とする専門事務所で構成されているのが特徴である。このような難関である国家資格の取得者に対しては、業法による保護政策がとられており、それぞれの仕事に対しては独占権が与えられているのが特徴である。法律分野においては弁護士、司法書士、行政書士が、会計分野においては公認会計士と税理士がそれぞれオーバーラップする分野をカバーしているものの、具体的な法律問題に対するアドバイスは弁護士に、会計監査は公認会計士に独占権が与えられており、無資格者は(例えその他の資格保有者であったとしても)当該業務を業とすることはできない。
また、弁護士法、税理士法などの規制により、それぞれの事務所を法人化することができなかった(弁護士法人、税理士法人の改正については後述)。例えば弁護士法第74条第1項において、「弁護士でないものは弁護士または法律事務所の標示又は記載をしてはならない」、同第2項において「弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない」と定めている。従って、弁護士となることができないイーコンサル社のような法人組織が法律事務所を名乗ることも、法律相談を法人として受けることもできないことになる。複数事務所の開設を認めている業法もあるものの、基本的にはこれら国家資格保有者に対しては個人事務所の開設が基本となっている。これは、独占を個人に対しては免許するものの、法人に免許することの危険性を見越しての処置であると思われるが、イーコンサル社のような共同事務所を設立する場合の障害となっている。
従って、イーコンサル社の基本理念としては、知的サービスを行うワンストップ型事務所を理念としているものの、現行法の基ではイーコンサル社自体が上記業務をイーコンサル社の名のもとで行うことはできない。顧客にとっては、様々な知的サービスをワンストップで行うほうが望ましいことは言うまでもない。そこで考えられたのが、ウェッブ上にバーチャルな組織としてのイーコンサル社を運営する方法である。バーチャルな組織としてイーコンサル社を組成することによって、現実の法律に基づいた組織とは別に、イーコンサル社の理想とするサービス形態をとることができるようになるのである。
顧客にはイーコンサル社の会員になってもらう形でイーコンサル社と契約を結んでいただく。理念的には、イーコンサル社の会員になることによって、各顧客はイーコンサル社の用意する各種の知的サービスを個別の事務所を自己で探す必要もなく、個別の契約を結ぶよりもはるかに安い手数料で享受することができる。それだけでなく、実際にこのような業務を複数の専門家に依頼したときに起こり勝ちである、同じ説明を何度も繰り返さなくてはならないといった煩雑な手間から逃れることができる。
また、所属する知的サービスを提供している各事務所にとっては、所属する各事務所が顧客を紹介しあうことによる顧客ベースの拡大を張ることができる、顧客情報を共有することにより、煩雑な顧客調査を行う必要がない優良顧客を獲得できるといったメリットが考えられる。
現時点では、(1)司法関連事務所(法律部門)、(2)不動産鑑定・調査・FP関連事務所(不動産部門)、(3)経営コンサルタント関連事務所(経営管理部門)、(4)金融・FP等関連事務所(金融部門)、(5)会計・税務等関連事務所(会計部門)、(6)社会保険・労働保険等関連事務所(労務管理部門)の6種類の独立事務所を会員事務所としている。ウェッブ上で前述各種サービスに対する顧客からの申し出を受けたイーコンサル社は各種事務所への割り振りを内部規約に基づいて行う。理念的には顧客へのインターフェイス機能を持つ事務所はイーコンサル社に限られることになる。
3.2.4イーコンサル社 顧客との法的契約関係
イーコンサル社の組織は、理念的には図1のような構成をとるものである。しかしながら、前述のような法的な要請により、実際の法律関係においては図1に示された組織には当てはまらない構成を採らざるを得ない。例えば、顧客からの依頼事項が法律問題である場合には、それに対する回答が文書で行われるにしろ口頭で行われるにしろ、弁護士がその名のもとに行う必要がある。例えイーコンサル社が依頼事項を受け付けたにしろ、現実の契約関係は顧客と法律事務所の間で発生していなくてはならず、その回答も弁護士が行わなくてはならないことになる。イーコンサル社の名のもとに回答することは弁護士法違反に当たる。従って、実際の案件に対しては、図2に見るように、個別の契約をそれぞれの業法の規定にのっとり結んでいただく必要がある。これは顧客にとっては従前の顧客、事務所間の関係と何ら進歩するところがないものであるが、現在の法的規制の下ではやむをえないものであると考えられる。
しかしながら、各種業法も規制緩和の方向にあり、将来的には図1に見られるような形態の組織がかたちづくれるものであると期待している。平成13年5月25日に成立した改正税理士法において、税理士法人を商法上の合名会社に準ずる特別法人として登記できる改正がなされたが、これはあくまでも税理士の集合体としての税理士法人に法人格を与えるものであって、イーコンサル社のような会社法人が税理士業務を行うことを認可するものではない(資料1参照)。本改正に関しては、より以上の自由化が与えられるとの観測もあり、その場合には、それによって設立された法人格をイーコンサル社に与え、組織の中核に据えることも可能であると思われる。実際の改正案は残念ながら不十分なものであり、イーコンサル社を運営していく上で税理士法人となるメリットもないことからイーコンサル社の税務法人化は採用できないであろう。
弁護士法についても、弁護士法人制度が平成14年4月1日より可能となる見込みである。弁護士法人の創設により、米国におけるロー・ファームに準じた組織が日本でも創設可能となる。これにより、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応できる体制を敷くことが可能になる。個人事務所であれば、担当弁護士の死亡その他の事情による弁護の中断も、法人としての弁護士法人が担当することにより、弁護士の移動などによる影響を受けずに案件を担当することができるようになる。ただし、弁護士法人の性格は税理士法人とほぼ同様であり、弁護士の集合体としての弁護士法人に法人格を与えるものであり、様々な業務を取り扱うイーコンサル社のような会社法人が弁護士業務を行えるようになるものではない(法務省「弁護士法の一部を改正する法律案要綱」)。弁護士法の改正については、特に添付資料を用意しないが、税理士法の改正点とほぼ同様のものである。
今後とも各種業法の改正が期待される。図1の理念をよりよく反映できる法的なバックグラウンドが整備された場合には、図2に見るイーコンサル社の法的な組織もそれに従って変更されていくものである。
図3 イーコンサル社
顧客と各事務所の実際の法律関係
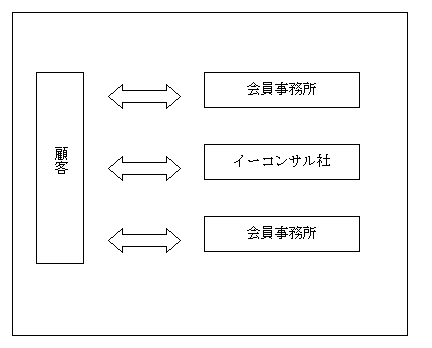
4.eビジネスの将来
4.1現代のeビジネスの目指す方向
ただ単にインターネットを用いたビジネスをすれば、eビジネスを名乗れるわけではないことは冒頭にも記したとおりである。eビジネスを実現する企業戦略には、どのようなものが必要とされるのであろうか。
イーコンサル社にとって、有益なビジネスモデルとして、「知識創造企業モデル」略して「知創型」といわれるモデルがある。「これまでのように既存のデータや情報を大量に収集し、処理するといった「情報消費型経営」から脱却し、新たな知識を創造し、活用することを中核とした経営体制、すなわち「知創型経営」を構築することが必要である」。また、「これまでの情報消費型経営は、目的を深く問うことなく、ひたすら効率を追求する経営であり、「How
to do」を優先してきた。そこでは、目的に対する手段の適合度や目標の達成度が、最も重要な評価基準になる。また、内と外を明確に区分した階層的な素引き構造の下で、できるだけ良質な人材を集めて、日常業務の改善・改良に力を入れることが求められてきた」(寺本 義也、岩崎 尚人(2000)『ビジネスモデル革命』p19)と書かれている。そして、他社との差別化を図れぬまま、際限のない価格引き下げ競争を強いられてきたのである。これを簡潔に図に表したものか下図である。
|
|
情報消費型経営 |
知創型経営 |
|
目標 |
効率性追求 |
創造性実現 |
|
評価基準 |
手段的 |
審美的 |
|
戦略 |
横並び |
独自化 |
|
組織構造 |
クローズドな階層的 |
オープンなネットワーク型 |
|
資源 |
有形固定資産 |
無形知的資産 |
|
コア人材 |
同質的 |
異質・異能 |
|
ビジネスモデルの原理 |
収穫低減 |
収穫逓増 |
(寺本 義也、岩崎 尚人(2000)『ビジネスモデル革命』p20)
従来型の事務所経営から、イーコンサル社への変革を的確に表しているといえるだろう。
従来から、知的専門家として、専門知識や顧客知識を蓄積することは常識として行われてきたのであろうが、個々の事務所に専門知識や顧客情報が蓄積されるだけで、それを有機的に結び付けてビジネスの創造に結び付けていくことはなかった。イーコンサル社では、顧客情報を蓄積、データベース化して共有の財産として使うことを目指している。eビジネスにおいては、顧客情報自体が価値を持っているのである。個々の事務所には膨大な顧客情報が眠っているはずである。眠っていた貴重な資源を表に出し、活用するのがイーコンサル社の役割となるのである。
また、コア人材に注目していただきたい。もともとが専門家の集団であるイーコンサル社の構成員は、その意味ではスペシャリストであり、ゼネラリストではない。しかし、イーコンサル社のような組織を使いこなそうとすれば、自身はある特定の分野のエキスパートになることが要求されるばかりではなく、イーコンサル社に備わる他の業務機能を使いこなせるようにならなくてはいけないのである。その意味で、知創型経営の分野で、プロデューサー&エキスパートという一見相反する能力が要求されていることが理解されるであろう。
ただし、同一人物がその両者を兼ね備えることは、実はかなり難しい。ある分野における専門家が他の分野の専門家に仕事を依頼する場合、どうしても、後は良しなに、となりやすい。これは、他の分野に専門知識がないため、口出しを控える、という意味のほかに、逆に依頼を受けた場合には、100%自分に任せてほしい、という意思表示の意味合いもたぶんに含まれているのではないだろうか。そのような意味から、イーコンサル社単体では、よりプロデューサー的な側面を重視したビジネスモデルを想定している。詳しくは後述するが、イーコンサル社ではプロのセールスマン、リレーションシップ・マネジャーとしての側面を重視したビジネススモデルを実現しようとしている。
4.2ソリューション・プロバイダー
ビジネスモデルの進化という観点から上記を俯瞰すると、以下のように言い換えることができるであろう。
まず最初に生まれたビジネスモデルは、単純に製品を作って売る、いわばコンピュータのハードウェアの販売に留まるモデルである。計算機械としてのハードウェアは実現したが、何のために計算するのか、どのように利用するのか分からない、といった時代である(コンピュータに関しては、当初は明確な軍事目的が存在していたのであるが、ここでは触れない)。しかし、製品を作れば売れる幸福な時代は長くは続かない。
第2世代として、ソフトウェアをハードウェアと結び付けて販売することが行われるようになる。いわゆる汎用のソフトウェア(例えば、汎用のプログラム言語)を付加するばかりではなく、特定業務に特化したソフトウェアの開発も行われるようになる。実は、初期のコンピュータにおいては、制御言語の数が少なく、その大半がいわゆる汎用言語であったため、その汎用言語を駆使して特定の業務に用いるプログラムを個別に作成することが必要であった。その意味では、コンピュータは初めから、ソフトウェアとは切っても切れない縁で結ばれていたといえる。しかしながら、この段階における、ハードウェアとソフトウェアの合体した商品として最も特徴をよく表しているのは、いわゆる家電製品である。いわゆるマイコンを組み込んだ製品群、あるいはこの時代に大きく発展した日本語ワープロなどがその例としてあげられるであろう。これら製品の大きな特徴は、従来型の何でもできる可能性は持っているのに、いざ動作させようとするととてつもなく手間のかかった従来型の汎用機から、小型の専門機器に移行したことにある。足し算をするのに電卓であれば何の手間もかからないのに、汎用機にプログラムを書き込んで計算させるとかえって手間だけがかかるのと同じである。
この考え方をさらに敷衍したのが第3世代のビジネスモデルである。これは、単純なハードウェアとソフトウェアの組み合わせでなく、それを顧客の要求に合わせてパッケージして、商品にするのである。それも、いわゆる「お客様の要求に応えてプログラムを書き換える」といったものではなく、顧客の抱える問題に対するソリューションをパッケージの形で提供するのである。この場合に、提供するのは、単純な製品(ハードウェア+ソフトウェア)ではなく、業務上の提案といった純粋なソフトウェア(別の言葉でいえばコンサル業務によるソリューションの提供)の提供までが含まれるのである。現在、多くのコンピュータ・メーカーは、製品の提供ばかりではなく、ビジネス上のソリューションを提供するソリューション・プロバイダーであることを目指し、様々な業務(コンサル業や金融業その他)を手がけるコングロマリットを目指している。
それでは、イーコンサル社のビジネスモデルはどこに属しているのであろうか。上記第3世代のビジネスモデルも、前章でふれた情報消費型経営モデルの、「クローズな階層型」組織を前提としている。もちろん、現在でも、例えばあるコンピュータ・メーカーが顧客にあるソリューションを提供する場合に、使用するのは必ずしも自社製品ばかりではなく、場合によっては競合他社の製品を使用することもあるあろう。しかし、様々な業務に進出する際に、第一義的には自社、それができない場合には他社との提携をもとにビジネスを展開していく手法は、やはり「クローズな階層型」組織を前提としているといってよいであろう。そうであるとすれば、第4世代のビジネスモデルは、イーコンサル社のような「オープンなネットワーク型」経営を前提としたネットワークを前提とした会社、あるいは、バーチャル・カンパニーが台頭してくるのではないだろうか。
イーコンサル社でも、無制限の参入退出を許しているわけではなく、会員制といった制度を前提としている。しかし、バーチャル・カンパニーの特徴である「オープンなネットワーク型」という点はよく表現されている。
5.ビジネスモデル特許
今後のビジネスを他と差別化した環境のもとで展開していくことを期待するのであれば、ビジネスモデル特許を取得することは、優れた武器になりうる。実は同様の計画はほかでも行われており、特許取得の計画もあると聞く。競合他社が特許を取得することは、その他各社は同様のビジネスモデルを使用することはできなくなる。場合によっては、その市場から締め出されることを意味する。そのような事態を避け、優位性を維持すべく、イーコンサル社も当初より、ビジネスモデル特許の取得を画策している。
5.1特許とは
特許の本来の目的は、新しい技術を保護するものである。特許法第1条に、「この法律は、発明の保護及び利益を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」とあるように、新しい発明の独占使用を特許権者に認めることにより、その利益を保護し、さらなる発明を促す効果を狙っている。発明や考案は、具体的な物体の所有権とは異なり、制度による保護がなければ、発明者が独占的に支配することはできない。逆に、ある発明を秘密にしておけば、発明自体は独占できるかもしれないが、発明を売却することもできないし、それを利用して利益を得ることもできない。また、社会全体の効用を考えた場合にも、発明が秘匿されることによって発明の有効利用が妨げられる上、情報が社会全体で共有されないため、同じ物を発明するための支出が社会全体で繰り返される無駄が生じる。
特にビジネスモデル特許の場合には、制度的な保護がとられない限り容易に模倣者が現れることが想像できる。無制限にビジネス特許を認めることは、市場における健全な競争を妨げるとの議論もあるように、競争原理の観点から見れば好ましいことであるかもしれないが、資本力のない中小企業にとっては、新規事業を開拓する意欲をそぐ結果となる。そこで特許制度を設け、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権を与えて発明の保護を図るとともに、その発明を公開して更なる技術の発展を図るものである。
日本におけるビジネスモデル特許については、資料2参照。
5.2イーコンサル社のビジネスモデル特許
イーコンサル社の組織の章で触れた事項で、特許性が認められるのであろうか。「インターネットなどを活用した事業モデルを対象とするビジネスモデル特許の成立にブレーキがかかり始めた。ネットベンチャーの原動力でもあったが、日米ともに特許当局が審査の厳格化に乗り出したためだ。企業も「何でも特許」ではなく、事業としての「質」を重視した出願が課題になってきた」(2001年8月7日付日本経済新聞)そうである。米国で特許論争を引き起こしたアマゾン・ドット・コム社の「ワンクリック特許」も、日本においては2001年5月に特許拒絶の仮決定がなされている。
確かに、各種知的サービスを行う専門家の集団は業法の規制もあり存在はしていなかった。また、各種知的サービスを集中的に受け付けるイーコンサル社のような組織もなかったことは事実であり、発明の要件は満たしているかとも思える。
しかしながら、新規性、進歩性の観点から見ると、それ以前からの慣行として各専門家が協力して業務に当たることはありえたわけであるし、この組織がインターネットというハードウェアを介さなくては存立しえないわけではない。時間的制約が緩いのであれば、手紙のやり取りでも代用できる。もし、インターネットというコンピュータという自然法則を介さなくてもイーコンサル社の理念が実現できるのであれば、ビジネス方法そのものを特許申請することになってしまうので、特許は認められないことになる。
実際には、現在のアイデア段階では特許取得は困難であると判断され、特許申請は見送られた。しかし、冒頭にも触れたとおり同様の仕組みを模索している競業他社も多い。今後、法制面の変化、あるいは現在進めているシステムの開発の進展によってより優れた特許取得可能なビジネスモデルが可能となった場合に備えて準備をすすめておく必要はあると思われる。また、このような論文の形で当該ビジネスモデルについて発表しておくことは、今後他企業が同様のビジネスモデルを特許申請した場合における有効な反証手段となる。大変消極的な防御手段ではあるが、このような形で発表しておく場合、自社が独占的優位を保つことはできないが、少なくとも同じビジネスモデルを使用し続けることは可能であり、市場から退場を余儀なくされるといった事態は避けられる。
6.提言
6.1イーコンサル社の法人化
イーコンサル社には、独立した法人格を与えることが好ましいと考えられる。前述のように、イーコンサル社と顧客間で会員契約は結ばれるものの、個別の契約はイーコンサル社と顧客間ではなく、各会員事務所と顧客の間で結ばれる。また、イーコンサル社の性格が極めてバーチャルなものであるから、必ずしも法人格は必要ないとの見方も出来るが、少なくとも顧客と会員契約を結ぶのであるから、単なる「人格なき社団」では、顧客の信用も得られないであろうし、何らかのトラブルが起こった場合にも、法人格を持って対処したほうが好ましいと思われる。
6.2イーコンサル社が行う事業
上記ビジネスモデルからは、コンサル業以外のどのようなビジネスがイーコンサル社に期待されているのか、あるいは将来展開をしていく場合に可能であるのかが、必ずしも明らかではない。以下において、バーチャルな組織としてのイーコンサル社の行う事業のほかに、法人組織をもつイーコンサル社がバーチャルな組織の中でどのような業務を展開していくことがそのメリットを最大限に生かしていくことになるかを検証する。
6.2.1アウトソーシング
イーコンサル社のアイデアは、そもそも独占的知的専門家の事務所と顧客の関係を以下に改善するかというとが発想の原点にある。しかしながら、イーコンサル社は法人格を備えた会社として設立されるのであるから、その企業を対顧客だけではなく、対会員事務所との関係においても、活用することが可能であろう。いわゆるB to Cビジネスである。
いわゆるeビジネスの活用方法として、アウトソーシングがあることは、前述のとおりである。自社ですべての業務をまかなうことが困難な場合には、外注するということは、実はeビジネスを持ち出すまでもなく、以前から広く行われてきたことである。ある会社が製品パンフレットを印刷する場合には、レイアウトを広告企画会社に作ってもらい、印刷会社に印刷を依頼することが当然のように行われてきた。また。企業活動において必要とされる事務用品なども、当然のように外部の業者から購入している。これらも実はアウトソーシングの一環であるといえるだろう。
しかし、eビジネスが可能にしたアウトソーシングの特徴は、上記のようないわば企業活動の根幹にかかわりのない枝葉の部分におけるアウトソースではなく、企業活動の根幹といえるような部分のアウトソースをも可能にしたことにある。例えば、工場を持たない製造業、在庫を持たない小売業、店舗を持たない小売業などなど。これらはいずれも従来型のビジネスモデルにおいては、必要欠くべからざると思われていた企業の主要なインフラをアウトソースによってまかなっているのである。
このようなアウトソーシング戦略をイーコンサル社に当てはめるとどうなるであろうか。イーコンサル社はそもそも独占的知的専門家の集まりをその母体にしている。実際のコンサルを行うのはイーコンサル社ではなく個々の会員事務所なわけであるから、正に会社の主要な業務をアウトソースしているといってもよいであろう。
逆に、イーコンサル社を個々の会員事務所が行うアウトソーシングの受け皿として活用する場合には、どのような業務を受け持つことが考えられるであろうか。
6.2.2イーコンサル社が行う事業
イーコンサル社が法人格を持ったとしても、実際のコンサル業務は会員事務所が担当することになる。顧客との間に発生する料金も、個別の事務所で徴収することになると思われる。しかし、案件によっては複数の事務所が係る場合も想定される。そのような場合には、イーコンサル社で一本化して料金を徴収したほうが分かりやすいのではないだろうか。それだけではなく、各事務所に代わって、いわゆるバックオフィス的な業務を一括して行うことも考えられる。
また、イーコンサル社が対顧客取引の窓口となる場合には、イーコンサル社が会員事務所の顧客管理データベースの基地としての役割を果たすことも考えられる。現在は当然のことながら、各事務所において顧客情報を個別に管理している。イーコンサル社の目的のひとつに、優良顧客ベース(つまりそれぞれの事務所とすでに取引実績を持っている)を共有することが考えられている。その場合、管理の無駄を省く意味からも、イーコンサル社が顧客データベースの管理を行うことが考えられる。
また、顧客のデータベースを管理するのであれば、そのデータベースを会員事務所が活用できるようなインフラの整備も必要になる。本格的なLANシステムなどが必要であるかどうかはデータベースの規模、利用度などに基づいて検討されなくてはならないが、いずれにしても何らかのシステムを備えなくてはならないことは明らかである。その場合、データベースの構築から維持管理にまで責任を持つのがイーコンサル社ということになるのは当然であろう。
6.3顧客ベースの拡大
日本においては各種専門家が免許を与えられている代わりに宣伝が出来ないなど各種の制約を加えられていることは前述のとおりである。そのような法的制約は、直接的にはイーコンサル社には加えられないので、ある程度の宣伝活動などが可能になるであろう。宣伝活動にも、ウェッブ上で行う宣伝活動と、実際に訪問を行って顧客を拡大していく方法と考えられる。
6.3.1ウェッブベースの宣伝活動
いくらすばらしいホームページを開設しても、それだけではビジネスが成立する(お金が取れる)わけではない。逆に、無料で多くの情報が公開されているのがインターネットであるから、以下にそれらと差別化し、顧客に実際にお金を使ってもらうことが課題になっている。これは、何も新しいビジネスモデルではなく、例えば遊園地において収入は入園料のみで得られるのではなく、乗り物に乗ってもらったり、敷地内で飲食をしてもらったり、お土産を買ってもらうことも立派なビジネスモデルの一部なのである。それでは、どのような手段を用いて入園してもらうのであろうか。入園してもらわない限り、中でお金を使ってもらうこともできない。
eビジネスにおいて最大の問題はここにある。実際にホームページにまでたどり着いてくれネットサーファーも、その時点では潜在顧客であるのか、ただ単にネットサーフィンをしていてたどりつたのかは分からない。宣伝によって遊園地の前まで来てくれたのであれば、入園の目的であろうとは想像がつくが、インターネットの場合には定かではないのである。そこで、実際にお金を払ってくれる顧客を探すのにどのような手法が用いられるかというと、いわゆる無料サービスを提供することが行われている。
無料サービスをうまく活用した例として、MicrosoftによるHotmailの買収(1998年、対価は400億円といわれている)がある。現在ではあまり珍しくない無料のメールサービスであるが、なぜMicrosoftはHotmailを買収したのであろうか。無料メールの会社などは、商品を無料で提供しているので、大した売上もないし、そのテクノロジーもおそらくMicrosoftにとっては児戯にも等しいと思われるのに、である。Microsoft
がほしかったのは、実はこの時点で900万人とも言われるユーザーだったのである。当時米国におけるプロバイダー大手のAOLが1200万人とも言われる顧客数を誇っていたのに対し、Microsoftのmsn.comは会員数が100万人しかいなかったのである。そこで膨大な顧客ベースを持つHotmailを買収することによって、一気にキャッチアップすることを狙ったのである(野口 芳延『ネットビジネス 勝者の条件』pp20-21)。つまり、とにかく遊園地の入り口(msn.comのサイト)まで来てくれる人数を増やすことによって、実際に入場してお金を使ってくれる人を増やすことを狙ったのである。
この手法はイーコンサル社のビジネスに適応できるであろうか。イーコンサル社で提供可能な無料サービスにはどのようなものがあるであろうか。考えられるものとしては、無料コンサルがあげられる。実際、各種専門家のホームページを閲覧していると、いわゆる無料サービスをうたっているものが多いことは事実である。しかし、無料サービスにはいくつかの問題がある。まず、回答の責任問題である。正式な契約もないままに顧客の質問に答えることは、危険を伴うし、第一、ネット経由の不完全な情報に基づいて回答する場合には、きちんとした回答を作成できない事態も考えられる。回答のために完全な情報を入手しようとして面接などしていたのでは、完全にコスト倒れになる。逆に、通り一遍の回答をするだけでは、顧客の満足は到底得られず、将来の顧客獲得に役立つとは思えない。また、このような無料で提供したコンサルの場合、顧客は無料を前提としてくるので、継続率が大変低いそうである。つまりただだからコンサルを依頼するのであって、お金を払うことは全く考えておらず、従って有料となる2回目からのコンサルには興味を示さないのである。逆に、割引券をつけた場合のほうが、コンサル依頼の継続率は高いという。割引でもなんでも、お金を支払うことを前提としてコンサルを受けるのであるから、その時点で顧客の満足を得られれば、継続の可能性が高まるのである。
イーコンサル社のようなコンサル会社にとっても、顧客数の増加は好ましいことである。しかし、無差別な顧客勧誘は、同時にターゲットを明確にした勧誘方法ではない。イーコンサル社の潜在的顧客というのは、かなり限られたニーズを持った顧客と考えられるから、無差別勧誘にはなじまないものがある。また、無差別の顧客勧誘は、不良顧客の増大を予想させる。今まで信用第一と思われてきた専門家集団にとって、不良顧客を招きいれるような施策は受け入れられないのではないか。また、もし不良顧客が混入した場合には、イーコンサル社の存立にもかかわるような影響が出ることが考えられることからすると、残念ながら、eビジネスの典型的な手法である無料サービスの提供による顧客ベースの拡大は残念ながら採用できない手法であろう。むしろ、初期加入者や継続加入者に対する特典を付けるといった対応のほうが好ましいといえるであろう。
6.3.2リレーションシップ・マネジャーとしての役割
それでは、実際に顧客の開拓を、足を使って行うリレーションシップ・マネジャーとしての役割を果たせないであろうか。知的専門家の事務所は、実際には個人事業に近いことは前述のとおりである。実際には先生と呼ばれる人間がリレーションシップ・マネジャーの役割を自ら果たしているのである。しかしこのような業務はアウトソース可能なのではないだろうか。
今までは、ある特定の業務の専門家として、例えば税理士が顧客開拓をするのであれば、税務の専門家として顧客開拓を行ってきた。しかし、顧客のニーズは多様で、それ以外の専門家に仕事を依頼したのかもしれない。イーコンサル社が顧客開拓を行う場合には、様々な能力を備えた専門家集団の代表として潜在的顧客のもとへ赴くのである。その場合において、優れたリレーションシップ・マネジャーに要求されるのは、具体的案件に対する専門家としての処理能力ではない。そうではなくて、イーコンサル社に存する個々の能力を使いこなして顧客の要求するサービスを作り出すプロデューサーとしての能力なのである。
このことは、金融機関での例を見れば明らかであろう。内外の一流の金融機関には、各種金融のスペシャリストがそろっている。しかし、実際に顧客との間を取り持っているのは、リレーションシップ・マネジャーと呼ばれる人々である。この職種に要求されるのは、必ずしも特定の金融商品の専門家としての知識ではない。金融商品といっても、守備範囲は広いわけであるから、一個人がすべての商品の専門家になるなどということは考えられない。この職種に要求されるのはむしろ、顧客のニーズをすばやくピックアップして、それを解釈、それを各種専門家に伝え、各種のソリューションを編み出させ、それを顧客に提案していくのである。
外資系の金融機関が非常に提案型の営業に優れているといわれるが、実はこのような能力に優れているのである。実際に、各種様々な金融商品が日々生み出されていくが、その中で本当に革新的なものは一握りしかない。逆に、その筋の専門家が見れば、デリバティブと麗々しく謳っていても、その仕組みが簡単に分かってしまうものがほとんどなのである。日本の金融界にも優れた人材は豊富にいるのであるから、一度世に出た商品のからくりを見破るのは簡単である。しかし、問題は、最初に顧客ニーズに合わせて商品設計をすることなのである。そしてその際に、優れたリレーションシップ・マネジャーを持っているかどうかで勝負は決まるのである。
また、このことは世界一のオンライン証券会社であるチャールズ・シュワブ・コーポレーション社長兼最高経営責任者であるデビッド・S・ポトラックが著書の中で別な形で触れている。「電子化した情報や取引のおかげで、シュワブの提供する商品には、すぐにその競争力を失ってしまう。そのため、唯一の差別化要因は、会社が顧客にサービスを提供する際のやり方にあり、また彼らの代理人として自ら新たな商品やサービスの開発をしていくスピードにある。」「この時のサービスのあり方つまり顧客はどんなふうに取引相手の企業を信用するとか、競合他社に先駆けてどれだけ新しい商品やサービスを提供できるかなど、顧客が取引のプロセスで経験するすべての事柄が相まって、企業間に差が生まれてくる。」(David
S. Pottruck and Terry Pearce (2000), CLICKS AND MORTAR, (坂和 敏訳(2000)『クリック&モルタル』p18))
このことをイーコンサル社に当てはめてみるとどうであろうか。同社は様々な業種の知的専門家をバックに抱えたスペシャリスト軍団であり、そのことを最大の売り物にしている。このことは、イーコンサル社は売込みをかけるのに最適なコンテンツを豊富に持っていることを示している。ただ、多様多種のコンテンツも、ただ単に所有しているだけでは宝の持ち腐れであり、有機的に結合することによって初めて顧客の要求に応えることができるようになるのである。もし、顧客のニーズに対して的確なソリューションを見出せるのであれば、個々の専門家が販売を担当するよりもはるかに大きな成果を期待できると思われる。今までの事務所形態ではそのような総合的な機能はなかなか期待できなかった機能であると思われる。イーコンサル社はそのような総合的な機能を売り物にしている会社であり、そのためにも個々の専門家とは異なったリレーションシップ・マネジャーの制度の導入は、競合他社との差別化にもつながり、また、リレーションシップ・マネジャーを有機的に組織の中で生かすことができれば、単なる他社差別化以上に期待できるものと思われる。
7.結論
以上のように、現状の法規制の下では、イーコンサル社は法人として法律相談を受けることができない、法律事務所を名乗れないなどの障害があるため、ワンストップ・知的サービス業というイーコンサル社のコンセプトを完全に実現することはできない。しかし、そのような障害を乗り越えてワンストップ・知的サービス業を実現されるためのバーチャルな組織としてのイーコンサル社と実際に法人格を持った、各種独占的知的サービス業者のアウトソースの受け皿としてのイーコンサル社を組み合わせることによって、以下のようなメリットを持った新しいビジネスの展開が望めると思われる。
イーコンサル社をバーチャルな組織にして、上記のような様々な業務を手がけることによるメリットはまず、サービスを提供する側にもたらされる。総合的なコンサルに要求されるさまざまな分野の専門家との協調にしても、ひとつの事務所を基本にしていた場合には、俗人的な関係に留まらざるを得なかった業務関係も、イーコンサル社のような仲介機関を介することによって、その業務に適した専門家とのコンタクトが簡単に取れるようになる。
第二のメリットは、顧客側にもたらされる。いわゆる士族、先生達は気位が高く、独立した事務所を構えている一匹狼であるために、悪い言い方をすればプロらしくない人種が少なからず含まれていた。実際にある業務を依頼したいと思っても、どこの誰がその分野の専門家であるのか分からず、いったん依頼してしまえば、いささかの不平不満があろうとも、担当を取り替えるなどということは考えられなかった。とにかく先生のご機嫌を損ねずに仕事をしていただかなくてはならなかったからである。ところが、イーコンサル社のような法人化された専門組織が仲介することにより、案件ごとにそれにふさわしい専門知識をもった専門家、あるいはそのチームを気兼ねすることなく使えるようになる。
法人組織を持ったイーコンサル社を活用してアウトソースの受け皿とすることによるメリットは、収入の道筋を多様化できることである。まず、イーコンサル社自体がコンサルを受け持てばコンサル料が期待できる。そのほか、上記のような多様な事業を手がけることにより、会員からの会員費、各種専門家へ業務を斡旋した場合には斡旋・紹介料、また、各種事務所の管理業務を一部肩代わりした場合にはマネジメント料、また、共通のベースで顧客データのデータベース化などを手がけた場合には、データベースの使用に対して、料金を徴収することができるであろう。
最後に、バーチャルな組織とすることによって、今後の法改正などに柔軟に対応してゆく可能性を残していることがメリットとしてあげられる。本文中にも記したとおり、ここ1・2年の改正は必ずしも満足行くものでもなく、イーコンサル社の業務が完全に自由化された訳でもない。しかし、今後とも規制緩和が続くのは確実と思われ、その場合の対応を容易にする意味からも、バーチャルな組織を保っておくことのメリットはあるものと思われる。
従って、本論文で述べたことは、2001年8月現在の法規制のもとでどのようなビジネスを展開していくかを論じたものであり、将来の法規制の改正に伴って、現実の組織は変化していくものであることをお断りしておく。
資料1 税理士法の改正
税理士法人制度の創設(第48条の2〜第48条の21関係)
1 税理士は、以下に定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人)を設立することができることとする。
2 税理士法人の社員は、税理士でなければならないこととする。
3 税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより税理士業務に付随する業務その他これに準ずる業務を行うことができることとする。
4 税理士法人は、設立の登記をすることによって成立するものとし、成立したときは、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならないこととする。
5 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負うこととする。
6 税理士法人の事務所には、その所在する地域の税理士会の会員である社員を常駐させなければならないこととする。
7 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のために税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となってはならないこととする。
8 税理士法人は、社員が一人になり、その後6月間その社員が二人以上にならなかった場合には、解散することとする。
9 合名会社に関する商法の規定(連帯無限責任、代表権等)等を準用することとする。
10 その他所要の措置を講ずることとする。
(財務省「税理士法の一部を改正する法律案要綱」)
資料2 日本におけるビジネスモデル特許
特許の基準は各国で若干の違いがあり、申請する国によって特許が成立したりしなかったりする。日本において特許で保護される発明に必要とされる様々な要件のうち代表的なものとしては、
l
特許法第2条に定義される発明であること
l
明細書の記載要件を満たしていること
l
新規性、進歩性があること
があげられる。
特許法第2条において、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と規定されている。発明に該当しないものとしては、エネルギー保存の法則や万有引力の法則などがあげられる。これらは法則そのものであって、人間によって発明されたものではない。また、自然法則に反する永久機関や、芸術活動の結果である美的創造物なども発明とはみなされない。
ビジネスモデル特許については、ビジネス方法そのものは、上記自然法則を利用していないので、日本では特許は与えられないことになる。ただし、ビジネスモデル特許については、ソフトウェア特許の概念が援用されており、ハードウェアとしてIT技術を用いる場合には、特許の対象となりうるとしている。
ソフトウェアにおいては、あるアイデアを具体的に実現するには、何らかの技術に依存することになる。その技術のひとつに、ITも含まれる。ITを活用することにより、ハードウェアとして新たな専用装置を創作しなくても、ソフトウェアの制御により、あたかも専用装置を創作したかのような効果が得られるのである(特許庁「ビジネス方法の特許について」)。
だからといって、既存のビジネスモデルをインターネット上に移行するだけでは、特許とは認められない。特許法第29条に規定する新規性や進歩性が求められるのである。例としては、市場調査・分析方法におけるアンケートを、インターネットを通して送付・回収するビジネスモデルが、単に送付・回収するための道具としてコンピュータネットワークを使用したに過ぎないとして退けられた申請がある(特許庁「特許にならないビジネス関連発明の事例集」)。
明細書の記載については、単純な記載漏れがあるといったことに留まらず、発明の詳細な記載において、ビジネス方法がコンピュータ上でどのように実現されるかが不明確であるといったものも含まれる。例としては、電子広告の選択方法に関する特許申請において、特許請求の範囲に記載された発明が、「電子広告の動作方法」とも「人が電子広告を選択する方法」とも把握することができるとして退けられた請求がある(特許庁同前)。不明確な申請に対して特許を与えることは、審査が困難であるといった現実的な理由とともに、事後的な特許の拡大解釈などを招きかねないので、認められない。
新規性・進歩性とは、当然のことながら、それ以前に日本内外で発表された発明ではいけないということであり、また、その分野の専門家が容易に思いつくものであってはならないということである。ここでいう発表に関しては、例えば自社のホームページに次期プロジェクト計画として公開した場合なども含まれる(ただし、特許法第30条に出願者自身が公表した場合には、6ヶ月以内に出願すれば、新規性を失わないとの例外規定が存在する)ので注意が必要である。進歩性に関しては、従来からあるシステムに容易に思いつくであろう新たな公知の技術を付加したような場合には、特許は認められない。例として、電子プリペイドカードによる決済に公知の技術である電子証明書により正当性を認証する処理を付加した特許申請が退けられている(特許庁同前)。
また、特許法第29条の冒頭に、産業上利用することができる発明と書かれている。ここでいう産業とは、一般的な製造業以外の農業、漁業など、広く含まれる。実務上は、「「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針」において、「「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型」にあたらないものは、原則として産業上利用することができるものとみなされる。
「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型としては、人間を手術・治療・診断する方法など、医療行為にかかわるものがあげられており、これらに特許は認められていない。ただし、医療機器や医薬品そのものは特許の対象となり得る。
大國 亨「ビジネスモデル特許戦略」より抜粋、一部加筆 (http://www.fpohkuni.com)参照
参考文献
原田 保、株式会社リンク総研編(2000)『eサービス』東洋経済新報社
法務省 「弁護士法の一部を改正する法律案要綱」http://www.moj.go.jp/HOUAN/BENGOSHIHOU/refer01.html
(2001/06/11)
Dr.
Ravi Karakota and Marcia Robinson (1999), e-Business Roadmap for Success,
(KPMGコンサルティング・渡辺 聡訳(2000)『e-ビジネス 企業変革のロードマップ』株式会社ピアソン・エデュケーション)
Peter
Keen and Mark McDonald(2000), THE ePROCESS EDGE, McGraw-Hill Companies
Inc., (沢崎 冬日訳(2001)『バリュー・ネットワーク戦略』ダイヤモンド社)
松本
直樹(1998)「金融ビジネス用システムの特許性」http://village.infoweb.ne.jp/~fwgc5697/SSB-SIG.HTM
(2000/11/22)
新谷 文夫(2000)『図解 eマーケティング』東洋経済新報社
野口 芳延(2000)『ネットビジネス 勝者の条件』日経BP社
David
S. Pottruck and Terry Pearce (2000), CLICKS AND MORTAR, Jossey-Bass Inc.,
Publishers, (坂和 敏訳(2000)『クリック&モルタル』株式会社翔泳社)
Don
Tapscott (1999), CREATING VALUE IT THE NETWORK ECONOMY, Harvard Business
School Press (DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部訳(2001)『ネットワーク戦略論』ダイヤモンド社)
寺本 義也、岩崎 尚人(2000)『ビジネスモデル革命』生産性出版
特許庁(2000)「ビジネス方法の特許について」http://www.jpo-miti.go.jp/info/interbiji0406.htm
(2000/11/22)
特許庁(2000)「第18回三極特許庁専門家会合結果概要」http://www.jpo-miti.go.jp/saikin/press120616.htm
(2000/11/27)
特許庁「制度概要」http://www.jpo-miti.go.jp/indexj.htm
(2000/11/27)
特許庁「「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針」http://www.jpo-miti.go.jp/PDF/Sonata/hobin/27/27-1.html
(2000/11/28)
特許庁「特許にならないビジネス関連発明の事例集」http://www.jpo.go.jp/techno/tt1303-090_jirei.htm
(2001/05/30)
特許庁「特許行政年次報告書2000年版」http://www.jpo.go.jp/tousi/nenzi2000.pdf
(2001/05/30)
遠山
勉「ビジネスモデル発明を特許出願するために必要な法的知識」http://www.ne.jp/asahi/patent/toyama/bm2.htm
(2000/11/22)
渡辺 邦昭(2000)『eマーケット経営革命』日経BP出版センター
山内特許事務所「ビジネスモデル特許コーナー」http://www.netwave.or.jp/%7Eyama-pat/biz.htm
(2000/11/27)
財務省「税理士法の一部を改正する法律案要綱」http://www.mof.go.jp/houan/151/houan/hou05b.htm(2001/05/29)