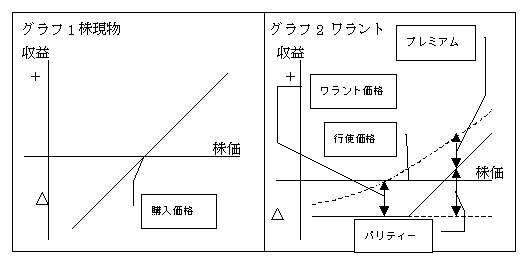
�o�c�Ǘ��iMGM701�j8�N���W�b�g
���Z���i������g���u���̎��ԂƉߋ��̔���
Rushmore University
Global Distance Learning DBA
�嚠
��
���Z���i�̔̔����Ɋւ���@���i�ȉ��A���Z���i�̔��@�Ɨ����j����я���Ҍ_��@������13�N4��1�����{�s�����B
���@�͂����������ҕی��ړI�Ƃ����@���ŁA���Z���i�̔��@�͂قƂ�ǑS�Ă̋��Z���i�̔̔��ɂ��āA����Ҍ_��@�͑S�Ă̏���Ҍ_��ɂ��ċK������@���ł���B�]���̏���ҕی�͎�ɋƖ@�ɗ��镔�����傫���A����ҕی�͏\���Ƃ͌���������B�o�ς̎��R���ɔ����Čl����҂̌o�ςɐ�߂�������d�v�������ɏ]���A���f�I�ȏ���ҕی쐭�]�܂�A���̈�Ƃ��ė��@�����肳�ꂽ�B
�{�_���ɂ����ẮA�܂����@����O�̏���҃g���u���̐��ڋy�ь���ɂ��č��������Z���^�[�̎������g���ĊT�ς���B
�����āA���ۂɑi�ׂƂȂ�������ɂ��āA�������g�A�ϊz�ی��A�O���Ďؓ���Ɋւ���i�ׂ����グ�A�ǂ̂悤�Ȏ����F����o�Ĕ����ɓ������������ǂ�B���@�{�s����A�i�ׂɂ����鎖���F��̌X���͓��P�������̂Ɨ\�z����Ă���B
����ɁA�����F��A�������R���A���Z���i�̔��@�A����Ҍ_��@�Ƃ̊W�ɂ����Ĉʒu�Â���B����ɂ���ẮA�����ɂ�����F�肪���@�ɂ������蓥�ݍ��������Ŕ����ɓ����Ă���Ǝv����B
�ŏI�I�ɁA���Z�@�ւɂ����鍡��̃R���v���C�A���X�̂�����ɂ��Ă̌��_�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
�ڎ�
1.�͂��߂�
2.���Z���i���������҃g���u���̎���
2.1���̓���
2.2�ʂ̋���
2.2.1�،���Ђ̎���
2.2.2�����̉���
2.2.3�ڋq�����̔c��
2.3���ݓI�ȋ��
3.�ߋ��̑i����
3.1�������g����
3.1.1�������g�Ƃ�
3.1.2�������g��������
����1
���i��
����2 ���i��
����3 �s�i��
����4 �s�i��
3.2�C���p�N�g���[��
3.2.1�C���p�N�g���[���Ƃ�
3.2.2�C���p�N�g���[������
����5
���i��
����6 �s�i��
����7 �s�i��
3.3�ϊz�ی�
3.3.1�ϊz�ی��Ƃ�
3.3.2�ϊz�ی��𗘗p���������ő�
3.3.3�ϊz�ی�����
����8
���i��
����9 ���i��
����10 �s�i��
����11 �s�i��
4.���Z���i�̔��@������Ҍ_��@
4.1���Z���i�̔̔����Ɋւ���@��
4.2����Ҍ_��@
4.3���Z���i�̔��@������Ҍ_��@�̓��e
4.3.1���Q�����Ǝ�����
4.3.2����
4.3.3�����`��
4.3.4�K��������
4.3.5�����̏ȗ�
4.3.6�_��E��������
5.���_
1.�͂��߂�
���{�ɂ����Ă����Z�r�b�O�o�����_�@�Ƃ��āA���Z���i�̔��Ǝғ��̎�舵�����i�������M���A�e��f���o�e�B�u�g�ݍ��ݏ��i�A�������g���Ƒ���ɓn��悤�ɂȂ�A���Z���i�̔̔��A���U������g���u������������悤�ɂȂ����B���Z���i�̔̔��ɍۂ��ċ��Z���i�̔��Ǝғ����[���Ȑ��������Ȃ�������A�ڋq���[���Ƀ��X�N�𗝉��ł��Ȃ������肵�����Ƃɂ��A���{����Ȃǂ̌ڋq�ɂƂ��ė\�z�O�̑��������������Ƃ��ĕ����ɂȂ��Ă���B�ڋq�ɑ�������`���͑����̏ꍇ�@����ɖ��L����Ă��Ȃ������B
���Z���i�̔��Ǝғ��ɑ���K���@�͑����̏ꍇ������Ɩ@�ɗ���ꍇ�������������A�Ɩ@�����݂��Ȃ����Z���i���w�������ڋq�E����҂̕ی�ɑ��Ă͓��R���Ӗ��ł��邵�A�܂��ڋq�̋~�ϋK�肪�Ȃ��ꍇ�����������B�ٔ��ɂ��~�ς����߂��ꍇ�A���Z���i�̔��Ǝғ��̐����`���̗L����A���Q�̈��ʊW�̗��ؐӔC���������ɂ���ȂǁA�ɂ߂ĕs���ȏ������ۂ���Ă����B�����̏ꍇ�A�ٔ��͒��������A���ʓI�ɋ����Q�����������ꂽ�ڋq�����������Ǝv����B
2.���Z���i���������҃g���u���̎���
���l���E���G���������Җ��ɑΏ����邽�߁A1984�N�ɍ��������Z���^�[�Ɠs���{���E���ߎw��s�s�̏�����Z���^�[���I�����C���Ō��u�S����������l�b�g���[�N�E�V�X�e���iPIO-NET�j�v���a�������B
���ݑS���ɒ[���ݒu�����̂�59�������A6��ށi��������k���A��Q���A����Ҕ��f���A���i�e�X�g���A���i�e�X�g���A���������Ə��j�̃f�[�^�x�[�X�����V�X�e���ł���B
�\1�͒n�������̂̏�����Z���^�[�����k��������э��������Z���^�[�̑��k�����t������������k�̌������W�v�������̂ł���B�Ȃ��A���v�͏��i�ʁi���i�̔̔��ɌW����́j�Ɩʁi���i�ł͂Ȃ��A�T�[�r�X�̒ɌW����́j�ɕʂ�Ă��邪�A���Z���i�͋��Z�E�ی��T�[�r�X�Ƃ��Ĉꊇ���Ėʂ̓��v�Ɋ܂܂�Ă���B
���Z�E�ی��T�[�r�X�ɑ��鑊�k�����͈�т��đ������Ă���i1985�N10,033���A1999�N77,528���j�B�܂��A���̑S�̂̑��k���ɐ�߂銄����1985�N�i377,135���j��2.7������1999�N�i686,369���j�ɂ�11.3�����߂�܂łɂȂ��Ă���B���e�I�ɂ́A�_��E���ɌW�鑊�k���ł������i1999�N58,605���j�A���Z�E�ی��T�[�r�X�ɌW�鑊�k��4����3���߂Ă���i���������Z���^�[�i2000�j�w������N��
2000�x���������Z���^�[�j�B
�\1
�ʂ̕��ތ����̐���
|
|
1985 |
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
�N���[�j���O |
12,583 |
15,841 |
15,124 |
14,974 |
14,102 |
13,574 |
13,005 |
|
�����^���E���[�X�E���� |
3,563 |
9,466 |
19,236 |
23,420 |
23,653 |
25,582 |
28,325 |
|
�H���E���݁E���H |
3,172 |
7,937 |
16,353 |
18,666 |
18,800 |
19,176 |
19,871 |
|
�C���E��C |
3,993 |
4,324 |
7,502 |
7,482 |
7,886 |
9,099 |
8,804 |
|
�Ǘ��E�ۊ� |
239 |
296 |
460 |
515 |
585 |
652 |
690 |
|
��� |
218 |
73 |
3,386 |
2,906 |
2,712 |
3,025 |
2,940 |
|
���Z�E�ی��T�[�r�X |
10,033 |
16,982 |
37,823 |
47,230 |
63,356 |
68,534 |
77,528 |
|
�^�A�E�ʐM�T�[�r�X |
4,139 |
6,383 |
9,886 |
16,808 |
24,574 |
26,086 |
32,746 |
|
����T�[�r�X |
1,049 |
2,247 |
3,888 |
4,438 |
5,300 |
6,093 |
6,775 |
|
���{�E��y�T�[�r�X |
14,857 |
22,982 |
51,504 |
40,854 |
39,480 |
47,239 |
54,778 |
|
�ی��E�����T�[�r�X |
6,058 |
11,323 |
15,820 |
18,014 |
20,385 |
22,579 |
24,928 |
|
���̖� |
9,308 |
8,186 |
13,587 |
13,270 |
15,791 |
15,550 |
17,456 |
|
���E�E���ƁE���� |
32,763 |
5,026 |
11,662 |
15,335 |
18,798 |
19,721 |
21,262 |
|
���̍s���T�[�r�X |
720 |
657 |
1.268 |
1.315 |
1.282 |
1.543 |
1.576 |
|
���v |
102,725 |
111,723 |
207,499 |
225,227 |
256,704 |
278,453 |
310,684 |
|
�����v��(���i���܂�) |
377,135 |
342,601 |
510,566 |
577,863 |
611,154 |
626,640 |
684,369 |
(�o�T
���������Z���^�[(2000)�w������N�� 2000�xp150��蔲��)
�\2
���e�ʕ��ތ���(1999�N�x)
|
�����v��(���i���܂�) �����v��(���i���܂�) |
���v |
���̍s���T�[�r�X |
���E�E���ƁE���� |
���̖� |
�ی��E�����T�[�r�X |
���{�E��y�T�[�r�X |
����T�[�r�X |
�^�A�E�ʐM�T�[�r�X |
���Z�E�ی��T�[�r�X |
��� |
�Ǘ��E�ۊ� |
�C���E��C |
�H���E���݁E���H |
�����^���E���[�X�E���� |
�N���[�j���O |
|
|
636,050 |
310,684 |
1,573 |
21,262 |
17,456 |
24,928 |
54,778 |
6,775 |
32,746 |
77,528 |
2,940 |
690 |
8,804 |
19,871 |
28,325 |
13,005 |
���k���� |
|
16,382 |
3,437 |
27 |
23 |
245 |
1,647 |
147 |
13 |
98 |
65 |
0 |
13 |
165 |
465 |
327 |
232 |
���S�E�q�� |
|
93,753 |
39,149 |
111 |
1,947 |
2,101 |
4,446 |
3,764 |
740 |
2,555 |
2,217 |
105 |
128 |
2,907 |
5,875 |
2,405 |
9,848 |
�i���E�@�\ |
|
24,524 |
15,516 |
230 |
395 |
547 |
904 |
1,247 |
268 |
1,444 |
5,744 |
70 |
54 |
216 |
600 |
2,716 |
1,081 |
�@�K�E� |
|
79,911 |
41,774 |
59 |
1,461 |
2,199 |
4,237 |
4,983 |
873 |
6,377 |
5,500 |
311 |
149 |
3,074 |
3,962 |
8,022 |
567 |
���i�E���� |
|
876 |
191 |
2 |
3 |
20 |
23 |
22 |
4 |
25 |
17 |
1 |
2 |
12 |
30 |
23 |
7 |
�v�ʁE�ʖ� |
|
17,329 |
7,388 |
7 |
1,834 |
634 |
617 |
1,503 |
249 |
600 |
1,236 |
17 |
22 |
164 |
223 |
134 |
152 |
�\���E�L�� |
|
219,868 |
85,044 |
27 |
11,169 |
4,890 |
7,494 |
32,320 |
1,711 |
7,485 |
8,109 |
1,878 |
78 |
1,679 |
5,421 |
2,302 |
491 |
�̔����@ |
|
381,420 |
202,355 |
200 |
12,038 |
10,469 |
15,741 |
32,629 |
4,741 |
24,018 |
58,605 |
2,157 |
338 |
3,911 |
11,696 |
21,477 |
4,335 |
�_��E��� |
|
54,985 |
31,185 |
180 |
985 |
2,317 |
2,300 |
3,321 |
599 |
4,070 |
5,878 |
193 |
127 |
1,676 |
3,009 |
2,540 |
3,990 |
�ڋq�Ή� |
|
510 |
62 |
2 |
3 |
9 |
7 |
9 |
0 |
17 |
4 |
1 |
0 |
1 |
2 |
4 |
3 |
��E�e�� |
|
729 |
389 |
23 |
11 |
34 |
37 |
51 |
4 |
33 |
16 |
0 |
19 |
19 |
48 |
91 |
3 |
�{�݁E�ݔ� |
|
15,189 |
7,945 |
24 |
1,233 |
833 |
730 |
1,710 |
361 |
482 |
1,493 |
31 |
19 |
221 |
537 |
215 |
66 |
�������k |
|
12,550 |
6,014 |
263 |
244 |
647 |
562 |
366 |
83 |
327 |
2,568 |
22 |
11 |
82 |
251 |
475 |
113 |
�����m�� |
|
12,884 |
8,108 |
543 |
448 |
518 |
868 |
604 |
144 |
344 |
3,756 |
31 |
30 |
88 |
251 |
361 |
122 |
���̑� |
(�o�T
���������Z���^�[(2000)�w������N�� 2000�xp152��蔲��)
2.1���̓���
���������Z���^�[�͋��Z���i�ɌW����ɂ��A���ڍׂȕ��͂��s���A���\�����B�\3�͋Ǝ�ʂ̋�����e�ʂɕ��ނ������̂ł���B
�،���ЁA��s�A�����ی���Ђ�ʂ��ċ��ł��W�����Ă���̂́A�����Ɋւ�����ł���B�،���Ђł͍��v47.3���A��s��40.0���A�����ی���Ђ�40.4�����߁A���̑��̋������|���Ă���B���e�I�ɂ́A�،���Ђł͕s�����m�ƃ��X�N���������A��s�ł͏��i���������A�����ی���Ђł̓��X�N���������̍��ڂ������B�ׂ����Ⴂ�ɂ��ẮA�،��E�ЂƋ�s���قړ������i�Q���J�o�[���Ă���̂ɑ��āA�����ی���Ђł͕ϊz�ی��݂̂ɑ�����͂��Ă��邱�Ƃ��e�����Ă���Ǝv����B
�،���ЂƋ�s�ɂ����Ă͌_��E���Ɋւ������2�ʂ��߂Ă���̂ɓ|���āA�����ی���Ђł͓K�����Ɋւ������2�ʂ��߂Ă���B����́A�ϊz�ی��̊��U�ɂ����āA������𗍂߂Ďؓ�����N�����ĕϊz�ی��ɉ������������Ⴊ��������ꂽ���Ɓi������ϊz�ی������j���e�����Ă���Ǝv����B
�܂��A���U�Ɋւ�����،���Ђɂ����ď����Ȃ��猩����̂͒��ڂɒl����B���ɁA���Ǝ�ł͐��l�Ƃ��đS�����v��\��Ă��Ȃ��̂ł��邩��A�،���Ђ̊��U�p����]�������ŋ����[���w�W�Ƃ����邾�낤�B
�\4�A5�ɂ����āAPIO-NET�ɐ\�����Ă�ꂽ����\�����Ď҂̔N��ʁA�E�ƕʂ̍\�����������B�،���Ђɂ����āA�N��\���ɂ�����60�ˈȏ�̍���҂�46.3���Ɩ����߂邱�ƁA�E�ƍ\���ɂ����Ă��A�Ǝ��]���҂Ɩ��E��67.2�����߂邱�Ƃ������ł���B�N��\���ɂ��ẮA�\������N��\�����������Ƃ��f����B�܂��A�\3�ɂ����Ă��A����Ҏ������s����ی���ЂƔ�ׂč������ƁA�܂�PIO-NET�S���k�Ɣ�ׂĂ��N��\��������ɕ��Ă��邱�Ƃ��A�X���Ƃ��Ďf����B�܂��A�E�ƍ\���ɂ����Ă��A�،���Ђɂ����Ă͈�ʓI�Ɍl�̎��R�ɂȂ鑽���̎����������߂Ȃ��Ǝ��]���ҁA���E�Ƃ��������̂̔䗦���ۗ����č����i67.2���B��s36���A�ی����40.4���j���Ƃ������ł���B�������A�����Ɋ܂܂�閳�E�̏���҂́A��ʓI�Ȗ��E�̐l�Ԃł͂Ȃ��A���Y�ƁA���邢�͂��̉Ƒ��Ƃ���������ґ��ł���Ǝv����B
�\3
�Ǝ�ʂ̋��
(��) ������
|
�̔��`�� |
���� |
�����Ɋւ����� |
�K�����Ɋւ����� |
|||||
|
�f��I���f |
�s�����m |
���i�������� |
���X�N�������� |
�ړI�O���� |
����s�� |
�����ʂɖ�� |
||
|
�،���� |
654 |
11.0 |
15.4 |
6.1 |
14.8 |
3.7 |
6.4 |
0.2 |
|
��s |
25 |
4.0 |
8.0 |
28.0 |
4.0 |
0 |
12.0 |
0 |
|
�����ی���� |
52 |
7.7 |
5.8 |
3.8 |
23.1 |
1.9 |
1.9 |
28.8 |
|
�̔��`�� |
���� |
���U�Ɋւ����� |
�_��E���Ɋւ����� |
���� |
����҂̎���� |
|||
|
�Д��I�ȍs�� |
�Ċ��U |
�����Ԋ��U |
���f�_�� |
��� |
���� |
|||
|
�،���� |
654 |
0.2 |
2.9 |
0.3 |
12.2 |
14.7 |
11.8 |
9.0 |
|
��s |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.0 |
12.0 |
4.0 |
|
�����ی���� |
52 |
0 |
0 |
0 |
1.9 |
0 |
7.7 |
3.8 |
��70�Έȏ�̏���҂ɐM�p����A���������M���A���Z�敨����A�������g�A�I�v�V������������X�N�E���^�[�����x��(RR)3�ȏ�̏��i(RR3�F�l�オ��v�E�����Nj��^�ARR4�F�l�オ��v�Nj��^�ARR5�F�ϋɒl�オ��Nj��^((��)�،��L��Z���^�[�u�����M���K�C�h�v���)�y�ъO���،��A�O�������M�����̈בփ��X�N�̔������i��ϊz�ی������U(�K��̔��A�d�b���U�̔��A�X�܂Ŋ��U)���Ă����ꍇ�̋����B
�Ȃ��A���̒����őΏۏ��i�ƂȂ��Ă���̂́A�ȉ��̂Ƃ���
|
�Ǝ� |
�Ώۏ��i |
|
�،���� |
�u�O�������M���v�u�O�����E�Ѝv�u�����M���v�u�Ѝv�u�������g�v�u���Z�v |
|
��s |
�u�O�������M���v�u�O�����E�Ѝv�u�����M���v�u�Ѝv�u�������g�v�u���Z�v�u�O�ݗa���v |
|
�����ی���� |
�u�ϊz�ی��v |
�\4
�_��ҔN��ʂ̋���
�i���j
|
|
���� |
�`20�� |
20�� |
30�� |
40�� |
50�� |
60�� |
70�� |
80�Έȏ� |
�s�� |
����(��) |
|
�،���� |
654 |
0 |
2.3 |
8.9 |
11.0 |
26.8 |
24.6 |
18.0 |
3.7 |
4.7 |
57.4 |
|
��s |
25 |
0 |
16 |
12 |
12 |
16 |
32 |
8 |
0 |
0 |
|
|
�ی���� |
52 |
0 |
1.9 |
13.5 |
13.5 |
19.2 |
17.3 |
15.4 |
11.5 |
7.7 |
|
|
PIO-NET �S���k |
407972 |
2.8 |
26.8 |
20.8 |
14.8 |
11.3 |
8.1 |
4.8 |
1.5 |
9.1 |
39.9 |
�\5
�_��ҐE�ƕʋ���
�i���j
|
|
���� |
���^������ |
���c�E���R |
�Ǝ��]���� |
���E |
���̑� |
�s�� |
|
�،���� |
654 |
20.2 |
6.6 |
38.8 |
28.4 |
0.5 |
5.5 |
|
��s |
25 |
20 |
8 |
32 |
4 |
28 |
8 |
|
�ی���� |
52 |
28.8 |
17.3 |
17.3 |
23.1 |
3.8 |
9.6 |
�i�o�T
���������Z���^�[�w�u���Z���i�ɌW�����҃g���u�����v�������ʁx���쐬�j
2.2�ʂ̋���
���������Z���^�[�ɂ����āA��L�����̈�Ƃ��čw�����z��300���~�ȏ�ő��k�҂����Ǝ҂Ƃ̘b��������]��10����ɂ��ĒǐՒ������s���Ă���i�Ǝ�͏،����8�ЁA��s1�ЁA���Z�I�v�V��������Ǝ�1�Ёj�B���̂����A�،����3���ɂ��ڏq����B
2.2.1�،���Ђ̎���
����5
���k�҂�64�̒j���B�ȑO����t�������̂������،���Ђ���[���Ȑ��������ɁA�O�������M���A�n���Ȃǂ̎�������đ����o�����B���̌�A�x�X��ς��Ď�����p���B�u���{��ۏ��܂��B�����Ɖ��Ă����܂��v�Ɗ��߂���܂܂ɓ����M����O�������w���A����ɑ������o�����B
�����ɍݏZ���Ă���̂ŁA����͂قƂ�Ǔd�b�Ŏ�����s�����B�בփ��X�N�ɂ��ēd�b�Ő����������A�����𑊒k���ꂽ��A�X�̏��i�̎d�g�ݓ����ڂ����������ꂽ���Ƃ͂Ȃ��Ƃ����B�܂��A�ژ_�����͊��U�̌㑗���Ă������A�������������Ă��邪�A������Ɠǂ��Ƃ͂Ȃ��A���������ǂ�ȏ��i���w���������A���v�͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�͔c�����Ă��Ȃ������B
����ɑ��āA�،���Ђ́A�d�b�ňבփ��X�N�A���i���X�N���������Ă���B�܂��A�ژ_�����̌�t�͏��i�������s�����㎩��ɑ��t���Ă���B���̍ہA�u�ژ_������ǂ�ŁA�d�b�ł̐����Ƒ���_������A�w�E���Ă��������v�Ƃ����Ă��邪�A���܂Ŏw�E���ꂽ���Ƃ͂Ȃ��Ƃ����B�i���������Z���^�[)�w�u���Z���i�ɌW�����҃g���u�����v�������ʁxpp49-50)
����6
���k�҂�75�̖��E�̏����B���N�O����a��łقƂ�ǖ����ʉ@�B���������Ď��R�ȉ�b�͍���ȏB
���N�O�����s��X�ǂɗa������L���Ƃ����ĊO���i����҂̋L���ł͊O���̍��A���ۂɂ̓h�����Č��Ѝ��M�j�������Ɋ��߂��w���B
���̌�A���{����A�z�����ڌ��肵�Ă����̂ʼn�悤�Ƃ������A���v���Ɛ�������A�t�ɂ��̑��̏��i�����߂�ꂽ�B�^�p������x��������Ă��Ȃ����A�p���t���b�g��1���������������Ƃ����B
����ɑ��ď،���Ђ́A��v�،���������n���Đ������Ă���B�בփ��X�N�ɂ��Ă��A���̌ڋq�ɂ��āA�،���Б��́g�낤���l�h�ƔF�����Ă����̂ŁA�x�X���������ɂ������B�ߋ��A���ꗬ�l�������̎��������B�S���O���������Ɉ�x�͗�����͂��ɂ����āA�^�p�����Ă���B���̐\���o�ł͂Ȃ��A���k���������̂ŁA����Ȃ��Ƃ������_�ɂȂ����A�ȂǂƂ��āA�،���Б��̐ӔC��ے肵���B�i���������Z���^�[�w�u���Z���i�ɌW�����҃g���u�����v�������ʁxpp50-53�j
����7
���k�҂�65�̏����B4�N�قǑO���瓜�A�a�Ŗڂ̏�Q�i����0.0��0.1�j������B���{�͈��S���Ƃ������t��M���A�O�������M����5000���~������ŁA1000���~�ȏ�̑��������B�p���t���b�g�̃��X�N���m�ɂ��ẮA�@���ŋ`���Â����Ă��邩��L�ڂ���Ă��邾���A��ɑ������Ȃ��A�Ƃ����������Ƃ����B�ڂ����������͂�����Ă��Ȃ��B�ڂ��ア���ߏ��ʂ͂悭�ǂ�ł��Ȃ��Ƃ����B
�،���Ђ́A�ڂ̕s���R��������̏�Q�ɂȂ��Ă���Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B��v�،��������͕K����t���Ă���B���X�N�̐��������Ă��邵�A�K������̋L�^������A�Ƃ��āA�،���Ђ̐ӔC��ے肵���B�i���������Z���^�[�w�u���Z���i�ɌW�����҃g���u�����v�������ʁxpp53-56�j
2.2.2�����̉���
��L���܂�8���ɂ��č��������Z���^�[�����O���o���ď،���Ђƌ��������A��̓I�����������Č��͂Ȃ��B�������A8����2���ɂ��ẮA���k�҂����Q��U��]��ł��Ȃ��A�����Ă�����Ă������肵���Ƃ��āA����ȏ�̌��͂��Ă��Ȃ��B
�،�����Ɋւ��镴���̉�����i�Ƃ��ẮA�i�ׂ��N�����A��������Ɏ������ށA���{�،��Ƌ���̂������x�𗘗p������@����ʓI�ɂ͍l������B�،��Ƌ���̂������x�Ƃ́A��ʂ̌ڋq�Ə،���Ђ̊Ԃŏ،�����ɂ��Ă̕������������ꍇ�A�ٌ�m����Ƃ���Ȃ邠������ψ����ϑ����A�ڋq�Ə،���Бo�����玖�����s���A�����ҊԂ̘b�������ʼn�����}�낤�Ƃ��鐧�x�ł���B
���������Z���^�[�̎���ɂ��ẮA���̌�A�i�ׂ��邢�͖�������Ƃ��������I�@�ւɕ������������܂�邱�ƂɂȂ������ǂ����ɂ͋L�q���Ȃ����A�������I�����Ă��Ȃ�6�����A5���ɂ��āA�������x�̗��p�ɂ��ď،���Ђɑ��āA�������Ă���B�ȉ������̍ۂ̏،���Б��̉ł���B�i���������Z���^�[�w�u���Z���i�ɌW�����҃g���u�����v�������ʁx�����p�B�����̐����͈��p�y�[�W)
l
�،��Ƌ���̂�����������p�������͂Ȃ��ip41�j�B
l
���k�҂̎咣�͎��Ђ̒������ʂƈقȂ�̂Ŏ�����Ȃ����A���k�҂��،��Ƌ���̂��������\���o��Ό��̐Ȃɂ��i�������A���ʂ͕ς��Ȃ��ƌ����j�Ƃ̂��Ɓip43�j�B
l
���̂Ƃ͍l���Ă��Ȃ��i�@����A�����s���͎��̂ł͂Ȃ��ƌ����Ӗ����j�̂Řb�������ł̉����ɂ͉������Ȃ��A�i���Ăق����ip46�j�B
l
�u�،�����@�ő�����U���֎~����Ă���̂ŁA�b�������ł̉����͕s�B�i�ׂ������͒���ɂ�낤���A���̎���ɂ��Ă͖�����������߂����B�،��Ƌ���̂�������́A����肪�Ȃ��̂ł���Ă����ʂł���v�ƉB�܂��A�u����҂��ٔ����Ă��ٌ�m�̉a�H�ɂȂ��đ��Q�z�����z�ɔF�肳��A����������������B�ٔ��ɂ͐�Ώ����g������v�Əq�ׂ��ip53�j�B
l
�ٔ��ɂ�锻�����o�Ȃ��Ƒ��Q�����͂ł��Ȃ��A�،��Ƌ���̂�������𗘗p�������͂Ȃ��ip56�j�B
�ȂǁA��������،��Ƌ�������x�̗��p�Ɋւ��āA��ϔے�I�ł���B
�������x�ɂ��ẮA�،����k�����s���{���ʂɂȂ��Ă��Ȃ��i���{�،��Ƌ���̓����n�拦������s�A��錧�A�Ȗ،��A�Q�n���A��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�A�R�����A���쌧�A���ꌧ�̋����t����j�Ƃ������ᔻ��������̂́A�̐S�̏،���Ђ����p�ɑ��đ�Ϗ��ɓI�ł��邱�Ƃ́A�⊶�Ƃ��킴��Ȃ��B���{�،��Ƌ���̂��̂��A�ƊE�̎���K���c�̂ł���B�������x�Ƃ́A���̓��{�،��Ƌ���ڋq�ی�̂��ߊO���̂�������ψ����ϑ����āA�����A�����ȗ��ꂩ�玖�Ԃ�A���Ԃ���Ԃ�������ٔ��𗘗p�����A�����̖����������߂鐧�x�ł���͂��ł���B������A�u�،��Ƌ���̂������x�͏���҂�肾���猙���v�i���������Z���^�[�w�u���Z���i�ɌW�����҃g���u�����v�������ʁxp15�j�Ƃ͂܂��ƂɈ⊶�Ƃ��������悤���Ȃ��B
2.2.3�ڋq�����̔c��
�،�����@��43���ɂ����āA�،���Ђ͌ڋq�̒m���A�o���y�э��Y�̏ɏƂ炵�ĕs�K���ƔF�߂��銩�U���s���ē����҂̕ی�Ɍ����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɋƖ����c�܂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B���̏����Ɋ�Â��A�،���Б��́u�ڋq�J�[�h�v���쐬�A�ڋq�����̔c���ɓw�߂Ă���Ƃ����B
�������A�u�،���Ђɑ�����8����̂���7����i1����͓��@���̂��ߊm�F�ł����j�̑��k�҂̒N�����g�ڋq�J�[�h�h�̑��݂�m��Ȃ������v�i���������Z���^�[�w�u���Z���i�ɌW�����҃g���u�����v�������ʁxp15�j�B�،���Ђ́A���̌ڋq�J�[�h�ɋL�ڂ���Ă���ڋq�̌o���A�����ړI�A���Y�Ȃǂ̎�������ɁA�ڋq�A�h�o�C�X���s�����ƂɂȂ��Ă���B�Ƃ��낪�A�ڋq�J�[�h�̋L�ڂ͊O�������s���A���e������J�ł���B�]���āA�،���Б��͌ڋq�J�[�h�ɂ���Čڋq�̓����Ɋւ���ӌ���c�����ăA�h�o�C�X���s���Ă���Ƃ��Ă��邪�A���X�N�̍������i�����߂�ۂ̉B�ꖪ�Ƃ��Ďg���Ă����Ƃ��Ă��A�ڋq������͕�����Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����ł���B
����Ɋւ��ẮA�p���̎��Ⴊ�Q�l�ɂȂ�ł��낤�B�u�p���ɂ́A�u�t�@�N�g�E�t�@�C���h�E�t�H�[���iFact-Find-Form�j�v�Ƃ����J���e�̂悤�Ȃ��̂�����B���q����̉Ƒ��\���E�N���Ȃǂ̑����A��̓I�ɂǂ��������R�łǂ�ȃA�h�o�C�X�����āA���q����͂ǂ�Ȕ��������������ȂǁA���_�ɓ���o�܂��L�����A�Ō�ɔ����E������̑o�������_���m�F���āA�T�C������v�i���z
�����w���{�ŋ��Z�T�[�r�X�@�x���{�o�ϐV����p31�j�V�X�e�������邻���ł���B�ڋq�J�[�h�����Z�@�֑��̈���I�ȏ؋��ۑS�Ɏg�킹�Ȃ����߂ɂ��A�����ɒl����V�X�e���ł��낤�B
2.3���ݓI�ȋ��
�S���̏�����Z���^�[���Ɋ�����͑O�L�ɂ悤�ɑ����̈�r�����ǂ��Ă��邪�A���ݓI�ȋ��͂͂邩�ɑ����Ǝv����B
�\6�Ɍ���悤�ɁA����10�N�̑����{�̒����ɂ����Ă��T�[�r�X�Ƃɕs���������Ă��\���o�Ȃ������l�̔䗦��68.7���ɒB����B�܂��A����\�����Ă��ꍇ�ł��A�w����A���p��A���U���֒��ڎ������܂�邱�Ƃ������i22.3���j�A���������Z���^�[���n�߂Ƃ��钆���I�Ȓ��ً@�ւɎ������܂�錏���͈��|�I�ɏ��Ȃ��i�ƊE�c�̂̑���1.5���A����Ғc��0.9���A���������Z���^�[�A������Z���^�[1.5���A���E�n�������c�̂̑��k����0.6���j�B����\�����ĂȂ��������R���A�ʓ|�����炠����߂��i47.7���j�A����\���o��قǂ̑��Q�ł͂Ȃ������i40.4���j�Ƃ��������ɓI�Ȃ��̂���ʂ��߂Ă���i�����{�L�u����Җ��Ɋւ��鐢�_�����v�i����10�N1���j�����{�j�B
�{�����͏�����S�ʂɊւ��钲���ŁA���Z���𒆐S�Ɏ��グ�����̂ł͂Ȃ��Ƃ͂����A���v�ɕ\�ꂽ���\�����Ă͕X�R�̈�p�ł���A����҂̕s���͍����A���\�����ĂɊւ�����̒A�������@�ւ̐����Ȃǂɉ��P�̗]�n�����邱�Ƃ��������킹��B
�\6�u����Җ��Ɋւ��鐢�_�����v(����10�N1��)
�uQ2
���Ȃ��́A����1�A2�N���炢�̊Ԃɗ��p�����T�[�r�X�ƂȂǂŁA�����s�����������ɂȂ������Ƃ�����܂����A����܂��B
|
���� |
20.9 |
�킩��Ȃ� |
0.8 |
|
�Ȃ� |
78.3 |
|
|
Q3
���Ȃ��͂��̕s���̂��ƂŁA�ǂ����ɋ���\���o�܂������B���̒����炢���ł������ĉ������B
|
�w����A���p��A���U�� |
40.4 |
�ٌ�m |
0.3 |
|
�������[�J�[ |
3.3 |
�ٔ��� |
�| |
|
�ƊE�c�̂̑��� |
1.5 |
���̑� |
0.3 |
|
����Ғc�� |
0.9 |
�\���o�Ȃ�����(SQ��) |
68.7 |
|
���������Z���^�[�A������Z���^�[ |
1.5 |
�킩��Ȃ� |
3.5 |
|
���E�n�������c�̂̑��k���� |
0.6 |
|
|
SQ
���Ȃ��́A�Ȃ��\���o�Ȃ������̂ł����B���̒����炢���ł������Ă��������B
|
����\���o��قǂ̑��Q�ł͂Ȃ����� |
40.4 |
�����ɂ��s���ӂȓ_�������� |
5.1 |
|
�ʓ|�����炠����߂� |
47.7 |
�ǂ��ɐ\���o����悢�̂��킩��Ȃ����� |
10.8 |
|
���Ԃ������邩�炠����߂� |
11.0 |
���̑� |
2.4 |
|
�����������邩�炠����߂� |
1.3 |
�킩��Ȃ� |
1.5 |
|
����\���o�Ă��������Ȃ��Ǝv���� |
25.8 |
|
|
�v�i�o�T
�����{�L��(1998)�u����Җ��Ɋւ��鐢�_�����v(����10�N1��)���)
3.�ߋ��̑i����
��L�����{�̒����ł����炩�ȂƂ���A���Z�Ɋւ������҃g���u�����i�ׂɂ܂Ŕ��W����̂͋ɂ߂ċH�ł���B�]���āA�K�������i�������T�^�I����҃g���u���Ƃ͌�����Ȃ��i�ނ���A���i�����҂ł���قNjƎґ��������ł���A���邢�͑����z���ɂ߂č��z�Ȏ���Ƃ����邩������Ȃ��j�B
�������A���Z���i�̔��@�����Ҍ_��@�{�s��ɂ�����i�����ɂ����Ă��A��{�I�Ȏ����F��̎p���͓��P�������̂Ǝv����̂ŁA����̕��͂͋ɂ߂ďd�v�ł��낤�B
���������Z���^�[�̋��Z���i�̕��ނɂȂ炢�A�،���ЁA��s�A�����ی���Ђ������i�����̂����A�،���Ђɂ����Ă̓������g�������A��s�ɂ����Ă̓C���p�N�g���[���i�O���Ďؓ���j�ɌW��i�������A�����ی���Ђɂ��Ă͕ϊz�ی��������i�������A���グ���S�Ă̎���ɂ����āA�����ی���ЂƂƂ��ɋ�s���i�בΏۂƂȂ��Ă���j���グ��B
3.1�������g����
3.1.1�������g�Ƃ�
1981�N�̏��@�����ŐV�����t�Ѝi�������g�j�̔��s���F�߂�ꂽ�B�������g�Ƃ́A����A�����ɑ���R�[���E�I�v�V�����̂����Ѝł���B���̃R�[���E�I�v�V�����́A���L�҂ɑ��Ĉ��̒l�i�i�s�g���i�j�Ŕ��s��Ђ̊������錠����^�������B
��
���m�ɂ̓R�[���E�I�v�V�����Ƃ͈قȂ�B�R�[���E�I�v�V�����ɂ����Ă͔��s�ς݊����ɑ��Č����s�g�����̂ɑ��A�������g�͐V�������s�����̂ŁA�����������ς��B1��������̍����w�W�����ω�����̂ŁA��ʂ̃������g�������]�������ꍇ�Ȃǂɂ́A�����̊������i�ɉe���������炷�B
���̌�1985�N�ɕ����^�̃������g�̔��s���������悤�ɂȂ����B�����^�ł́A�������ƃ������g��������������A���Ƃ͕ʂɐV�����؏������s�����B���s��͍��ƃ������g�����ė��ʂ����邱�Ƃ��ł���B���݂͕����^����ʓI�ł���B
�������g�́A���������̉��i�ōw���ł��錠���i�I�v�V�����j�ł���̂ŁA���⊔���Ƃ͑傫���قȂ����l����������B�������g���i�́A�����ɘA�����A�������̐��{�̒l���������邱�ƂƁA�����s�g���Ԃ��߂���Ɩ����l�ƂȂ邱�Ƃ������ł���B
�������g�́A���̃I�v�V�����ł���̂ŁA�������i�Ƃ��ẮA���������Ɠ����̒l�オ��v�����҂ł���̂ɑ��āA������菭�Ȃ����z�Ŏs��ɎQ���ł���A�����͈��z�i�������g���i�j�Ɍ�����ȂǁA��ϗD�ꂽ���������������i�ł���B
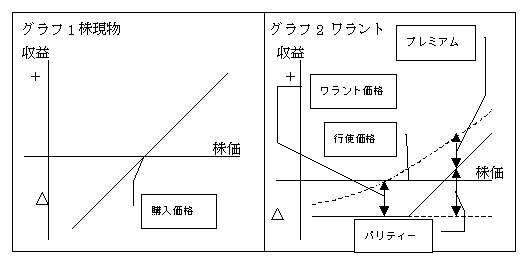
�O���t1�ɂ����āA��������ۗL�����ꍇ�̊����Ǝ��v�̊W�������Ă���B�X��1�̒����Ƃ��Č������B�]���āA�����Ǝ��v�̕ϓ����͓���ł���B
�O���t2�ɂ����āA�������ϓ������ꍇ�̃������g���i�̕ϓ��́A�j�Ȑ��ŕ\����Ă���B�������g�̗��_���i�́A�����A�����s�g���i�A�������g�����܂ł̊��ԁA�����A���ҕϓ����i�C���v���C�h�E�{���e�B���e�B�[�j�Ō��肳���i�{�_���ɂ����ẮA���w�I�������͋��߂Ȃ��̂ŁA�z���̉e���Ȃǂ͔r������j�B�܂��A�������g�̗��_���i�́A�p���e�B�[�iIntrinsic
Value�A�{���I���l�Ƃ������j�ƃv���~�A���iTime Vale�A���ԓI���l�Ƃ������j�����ɕʂ��B�p���e�B�[�͊������s�g���i�ȉ��̏ꍇ�ɂ̓[���ɂȂ�B�v���~�A���́A�������g�����D�ꂽ�������w�����邽�߂ɏ�悹������g�v���~�A���h���ł���B
�܂��A�j�Ȑ��ŕ\���ꂽ�������g���i�̕ϓ��́A�����݂̂��ϓ����āA���̑��̐����ϐ����s�ς̏ꍇ�������Ă���B�]���āA�����ւ̏㏸���҂����܂�A�������g���w�������ƁA�j�Ȑ����̂�����փV�t�g���邱�Ƃ����肤��i���w�I�ɂ͊��ҕϓ��������܂����ꍇ�ȂǁB���l�ɉ����V�t�g�����肤��j�B�܂�A�������̂��㉺���Ȃ��Ă��A�������g���i���㉺����ꍇ�����肤��̂ł���B�܂��A�������g���̂̉��i�͊��������w������ꍇ�ɔ�ׂĂ͂邩�ɏ��Ȃ����z�ōςށB���̃��o���b�W���ʂ��܂߁A�����̏㏸�A���ҕϓ����̕ϓ��Ȃǂɂ���āA�������g���i�����ۂ̊����̕ϓ�����傫�������ė���������ꍇ�����肤��B
�������g�̉��i���_�͋ɂ߂ĕ�����ɂ����悤�ŁA�������̒��ł��A�u�������g�̉��i�́A�����̒l�オ��ւ̎v�f�i�v���~�A���j�����_�I���l�i�p���e�B�[�����̎����ƍs�g���i�Ƃ̍��z�j�ɉ��Z����A�v���~�A���ŕϓ�����v�f���傫���A���̂��߂ɕs����ɂȂ肤��v�i��㍂�ٕ�7�E4�E20��10�����������w����^�C���Y�x885��pp207�|222�j�ƁA���������߂����Ȃ�F��������Ă���B
�v���~�A���ɕt���ẮA�����ƍs�g���i���������������g���w�����邱�Ƃ�z�肷��Ε�����₷���ł��낤�B�����ƍs�g���i���������̂ł��邩��A�p���e�B�[�̓[���ł���B�]���āA���̃������g�̉��i�̓v���~�A�����������ō\������邱�ƂɂȂ�B�������㏸�����ꍇ�A�������g���s�g���čs�g���i�Ŋ����w���A�s��Ŕ��p���邱�Ƃ��\�ł��邵�A�������g�Ƃ��Ĕ��p���邱�Ƃ��\�ł���B���ۂɂ́A���ɕϊ�����ƃv���~�A���i�������g�̎��ԓI���l�j��������邱�ƂɂȂ�̂ŁA���_�I�ɂ͍œK�ȍs���Ƃ͌����Ȃ��B������ɂ��Ă��A�����Ɋ����w�������̂Ɠ����i���m�ɂ́A�����ł͂Ȃ����A���w�I�������͂����ł͋��߂Ȃ��j���v����ɂ��邱�Ƃ��ł���B�t�ɁA���������������ꍇ�A�������g���w�����Ă���A�ő呹���̓������g���i�Ɍ�����B���������w�������ꍇ�ɔ�ׂ�ƁA�͂邩�ɏ��Ȃ������ōςށB
�����������s�g���i�̎��_�Ń������g���w�������ꍇ�A�����㏸�Ɖ����̊m���́A�ق�50�����ł���B�������㏸�����ꍇ�͂������藘�v���������邱�Ƃ��o���A���������������ꍇ�̑����̓������g���i�Ɍ�����B
���ۂɁA���̂悤�ȗD�ꂽ���������������i�������w���ł���̂ł���A�N�ł����������Ǝv���̂ł͂Ȃ����낤���B�]���ăv���~�A���͍����Ȃ�B�ǂ̒��x�����Ȃ邩�Ƃ����ƁA���̃������g���Ă��悢�Ǝv���l�Ԃ̐��ƁA�����Ă��悢�Ǝv���l�Ԃ̐����������Ȃ�܂ŏオ��B���ۂɂ́A�������g�̎���ł͏[���Ȏs�ꂪ�ł���قǎs��Q���҂������Ȃ��̂ŁA�K�������s�ꌴ�������S�ɓ����Ƃ͌����Ȃ����A�����Ƃ��Ă͏�L�̂Ƃ���ł���B
3.1.2�������g��������
����1
���i��
�����̊T�v�BX�̍�A�́A�،����Y�̎Ј�B�̊��߂ɂ��O���ă������g��X���`�ōw���������A�������g�͖����l�ƂȂ��đ��Q�������BX�́A�������g�̍w���s�ׂɕt��������^���Ă��Ȃ��A���ɏ������Ă����Ƃ��Ă��AB�͏،��ɂď[���Ȓm���̂Ȃ�A�ɑ��ă������g�̊댯���ɂ��K�v�Ȑ��������Ȃ������Ƃ��āAY�ɑ����Q���������߂��B
�������ɂ����ẮAB�̓������g�̊댯���ɂ��Đ������Ȃ��������Ƃ͔F�߂����̂́AA��X�̑㗝�Ƃ��ď،���������Ă������Ƃ͓����ҊԂɑ������Ȃ����ƁAX��Y����u�O���V�����،��̎���ɂ��ւ���������v����́A���e���m�F�̏����m�F���ɋL�����ĕԑ����Ă��邱�Ƃ�F��A����������Ɋ댯���ɕt���������Ȃ������Ƃ��Ă��A���̊댯����m��������������g�w����i�߂Ă���Ƃ��Č����̐��������p�����B
����ɑ��čT�i�R�ɂ����ẮA�����F��ɑ啝�ȕύX�͂Ȃ����̂́A�������g����͓��@���̍������i�ł��邱�ƁAA�ɑ���B���������g�Ɋւ��郊�X�N�̐�����ӂ��Ă���A���s���s�ӔC���ׂ��ł��邱�ƁA����m�F���ɋL����ĕԑ������͎̂���㑊���̎��Ԃ��o�߂�����ł���\�������邱�Ƃ�F��A��������j�������B�������AA�͏،������ʂɒm���A�o����L���邱�ƁA�������g�̉��i�̕ϓ��𒍎����đ��Q���ŏ��ɂ���`����B�ł͂Ȃ�A�������ׂ����Ƃ���A�ߎ�������6���ƔF�肵���i�������ٕ�8�E3�E18��5�����������w����^�C���Y�x923��pp146-150�j�B
����2
���i��
X��X�̕�e���]�[�ǂœ|�ꂽ��A��e���s���ď،���ЂƂ̎�����J�n�����B�����M���̒�z���ɕs���������Ă����Ƃ���AY�،���Ђ���V�������z�����i�Ƃ��ă������g���Љ�������n�߂��B���Ǒ����������BX��Y�Ƃ̎���������Ǒ��ɔ����A�������Ƒi�����B
�������ł́AY�̎Ј�A���������g�̐����A���@���ɂ��Đ����������ƁAX�����ЂŃ������g�ɂ��Ē��ׂ�Ȃǂ��Ēm����L���Ă������Ƃ�F��AX�̐��������p�����B
����ɑ��čT�i�R�ł́AX�y�ѕ�e�������o����L���Ă������Ƃ͔F�߂���̂́A�������g�̂悤�ȐV�폤�i�ɂ��ẮA�̔���Ђ͂��̐����A���X�N�ɂ��ď[���ɐ������A���������߂�ׂ��ł���A����I�Ȑ������`���V���𑗕t����ɂƂǂ܂�A�����`�����ʂ����Ă��Ȃ��B�܂��A�ʂ̎���ɂ��Ă��،���Ђ̒S���Ј��̔��f�ōs���Ă���ȂǁA�،���Ђ̐����`���ᔽ��F�߁A���Q�����ӔC��F�߂��B
�������AX�ɂ��āA����I�ɂ��������������̂��Ă���A���g���X�ɏo�����ă������g�̉������ǂ�ŗ����ł��Ȃ������ɂ�������炸�A����ȏ㒲�����邱�ƂȂ����u�������ƂȂǂ���A�ߎ����E��2���F�߂��B�i��㍂�ٕ�7�E4�E20��10�����������w����^�C���Y�x885��pp207-216�j
����3
�s�i��
X��Y�،���ЂƂ̊ԂŃ������g������s���A��������̉e�����A�����������s�g���i����������܂܌����s�g���Ԃ��o�߁A�������g�������l�ƂȂ葹���������BX��Y�̒S���Ј�A���������g�ɂ��Ă̐����`����ӂ�A�K���ׂ���Ƃ����Ċ��U�����Ƃ��đ��Q���������߂��B
�������ł�X��Y�Ɉϑ����Ă��������̂قƂ�ǂp���Ĉ�����̃������g���w�������Ă���ȂǏ،���Ђ̉c�ƒS���҂̊��U�s�ׂɂ���@����F�߂����̂́A�������o�����������g�ȑO�ɂ��������g���w���������Ƃ�����A���̍ۂ͔��p���ė��v���o���Ă������ƁAX�̓����o���Ȃǂ����āA85���̉ߎ�������F�߂��B
�T�i�R�ł́AX���������o�����������g�ȑO�Ƀ������g��������Ă���A���O�̎���ɂ�����A���烏�����g�ɂ��Ă̐������Ă���ƔF��ł����ƁA���̂���A��X�ɑ��������g�̐������𑗕t�A���e���m�F�����|�̊m�F�����������Ă��邱�ƁA�������̓��e���������g�̐�����������Ă��邱�Ƃ�F�肵���B�܂��AX��42�˂̏����ŗ������⒆�Ƃ���������͂���ɂ���A��L�����Ƃ��o�c�A���Y������A�����̏،���ЂƂ̎��������A1�ЂƂ�Y�Ƃ�葽�z�̎�����s���Ă���A���̐M�p������s���Ă���ȂǑ�ϔM�S�ȓ����Ƃł��邱�Ƃ���X�̐�����S�ʓI�ɑނ����B�i�������ٕ�4�E3�E30��8�����������w����^�C���Y�xNo.885pp216-222�j
����4
�s�i��
X��1917�N���܂�BY�،���ЂƊ����̐M�p����ƃ������g������s�����BY��X�̎���Ɋւ��A�K���������ᔽ�A�����`���ᔽ�A�f��I���f�̒�����X�͑����������Ƃ��č��s���s�܂��͕s�@�s�ׂɊ�Â����Q�����𐿋������B���ƂȂ���������_��X��71�ˁB
�������ł́AX�̎咣��S�ʓI�ɑނ��A���������p�����BX�̓������g����ɂ��Ă̂ݍT�i�����B
�T�i�R�����͈ȉ��F�肵���B
�K�����`���ɂ���
X��1917�N���܂�Œ��w���ƌ�A�����ɂ����ق��͔_�Ƃɏ]�����Ă����B�������71�˂ł������B1971�N������Y�،��Ɗ����̈ϑ�����������s���A1980�N������͐M�p������s���Ă����B1955�N��������{�o�ϐV�����w�ǁAY�،��̃��|�[�g�ɂ��ڂ�ʂ��A�����u����ɂ��o�ȁA�����`���[�g�����Ȃǂ��Ă����B����ɂ����Ă��A���������w�肵�Ď�����s�����Ƃ��������߂Ă���ȂǁA�m�����L�x�ŁA�V���L���Ȃǂ�ʂ��ă������g�ɂ��Ă��m����L���Ă����B
�܂��A�N��ɂ��Ă��A����҂Ƃ̎�����ւ���K�肪Y�ɂ����đ��݂����Ƃ͔F�߂�ꂸ�AX�̊�������A�M�p����ɂ��Ă̒m���A�o�����l������ƁA����҂ł������Ƃ��������œK���������ɔ�����Ƃ͌����Ȃ��B
X�͖{���ȑO�Ƀ������g����̌o�����Ȃ����AY���Ј������ă������g�ɂ��Đ��������Ă��邱�ƁAX�̏�L�m���A�o�������Ă���ƁA�ȑO�Ƀ������g����̌o�����Ȃ��������Ƃ������ēK���������ɔ�����Ƃ͌����Ȃ��B
�����`���ɂ���
Y�̎Ј��̓������g�ɂ������t���ł��邱�ƁA���l�����ł���\�������邱�ƁA�،���ЂƂ̑��Ύ���Ŏs�����łȂ����ƂȂǂ�����̏�A�u�O���V�����،�����������v����t�AX�̏����A��������m�F�������Ă���B�܂��A�������g�w�����X�Ɍ�t�����a����ɂ������s�g�������L����Ă���B�܂��A�������g�̉��i�ɂ��ẮA���{�o�ϐV�����ɖڈ��ƂȂ鉿�i���f�ڂ���Ă����B�ȏォ��AY�͐����`�����ʂ����Ă����ƔF�߂���B
�f��I���f�̒ɂ���
X�y��Y�̎Ј��̋��q�ɂ����Ă��A�f��I���f�̒��������Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�ȏォ��AX�̐��������p�����B�i�������ٕ�7�E5�E31��9�����������w����^�C���Y�xNo.897pp144-150�j
3.2�C���p�N�g���[��
3.2.1�C���p�N�g���[���Ƃ�
�C���p�N�g���[���Ƃ́A�O���ב��F��s�����Z�҂ɑ��čs���g�r�����̂Ȃ��O�ݑݕt�ł���B
1980�N�ɉ������ꂽ�O���ב֊Ǘ��@�ɂ������������P�p����A���Z�҂����R�ɊO�ݑݕt������悤�ɂȂ����B�C���p�N�g���[���𗘗p���邱�Ƃɂ��A��Ƃ͎������B��i�̑��l���A�O���č��ƃ}�b�`�����邱�Ƃňבփ��X�N�̃w�b�W���s����Ȃǂ̃����b�g������B
�O���Ăł���̂ŁA�ؓ��ꎞ�ƕԍώ��̈בփ��[�g�ɂ��A�����~�x�[�X�������قȂ�B�܂�A�ݕt�������͈̂בփ��X�N���B
�\7
�C���p�N�g���[�������V�~�����[�V����
�~���� 1�N 0.54���A�h������ 1�N 6.76�� �h���~�ב� 108.80
�i���[�g��2000�N10��31���̃��[�g ���C�^�[���ׁj
|
�ԍώ��בփ��[�g |
115.00 |
110.00 |
105.00 |
102.3712 |
100.00 |
95.00 |
|
�~�x�[�X�������� |
12.94299 |
80.32424 |
3.12186 |
0.540081 |
�|1.78871 |
�|6.69927 |
�\7
�̂悤�ɁA�h���Ŏؓ�����N�������ꍇ�A�ԍώ��̈בփ��[�g���ؓ��ꎞ�̃��[�g�i108.80�j������ꍇ�A�~�x�[�X���������͏㏸����B�t�ɁA�~���ɐi�ނƉ~�x�[�X���������͒ቺ����i�����}�C�i�X�Ƃ́A�ؓ�����z���ԍϋ��z�̕������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ӗ�����j�B�����ĉ~�x�[�X�����������~���ĂŎؓ���������ꍇ�Ɠ���ɂȂ�̂́A102.3712�~�̏ꍇ�ł���B���̃��[�g���A�ؓ��ꎞ�_��1�N���̈ב敨���肵���ꍇ�̃��[�g�ɂȂ�i���̃V�~�����[�V�����ł́A�Όڋq�}�[�W���A�����E�בփ��[�g�ɂ�����r�b�g�E�I�t�@�[�E�X�v���b�h���͖������Ă���B���ۂɂ��̃��[�g�Ŗ��ł���Ƃ͌���Ȃ��j�B���ꂪ�����ْ�̗��_�ł���B�]���āA���_�I�ɂ͊O���Ă̎ؓ�������Ă��A�����ɐ敨�ב֗\����s���A�ԍϋ��z���m�肳����A�בփ��X�N������ł��邾���łȂ��A�����ْ�ɂ������I�ɂ͉~���ĂŎؓ�����N�������ꍇ�Ɠ������ʂ���B
�ȉ��A3���̃C���p�N�g���[���ɌW�锻�����Љ�邪�A1���̓X�g���[�g�̃C���p�N�g���[���A1���͈בփI�v�V�����Ƃ̑g�ݍ��킹�A1���̓J�����V�[�E�X���b�v�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ɠ��e�I�ɈႢ������̂ŁA�X�̎���ɂ��Ă͂��ꂼ��̍��ł��ڂ����������B
��L�V�~�����[�V�����͌��݂̃��[�g���g���Ă��邪�A�C���p�N�g���[�������p���ꂽ1980�N��㔼�́A���{�̋��������������A�X�C�X�t�����̂悤�ɉ~��傫�����������̒ʉ݂����݂����B�[�������̌���͑z�������Ȃ����A���������ቺ�ɑ���ڋq�̗v�]�͋��������w�i������B
3.2.2�C���p�N�g�E���[������
����5
���i��
�@�B�̔��Ƃ�X�Ёi���{��480���~�A�]�ƈ�3���j�̑�\��A�́A�����ɔ[������@�B�̎d����ɑ���O�n��4000���~�̂���3000���~��A�̓y�n������S�ۂɎؓ�������Y��s�ƍs���Ă����B���Y�ؓ���ɂ��AY��s�̓C���p�N�g���[���ɂ��ؓ�������߁A����X�Ђ̓h�����ăC���p�N�g���[����g�B���̌�A�~����͋}���AX�Ђ͈ב֍����������B
X�Ђ́AY��s�ɑ��āA�O���ב��F��s���O���č��̃��X�N�E�w�b�W���s���K�v���Ȃ��A�O����ɒm���E�o���̂Ȃ����̂ɑ��ăC���p�N�g���[���̗��p�����߂�ꍇ�ɂ́A���R�ڋq�̂��߂Ɉב֗\����Ȃ��ׂ��M�`����̋`��������̂ɂ����ӂ����Ƃ��āA���Q���������߂��B
�����ł́A�C���p�N�g���[���ƈב敨�\��͖{���ʌ̎���ł���Ƃ��āA��s���C���p�N�g���[�����s���ɓ��R�敨�\��p���ׂ��`���͂Ȃ����̂Ƃ����B�������AX�͉ߋ�1�x������p�ɗA�o�������Ƃ�����Ƃ͂����O���בւɂ��Ă͑S���̑f�l�ł���B�܂��AX�ɃC���p�N�g���[���𗘗p����K�R���͑S���Ȃ��B���[�����s���̐�����X�ɃC���p�N�g���[���������~���Ďؓ���Ǝ����قȂ�Ȃ����̂��Ƃ��F����^������̂ł������B�܂��AA�̓C���p�N�g���[���ɂ��Ď��璲�ׁA���邢�͋��Z�W�҂ɑ��k����Ȃǂ��Ă��̖��_��m���āAY��s�ƌ����悤�Ƃ������A�炿�������Ȃ��������ƂȂǂ���A��s�̐M�`���ᔽ��F�߁A�~���Ďؓ���������ꍇ�̏o�o�����ł��낤�z�ƃC���p�N�g���[���ԍς̂��߂Ɏ��ۂɏo�o�������z�̍��Q�z�Ƃ��đ��Q����������F�߂��B�i���n�ُ��a62�E1�E29��24�����������w���Z�@������xNo.1149pp44-46�j
����6
�s�i��
�I�v�V�����t�C���p�N�g����[��
�{���ɌW��ؓ���͐敨�ב֗\��t���h�����ăC���p�N�g���[���ƃm�b�N�A�E�g�E�I�v�V�����̔����g�ݍ��킹�����̂ł���i�������̒��ł̓I�v�V�����A���邢�̓m�b�N�A�E�g�E�I�v�V�����̌ď͎̂g���Ă��炸�A�t�я����y�ѓ���̕t�����敨�\��Ƃ��Ă��邪�A���ۂɂ̓m�b�N�A�E�g�E�I�v�V�������̂��̂ł���j�B�ᗘ�Ŏ������B�ł�����Z���i�Ƃ��āA�u�p�b�P�[�W���[���^�C�����[�\��^�v�ȂǂƂ����킯�̕�����Ȃ��j�b�N�l�[����t���Ă��邪�A���e�͎��ɒP���ł���B
�������炱�̏��i������������������p����B
�u�i1�j�����́A�퍐���玟�̖��ŁA700���x�C�h�����ؓ����i�C���p�N�g���[���\��t�j�B
�ؓ���
�������N12��26��
�ԍϊ���
����2�N3��26��
�ؓ��ꎞ�̉~�]���[�g
1�h����144�~65�K�i�ȉ��A�בփ��[�g�́u1�h�����v�̋L�ڂ��ȗ�����B�j
�ؓ��ꎞ�~�݊z
10��1255���~
�h������
�N9.0625�p�[�Z���g
�������v
715��8593.75�ăh��
�ԍώ��̊O�]���[�g
143�~33�K
�ԍώ��~�݊z
10��2604��1242�~
�~�̎������B����
�N5.40�p�[�Z���g
�i2�j�����͔퍐�ɑ��A���̖��ŁA700���ăh����A�o����i����n���j���Ƃ�\��i�h���敨����\��j�B
�_�i
142�~75�K
�s�g����
����2�N3��22��
��n����
��3��26��
�ڕW����
139�~75�K
�t�я���
1 �������̃h���~���ꂪ�A�_�i��142�~75�K���h�����~���ɂȂ��Ă����ꍇ�́A�����̓h���̔���n�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
��
2 �������̃h���~���ꂪ�A�_�i��142�~75�K���h�����~���ɂȂ��Ă����ꍇ�́A������700���ăh�����_�i��142�~75�K�Ŕ���n���`��������B
����
�s�g�����܂łɃh���~���ꂪ�ڕW�����139�~75�K����x�ł�������h�����~���ƂȂ����ꍇ�́A���̃h���敨����\��͏��ł���B�v
�i�����n�ٕ���4�E6�E26������18�������w���Z�@������xNo.1333
pp44-45�j
�Ȃ�Ƃ�������ɂ������i�����ł���B���́A���̏��i�́A���[���Ƃ͑S���W�̂Ȃ��m�b�N�A�E�g�E�I�v�V�����p�����A����ɂ���ē�����I�v�V�����E�v���~�A���i���̃v���~�A���̓������g�̃v���~�A���Ƃ͈قȂ�B�����ł̓m�b�N�A�E�g�E�I�v�V�����̉��i�̂��ƁB�������g�ɂ����Ă̓������g���i�Ɠ���ł���j�������ɕ�U���邱�Ƃɂ���ă��[��������ጸ����P���Ȏd�g�݂ł���B
�����Ŕ��p���Ă���̂́A142�~75�K���X�g���C�N�A139�~75�K���g���K�[�Ƃ���m�b�N�A�E�g�E�h���R�[���E�I�v�V�����ł���B�m�b�N�A�E�g�E�I�v�V�����Ƃ́A�I�v�V�������Ԓ��Ɉ�x�ł��h���~�X�|�b�g�E���[�g���g���K�[���i�ɓ��B����ƁA�I�v�V�������̂����ł���i�m�b�N�A�E�g�j�I�v�V�����ł���B���ł��Ȃ��ꍇ�́A�ʏ�̃I�v�V�����Ɠ������������B�I�v�V�����������s�g�����ȑO�ɏ��ł��Ă��܂��\��������̂ŁA�v���~�A���̓m�b�N�A�E�g�̂Ȃ��I�v�V�����������Ȃ�B
�����ŁA����ɂ������Ă���悤�ɁA��x�ł��h���~���ꂪ139�~75�K�ɓ��B�����ꍇ�A���̃m�b�N�A�E�g�E�I�v�V�����͏��ł���B
���ł��Ȃ������ꍇ�ŁA�t�я���1�ɂ������Ă���A�����s�g���̃h���~���ꂪ142�~75�K���~���̏ꍇ�i������139�~75�K���~���j�ɂ́A�I�v�V�����̔�����i��s�j�͌������s�g����K�v�͂Ȃ��i�I�v�V�����̔�����́A�s��ł��L���ȃ��[�g�Ńh������j�B
����ɑ��āA�t�я���2�ɂ������Ă���A�����s�g���̃h���~���ꂪ142�~75�K���~���̏ꍇ�ɂ́A�I�v�V�����̔����i���̏ꍇ�͌����j�̓I�v�V�����̔�����i��s�j�ɑ��Ă��̎��_�̑�����s���ȃ��[�g�Ńh����n���`�����B
���́A�i2�j�̃I�v�V�����́A�i1�j�̃��[���Ƃ͑S���ʌ̌_��ŁA�����P�Ƀ��[��������ጸ���邽�߂̃v���~�A����ړI�Ŕ��p������̂ł���B�]���āA�i1�j�̃��[���́A�ʂɐ敨�ב֗\��t�̃C���p�N�g�E���[���łȂ��A�~���ă��[���ł����܂�Ȃ��B�܂��A�{���ł̓��[�����z�Ɓi2�j�̈ב֗\����z���ɐݒ肵�Ă��邪�A������قȂ��Ă��Ă����܂�Ȃ��B�܂��A�i2�j�̈ב֗\��i�m�b�N�A�E�g�E�I�v�V�����j�̌_�i�i�X�g���C�N�E�v���C�X�j�ƖڕW����i�g���K�[�E�v���C�X�j�A���邢�͊�����C�ӂɃZ�b�g���邱�Ƃɂ��A�i1�j�̃��[���̋������X�ɒጸ�����邱�Ƃ��A�t�ɕs���ȃ��[������������邱�Ƃɂ���Ă��L���Ȉב敨�\����肷�邱�Ƃ��\�ł���B�܂��A���̎���ł̓h���R�[���E�I�v�V�����p���Ă��邪�A�ב֑���̌��ʂ��ɉ����ăh���v�b�g�E�I�v�V�����p������A�h���R�[���ƃh���v�b�g���ɔ��p����i�X�g�����O�����邢�̓X�g���h���Ƃ����j���Ƃ��\�ł���B
����ɂ����A�i2�j�̈ב敨�\��́A�ݒ��̂悤�ɂ�����I�v�V�����łȂ��Ă��悢�B������s���Ȉבփ��[�g�Ŗ�肷�邱�Ƃɂ��A���������i1�j�̃��[�������ɕ�U�����邱�Ƃ��\�ł���B����בփ��[�g�Ƃ͈قȂ�敨�ב֗\��i�I�t�E�X�|�b�g�ב֗\��j�́A����X�g���C�N�̃R�[���E�I�v�V�����̔����i����j�ƃv�b�g�I�v�V�����̔���i�����j��g�ݍ��킹�邱�ƂŔC�ӂɍ��o����B�������A�I�t�E�X�|�b�g�ב֗\��́A�s���N�Ȏ���ނ��ƂɂȂ�̂ŁA���݂ł͂قƂ�ǂ̋��Z�@�ւ͎t���Ȃ��Ǝv����B
�܂��A�i2�j�̈בփI�v�V�����̑��Ƀf�t�H���g�E�X���b�v��g�ݍ��߂A�N���W�b�g�E�f���o�e�B�u�ɁA�����ɌW��I�v�V������g�ݍ��߂G�N�C�e�B�[�E�f���o�e�B�u�ɁA�V��ɌW��I�v�V������g�ݍ��߂ΓV��f���o�e�B�u�ɕϐg����B�܂��A�i1�j�̃��[�������܂��͗a���ɓ���ւ���A�^�p���i�ɂȂ�B�ꌩ���G�Ɍ�����X�L�[���ł��邪�A��������A�ӊO�ƊȒP�Ȏd�g�݂ł��邱�Ƃ�������ł��낤�B
����
�s���Y���X�Ђ̎В�A�́AY��s�x�X���㗝C�ɁA�ᗘ�Ŏ������B�ł��鏤�i�̏Љ�����߂��Ƃ���A��L�̐敨�\��t�h�����ăC���p�N�g���[���ƃh���敨����\��Ƃ��Z�b�g�ɂȂ��Ă��鏤�i�u�p�b�P�[�W���[���^�C�����[�\��^�v���Љ�ꂽ�B
B��A�ɖ{�����i���Ă���ɍۂ��A�����̈ב֑������b�ɋ�̓I�ɋL�ڂ������ʂ������āA�{���i�͈ב֑��ꂪ�~����Ő��ڂ����ꍇ�ɂ͒����������ł��鏤�i�ł��邱�Ƃ�����A���킹�ĉ~���̏ꍇ�ɂ͈ב֍������邱�Ƃ����邱�Ƃ���������B���̍ہAA�̗v���ɉ�����X�Ђ̉�v�m�ɏ��i�����̃t�@�b�N�X�𑗕t�A��������|�`�������A��v�m����A���������Ă���̂ł������ł悢�Ƃ̉��B���̌�AC��A�̈ӎu�m�F�̂���X�Ђ�K��A�u�В��A���̏��i�̓��X�N������܂���B�~���˂炢�̏��i�ł���B�����A1�~�Ԃ�Ă�700���~�Ԃ���т܂���B�v�Ƃ̌��t�Ő��������BA�͎������~����̈ב֑����\�z���Ă���|�������B���ɉ~���ɂȂ����ꍇ�ł��I�[�v���E�C���p�N�g�E���[���ɏ�芷���A���Z���Ɋ܂ݑ��v�Ƃ��ė��p���邱�Ƃ��ł���ƍ������B
X�Ђ͌��ǃC���p�N�g�E���[���ւ̎芷�����s�킸�A���ς����B���ǁAX�Ђɓ����̑���ƌ_�i�Ƃ̍��z�Ɍ_����z700���ăh�����悶�����z�̈ב֍��������������B���̎��ɂȂ��Ďn�߂Ĉב֍������\�z�ȏ�ɑ傫�����ƂɋC�t���AX�Ђ�Y��s�x�X���㗝B�y�юx�X��C��A�ɑ��ď�L�_��̊댯�����\���������Ȃ��������ߊ댯�Ȍ_������Ƃ���Y��s�ɑ��Q���������߂�i�����N�������B
�����ł͉��L�̂悤�ɔF��A�����̐��������p�����B
A�͍ٔ��ŁA�{�_��ɂ������ጸ���ʂ��P�����x�ł��邱�Ƃ���A���X�N�������x�ł���ƐM�����Ǝ咣���邪�A��������ɂ����̂͌����s�g�������߂��Ă���ł��邱�ƁAY��s�̐��������ɂ����l�̋L�ڂ͌����Ȃ����ƁB
�܂��AB�AC�������ɍۂ��ĉ~�����ʂ��݂̂��������Č_������U�����Ƃ��F�߂��Ȃ����ƁB
A�͋�s����20���~���ؓ�������Ď��Ƃ��s���Ă���o�ϐl�ŁA�ב֑���͂��܂��܂ȗv���ŕϓ����A�\��������ł��邱�Ƃ͏펯�Ƃ��ė������Ă���Ɖ�����邱�ƁB�i�����n�ٕ���4�E6�E26������18�������w���Z�@������xNo.1333
pp43�|48�j
����7
�s�i��
�X���b�v�t���[���~�E���[��
�{���́A�O���ăC���p�N�g�E���[���ł͂Ȃ��A���[���~���[���ɃI�[�X�g�����A�E�h��/�~�X���b�v��g�ݍ��킹�����̂ł���B
�������炱�̏��i������������������p����B
�u�@
�����́A�퍐����A���̖��ŁA���[���~��5���~��������i�ȉ��u���[���~���[���v�Ƃ����B�j�B
����
5�N�i1990�N10��8��〜1995�N10��6���j
����
�N8.63�p�[�Z���g�i�N360���̓�����v�Z�A�N365���Ɋ��Z����ƔN8.75�p�[�Z���g�j
������
���N4��8���A10��8��
�ԍϕ��@
�����ꊇ�ԍρi���O�ԍϕs�j
�A
�����́A�퍐�Ƃ̊ԂŁA���̖��ŃI�[�X�g�����A�h���i�ȉ��A�u���h���v�Ƃ����B�j�Ɖ~����������i�������A�퍐����A57��7684.86���h����1���h������103.64�~�Łu�����v���ƂɂȂ�B�ȉ��u���h��/�~�X���b�v�v�Ƃ����B�j�B
����
5�N�i1990�N10��8��〜1995�N10��6���j
�������z�E�퍐�x���z
57��7684.86���h��
�����x���z�E�퍐���z
5987��1258�~
������
���N4��8���A10��8���v�i���n�� ����7�11�28��1�����������w���Z�@������xNo.1444p66�j
��͂�A������ɂ������i�ł���B�������A�A�̃X���b�v���@�̃��[���Ɛ藣���čl���Ă݂Ă������������B����ƁA�A�̃X���b�v�́A�_���������6������Ƃ�103.64�~�ō��h�����w�����邱�Ƃ��肵���敨�ב֗\��ɈقȂ�Ȃ����Ƃ�������B����103.64�~�Ƃ������[�g�͔C�ӂɌ��肷�邱�Ƃ��ł���̂ŁA103.64�~��荂�����[�g�ō��h�������Ƃ��肵�A���̍����������[���ɕ�U�A�����������������_������Ԃ��Ƃ��A�t��103.64�~���������[�g�ō��h�������Ƃ��肵�A���̍��v�������[���Ŗ��ߍ��킹�邽�߁A�����������グ���_������Ԃ��Ƃ��ł��邱�Ƃ�������B����6�ŏq�ׂ��Ƃ���A�������Ă݂�A���Ƃ������Ƃ̂Ȃ�����ł���B
���̗�ł́A103.64�~�ō��h�����\������Ă���̂ł��邩��A103.64�~��荂�����h�����������v���o�A���p���[�g��103.64�~�������������o�邱�Ƃ�������B
��R����
X�Ђ͐��s���ɍ��v6���̃r�������L����s���Y���Ƃ��c�ފ�����ЁB1989�N���Ѓr���w���̂���Y��s����ؓ�����N�������B���̌�A���Ƃ̕s�U��������x���������S�ƂȂ�AY��s��������y����Ƃ��ď�L�X���b�v�t�~���ă��[�����Љ��A���s�����B���̌�A�~�����h�������i�s�AY��s�ɑ��Đ����`���ᔽ�������Ƃ��đ��Q���������̑i�����N�������B
�����ɂ����āA�{���i�͈�ʂɂȂ��݂̔������Z���i�ł���A�M�`����A�퍐�͌����ɖ{���ܕi�̊댯���ɂ��ēK�Ȑ���������`�����Ă���ƔF�肵���B�������A���̐����͈̔́A���x�ɂ��ẮA�ڋq���K���������̎d�g�݂����S�ɗ�������܂ł̕K�v�͂Ȃ��A�u�K�v�s���Ȃ͖̂{�����i�����Č_�����������ꍇ�ɋ�̓I�Ɏ����������ǂ̂悤�ɂȂ�A�ǂ̂悤�Ȋ댯��������̂��Ƃ������Ƃł��邩��A�퍐�́A�����ɑ��A�{�����i���ב֑���̕ϓ��ɂ��ڋq�̕��S����������������E�������̂ł���A�~�����i�߂Ύ����������㏸����Ƃ����댯�������邱�ƁA���h���Ɖ~�̌������[�g��������ɂȂ�Όڋq�̕��S�������������������ɂȂ�̂��Ƃ������ƁA�敨�\������邱�Ƃɂ�肻�̎��_�ȍ~�̈בփ��X�N�����������@�����邱�Ƃɂ��Đ������邱�Ƃ�v���A����ő����Ƃ����ׂ��ł���v�i���n��
����7�11�28��1�����������w���Z�@������xNo.1444p71�j�Ƃ��Ă���B
Y��s�����[�������ɍۂ��Č�t�����uA$/�~�R���r�l�[�V�������[���̂��ē��v�ł́A�בփ��[�g��������ɂȂ�Ύ���������������ɂȂ�Ƃ����V�~�����[�V�����\���L�ڂ���Ă���A����Ɍ����Ő�������A��ʐl�ł���Η����\�ł������ƔF�肵���B
�܂��AY��s�̈ב֑���̐����ɂ����Ă��A�f��I���f������Ƃ͔F�߂��Ȃ����ƂȂǂ���A�����̐��������p�����B�i���n��
����7�11�28��1�����������w���Z�@������xNo.1444pp64-72�j
��R����
���R������s���Ƃ���X�Ђ͍T�i�����B�T�i�R�ɂ����āAX�Ђ͑i���Ƃ��ēK�����̌����ᔽ�ƃA�t�^�[�P�A�`���ᔽ��t���������B
�T�i�R�ɂ����Ă��A���R�̔F����قړ��P�����B
����ɁA�K�����̌����ᔽ�ɑ��ẮA��s�Ƃ̎���ɂ����Ė{�����i�̂悤�ȋ��Z���i�����U���邱�Ǝ��̂��M�`���㋖����Ȃ��ꍇ����ʓI�ɑS�����݂��Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ��B�������A�i�N�s���Y�ƒ��Ƃ��c�݁AY��s�ȊO����̎ؓ��������T�i�l�iX�Ёj�ɑ��Ė{���i�����U���邱�Ƃ��M�`���㋖����Ȃ��Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����B
�A�t�^�[�P�A�`���ɂ��Ă��A�T�i�l�iX�Ёj�͊댯����̕��@�i�ב֗\��j�ɂ��Ă��炩���ߐ������Ă���̂ł��邩��A�T�i�l����̑��k�⓭���������S���Ȃ��Ă��A��T�i�l�iY��s�j���炱����\���ׂ��@�I�`��������Ƃ͂����Ȃ��Ƃ��āAX�Ђ̍T�i�����p�����B�i��䍂�ٕ���9�E2�E28��1�����������w���Z�@������xNo.1481pp57-61�j
3.3�ϊz�ی�
3.3.1�ϊz�ی��Ƃ�
�i�����ɂ���ĕϊz�ی��̃C���[�W�͈���I�Ɉ����Ȃ��Ă��܂��A���݂ł͓��n�̕ی���Ђł͐ϋɓI�Ɏ�舵��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�ϊz�ی��Ƃ͂ǂ̂悤�ȏ��i�Ȃ̂��낤���B
�ϊz�ی��͏��a61�N10���ɒa�������V�����ی��ł���B���S���▞�����ɂ͌_��őO�����Ē�߂�ꂽ���z�̕ی������x������u��z�v�ی��ɑ��āA�u�ϊz�v�ی��͎��S�ی����Ɩ����ی����������A��ߋ������������ی���Ђ̓��ʊ��莑�Y�̉^�p���тɉ����ĕϓ�����ی��ł���B
�ϊz�ی��̓����ȑO�Ɉ�ʓI��������z�ی��̏ꍇ�A���Y�^�p���ʂ��z�����ɔ��f���ꂽ���A�ϊz�ی��ł͕ی����ɔ��f�����B�܂��A���q�E�z���Ƃ������C���J���Q�C�������łȂ��A��������ЍȂǗL���،������ɔ������p�v��]���v�Ȃǂ̃L���s�^���Q�C���܂ŗ����Ɋ܂܂��̂ŁA�������v�������҂ł���B�����Ώۂ��L���،���̂Ȃ̂ŁA�����I�ɂ̓C���t���ɑ��ċ����ی��ł��邱�Ƃ������ł���B
�ϊz�ی����������ꂽ���������̖ړI�́A�����̏㏸�ɍ��킹�ĕۏ؊z�����������邽�߂ł���B�ی��_��͕��ʒ����ɂ킽��̂ŁA�����[�����Ǝv�����ی����z�������̏㏸�Ƌ��ɖڌ��肵�Ă��܂��A�ی��̋@�\���[���ɔ����ł��Ȃ��ɂȂ�̂�����邽�߂ɊJ�����ꂽ�B�ϊz�ی��͎��єz���^�̏��i�Ȃ̂ŁA�ڌ��肵�Ă��܂����Ƃ����肤��B���̂悤�ȏꍇ�ł��Œᎀ�S�ی����z�͕ۏ���Ă���B�ȏ�̂悤�ȏ��i��������������ϗD�ꂽ�ی����i�Ƃ��Đv���ꂽ�B
�������̂悤�ȕϊz�ی������i�����̒ʂ�ɔ̔����Ă���Ζ��͂Ȃ������̂��낤���A�ꕔ���Z�@�ւɋ߂Ă���m�b�҂������ő�Ƃ��Ĉȉ��̂悤�ȃX�L�[�����l���o�����B
3.3.2�ϊz�ی��𗘗p���������ő�
���肱�ݑΏۂƂȂ�͕̂s���Y���S�̎��Y�\�������A������n�傽���ł���B�n�傽���̑����́A�y�n�͎����Ă��邪�������͂��߂Ƃ�����Z���Y�����܂�ۗL�����A���Y�̗��������Ⴂ���Ƃ������ł���B�y�n�̒l�i�͕ϊz�ی��̗��s�����o�u���₩�Ȃ肵���͑����オ���Ă���A�ЂƂ��ё������N����Ƒ����ł��x�������A��ނȂ��y�n�����������Ȃ��P�[�X�����Ȃ肠�����B�n��Ɍ��炸���{�l�͓y�n�ɑ��鎷���������A���q�̑�܂œy�n��`�������Ɗ���Ă���Ƃ�����B�����ŕی���Ђ���s�ƌ������Ĉȉ��̂悤�ȃX�L�[���������������B
·
�n��A���y�n��S�ۂɋ�s����5���~�������N�����B
·
A�̎qB���ی��҂Ƃ���5���~���ꎞ�����ŏI�g�ϊz�ی����w������iA���g����ی��҂ł��B�܂��A��ی��҂��{�l�łȂ��ꍇ�́A�N�����ɂ��邱�Ƃɂ�葊���ł̉ېŕ]���z���ی�����70������ی����z��2�����T���������z�ɂȂ����𗘗p�������̂�����B���̏ꍇ�ł��A3�N���O�������邱�Ƃɂ��A�ی����������ł���j�B
·
�������ݕی����͐����ی���Ђ̓��ʊ���ʼn^�p�i10�����x�̂��Ȃ荂���^�p���т������A��������̎ؓ������������^�p���[�g�ŃV�~�����[�V��������������������j�B
·
A�����S����BB����ی��҂̏ꍇ�͉��A���߂�������iA����ی��҂̏ꍇ�͕ی������x������j�B
·
������̏ꍇ���ی���Ђ����������߂���E���S�ی����͑������Y�Ɋ܂܂�邪�A���̐ŕ]���z�͐Ŗ@�㕥���|������5���~�ł���i�_��ҁE��ی��ҁE���l�̑g�ݍ��킹�ɂ��A������ŋ��͑����ŁE�����ŁE���^�łɂȂ�ꍇ������A�ŗ��E�ߐŌ��ʂ͈ꗥ�ł͂Ȃ��j�B
·
���߂���E���S�ی����ŋ�s������ԍρA�^�p�v�ؓ����̗����Ƒ����ł��x�����B
��s�ɂƂ��Ă͒S�ەt�̗D�Ǒݏo�悩���Y�Ƃ��Ƃ肱�ރ����b�g������A����ɐ����ی���Ђ��狦�͗a�����邢�͎萔��������B�ی���Ђɂ��Ă��A���z�̕ی�������A�ڋq�ɂƂ��Ă������ő�ƂȂ�͂��ł������B
�m���ɁA�^�p�����܂������A�Ȃ�قǐŐ��̖ӓ_��˂������Ƃ����邾�낤�B�����������ɂ́A�L���،��A���Ɋ�������̓o�u���̕���Ƌ��ɒ���A�������̑��ی���Ђ̓��ʊ�����^�p���т��ቺ�A�������ݕی��������荞�ނ悤�ɂȂ����B
����Ɉ������ƂɁA�n�呤���؋��̒S�ۂƂ��ċ�s�ɍ�������Ă���y�n�̒l�i���A�o�u������Ŗ\�������B��s�����ʋK���̊�A�y�n�S�ۗZ�����������Ă����ߒ��ŁA��s�͒S�ۊ�����N������������ɑ��Ēlj��S�ۂ̍������ꂩ�؋��ԍς𔗂��Ă���B
��������A�����������������ƂɋC�������A���̎��_�ł͎c�O�Ȃ��疜���x���B
�܂��A���ʊ���̉^�p���т͒���A����Ƃ��Ă����̎��_�ł͑啝�ɖڌ��肵�Ă��܂��B����ꌳ�{�͂��납�����������x�����Ȃ���Ԃ��l������B���ɒS�ۂƂ��Ē����y�n���l�����肵�Ă���B�����͎����ɑ��ď[���ȒS�ۂł�������������Ȃ����A���̎��_�ł͒S�ۊ���ɂȂ��Ă���B
A�Ƃ��ẮA�������l���đP�ӂł�������ƂƂ͂����A�ߎS�߂��錋�ʂł���B�����Ă��Ă�������ԍς��Ȃ�������������Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�؋���ԍς��悤�ɂ��ی�����đ���Ȃ����͓y�n�p���āA����ł�����Ȃ��Ƃ��͑��̎��Y���A�Ɛg����݂͂�����Ă��܂��B�ł́A����ł��܂��A�Ƃ��v�����A��Ђł��������߂̂��̎��_�Ŏ���ł��܂��ƁA���ׂĂ������l�ɂ��Ԃ��Ă��܂��A���Y���c�����肪�؋������c���Ă��Ȃ��B��������n���A���ʂ��n���̏�Ԃł���A�i�ׂ����������̂���������ʂƂ���ł���B
�i�ׂɊւ��Ă͂�����������o�Ă���B����8�N7��30���̓����n�ٔ����ȗ��A�����������ی���ЂƋ�s�̐ӔC��F�߂��������o�Ă��邪�A�K�������������i�̔�������ł͂Ȃ��B
3.3.3�ϊz�ی�����
����8
�������i��
�ŏ��̌������i��Ƃ��ĕی��_������y�ы�s�ؓ���_��ɂ��ėv�f�̍��낪����Ƃ��Ă�����̌_��������Ƃ����A����8�N7��30���̓����n�ٔ�������������B
�����̊T�v�B����X��68�̔_�Ƃɏ]�����鎑�Y�ƁB�����ł̎x�����ɔ��R�Ƃ����s���������Ă����Ƃ���A�퍐Y��s�̎x�X��A���O�q�̂悤�ȑ����l���ی��҂ɂ��邱�Ƃɂ������܂ōl�������ϊz�ی����g���������ő���Ă����B���̍ہA���Ȃ荂���^�p���т�ۏ���Ă���̂ɓ������Ƃ��A�����̕s���@�����BA�x�X���̐����ɂ��AX�����������B���̌�AA�͔퍐Z�ی���ЂƘA�������_����e�����߂�Ȃǂ������A���̍ہAZ�ی���Ђ͎����I�Ɍ_��̐��s�����邾���ŕϊz�ی��̓��e���ɂ��Ă͉���������Ȃ������B���̌�A�^�p������������Ƃ����o�A���Ǒi�ׂƂȂ����B
�{�_��ɂ��ẮAA�x�X�����ϋɓI�Ɍ_������ɂނ����U�����Ă���A�������������������ۏ��Ă���悤�Ɍ������������Ƃ���X���_��ɉ������BZ�ی���Ђ͌_������ɍۂ�����������s��Ȃ��ȂǁAX�ւ̐����`����S���ʂ����Ă��炸�A�v�f�̍����F�߂�B��s�ؓ���_���A�x�X���̌����Ɋ�Â��_�����̂ł���A�v�f�̍����F�߂�B�ȏ�ɂ��A�قڑS�ʓI�Ɍ����̎咣���F�߂��锻���ƂȂ����B�i�����n�ٕ���8�E7�E30������25�������w���Z�@������xNo�D1465�Cpp90-109�j
����9
���i��
�ϊz�ی��̕�W��8�Ɠ��l�ɋ�s���s��������ł���B�{����ł́A�ی��_��ɂ��Ă͗v�f�̍��낪����Ƃ��Ė�����F�߂����̂́A��s�̕s�@�s�אӔC��F�߁A�������̉ߎ�������25�|30���ƔF��A��s�ƕی���Ђ̑��Q�����ӔC��F�肵���B
����X�̈ꑰ�͕s���Y���Ƃ��c�ގ��Y�ƈꑰ�BX�ق��̌����͂�������ی��_�������68-79�̍���҂ŁA�w����1�l���������w�Z�𑲋Ƃ��Ă���ق��͎��K�w�Z�A�q�포�w�Z���ƁBX�ꑰ�͂������Y��s�̉i�N�̎����B
�_��̌o�ܓ��͔���8�ɂ�����o�܂Ƃقړ��l�ŁA��s����̂ƂȂ��ĕϊz�ی��̌_������܂Ƃ߂��B�����ɂ����āAX�ꑰ��Y��s�ɑ��đS���̐M���Ă������Ƃ�m��Ȃ���A�s�����ϊz�ی��̃��X�N���\�����������A������ɂ��ĕs���������肽�āA���X�Ɋ��U�������Ƃ�F�肵���B�܂��A�ϊz�ی��ɉ�����A�ی��،��ɂ���^�p���т����U���̐����ƈقȂ�Ƃ̌���X�ꑰ�̈������̎���ɑ��āA�呠�Ȃ̎w���ōŒᐔ�l���L�ڂ���Ă���ȂNj��U�̉�����ȂǕs�K�ȑΉ��ɏI�n�����Ƃ����B
�������A�ϊz�ی��̔̔����i�����ی���Б㗝�X�c�ƈ����ꉞ�̐��������Ă���A���̍ی�t���ꂽ���ʂɑ���X�̈ꑰ��������������������Ă��Ȃ����ƁA�n��̑��q�Œn��̋�s�ؓ���̘A�ѕۏؐl�ƂȂ��Ă���l�����Љ�I�ɂ����Ȃ荂���n�ʂ��߂Ă���i�_���e���r�ǂ̕������v���f���[�T�[�j�A�_����e�𗝉�����ɏ\���Ȓm����L���Ă���ƔF�߂��邱�ƁA���̂��̂ɑ��A�ی���Б㗝�X�c�ƈ��������ɂ����ނ��Ă��邱�ƂȂnj������̗����x���F�肵���B
�ȏ�����Ă��āA�ی��_��ɂ��Ă͗v�f�̍���ɂ�閳����F�߂����̂́A��s�ؓ���ɂ��āA���떳���͔F�߂Ȃ��������̂́A���Q������F�߂��B�������̉ߎ�������25-30���ƔF�肵���B�i���l�n�ٕ���8�E9�E4��5�����������w���Z�@������xNo�D1465�Cpp56-89�j
����10
�����s�i��
��{�I�Ȍڋq�̃^�C�v�͏��i��Ɠ������n��ł���B������tX�͓����s���ɕs���Y�����L�A�����ł̎x���ɂ��ĕs�������炵���Ƃ���A���Y��s����Z���ƕϊz�ی���g�ݍ��킹���u�Z�b�g���i�v�����U���ꂽ�B�Ȍ�̌o�܂͔���8�Ƃقړ����B
�ٔ����̔F��ɂ��A�ی����Z�͐��^�C�v�̗\�藘�����L�ڂ����p���t���b�g�������A�ϊz�ی������{�ۏ؏��i�łȂ����Ƃ�������Ă���A�\�z���������̎��_�ɂ������ʓI�ȗ\�z���q�ׂ����̂ɉ߂��Ȃ��B���ʓI�ɊO�ꂽ�Ƃ��Ă��A�\�����͓̂����̌o�Ϗ�̉��ł́A���������ɔ��ł��Ȃ��Ƃ����B�܂��A�{���̂悤�ȁu�Z�b�g�v���i�ɂ����ẮA��s���ϊz�ی��̐����`�����ƍl�����邪�AY��s��Z�ی���Ђ̐��������킹��ƁA�s���S�ł���Ƃ͔F�߂��Ȃ��B�܂��A�����ɗp�����ی��v���ɂ͖��炩�ɉ^�p���т�����������P�[�X�����L���Ă������B�܂��A�ϊz�ی��ɂ��āA�ی��_��ҁA��ی��҂ɂ��ė������Ă����ق��A�ϊz�ی��ɂ����Ă͎��S���ɕی������x�����A���̍Œ�z�͕ۏ���Ă��邱�ƁA�i��{�ی����z�j�A�ی����͊������ɓ�������ĉ^�p����A�ی����A���Ԗߋ��́A�^�p�̌��ʕϓ����邱�ƂȂǂ𗝉����Ă����ƔF�߂���ƔF�߂��B�]���āA���떳���͐��������A�^�p����肪X�̗\�z�Ȃ������҂���������ɉ߂��Ȃ��Ƃ��āA�����̐������p�������B�i�����n�ٕ���8�E3�E28������14������
�w���Z�@������xNo�D1465�Cpp121-130�j
����11
�����s�i��
����������͒n��B�i�ׂɓ���o�܂Ȃǂ͏�L�Ƃقړ����B
�{���ɂ�����F��ł́A�����������Ԕ̔���Ђɂ����Čo���S��������܂ŋ߂Ă��邱�ƁA�����͔퍐��s�Ƒ����Ŏx�����ɂ��ċ��c�������Ă���A���̍ہA��������H���������ƂɊԌ���Ȃǂ��l���ɓ���Đ����Ȏ��Z�����Ă��邱�ƂȂǂ���A���Z�W�̒m���ɂ��s��������Ƃ͍l�����Ȃ��Ƃ����B�܂��A�ی���Ђ��ꉞ�̐����`���͉ʂ����Ă���Ǝv���邱�ƁA��������̗v�]�ɂ��lj��ő��̕ی���ЂƂ��ϊz�ی��_���lj��Ō���ł��邱�ƂȂǂ���A�ی��A��s�_��Ƃ��L���ł���A�����s�i�ƂȂ����B�i�����n�ٕ���7�E12�E26������37�������i1995�j
�w���Z�@������xNo�D1465�Cpp130-143�j
4.���Z���i�̔��@������Ҍ_��@
4.1���Z���i�̔̔����Ɋւ���@��
����13�N4��1�������Z���i�̔��@���{�s����邱�ƂɂȂ����B���Z���i�̔��@�̖ړI�́A�u���Z���i�̔��Ǝғ������Z���i�̔̔����ɍۂ��ڋq�ɑ��Đ������ׂ������y�ы��Z���i�̔��Ǝғ����ڋq�ɑ��ē��Y�����ɂ��Đ��������Ȃ��������Ƃɂ�蓖�Y�ڋq�ɑ��Q���������ꍇ�ɂ�������Z���i�̔��Ǝғ��̑��Q�����̐ӔC���тɋ��Z���i�̔��Ǝғ����s�����Z���i�̔̔����ɌW�銩�U�̓K���̊m�ۂ̂��߂̑[�u�ɂ��Ē�߂邱�Ƃɂ��A�ڋq�̕ی��}��A�����č����o�ς̌��S�Ȕ��W�Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���v�i���Z���i�̔��@��1���j�ƂȂ��Ă���B
�d�v�����Ɋւ��Đ����`���ᔽ��Ƃ��A����ɂ���Čڋq�ɑ�����^�����ꍇ�ɂ͌��{�����z�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ƃ���Ă���B�]���āA�O�q�̂悤�ȋ��Z���i�Ɋւ��鎖���ɂ��ẮA���Z���F�̔��Ǝғ��������`���ᔽ��Ƃ��Ă���ƔF�肳�ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����������U���Ȃ��Ă͂����Ȃ����ƂɂȂ�i����4���A��5���j�B�������A�ϊz�ی������̂悤�ȏꍇ�A���Z���i�̔��@�͎����ɂ��Ă͉���̋K���u���Ă��Ȃ��̂ŁA����ꕔ���ɂ��Ă͉���̏��u���Ƃ��Ȃ����ƂɂȂ�i������̖@���Ɋ�Â����Q�������𐿋����邱�Ƃ͉\�j�B
4.2����Ҍ_��@
���Z���i�̔��@�Ɠ����ɏ���Ҍ_��@���{�s�����B���Z���i�̔��@�����Z���i�ɒ��ڂ��ċK����������̂ɑ��āA����Ҍ_��@�͎��R�l�ł������҂����ԏ���Ҍ_��ɒ��ڂ��ċK���������Ă���B�]���āA���Z���i����@�ł͋��Z���i�̔̔����ɌW��S�Ă̌_��i��O�͂�����̂́j��ΏۂƂ��Ă���̂ɑ��āA����Ҍ_��@�ł͎��Ǝ҂Ə���҂̊ԂŒ��������S�Ă̏���Ҍ_���ΏۂƂ��Ă��邱�Ƃ��傫�ȑ���_�Ƃ��Ă�������B�܂��C���Z���i�̔��@�̑�8���ɋK�肷�邢����R���v���C�A���X�̌��\�ɌW������͏���Ҍ_��@�ɂ͑��݂��Ȃ��B����Ҍ_��@�Ƌ��Z���i�̔��@�͑I��K�p���\�Ȃ̂ŁA�ڋq�A����҂͗L���Ȗ@���̓K�p���邱�Ƃ��\�ł���B
����Ҍ_��@�̖ړI�́u���̖@���́A����҂Ǝ��Ǝ҂Ƃ̊Ԃ̏��̎��y�їʕ��тɌ��͂̊i���ɂ��݁A���Ǝ҂̈��̍s�ׂɂ�����҂���F���A���͍��f�����ꍇ�ɂ��Č_��̐\���ݖ��͂��̏����̈ӎv�\�������������Ƃ��o���邱�ƂƂ���ƂƂ��ɁA���Ǝ҂̑��Q�����̐ӔC��Ə�����������̑��̏���҂̗��v�̗i���}��A�����č��������̈������ƍ����o�ς̌��S�Ȕ��W�Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���v�i����Ҍ_��@��1���j�ƂȂ��Ă���B
4.3���Z���i�̔��@������Ҍ_��@�̓��e
4.3.1���Q�����Ǝ�����
���Z���i�̔��@�ł͏d�v�����Ɋւ�������`���ᔽ�͑��Q�����ӔC�����Z���i�̔��Ǝғ��ɐ���������B�d�v�����ɂ��Đ��������Ȃ��������Ƃɂ��ڋq�ɑ������������ꍇ�ɂ͌��{�����z�������Čڋq�ɐ��������Q�̊z�Ƃ��A��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă���B
����Ҍ_��@�ɂ����ẮA�O��ƂȂ�����͍����قȂ���̂́A����Ҍ_��@��4���ɂ����āA���Z���i�̔��@�ɂ����錳�{�����z�̑��Q�����Ƃ͈قȂ�A������̂��̂̎�������F�߂Ă���B
�O�q�̂悤�ɁA���Z���i�̎���ɍۂ��A�l�ڋq�����Z���i����Ǝ҂Ǝ���������ꍇ�ɂ́A���Z���i����@�A����Ҍ_��@�Ƃ��ɓK�p�\�ł���̂ŁA���g�ɗL���Ȗ@����I�Ԃ��Ƃ��ł���B���Z���i����@�Ɋ�Â��Όڋq�͎����ŋ��Z���i�p������Ō��{�����z�Q�����Ƃ��ĕ�U���邱�Ƃ����Z���i�̔��Ǝғ��ɗv���ł��A����Ҍ_��@�Ɋ�Â��Ώ���҂͊��ɗ��s���ꂽ����s�������Ƃ��Ď��Ǝ҂ɕԊҐ������邱�Ƃ��ł���B������ɂ��Ă��قړ��l�̌��ʂ�������B�������A���Z���i�̔��@�ɂ����Đ����ł���̂͑��Q�����ł���̂ŁA�ߎ����E�ɂ���Čڋq�̎擾�ł�����z���팸�����\���͎c��A����Ҍ_��@�ł͌_��̎�������F�߂Ă���̂ŁA����҂��x���������z�͑S�z���Ǝ҂ɐ����ł���B����A���Z���i�̔��@�ɂ����Ă͏d�v�����̕s���m�������`���ᔽ�ƂȂ苁�������������邪�A����Ҍ_��@�ɂ����Ă͕s���v�����̕s���m�ɂ��Ă͎��Ǝ҂́u�̈Ӂv�����Ƃ���Ă���i�̈ӂ̗��͏���҂ɂ���ƍl������j�ȂǁA���̗v������ʂɂ͎�̐H���Ⴂ������B
����Ҍ_��@�����Z���i�Ɋւ��镴���ɓ��Ă͂߂��ꍇ�ɂ��ẮA�o�ϊ�撡�����s���������Ɏ���Ƃ��Ď��グ���Ă���B
�u�i����4�|16�j
�،���Ђ̒S���҂ɓd�b�Ŋ��U����āA�O���w�������B�~���ɂȂ�Ȃ��ƌ���ꂽ���A�~���ɂȂ����B
�i�l�����j
�����ɂ����邻�̉��z�A�����ɂ����ē��Y����҂����ׂ����z���̑��̏����ɂ�����ϓ����s�m���Ȏ����i�~���ɂȂ邩�ۂ��j�ɂ��āA�f��I���f��i�~���ɂȂ�Ȃ��ƍ��������Ɓj���Ă���̂ŁA��4���1����2���̗v���ɊY�����A��������F�߂���B
�i����4�|17�j
�؋����Č_�Ă�10�N��ɗ��v���o��ƌ����āA�ꎞ�����̏I�g�ی��ɉ����������A�z�����������Q���o��B��s����200���~�肽�B���̕ԍϊz��293���~�����A10�N��̖�������360���~�ɂȂ�Ɗ��߂�ꂽ�B�������A�\��ʂ�̔z�����o�Ȃ��Ȃ�A�����̕��������Ȃ����B
�i�l�����j
�����ɂ����邻�̉��z�A�����ɂ����铖�Y����҂����ׂ����z���̑��̏����ɂ�����ϓ����s�m���Ȏ����i���v���o�邩�ۂ��j�ɂ��āA�f��I���f��i�؋����Č_�Ă�10�N��ɗ��v���o��ƍ��������Ɓj���Ă���̂ŁA��4���1����2���̗v���ɊY�����A��������F�߂���B
�i����4�|18�j
�ߋ��̐��l�f�[�^���������Ȃ���A�u���܂Ō��{���ꂵ�����Ƃ͂Ȃ��̂ŁA��������{���ꂵ�Ȃ����낤�B�v�Ƃ���ꂽ�̂ŋ��Z���i���_�����A���{���ꂵ���B
�i�l�����j
�u��������{���ꂵ�Ȃ����낤�B�v�ƍ����邱�Ƃ͒f��I���f����邱�Ƃɂ͂����炸�A��4���2����2���̗v���ɊY�����Ȃ��̂Ŏ�����͔F�߂��Ȃ��B�v�i�o�ϊ�撡�i2000�j
�u����Ҍ_��@�y����W�z�vpp10-11�j
��L����͑�ϖ��m�ɋL�ڂ���Ă���B����ł��قړ����w�E���Ȃ���Ă���A���i�̔����Ɉ�ʓI���ʂ��Ƃ��ď�������ꍇ�A���ʓI�ɂ��̌��ʂ����O�ꂽ�Ƃ��Ă��A��s�E�ی���Ђ͐ӔC��Ȃ��i����10�j�Ƃ��Ă���B�܂��A�V�~�����[�V���������Ƃ��ĉ���ނ��̉^�p���[�g��������Ă��鎑�����������ꍇ�́A�����\���ɂ��Ă��v���X�ʂɔ�d���u����邩�����Ő������ꂽ�ł��낤�Ƃ��Ƃ͑z���ɓ�Ȃ����A�����`�����ʂ����Ă���ƔF�肳��Ă���i����7�A10�j�B
4.3.2����
�܂��A����Ҍ_��@�ł́A���@�̋K��ɔ�ׂ�Ǝ������Ԃ��Z�k����Ă���i���@�ł͎�����̏��Ŏ����͒ǔF������Ƃ�����5�N�A�s�ׂ̂Ƃ�����20�N�ŏ��ł���i���@126���B���Z���i���i�̔��@�ɂ����鑹�Q�����������̎����̋K��͖��@��724�������̂܂ܓK�������B���Ԃ͑��Q�y�щ��Q�҂�m�����Ƃ�����3�N�A�s�@�s�ׂ̂Ƃ�����20�N�j�̂ɑ��āA����Ҍ_��@�ł́A�ǔF�����邱�Ƃ��ł���Ƃ�����6�����A����Ҍ_��̒����̎�����5�N���o�߂���Ə��ł���B�i����Ҍ_��@��7���j���Ƃ����ӂ�v����B�܂��A����ȊO�̖��@�̋K������p�����̂ŁA�@��ǔF�̋K����K�p�����B�@��ǔF�Ƃ́A������\�ȍs�ׂɂ��āA
1.
�S���܂��͈ꕔ�̗��s
2.
���s�̐���
3.
�X��
4.
�S�ۂ̒�
5.
���������ׂ��s�ׂɂ���Ď擾���������̑S���܂��͈ꕔ�̏��n
6.
�������s
�̂����ꂩ���������ꍇ�ɂ͒ǔF�������̂Ƃ݂Ȃ����B
������ł���Ƃ��Ƃ́A������̌���������~�Ƃ��i���@��124���j�ł���B��̓I�ɂ́A����҂�����Ҍ_��@��4���ɋK�肷��u��F�v�ɋC�t�����Ƃ��A���邢�́A�s�ދ��E�ċւȂǂ́u���f�v��E�����Ƃ��ł���i�o�ϊ�撡�i2000�j
�u����Ҍ_��@�̉���vp28�j�B
�]���ď�L����ɂ����Ă��A�_���5�N���o�߂���Ώ���Ҍ_��@�̓K�p�͂Ȃ��Ȃ�B�܂��A����҂�����Ҍ_��i�ϊz�ی��j�ɂ���F���Ă������ƂɋC�t���Ă���6�������o�߂�����A�@��ǔF�Ƃ݂Ȃ����s�ׂ������ꍇ�ɂ�������͏��ł���B
�܂��A����Ҍ_��@�ł͂ЂƂ̌_��ɕ����̎��Ǝ҂��W�鎖��ɑ��ē��ɋK���u���Ă��Ȃ��̂ŁA�ʂɏ���Ҍ_��@���K�p�����Ǝv����B���̏ꍇ�A�Z�����s����s�Ƃ̌_��ɑ��Ă�����Ҍ_��@�͓K�p����邪�A�ی��_��Ƃ͕ʌ̌_��Ƃ݂Ȃ���A�ی��_��Ɋւ�������`���͂Ȃ����̂Ǝv����B���̓_�́A����8�ł����l�ɔF�肳��Ă���B
4.3.3�����`��
�����`���ɂ��ẮA�O�L����̂Ȃ��ł��F�߂��Ă���B���Z�@�ւ����i��̔�����ɍۂ��āA�����`�������邱�Ƃ́A���łɍL���F�߂��Ă��闝�_�ł���Ƃ����Ă悢�Ǝv����B
�V���ɐ��肳�ꂽ���Z���i�̔��@�ɂ����Ă��A���Z���i�̔��Ǝғ��ɏd�v�����̐����`�����ۂ���Ă���i���Z���i�̔��@��3���j���A����Ҍ_��@�ɂ����ẮA���Ǝ҂̓w�͋`���ɂƂǂ܂��Ă���i����Ҍ_��@��3���1���j�B
�����`���̋�̓I���e�ɂ��ẮA���Ɩ@�̗�ł́A��n��������Ɩ@��35���ɂ����āA������������܂łɈ��̏d�v�������L�ڂ������ʂ���t������ő�n���������C�҂����Đ��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƋK�肵�Ă���B�ʏ�̏��i�ƕs���Y���i�̎���p�x�̍����l������A��ނȂ����̂�������Ȃ����A����10�N�̒i�K�ł͍��������R�c��̋c�_�ɂ����āA���Ǝ҂ɏ��`��������Ҍ_��@�̂Ȃ��Ŗ��m�Ɉʒu�t����K�v������������Ă���i�o�ϊ�撡�u����Ҍ_��@�i���́j�̋�̓I���e�ɂ��āvp14�j�B����ɁA�u����ɑ��ẮA���Ǝ҂ɐV���ȋ`�����ۂ����ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ������������A�]���A����ɂ����郁���b�g������\�ɑ傫���o���āA����҂����Ȍ�����s����Ń����b�g�Ɠ��l�ɕK�v�ȃf�����b�g�ɂ��Ă͏o���Ȃ������Ȏ��Ǝ҂����X�ɂ��Č����邽�߁A�d�v�����Ɋւ�����̊J�����`���Â���K�v������̂ł���A����܂œK�Ȏ��Ɗ������s���Ă��Ă���A����҂ɖ����������Ă��鎖�Ǝ҂ɂƂ��ẮA�V���ȋ`�����ۂ�����Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ƍl����v�i�o�ϊ�撡�u����Ҍ_��@�i���́j�̋�̓I���e�ɂ��āvp14�j�Ɩ��m�ɒf�肵�Ă���B����ɂ�����炸�A���ۂɌ��z���ꂽ����Ҍ_��@��3���1���ɂ����Ď��Ǝ҂̓w�͋`���ɂƂǂ܂��Ă���̂́A����ҕی삪�啝�Ɍ�ނ����Ƃ̈�ۂ���������Ȃ��B
�܂��A������̖@���ɂ����Ă��A���Z���i�̔��Ǝғ��^���Ǝ҂ɑ��ď[���Ȑ��������邱�Ƃ����߂Ă�����̂́A�ڋq�^����҂̗������m���߂邱�Ƃ�S���v�����Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ́A�u���Ԑ����i��ꎟ�j�v�ɂ����āA�u��������[���Ƃ��Đ����`�����l����ꍇ�ɂ́A�u����������X�N�͈ړ]����v�A�u�������Ȃ���Έړ]���Ȃ��v����{�Ƃ��āv�i���Z�R�c��u���Ԑ����i��ꎟ�j�vp15�j���邱�ƁA�u���p�҂����Z���i�̓��e���ׂĂɂ��Ēm�邱�Ƃ�z�肷��͔̂��I�ł���v�i���Z�R�c��u���Ԑ����i��ꎟ�j�vp15�j�ƒf���Ă��邱�Ƃ�������炩�ł��낤�B
���̓_�ɂ��ẮA����7�ł��A���̐����͈̔́A���x�ɂ��ẮA�ڋq���K���������̎d�g�݂����S�ɗ�������܂ł̕K�v�͂Ȃ��A��̓I�ɑ��ꂪ������ɂȂ�Όڋq�̎������S��������ɂȂ邩�Ƃ������ƁA�敨�\��Ȃǂ̃w�b�W��i���u���邱�Ƃɂ�肻�̎��_�ȍ~�̈בփ��X�N�����������@�����邱�Ƃɂ��Đ������邱�Ƃ�v���A����ő����i���n��
����7�11�28��1�����������w���Z�@������xNo.1444p71�j�A�Ƃ��Ă���B
�܂��A����Ҍ_��@�ɂ����Ă͂���ɁA�u����҂́A����Ҍ_����������ɍۂ��ẮA���Ǝ҂�����ꂽ�������p���A����҂̌����`�����̑��̏���Ҍ_��̓��e�ɂ��ė�������悤�ɓw�߂���̂Ƃ���v�i����Ҍ_��@��3���2��
�j�ƁA����҂̓w�͋K��܂Œu���Ă���B�������{�����͓w�͋K��ł���A�u����҂��{���2���ɋK�肳�ꂽ�w�͂����ɉʂ����Ȃ������Ƃ��Ă��A�{���Ɋ�Â��Č_��̎��������F�߂��Ȃ��Ȃ�����A���Q�����ӔC������������A�ߎ����E�̔��f�ɂ����Ė@�I�ɉe�����y�肷�邱�Ƃ͂Ȃ��v�i�o�ϊ�撡�u����Ҍ_��@�̉���vp6�j�Ƃ���Ă���B
���ۂ̔���ɂ����ẮA�ڋq���̓w�͂ɂ��āA���������f�������Ă���悤�Ɏv����B�������̂͌ڋq�����i�̔����ɂ����Ă��A�ߎ����E�F��̗��R�Ƃ���Ă���B�Ⴆ�A����2�ɂ����ẮA�T�i�l�i�����j���������g�ɂ��Ă̏����q����̂�����A��������X�ɏo�����������g�ɂ��Ē��ׂ悤�Ƃ����������ł����ɂ����ɂ�������炸�A���Ԃ���u�A������p�����đ��Q�������Ƃ��āA�ߎ����E����ɂ�����T�i�l���̗����x��F�肵�Ă���i��㍂�ٕ�7�E4�E20��10�����������w����^�C���Y�x885��p215�j�B�܂��A����9�ł��A���������A�ی��،��̑��t���Ȃ��炻�̓��e�����������A������1�l�͕ی��،��̋L�ڂɋ^�������₢���킹�������̂́A�s���m�ȉ����Ă��Ȃ��ɂ�������炸����ȏ�̒Nj���������߂Ă��܂������ƂȂǂ��ߎ����E�̗��R�Ƃ��Ă����Ă����i���l�n�ٕ���8�E9�E4��5�����������w���Z�@������xNo�D1465�Cp84�j�B
�ڋq���s�i��ł́A��O�Ȃ��A�ڋq���̓��Y���Z���i���邢�͋��Z�����ʂɑ���m���A�o��������Ă���A���Z�@�֑��̐ӔC��Ƃ��闝�R�Ƃ���Ă���B
4.3.4�K��������
�����`���͓Ɨ����đ��݂���̂ł͂Ȃ��A�K���������Ƃ̊֘A�ɂ����đ�����ׂ��ł��낤�B
�K���������Ƃ́u���`�ɂ́A���̗��p�҂ɑ��ẮA�@���ɐ�����s�����Ă����̋��Z���i�̔̔��E���U���s���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������[���ł���A�L�`�ɂ́A���p�҂̒m���E�o���A���Y�́A�����ړI���ɏƂ炵�ēK���������i�E�T�[�r�X�̔̔��E���U���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������[�����Ӗ�����v�i���Z�R�c��u���Ԑ����i��ꎟ�j�vp38�j�B�������A�Ⴆ�Εs�K���Ƃ���闘�p�҂��Ȃ��������]����ꍇ�Ȃǂɂ����ẮA�_��ɂ����鎄�I�����̌������܂���A�u�ꗥ�ɖ����Ƃ����舵����@�߂Ŗ����I�ɋK�肷�邱�Ɓv�͓���i���Z�R�c��u���Ԑ����i��ꎟ�j�vp17�j�Ƃ��ċ��Z���i�̔��@�ɔ��f����Ȃ������̂͑�ώc�O�Ȃ��Ƃł���B
����7�T�i�R�����ɂ����āA���`�̓K�����ɂ��āA�u��ʂɁA�Ǝ҂��ڋq�ɂ����������U����ۂɂ́A�ڋq�̈ӌ��Ǝ���ɉ����������i�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͓��R�ł���A���ɋ��Z�E�،�����̂悤�ɐ�含�y�ъ댯������������ɂ��ẮA�K�Ȋ��U�����ׂ��`���́A�M�`��F�߂���ׂ��@�I�`���Ƒ�������ׂ��ł���v�i��䍂�ٕ���9�E2�E28��1�����������w���Z�@������xNo.1481p59�j�Ɣ��f����Ă���i�������A�{�i�ׂɂ����ẮA�K���������ᔽ�͂Ȃ��Ɣ��f����Ă���j�B�������A��ʓI�ɂ́A�K�����ᔽ�������Ē��ڎ��@���@�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�����`���ᔽ�肷���Ŋ��Ă����ׂ��ł���Ƃ�������̕����ٔ���̑唼�ł���i����
�r�F�w�������U�ƕs�@�s���x����^�C���Y��p318�j�B
�܂�A�K�����������ڋq�ɑ��ẮA���R�����`���̒��x���y�������ƍl������B���̂��Ƃ́A����4�ɂ����āA�u�P�ɍT�i�l���{���������70���鍂��҂ł��������Ƃ̈ꎖ�������āv�܂��A�u�{������ϑO�ɍT�i�l���������g����̌o�����Ȃ��������Ƃ������āA�{������K�����̌����ɔ�����Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��v�i�������ٕ�7�E5�E31��9�����������w����^�C���Y�xNo.897pp144-145�j�Ƃ��Ă���B
4.3.5�����̏ȗ�
����ɁA���Z���i�̔��@��3���4����2���ł́A�ڋq����d�v�����̐����͗v���Ȃ��Ƃ̈ӎv�̕\�����������ꍇ�ɂ́A�d�v�����̐������ȗ����ėǂ��|�K�肳��Ă���B�m���ɁA������A���̋��Z��������čs���Ă���ڋq�ɑ��ẮA���Z���i�̔��Ǝғ��A�ڋq�Ƃ��ɏd�v�����̐������ȗ����Ă��܂��v���������ē��R�ł��낤�B�������A�ڋq�ɋ}���ł��邩��Ƃ��A�ʓ|�����������₱���������͎~�߂Ă���A�Ƃ���ꂽ�ꍇ�ɂ��F�߂Ă��܂��̂͂������Ȃ��̂ł��낤���B
����Ҍ_��@�ɂ����Ă��u���Y���Ǝ҂����Y����҂ɑ����Y�����������悤�Ƃ����ɂ�������炸�A���Y����҂���������Ƃ��́A���̌���ł͂Ȃ��v�i����Ҍ_��@��4���2���j�Ɠ��l�ȋK�肪����B���̋K��Ɋւ��ẮA����҂����������ۂ������R���u�������鎞�Ԃ��Ȃ��A�������邱�Ƃ��ʓ|�ł���v�Ƃ������ꍇ�ł��K�p�����Ƃ��Ă���i�o�ϊ�撡�u����Ҍ_��@�̉���vp15�j�B����10�N�ɂ����鍑�������R�c��ɂ����ẮA���`����Ə������̂́A�u�P�ɏ���҂��������ۂ����Ƃ����̂ł͏\���ł͂Ȃ��A����҂������I���\���ɗ���������ŏ������ۂ����ꍇ�Ɍ���ׂ��ł���v�i�o�ϊ�撡�u����Ҍ_��@�i���́j�̋�̓I���e�ɂ��āvp14�j�ƋL����Ă���̂Ɣ�ׂ�ƁA�啝�Ȍ�ނ���������B
���ړI�Ɍڋq�������������ۂ����A�Ƃ�������͎��グ������̒��ɂ͌�������Ȃ��i���̂悤�Ȏ������A�������ێ�����̂�����Ȃ�̂ŁA�i�ׂɂȂ�Ȃ������A�Ƃ������Ƃ��l������j�B�����A����6�ɂ����āA��s�����A���i�̐�������v�m�ɐ�������t�@�b�N�X�𑗂�悤�˗����ꑗ�t�A��v�m�ɑ��ďڍׂȐ��������邱�Ƃ�`�������A�����В����������Ă���̂ł���A����ł悢�Ɖ��Ⴊ����i�����s�i�j�i�����n�ٕ���4�E6�E26������18�������w���Z�@������xNo.1333
p46�j�B
�܂��A����������ꍇ�̕��@�ɂ��Ă͈�ؐG��Ă��Ȃ��B�Ⴆ�A���݂̏����ł͓d�b��ʂ��Đ����������邱�Ƃ��ܘ_�F�߂���ł��낤���A���ʂ���t������@���F�߂���ł��낤�B���ʂ���t����ꍇ�ɂ́A��t������Ő����������Ȃ��Ă͈�ʓI�ɂ͐������������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���邪�A���@�̏�����͔F�߂��Ă���Ɨ��������B
4.3.6�_��E��������
�_��E�������ʂ̌�t�͗��@�ɂ����ċ`���Â����Ă͂��Ȃ����A���Z���i����@�ɂ����Ă͋`���Â��Ă�����ׂ��������Ǝv����B���Ȃ��Ƃ��A����I�Ɍ_����e�ɂ��ď��ʂŌ��z���邱�Ƃ͋`���Â���ׂ����Ǝv����B����ƂȂ�������ɂ��ẮA���@���̋�������A���邢�͈ȑO�o���̂Ȃ��������������ɍۂ��āA����ȑO�̎���Ƃ͕ʌ̌�����݂���A���߂Ď���̈ӎu���m�F����Ȃǂ̎葱��������Ă���B
�\8
|
���� |
�������ދy�ђ������� |
|
����1 |
�������g�̎��������|�̊m�F���i�L������j |
|
����2 |
�O���V�����،���������� |
|
����3 |
������ |
|
����4 |
�O���V�����،���������� |
|
����5 |
���ɋL�q���� |
|
����6 |
�p�b�P�[�W���[���^�C�����[�����Ɋւ���O���i�L������j |
|
����7 |
A$/�~�R���r�l�[�V�������[���̂��ē� |
|
����8 |
�ϊz�ی��_��̐\�����i�L������j |
|
����9 |
��s�ؓ�������p�ꎞ���I�g�ی��ɂ�鑊���Ŕ[�Ŏ����J��V�~�����[�V���� |
|
����10 |
�p���t���b�g�i�ی������P�K�����킸�ɁA���z�̑����őł��闝�z�̑�����v�������J������܂����I�j |
|
����11 |
�ۏ�v�� |
�\8�́A���Z�@�ւ���t���������A�y�сA�ӎu�m�F�����Ƃ��Čڋq�̋L����������߂����ނ������甲���o�����B����͂�������A�����`���ɂ��đ����Ă���A�Ⴆ�Ύ������U���Ȃǂɂ�������̂��̖̂��������߂����̂͂Ȃ��̂ŁA��L�ȊO�ɂ�����Ɉ�ʓI�ɕK�v�ȏ��ނ͐����Ă�����̂Ǝv����B
�\8���ꗗ���ĕ�����Ƃ���A���ɋ��Z�@�֑��ŁA�V�K�E�V�����̊J�n�ɓ������ẮA���܂��܂ȏ��ނ����Ă���B�ނ���A�ڋq���������s�ǂɊׂ��Ă���Ǝv���A���̓_�ɂ��ẮA�S����s����̒ʒB�ɂ����Ă��A�\����̗��ӓ_�Ƃ��āA�u�i1�j�_�́A���m�A���Ղŏ���҂��������₷���\����p���č쐬����ׂ��ł���B
�_�ɂ����ẮA�_����e��K�i�ɕ\�����邽�߂ɐ��p����g�p������Ȃ��ꍇ�����邪�A��ʓI�ʔO�ɏƂ炵�A����҂����悻�����ł��Ȃ��悤�ȕ\�����Ȃ��悤���ӂ��ׂ��ł���B�܂��A�K�v�ɉ����Ē�`�K���݂��铙�ɂ��A����҂̗����𑣂��悤�z�����ׂ��ł���B
�i2�j���߂ɋ^�`�����˂Ȃ��\���́A����҂Ƃ̊Ԃɖ��p�̍����╴�����������˂��A������ׂ��ł���B
�i3�j�_�̎����I�ȗ����̂��₷�����l�����A���̊����̑傫���̊m�ۂ�}��ƂƂ��ɁA���ĂɈ������Ă��邩�ɒ��ӂ��ׂ��ł���B�v�i�S����s����A����(1999)�u�u����҂Ƃ̌_��̂�����Ɋւ��闯�ӎ����v�̐���ɂ��āvpp4-5�j�Ƃ��Ă���B�������A�{�ʒB�͌_���̂��̂Ɍ��y�������̂ł��邪�A��������ʂɓK�p���ׂ������ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
5.���_
����K�v�Ƃ����̂́A���Z�@�֑��ɓs���ɂ�鎩�Ȗh�q�̂��߂̃R���v���C�A���X�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���Z�@�֑��̏؋��ۑS�̕��@�Ƃ��Ă̏��ނ����邾���ł́A�ڋq�̗����͓����Ȃ��B���Z���i�̔��@�A����Ҍ_��@����̒����I�ȖړI�́A����ҕی���[�������邱�Ƃɂ��A����҂����Ď��{�s��ɎQ�������߁A�����o�ς̔��W��}�邱�Ƃɂ���B���Z�@�ւ��ڋq�ɑ��čs���������A���ށE�����̌�t���A�^�̈Ӗ��̏���ҕی�Ɏ����邽�߁A����҂ɋ��Z���i�̍w���ɍۂ��ė����邽�߂̐����ł���A���ށE�����łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���s�@�̊�ł��A���Z�@�ւ͂��Ȃ�T�d�ɋ��Z�@�֑��̐ӔC�����}��ׂ��A�e�폑�ނ����Ă��邱�Ƃ́A�\8��������炩�ł���B���Z���i�̔��@�A����Ҍ_��@�̎{�s��́A����ɂ��̌X���������Ȃ邱�Ƃ����O�����B�e�폑�ނ̒������A�P�Ȃ���Z���i�̔��@�A����Ҍ_��@�̋K���邽�߂̉B�ꖪ�ƂȂ�Ȃ����Ƃ��肢�����B
�Q�l����
���� �r�F�i1999�j�w�������U�ƕs�@�s���x����^�C���Y��
�V�������Z�̗���Ɋւ��鍧�k��i1998�j�u�_�_�����vhttp://www.mof.go.jp/singikai/nagare/tosin/1a031aa2.htm
�i2000/09/27�j
������Ѓo�[�h���Y�R���T���^���c�i1996�j�u�ϊz�ی��͒N�̐ӔC�H�\�\�\���X�N�Ǘ�����ԑ厖�v�w�o�[�h���|�[�g�x��127���@http://www.bird-net.co.jp/rp/BR960909.html�@�i2000/08/02�j
�����V���u�u�M�p�v�t��̈������@��f�āv1996�N9��6���t���А�http://www.chunichi.co.jp/news2/chu/shasetsu/9609/960906sh.htm�@�i2000/08/02�j
�����@�T���i2000�j�@�w�����@���Z�R���v���C�A���X�Ɩ@�߃|�C���g�x�@�o�ϖ@�ߌ�����@
���Z���i2000�j�u���Z���i�̔̔����Ɋւ���@���ėv�j�vhttp://www.mof.go.jp/kouan/hou11b.htm
�i2000/08/02�j
���Z���i2000�j�u���Z���i�̔̔����Ɋւ���@���{�s�߈Ă̌��\�ɂ��āvhttp://www.fsa.com.go.jp/jp/news/newsj/kinyu/f-20001006-1.html
�i2000/10/17�j
���Z���i2000�j�u���Z���i�̔̔����Ɋւ���@���{�s�߁i�āj�vhttp://www.fsa.go.jp/news/newsj/kinkyu/f-20001006-1.pdf
�i2000/10/17�j
���Z�R�c��i1999�j�u���Ԑ����i��ꎟ�j�vhttp://www.mof.go.jp/singikai/kinyusin/tosin/kin005.pdf
�i2000/08/29�j
���Z�R�c��i1999�j�u���Ԑ����i��j�vhttp://www.mof.go.jp/singikai/kinyusin/tosin/kin010d.htm
�i2000/08/29�j
�o�ϊ�撡�i2000�j
�u����Ҍ_��@�̉���v�vhttp://www.epa.gp.jp/2000/c/0605c-abridment.pdf
�i2000/09/20�j
�o�ϊ�撡�i2000�j
�u��������@����Ҍ_��@�vhttp://www.epa.gp.jp/2000/c/shouji/keiyakuhou0.pdf
�i2000/09/20�j
�o�ϊ�撡�i2000�j
�u����Ҍ_��@�y����W�z�vhttp://www.epa.gp.jp/2000/c/shouhi/keiyakuhouex.pdf
�i2000/09/20�j
���������Z���^�[�i1998�j�u����Ҏ���ɌW������ҋ��̎��ԁvhttp://www.kokusen.go.jp/cgi-bin/byteserver.pl/pdf/n-19981026_1.pdf
�i2000/10/27�j
���������Z���^�[�i2000�j�w�u���Z���i�ɌW�����҃g���u�����v�������x���������Z���^�[
���������Z���^�[�i2000�j�w����Ґ����N��
2000�x���������Z���^�[
���{�@�P�Y�i2000�j�u����Ҍ_��@�A���Z���i�̔��@�Ƌ��Z����v�w���Z�@������x1587�Fpp6-11
���{�@�P�Y�ďC�i2000�j�w���Z���i�̔��@�E����Ҍ_��@���킩���xBSI�G�f���P�[�V����
���{�ٌ�m�A����i1998�j�u���{�Ńr�b�O�o���i���Z���x���v�j�ɔ�������ҕی����ɂ��Ă̈ӌ����vhttp://www.nichibenren.or.jp/sengen/iken/980319_2.htm
�i2000/08/29�j
���{�ٌ�m�A����i1999�j�u�V�������Z�̗���Ɋւ��鍧�k��u�_�_�����v�ɑ���ӌ����vhttp://www.nichibenren.or.jp/sengen/iken/9901-03.htm
�i2000/08/29�j
���{�ٌ�m�A����i1999�j�u���Z�R�c���ꕔ��u���Ԑ����i��ꎟ�j�v�ɑ���ӌ����vhttp://www.nichibenren.or.jp/sengen/iken/9908-06.htm
�i2000/08/29�j
���{�ٌ�m�A����i1998�j�u��s�����菑�y�я���҃��[���_�ɑ�����P��āvhttp://www.nichibenren.or.jp/sengen/iken/9810-07b.htm
�i2000/08/29�j
���{�ٌ�m�A����i1998�j�u����Ҍ_��@�i���́j�̋�̓I���e�ɂ��Ă̍��������R�c�����Ґ�������ԕɑ���ӌ��vhttp://www.nichibenren.or.jp/sengen/iken/9810-12.htm
�i2000/08/29�j
���{�ٌ�m�A����i1999�j�u�������ҐM�p�@�̐���Ɍ����āvhttp://www.nichibenren.or.jp/sengen/iken/9907-01.htm
�i2000/08/29�j
���{�ٌ�m�A����i1999�j�u����Ҍ_��@���٘A���āvhttp://www.nichibenren.or.jp/sengen/iken/9910-22.htm
�i2000/08/29�j
�������A����N�v�ďC�i1990�j�w�_�C�������h�@�t�@�C�i���V�����E�v�����i�[�{���u������16�������X�N�}�l�W�����g�x�@�@�_�C�������h��
�����{�i1998�j�u�u����Җ��Ɋւ��鐢�_�����v�i����10�N1���j�vhttp://www.sourifu.go.jp/survey/shouhisha.html
�i2000/10/27�j
�����@��A���@�G�s�i2000�j�w����Ҍ_��@�@���Z���i�̔��@�@���S����x�@���{�@��
���z�@�����i2000�j�w���{�ŋ��Z�T�[�r�X�@�x�@���{�o�ϐV����
�R�c�@����i2000�j�u���Z���i�̔̔����Ɋւ���@���̐����v�w���Z�@������x1590�Fpp6-17
�S����s����A����i1998�j�w��s�̎Љ�I�ӔC�ƃR���v���C�A���X�ɂ��āx�S����s����A����
�S����s����A����i1999�j�u�u����҂Ƃ̌_��̂�����Ɋւ��闯�ӎ����v�̐���ɂ��āvhttp://www.zenginkyo.or.jp/news/news021.htm
�i2000/08/29�j
�S����s����A����i2000�j�u��s�����菑�ЂȌ^�̔p�~�Ɨ��ӎ����̍쐬�ɂ��āvhttp://www.zenginkyo.or.jp/news/newsgintori.html
�i2000/09/25�j
�������ٕ�8�E3�E18��5�����������w����^�C���Y�x923��pp146-150
��㍂�ٕ�7�E4�E20��10�����������w����^�C���Y�x885��pp207-216
�������ٕ�4�E3�E30��8�����������w����^�C���Y�xNo.885pp216-222
�������ٕ�7�E5�E31��9�����������w����^�C���Y�xNo.897pp144-150
���n�ُ��a62�E1�E29��24�����������w���Z�@������xNo.1149pp44-46
�����n�ٕ���4�E6�E26������18�������w���Z�@������xNo.1333
pp43�|48
���n�ٕ���7�11�28��1�����������w���Z�@������xNo.1444pp64-72
��䍂�ٕ���9�E2�E28��1�����������w���Z�@������xNo.1481pp57-61
�����n�ٕ���8�E7�E30������25�������w���Z�@������xNo.1465�Cpp90-109
���l�n�ٕ���8�E9�E4��5�����������w���Z�@������xNo.1465�Cpp56-89
�����n�ٕ���8�E3�E28������14������
�w���Z�@������xNo�D1465�Cpp121-130
�����n�ٕ���7�E12�E26������37�������i1995�j
�w���Z�@������xNo�D1465�Cpp130-143