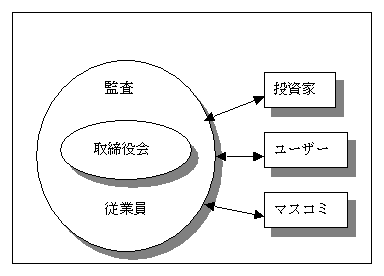
ヒューマン・リソース(HRE703)4クレジット
コンプライアンスを機能させるための組織
Rushmore University
Global Distance Learning DBA
大國 亨
このコースワークを提出するにあたって、ここに記述されている文章/アイデアは、引用の表記がない限り、私の作品であります。また、私がこのコースの研究を手がけるまでは、このコースワークは存在しなかったことを確認します。
金融庁の金融検査マニュアルの施行を受け、コンプライアンスという言葉も、大変一般的なものとなってきた。
そして、金融機関も、コンプライアンス担当部署の設置に続々と乗り出してきている。しかし、コンプライアンス担当部署をどのように設置し、どのような人員を配備するかといった問題については、まだまだ試行錯誤の段階であるといってよいだろう。
コンプライアンスの確保は、何も金融機関にだけ求められているわけではなく、一般企業へも当然に求められているのである。
本論文においては、コンプライアンスを機能させるための組織とはいかなるものであるかを、内外の事例を取上げ、それぞれ何が問題であったのか、どうすれば防げたのかを明らかにし、さらにコンプライアンスを機能させるにはどのような組織を作ればよいのかを導き出すことを目的とするものである。
目次
1.はじめに
2.コンプライアンスとは何か
2.1組織の暴走
2.1.1薬害エイズ事件
2.1.2過去の主な薬害事件
2.2なぜ同じ誤りが繰り返させるのか
2.2.1事件の分析に関して
2.2.2事件の事後処理
3.コンプライアンスを実現する組織
3.1組織とは何か
3.1.1良い組織の条件
3.1.2共同体と機能体
3.2組織崩壊のメカニズム
3.2.1機能体の共同体化
3.2.2環境への過剰適応
3.2.3成功体験への埋没
3.3金融庁検査マニュアル
3.3.1コンプライアンスとリスク管理
3.3.2コンプライアンスと組織
4.内部監査と外部監査
4.1外部コンプライアンス監査活用のメリット
4.2組織のイメージ
4.3外部監査は万能か
5.結論
資料1薬害エイズ厚生省判決
資料2三菱自動車リコール隠し事件
資料3雪印乳業集団食中毒事件
参考文献
1. はじめに
企業・官庁による不祥事が後を断たない。金融機関をはじめとして、あらゆる企業においてコンプライアンスの確立があらためても求められている。ところで、一連の不祥事を分析してみると、個人の犯罪という側面ももちろんあるだろうが、何らかの原因で組織そのものがバランスを失い、内部からの自壊作用によって組織そのものが崩れてしまったような例が散見される。組織はなぜ自壊作用を起こしてしまったのであろうか。どのようにすれば、組織の自壊を防ぐことができるのだろうか。そして、コンプライアンスを機能させる組織とはいかなるものなのであろうか。
2.
コンプライアンスとは何か
コンプライアンスは、通常法令遵守などと訳されることが多い。しかしながら、コンプライアンスの意味合いは、単なる法令遵守にとどまるものではない。むしろ、倫理基準といったほうが適切であろう。単なる法令遵守であれば、法令という明確な物差しをもって行動を律するわけであるから、違反であるか否かは明確に区別される。これに対して、倫理基準は倫理というあいまいなものが判断に関わってくるので、そのように明解な区別が常に可能となるわけではない。
コンプライアンスは、よく車のブレーキに喩えられる。ブレーキのない車には危険で乗っていられないと。コンプライアンスとは、車が暴走しそうなときに、ブレーキをかけて危険な状態に陥らないようにする機能であると言えるだろう。別の言い方をすれば、組織が持っている自浄作用とも言えるだろう。
車を運転して交差点に差し掛かったとき、黄色信号に変わることがある。そんな場合に、アクセルを吹かして通りぬけてしまう人と、ブレーキを踏んで止まる人とがいる。車の運転において、黄色信号を通り抜けてしまうことは、現実にはよくあることで、それだけで交通違反として捕まることもないだろう。コンプライアンスでも同じことである。黄色信号に突っ込んでも、今回は大丈夫かもしれない。しかし、黄色信号に突っ込むことが常態化したら、極めて危険である。交差点が広くて、横切りきらない内に赤信号になるかもしれない。気の早い右折車が右折を始めてしまうかもしれない。もちろん、状況によっては交通違反でペナルティーを受けるかもしれない。
組織が常態的に行っている業務も、状況の変化、環境の変化などによって、実態に適合しなくなっている可能性もある。今までやっていたことだからといって、明日も大丈夫とは限らないのである。そのようなリスクに対して、これではいけないと声を上げることがコンプライアンスの持つ自浄作用である。
コンプライアンスの確保のために、担当部署の設置、既存の検査部や法務部の拡張、コンプライアンス・オフィサーの配備など、様々な組織上の施策が採られるのが一般的である。しかし、コンプライアンスは、この自浄作用抜きには機能しない。組織に自浄作用がなければ、コンプライアンスなぞは、違反が見つかりさえしなければかまわない、といった程度の認識しか生み出さないであろう。
そのような事態も、もちろん好ましくないことではあるが、コンプライアンス違反を違反として認識しているだけ救いがある。組織にとってさらに恐いのは、悪いと知りながらコンプライアンス違反をする人間がいることではなく、コンプライアンス違反を違反と認識することなく、なんの疑問も持たずに組織の論理がまかり通ってしまうことである。こうなると何の歯止めもなくなって、組織が暴走することになる。
2.1 組織の暴走
昨今の組織の暴走劇を見ていると、組織は必然的に暴走するようにも思える。組織はなぜ斯くも暴走し易いのであろうか。以下、幾つかの例を挙げながら、それらに共通する組織の病理を検討する。
2.1.1薬害エイズ事件
2001年9月に元厚生省の役人に下された東京地裁の判決は、組織として仕事をし、責任の所在があいまいな官僚組織に対しても官僚個人の責任が問えるとした点で新しい判決であるといえるだろう。しかも、この判決では官僚個人の行った政策・施策ではなく、不作為に対して責任が問われた点でも官僚たちの常識を覆した判決であると言えるだろう。
個人の責任が問われたのは初めてではあるが、国に不作為の責任を認める判決は、ハンセン病訴訟における熊本地裁の判決、戦時中に強制連行・逃亡した中国人を保護する義務を国は果さなかったとする東京地裁の判決などで認められている。そしてさらに具体的に行為に係った(不作為であるから係らなかったというべきであろうか)官僚個人の責任をも問えるとしたわけであるから、ある面では一歩前進であったといえるであろう。
但し、厚生省の元生物製剤課長一人に司法の裁きが下されたことに関しては、厚生省という組織が行ってしまった犯罪を一人の責任のみに帰してしまったという感をぬぐえない。医学部を卒業して専門知識を持つ医系技官の生物製剤課長に対して、上司である薬剤局長は事務官が就くことになっており、今回の事件では訴追を逃れた。例え上司であっても、今回の事件の発端となった血液製剤の安全性を見極める能力にかけるとされたわけである。もしそうであれば、上司は指揮も監督もせず、責任も負わないことになってしまう。同じように血液製剤が原因で血友病患者にエイズを感染させた事件を起こしたフランスでは、担当大臣、首相まで起訴されたの比べると、責任追及がいかにも甘いと思われるがいかがであろうか。今回の事件では、薬害エイズに係る個人名がクローズアップされすぎたために、組織としての厚生省が引き起こした犯罪を断罪、再発防止の歯止めとするという側面が関心の中心とならなかったことが惜しまれる(但し、判決では事件には上司や同僚らも係っており、こうした人々にも責任の一端があったと指摘している。資料参照)。
2.1.2 過去の主な薬害事件
最近ではエイズ薬害事件が大いに話題となったが、実は過去にも幾多の薬害事件が起きており、多くに旧厚生省が係っていた(以下、薬害関係の記事は主として柳田邦男『この国の失敗の本質』pp37-39)。
l
サリドマイド事件
サリドマイドは西独で1957年に開発された催眠剤。日本でも催眠剤として使用された。西独においては1961年11月に小児科医レンツ博士が妊婦の服用は胎児に危険があると告発、半月後にサリドマイドの使用禁止と回収が決定された。これに対して日本では厚生省もメーカーもレンツ論文を無視、発売停止と回収に踏み切ったのは1962年9月になってからであった。しかも回収が不徹底で、妊娠初期にサリドマイドを服用した妊婦から手足、耳に障害をもって生まれた子が300人を超えた。
(因みに、サリドマイド剤の分子構造には人間の右手と左手のような鏡像体を持つ(不斉化合物)2種類がある。このうち一方には薬効があるが、他方は催奇性があったために悲劇が起きた。このような化合物を有機金属化合物触媒を使って作り分けることを可能にしたことを評価されて名古屋大学の野依
良治教授は2001年ノーベル化学賞を受賞した。)
l
キノホルム事件
キノホルムは戦後、アメーバ赤痢の薬として使われていた。その後整腸薬としても使われるようになり、広範に使われるようになった。しかし、スモン病(視神経や脊髄などに障害が生じて慢性化する難病)との関連など、副作用があるとしてアメリカでは1960年にFDA(Food
and Drug Administration(米国食品医薬品局))が1960年に医師の「要指示薬」に指定、店頭販売を禁止、適用もアメーバ赤痢だけに限定した。しかし、医学会でもスモン病の原因はウイルス説とキノホルム説が対立しており、しかも初めはウイルス説が有力であった。1970年になってようやく学会でもキノホルム説に軍配が上がり、販売が中止された。それ以前の期間、日本の厚生省はキノホルムの販売を整腸薬として認めつづけ、スモン病患者が世界的に見ても多発し、その数1万数千に達した。
l
クロロキン事件
クロロキンは古くからあったマラリア治療薬。外国では網膜症の副作用が明らかにされていた。日本では、1958年クロロキンは腎炎にも有効であるとの報告を基にして、生産が拡大された。そのころアメリカではFDAがクロロキンの適用をマラリアに限定、メーカーに対し、医師向けの「副作用警告書」を発行させていた。日本でも副作用被害報告が相次いだことから1974年になって製造が中止されたが、その後も使用禁止などの措置は取られず、1976年に厚生省の薬事審議会が腎炎などへの効果を否定するまで使われ続け、製薬会社は在庫を一掃したとも言われた。クロロキン薬害によって失明した腎炎などの患者は数百から数千人に上るといわれている。
l
水俣病、ハンセン病
水俣病、ハンセン病は薬害事件ではないが、上記薬害事件と極めて似通った構図をたどった。
1950年代にはすでに地域に特有な奇病として注目されていた。1956年、熊本大学の研究班は、水俣病は有機水銀中毒である疑いが濃いと発表した。1957年の時点で熊本県はチッソの工場廃水による魚介類の汚染が水俣病の原因である可能性が強いと見て魚介類の捕獲、販売を禁止しようとしたが、厚生省は水俣病と工場廃水の因果関係が明らかではないとして規制を拒否した。1958年イギリス人の神経学者は知覚障害・運動障害・視野狭窄・言語障害などの症状1937年イギリスの農薬工場で発生したメチル水銀中毒患者の臨床症状と極めて似通っていることを指摘した。その後も紆余曲折をたどり、最終的に政府が水俣病をアセトアルデヒドの製造過程で生成されたメチル水銀化合物による有機水銀中毒であることを認めた1968年まで、生産は続けられた(group
60 http://www.d4.dion.ne.jp/aoisora/sub84.htm
09/30/2001)。
ハンセン病は、その昔らい病とも呼ばれた、らい菌により末梢神経や皮膚が侵される慢性の細菌感染症である。らい菌の毒性は極めて弱く、感染しても発病するのはまれであるといわれる。しかし、かつては遺伝病であるとか、極めて感染力が強いとの思い込みかららい予防法(1996年廃止)に基づく強制隔離政策が取られ、社会的偏見も極めて強かった。2001年熊本地裁の判決では、1960年以降は治療法の確立によって患者を隔離する必要がある疾患ではなくなっており、厚生省はこの時点で隔離政策を変更する必要があったのにこれを怠ったのは重大な過失があるとして国の責任を認めた(熊日ニュース2001年5月11日
http://www.kumanichi.co.jp/sokuho/20010511.html
09/30/2001)。
2.2
なぜ同じ誤りが繰り返されるのか
なぜ同じような誤りが繰り返されるのであろうか。以上の事件を概観すると、幾つかの共通項が浮かび上がっていくる。
2.2.1 事件の分析に関して
第一に、事件の重大性に関する認識が足りないことがあげられる。上記の事件はいずれも多数の人命に関わることであるから、事件が重大であることはもちろんである。しかし、その場合でも大変反応が鈍い。
また、分析に大変慎重を期すことも特徴的である。多数の人命が失われている現実があり、その事実への関与が疑われている薬物なり物質がある。しかし、確定的な証拠はない。確定的な証拠が存在しないことを理由として、処分を引き伸ばす。そしてその間も被害は増大するのである。
実際には、上記の例でも明らかな通り、ある物質なり薬物なりを摂取した全員が病気なり死亡したりする訳ではない(そのような事例があるとすれば、明らかな殺人・傷害事件であり、厚生労働省(上記事例では旧厚生省)が関わる事例ではない)。むしろ、疫学的な事件では、多数の傍証から結論を導くのが普通である。
上記には記載しなかった東京大気汚染公害訴訟の裁判においても、排気ガスと人間の喘息との関係を“完全に”証明した疫学モデルは存在しないと国は主張し続けているという。同訴訟において、原告側が証拠として提出した青森県立保健大学教授 嵯峨井 勝の実験に対して、国側の証人は「慢性疾患としての全特徴を明確に示す喘息の動物モデルは存在しない」「これらのモデルはヒトの喘息の特徴を部分的には模してはいるものの、ヒトの疾患(気管支喘息)そのものを再現していない」(矢貫 隆「自動車の罪」『CAR
GRAFHIC』 2001年11月号p204)と反論しているそうである。実は、川崎、名古屋南部、尼崎と続いた大気汚染公害訴訟は、すべて原告側の勝利に終わり、残るは東京のみであるにもかかわらず、国側はこのような態度を取り続けているのである。嵯峨井教授は、これに対し、「医学の知識や、治療方法などは、ヒトと部分的に類似したモデルを使いながら発展してきたのです。そうした面を見ようとせずに、完全に同じ動物モデルでないから因果関係を認めようとしないのは、星を取ってくれと泣く子どもと同じ論理です。立派な完璧主義を装いながら、問題を泥沼にたたき込む議論といえます。公害問題において、完璧主義ほど無責任なものはないと私は思います」(矢貫 隆 同前p204)と慨嘆している。同教授が大学を出た後、富山県の衛生研究所に勤務し、そこでイタイイタイ病に出合ったことが、後の公害病研究を専門とすることにつながったそうである。そして、彼はこうも供述している。「水俣病の時もそうでした」(矢貫 隆 同前p204)。この時の行政の対応は、「魚介類が要因である可能性が高くても、魚介類に含まれる原因物質を特定できなければ、漁獲を禁止することはできない。」「チッソ水俣工場の排水が汚染源である疑いが濃くても、排水のなかのどのような化学物質が水俣病に結び付くのかが特定できなければ、排水や操業を停止させることはできない。」(柳田
邦夫『この国の失敗の本質』pp45-46)というものだったそうである。
一見、科学的な議論を尽して結論を得ようとすることは、単にその場の思いつきで原因を決めつけてしまうよりは思慮深い方法に思える。しかし、政策や対策はそれを行った場合の損失と、それを行ったことによって救われる利益を比較検討して決められるべきである。過去の厚生省の対策は、度を越した完璧主義が単なる保守主義(あるいは単なる守旧主義か)、独善に陥り、救うべき利益を見逃してしまった感が強い。
このことは、厚生省などの組織が大変権威主義に陥り易いことと関連している。それまで存在しなかった病気や事件であるから、権威者などは存在しないはずである。もちろん、その事件の分析、対処方法の考案等についての適任者は存在するであろう。ところが、その適任者を選任する際に、旧来の基準をそのまま当てはめ、選任後は任せっきりになってしまう。エイズ事件の阿部
英被告はまさにこのパターンであろう(ただし裁判では無罪判決が出ているのはご存知の通り)。いったん決まってしまうと、それが固定化し、固定化したことが権威となり、権威は新しい概念を認めない、というパターンである。
また、事件の処理に際して、情報を秘匿しようとする強い傾向があることも見逃せない。この情報の秘匿は内部に対しても、外部に対しても行われる。
内部に対しては、セクショナリズムに陥った官僚組織がそれ以外に対して情報を秘匿する傾向があり、それが権威を際立たせる源となっている。
外部に対しては、もちろん権威を強調する意味もあるのであろうが、情報秘匿の理由としてむしろよく持ち出されるのは、「国民のパニック防止」というものである。最近の狂牛病に関する情報の伝達においても、被害が少ないうちに情報を公開すると、かえって国民の間にパニックを引き起こしかねないので、対策が進んでから公開しよう、といった対応が取られた。しかし、情報が共有されなかったことから、後に狂牛病と認定された牛の所属した農場から第一報の後も牛が出荷され、結局行方が分らなくなってしまった。
この時も、“完全に狂牛病と認定されたわけではないから”という理由で、処分が遅れたのである。
しかも、情報の公開が遅れ、その上情報を適確に掴んでいる部署がはっきりしない(この事件では管轄が農林水産省と厚生労働省の2省庁に別れたことも拍車をかけた)ことも手伝い、パニックこそ起こらなかったものの、牛は危ないのではないかという不信感だけが残った。牛丼の吉野家ディー・アンド・シー社長
安部 修仁は2001年10月9日、「8月中間決算発表の席上で、10月以降、売り上げに狂牛病問題の影響が出始めたことを明らかにした。行政当局の対応などが「消費者不安を増幅させたようだ」」と指摘するとともに、「「スーパーや外食などでは牛肉関連の売り上げが約3割減る影響が出ているとみられる。特に家族を中心顧客としている企業は客数の落ち込みが深刻で死活問題になっている」」(日本経済新聞2001年10月10日http://www3.nikkei.co.jp/kensaku/kekka.cfm?id=2001101001680
(10/11/2001))と述べている。そもそも狂牛病問題に関しては、全国の食肉処理場で実施する簡易検査で要請の牛が出た場合に確定検査の結果を踏まえて最終的な診断を行う、狂牛病研究の第一人者である帯広畜産大学の品川森一教授ですら、「感染源と見られている肉骨粉飼料が国内で牛に対して完全に禁止されず一部で使われていたことについて「私のような専門家でさえ牛に肉骨粉は使っていないと説明を受けてきた。肉骨粉が日本で使われる余地があったとは信じられなかった。」」(日本経済新聞2001年10月17日)と語っている。これでは、当局の対応を信じろといっても無理である。おそらく、安全宣言は早々に出るのであろうが、需給のバランスの狂いははるかに長期化するのではないか。
この権威云々に関しては、最近話題となっている旧石器捏造事件も参考になるであろう。同事件は東北旧石器文化研究所の藤村新一前副理事長が同氏の手がけた多くの旧石器遺跡において捏造を働いたというものである。日本における旧石器遺跡の発掘のほとんどに関わってきたといわれる同氏の引き起こした事件だけに、その影響は大きく、教科書の書き換えにまで発展している。ところで、同氏は実は市井の一介のアマチュア考古学愛好家でありながら、手弁当で東北旧石器文化研究所を設立、副理事長に就任した人物である。無名の時代には、当然権威がなく、権威主義の学会で自分の研究を認めさせるのに血のにじむような思いをしたことであろう。ところがいったん権威になると、石器のでっち上げをしても、誰もとがめだてしなくなる。そしてその権威が引き剥がされた今、同氏の関連した遺跡はおそらく全てでっち上げのレッテルを貼られるのであろう。現在ではマイナスの権威となっている同氏をかばうものは全くおらず、まともな検証もされないままニセ遺跡のレッテルだけが貼られることになるのではないだろうか。事件は事件として、その事後処理も検証されなくてはならない。
2.2.2 事件の事後処理
上記薬害事件において、事件の事後処理はどのように行われてきたのであろうか。薬害エイズ事件、公害裁判などは依然として係争中であるが、それ以外の事件の多くは決着済みの事件である。それら薬害事件からは、ひとつのパターンが読み取れる。
それら事件の多くについて、ある薬物について副作用報告などが主に外国で出される。日本では、例え報告を知っていたとしても、無視されるか、その薬物を認可した(その認可にかかわった厚生労働省、薬事審議会、実験を引き受けた医者が存在し、さらに業界など関係各団体への配慮あるといわれている)手前、すぐにそれが誤りであったとは言いにくいため、“確実な証明がされていない”という理由で、使用中止などどの強い措置をとることが遅れる。その間に被害は広がる、というパターンである。同じような事件が何度もおきるのは、事後処理に欠陥があるからだと考えられる。
日本におけるこれらの事件処理において特徴的なのは、その事件に関わりのある省庁などの責任部門が、徹底した責任逃れをするか、例え責任者の追求が行われたとしても、誰かをスケープゴートにして組織に責任追及の手が伸びないようにする犯人探しが行われることである。その場合、特定の個人に対して何らかの処分が下されるが、往々にして処分は形式的で、以後の官僚生命に影響を及ぼさない軽微なものにおわりがちである。しかし、旧石器偽造事件のような個人犯罪も、それを許してしまった考古学会の存在を抜きにしては成立しないはずである。犯人探しが先行するため、なぜそれが起こったかというメカニズムの解明がなされない。そのような解明は必然的に組織にメスが入ることになるため、内部からは積極的には行われない。外部からの圧力をかわすためだけに、実名を挙げた犯人探しが行われ、それで一件落着、人のうわさも七十五日、となるのを待つだけである。
そのような事後処理が行われる結果、事件の記憶・記録が有意義な形で引き継がれない。間違いを犯したのはその個人であり、私は違う、というわけである。当然、事件を教訓として組織を刷新する、マニュアルなどを作成して同じ過ちを繰り返さないようにするといった努力は行われないか、形式で終わる。
全く同じことを、生命保険会社のコンプライアンスの仕事に携わって強く感じる。コンプライアンスに関わる問題は、法令や業界・会社の内規に違反する事件であるから、本人の処分は必然である。しかし、それ以上の、たとえば組織の問題などは大きく取上げられることはあまりない。たとえば、生命保険の勧誘において、コンプライアンスに関わる問題が頻出しているのは販売体制に問題があるのではないか、と思われても、そのようなことが問題になることはまずない。何しろ、コンプライアンスの徹底を指示しているそばから、人事評価をより業績主義に改訂する、といったことが現実に行われているのであるから。業績とはもちろん保険の販売実績である。金融庁のマニュアルにも、過度の実績主義はいさめられているし、「業績評価、人事考課等に当たって、保険募集に関する法令等の遵守に係る取組み状況を、業務推進より優先させるなど、的確に反映し得るための方策を講じているか」(金融庁「保険会社に係る検査マニュアル」、同マニュアルについては後述参照)といったことが問題にされている。コンプライアンス評価を人事考課に取り入れる、といったことは抽象的には行われることにはなっている。しかし、従業員にとっては、コンプライアンスを重視したからかどうかの理由はともかくとして、契約件数が減ってしまったら給料は下がってしまう現実のほうが重要なのである。
もちろん、営利企業において、販売を行う側が大きな力を持っていることは当然である。しかし、それ以上に強く作用するのは、もしそんなことを問題にしたら組織そのものの、あるいは経営陣の責任が問われることになる、という意識である。経営陣として責任を取りたくないなどという意識が表立って言葉として表に出てくることはありえない。しかし、潜在的には誰でも思っていることであり、しかもお互いにそう思っていることはわかっているのであるから、自分の地位を犠牲にしてまで誰も口には出さないのである。
それでは、どのような形式の事後処理が好ましいのであろうか。これに関しては、柳田邦男が著書の中で興味深い手法を紹介している。「装置産業や交通機関などで発生する事故の原因分析法として広く普及しているものに、Fault
Tree Analysis(FTA=失敗樹木分析)と呼ばれる欠陥分析法がある。事故というものは単一の原因だけでおきることは稀であり、大抵の場合、多くの要因が連鎖的に重なり合って破局に至るのである。」「従って、事故から安全対策のために教訓を引き出すには、破局をもたらすに至った最後の突破口とも言うべき一つのミスだけを指摘しても駄目であって、事故に関わった大小さまざまな欠陥やミスの連鎖関係を、時系列に沿って、コンピュータ・プログラムのロジック・フロー(論理の流れ)のような形に分析整理して捉える必要がある。それがFTAである(その分析図は、樹木の枝分かれのようなイメージになることから、Fault
Treeと呼ばれる)。」(柳田邦男『この国の失敗の本質』pp252−253)
3.
コンプライアンスを実現する組織
優れた分析方法を生かすための土台として、そのような分析を受入れる組織を作らなくてはならないだろう。組織には、どうしても、上記のように問題を隠したり、自己改革を妨げるような意識が働いたりするようである。組織の問題を正す場合には、このような傾向があることを承知の上で、自動的に働くメカニズムとしてコンプライアンス体制を組み立てなければいけないことがわかる。
そのような自動的メカニズムの考察の前に、組織とはどのような性質、傾向を持つものであるかについて、以下において明らかにしておく。
3.1
組織とは何か
組織には、幾つかの共通した構成要素がある。前経済企画庁長官 堺屋 太一は、組織の構成要件として、1.構成員、2. 共通の目的と共通の意思、3.一定の規範、4. 命令と役割、5. 共通の情報環境、の5つを挙げている(堺屋 太一『組織の盛衰―何が企業の命運を決めるのか』pp83-86)。
まず一つ目の構成員の存在とは、組織にとっては、その組織を構成する構成員が存在することが必要だということである。構成員が存在し、線引きが行われることによって、非構成員と構成員が区別される。ただし、組織の性格や機能によって構成員の定義も異なるのが通常である。一定の地域に住んでいれば自動的に地域コミュニティーの構成員とみなされるであろうが、血縁関係がなければ血族コミュニティーに加わるのは困難であるなど、様々な規制や要求が加わっているのが普通である。
次に挙げられた共通の目的・意思とは、組織には通常何らかの分野において何らかの目的を達成しようとする意志が働いているのが普通だということを示している。構成員が、バラバラに別々のことを成し遂げようとしているのでは、組織とは呼べないからである。逆に、目的や意思が明確であればあるほど構成員の組織に対する帰属意識が高まるという特徴を持っている。
3番目の一定の規範とは、ある組織においては、ある行為やその結果の善悪、美醜を評価する、一定の行動規範が存在することを指す。いわゆる「永田町の論理」などもこれに当たる。共通の規範を持つ人間が組織の構成員で、この規範が途切れる地点が構成員と非構成員を区別する基準となるのである。
次に挙げられた命令と役割とは、組織においては、命令を下す権限が与えられた人間がおり、組織の構成員には役割が与えられており、何らかの役割を果すことが期待されているのが通常である、ということである。ただし、いわゆる同好会や趣味の会などでは、必ずしも命令権者や役割が明確に規定されていない場合がある。その場合でも、組織の趣旨に背く行動をとれば、退会を求められるなど、制裁・不利益が与えられるのが通常である。
最後の共通の情報環境とは、組織においては、ある情報環境を構成員が共有していることが必要である。宗教団体などを考えると分り易い。ある宗教団体には、その構成員のアイデンティティーの中心となるべき教義(その他教主、御神体などとともに)が置かれるのが普通である。その教義によって構成員はそれ以外の人と区別される。逆に言えば、教義が異なれば、異なった組織ということになる。
過去の歴史を振り返ると、隔絶された環境(地理的、政治的環境など)に置かれた結果、情報環境が途絶、元々の組織とは異なる教義をもつに到り、元々の宗教団体とは袂を分った(あるいは別の宗派として認識されるに到った)宗教が多数存在する(例えば、ローマカトリックとギリシャ正教、エチオピアに取り残されたコプト教(キリスト教の一派)、大乗仏教と小乗仏教、ラマ教などなど)。あるいは、軍隊という共通のルーツを持ちながら、まったく異なった組織の論理を持つ陸海空軍なども同じことが言えるであろう。情報環境が異なってしまうと、組織は組織ではいられないのである。
3.1.1よい組織の条件
一般的に、組織の良し悪しを図る尺度として挙げられるものは、組織の大きさ、固さ、強さであるという(堺屋 太一 『組織の盛衰―何が企業の命運を決めるのか』 pp88-90)。
大きさとは、まず組織の構成員の数である。単純に構成員の多い組織が一般的にはよい組織とみなされる。また、組織の構成員が共通の情報環境を持つことが組織の必要条件であったのであるから、情報量の多さもこの範疇に含まれるであろう。また、企業などにおいては資産額、売上高、経常利益、業界シェアなど、様々な数字をもって組織の良し悪しの基準とされるのは、経験からも明らかであろう。これらの数字は大きいほど良いとされていれる。
次の固さとは、共通の目的と共通の意思による組織への帰属意識とも言いかえられるであろう。組織において中核的な構成員になればなるほどこの固さが問題になる。
最後の強さとは、目的達成能力の高さといいかえられるであろう。組織には、その組織特有の目的がある。その目的を達成するためには、組織が一丸となって事に当たらなくてはならない。命令は迅速に決定され、確実に実行されなくてはならない。
以上3点が良い組織の条件とされるのであるが、問題は上記3条件が鼎立しないことにある。
まず、組織の大きさを優先した場合、どうしても組織としての固さや強さは失われてしまう。組織が大きくなれば、1人のリーダーの下に一致団結とはいかず、どうしても下部組織を置かざるを得ない。その場合、組織の中に内部組織を抱え込むことになり、その内部組織自体がひとつの組織としての特性を持つことになる。その構成員は元々の組織の構成員であると同時に内部組織の構成員であることになり、組織としての固さが失われることになる。また、良く官庁を揶揄する場合に使われる、省益あって国益無し、さらに局益あって省益なし、という事態が引き起こされる。内部組織が元々の組織とは異なる情報環境、目的を持つに到り、効率的に目的達成を図ることができなくなり、組織としての強さも失われることになる。
次に、固さが追求された場合はどのような事態が引き起こされるであろうか。固さとは、組織構成員の帰属意識の強さのことでもあった。一般的には組織への帰属意識が強いほうが良い組織であるとみなされるが、帰属意識が強すぎると様々な問題が引き起こされる。帰属意識を高めることが組織を良くすることに繋がるわけであるから、構成員の間で、帰属意識の高さが競われるようになる。通常、組織への帰属意識は、中核的な構成員の方が高い。そうなると当然、その中核的な構成員を中心として組織内組織が作られるようになる。主導権争いや権限争いが繰り広げられることになり、組織としての大きさの追求はできなくなるし、分派の結果組織としての強さも失われてしまうであろう。
強さが追求される場合はどうであろうか。強さとは、目的達成能力のことであった。その場合、構成員に要求されるのは、能力である。業務遂行に当たっての能力が最も重視される結果、能力のないものは組織からはじき出されていき、組織としての大きさを追求するわけにはいかなくなる。また、能力重視は、帰属意識の高さを要求しない。能力だけを武器に組織を渡り歩くようなスペシャリストも重用されることになる。当然構成員のモチベーションは低下、組織としての固さは失われることになる。
以上のように、組織としては大きさ、固さ、強さのいずれも手中に収めたい目的であるが、残念ながら全てを一時に実現するわけにはいかないのである。
3.1.2
共同体と機能体
上記において、何の定義もせず、組織という言葉を用いたが、すべての組織が同じような機能や目的を持っているとは思えない。営利を目的とする近代的な株式会社組織と趣味の同好会では、組織としての違いがあるはずである。
この点について、堺屋 太一は著書のなかで、興味深い分類をしている。彼は、組織を共同体(ゲマインシャフト)と機能体(ゲゼルシャフト)に二分した(堺屋
太一 同前 p107)。共同体と機能体の特徴を表にすると、以下のようになる。
|
|
共同体 |
機能体 |
|
典型 |
家族・地域社会 趣味の会・社交クラブ |
企業・官公庁・軍隊 |
|
目的 |
構成員の心地良さ (好みの充足) |
外的目的の達成 (利潤・行政・勝利) |
|
良い組織の尺度 |
固さ(結束力・仲間意識) |
強さ(目的達成力) |
|
理想の状態 |
公平性と安住感 |
最小の負担で目的達成 |
|
人材評価の尺度 |
内的評価による人格 |
外的評価による能力と実績 |
(堺屋 太一 『組織の盛衰―何が企業の命運を決めるのか』 p111)
共同体とは、構成員の満足を目的として組織である。従って、構成員の内的な評価によってその価値が定まる。当たり前のことだが、草野球のチームの戦績が悪くても、必ずしも監督のくびが飛ぶわけではない。野球をすることが目的で、皆が満足していれば、別に成績にこだわる必要はない。
これに対して、機能体はプロ野球のチームである。プロ野球のチームは勝つことが要求される。成績が悪ければ、監督なり選手なりの責任を問う声が必ずあがる。その際の評価の基準は、チーム(あるいは個人)の成績という外的な尺度が採用されるため、大変明確である。
ところで、草野球のチームでは、成績が悪くても、絶対に監督や選手の責任が問われないのだろうか。プロ野球のチームでは、成績が唯一最大の評価の拠り所であって、結束力や仲間意識は必要ないのであろうか。
実はそんなことはないのであって、草野球のチームですら、レギュラー選手には野球が上手な人間が構成員の中から選ばれるであろう。そうすると、当然レギュラー争いが構成員の中で起こる。逆に、プロ野球の選手ですら、一見公平に見える打率などの外部評価だけで査定したら、不満が募るのではないだろうか(おれが勝てなかったのは打線が悪いからだ。おれが打てなかったのは、監督がバントのサインばっかり出したからで、ちゃんとチームプレーには貢献している、など。)。
組織とは、生き物のように、上記の様々な分類の間を行ったり来たり、あるいはひとつの組織の中に様々な要素を織り込みながら存在しているのである。
3.2組織崩壊のメカニズム
堺屋は、組織が崩壊するメカニズムには3種類しかないと断じている。「第一に、「機能体の共同体化」(または「共同体の機能体化」)。第二は「環境への過剰適応」。そして三番目は「成功体験への埋没」である。」(堺屋 太一 『組織の盛衰―何が企業の命運を決めるのか』 pp166−167)
3.2.1機能体の共同体化
「機能体の共同体化」とは、上記プロ野球集団の例を考えれば分り易いであろう。機能体であるプロ野球組織は、勝利を至上目的とし、そこに属する個々人は、打率や勝利数といった一定の外部的評価を基準として評価される。しかし、それだけでは選手にとって居心地の悪い組織になってしまう。そこで、選手の帰属意識を高めるための方策が採られることになる。組織としての「固さ」を追求するのである。その結果、「機能体の共同体化」が引き起こされる。組織として勝利を目指すのではなく、内部にいる個人の快適さが重視され、結果として勝利することができなくても、「しょうがない」となるのである。
このことが顕著に表れたのが、旧日本軍である。堺屋も著書の中で事例として取上げており、その他旧日本軍の敗因を組織としてのあり方の問題として捉えている例は多い。明治時代に欧米の軍隊を手本として近代国家にふさわしい軍隊として組成された旧日本軍は、日清・日露戦争の栄光をバックに、日本国内において、それこそ天皇をも凌ぐ権威と実力を手に入れたかに思われた。ところが、たった一度の敗戦を機に、敗戦後の日本に組織としては何の痕跡も残さず消え去ってしまったのである。
ここでは具体的な事例は取上げないが、その栄光と敗北の鮮やかなコントラストは、「機能体の共同体化」がいかにたやすく強固な組織をも崩壊させてしまうかを示している。薬害事件を何度引き起こしても、いまだに厚生省は崩壊していないが、「強さ」、「大きさ」、「固さ」を兼ね備えたかに思えた旧日本軍は、その重圧に耐え切れず、崩壊してしまった。
旧日本軍に関しては、日本を守るための軍隊という本分を忘れ、ひたすら組織内部の論理を優先、最終的にはその母体である日本を崩壊の危機にさらしてしまったのである。機能体の共同体化が招いた悲劇である。
また、堺屋は「共同体の機能体化」も組織崩壊の要因としてあげている。これも、上記草野球チームを考えれば分り易いであろう。もともと、地域や職場の親睦を目的とした草野球のチームが勝利だけを目指してメンバーの選定や入れ替えを実行したらどうなるだろうか。ギスギスした人間関係に嫌気したメンバーは離脱、親睦を目的としたチームは崩壊してしまうだろう。
いずれにしても、組織が本来の目的とは異なった目標を追求しだしたとき、組織は崩壊の危機に晒されるのである。
3.2.2
環境への過剰適応
次に挙げられた、「環境への過剰適応」では、恐竜の例が挙げられている。「恐竜の栄えた時期の地球は、気候温暖で著しく湿潤、運動は緩慢でも巨体を持つ巨大爬虫類が生息するのに適した状況だった。それが何らかの理由(例えば隕石の落下で立ち昇った塵で太陽光線が遮断されたりして)寒冷化し乾燥化して、身体は小さいが動きの早い哺乳類に有利な状況に変わった。ところが、恐竜は、その化石類から見ると、末期になるほどますます巨大化しているという。」(堺屋
太一 『組織の盛衰―何が企業の命運を決めるのか』 p183)
このことは、日本の生命保険会社に大変良く当てはまると思われる。日本の生命保険は戦後、倍々ゲームのような成長を遂げてきた。しかし、バブルも崩壊し、生命保険加入率が90%以上になると、業界として完全に頭打ちの状態になってきた。当然、従来の販売手法である生命保険の営業職員(生命保険のおばちゃん)を大量に動員したローラー作戦が曲がり角に来ている(あるいは通り過ぎてしまった)ことは明らかである。ところで、生命保険加入率が90%を超えた現在でも、外資系の生命保険会社の参入は止まっていない。なぜならば、彼らは従来型の日本の生命保険会社と同じ手法で同じ土俵に立って勝負しようとしているのではない。彼らは、新しい商品を新しい販売チャンネルで販売するために参入しているのである。
ところが、生命保険業界の業界紙にはいまだに、営業職員をいかに勧誘し、いかに育て上げていくかといった連載記事が多く載っている。巨大化した日本の生命保険会社には、大量に辞めていく営業職員を大量に補充するシステムが出来上がってしまっていて、とてもではないが急激な方向転換はできないのである。
平成11年末在籍の営業職員326,974人に対して平成12年末在籍数は293,293人、ただし、平成12年度中に一般過程試験(これに通らないと生命保険の販売ができない)に合格者合格した物の数は154,974人(出典
『平成13年版生命保険統計号』株式会社保険研究所)。一般過程試験は、会社を変わらなければ一生有効である。上記の数字が意味しているところは、半分辞めて同じ数だけ新人を採用しているということである。
日本の生命保険会社は、恐竜の最後のような末路を辿るのであろうか。
3.2.3
成功体験への埋没
最後にあげられた「成功体験への埋没」とは、成功した過去の経験から抜け出せず、環境がいかに変化しても十年一日の如く従来の手法から抜け出せなくなってしまうことをいう。
ここでも例として取上げやすいのは、旧日本軍であろう。旧日本軍にとっての栄光の成功体験は日露戦争における勝利であった。陸軍は二百三高地攻略の経験から白兵による銃剣突撃(もっとも突撃するのは兵隊で将校ではなかったのであるが)を、海軍においては日本海会戦における見事な艦隊決戦における勝利の経験から、大艦巨砲主義とも揶揄される艦隊決戦を最重要視した。
ところが、20世紀の戦争は科学技術の発展とともに大きく変貌していった。そして、大艦巨砲主義に決定的なダメージをもたらしたのは、実は旧日本軍だったのである。太平洋戦争緒戦における真珠湾攻撃も戦術として世界に衝撃を与えたが、その後のシンガポール攻略に際し、後にマレー沖海戦と呼ばれる戦いにおいて、英戦艦プリンス・オブ・ウェールズとレパルスを航空機のみで撃沈したことは、世界各国の海軍軍人の度肝を抜いた。真珠湾に停泊していた戦艦はともかく、戦闘態勢にある航行中の戦艦は航空機単独の攻撃では沈まないと思われてきたからである。当時の英国首相チャーチルも「あらゆる戦争で、私はこれほど直接のショックを受けたことはなかった」(太平洋戦争研究会 『太平洋戦争』p54)と回想しているそうである。そこで、各国海軍は航空戦力との連携、航空戦力の活用を図る方向に大きく方向転換した。ところが、このような戦果も、旧日本軍の大艦巨砲主義を捨てさせることはできず、結局日本海軍は戦艦大和・武蔵とともに轟沈したのである。いかに日露戦争における成功体験が強烈であったかを示している。
これに関して思い起こされるのは、ある大手重電メーカー(名は秘す)における事例である。業界でも最大手のメーカーであった同社は、その巨大化と同時に官僚化に悩まされていた。そのことを自覚していたのは、外部の人間ではなく、当然内部の人間である。そこで、内部改革のための部署(機構改革部と仮に名づける)が設けられた。当然機構改革をもくろんでいたわけであるが、その部署の部長は真面目な性格であったためか、自分の部署を潰さずに他人の部署を潰すことはできないと、その配下の機構改革部の存続期間に時限を設けた。そして、機構改革の青写真を経営陣に提出して機構改革部は予定通り消滅した。ところが、結局消滅した部署は機構改革部だけであったそうである。名門企業であるから、組織内の各部署は当然有能な人材を多く抱え(同社は日本で最も多くの博士を雇っている会社といわれていた)、専門分野では多くの業績を上げてきたのであろう。ビジネス環境が少々軽少短薄を指向したからといって、簡単に過去を捨てられなくなってしまっていたのである。
内部の人間の誰もが全体としては変わらなくてはいけないことを認識していながら、個別の部署で抵抗した結果、結局変われなかったのである。
3.3
金融庁検査マニュアル
金融機関のコンプライアンスについては、金融庁の検査マニュアルが今後の金融機関経営の上で守らなくてはならない基準について、大変有意義な情報を提供してくれている。
「金融検査については、平成10年に「新しい金融検査に関する基本事項について」(蔵検第140号)を定め、自己責任原則の徹底と市場規律を基軸に、明確なルールを前提とした透明性の高い行政への転換を図ってきているところである。平成11年には「預金当受入金融機関に係る検査マニュアル」、平成12年には「保険会社に係る検査マニュアル」を定め、これにより、監督当局の検査監督機能の向上及び透明な行政の確立のみならず、金融機関等の自己責任に基づく経営を促し、もって金融業性全体に対する信頼の確立を図っているところである」(金融庁「証券会社に係る検査マニュアルについて」金検第170号)。さらに、平成13年には「証券会社に係る検査マニュアル」も制定された。その後も細かな変更・改訂が加えられ、現在の金融庁検査の際の運用基準となっている。
3.3.1
コンプライアンスとリスク管理
金融検査マニュアルの構成は、法令遵守等のコンプライアンス態勢の確立に関する事項と、市場関連リスク・信用リスクといったリスク管理態勢の確立を2本の柱として成り立っている。しかし、コンプライアンスとリスク管理とは実は表裏一体の関係にあるのである。
コンプライアンスとリスク管理の関係については、雪印乳業の食中毒事件と三菱自動車のリコール隠し事件が大変参考になる情報を提供してくれているので取上げてみたい。両事件の経緯については、資料1、2において報道機関による発表を引用しておいたので、事実関係については参照されたい。
いずれの事件においても、事件の端緒に、明確な法令違反(コンプライアンス違反)が存在したことは間違いない。両事件共に、企業として許されない行動をとったことは事実である。しかし、ここで問題にしたいのは、事件が発覚した後の両社の対応である。いずれの事件も、企業にとって由々しき事態であり、適確かつ迅速な対応が求められていた。ところが、両社の取った対応はまさにこの逆であった。事件が発覚した後も、責任の所在がはっきりしないばかりか、事実関係すらはっきりしなかった。両社とも、記者会見の場において社長が記者会見中に、その場に居合わせた担当者が社長の会見内容とは異なる事実を発表するという失態を演じた。
「最も象徴的だったのは、集団食中毒が判明して4日目、ようやく謝罪会見に姿を見せた社長の石川哲郎が、会見の席で大阪工場のバルブから、長期間洗浄していないことを示す乳固形分が見つかったことを知らされ、同席した大阪工場長の下野勝美に向かって「君、それは本当か」と声を荒げたシーンだった。」(雪印乳業の場合。産経新聞取材班『ブランドはなぜ墜ちたか―雪印、そごう、三菱自動車
事件の深層』p22)
「クレーム隠しの社内報告調査中間報告を運輸大臣、森田一に提出した三菱自動車工業社長の河添克彦(当事)は、その後の記者会見で集中砲火を浴びていた。報告に盛り込まれなかった違反が、会見の最中に発覚したためだ。」「「今回リコールの対象となった車の中で、すでに修理を終えたものはありますか」との質問に、河添に代わって答えた三菱自動車の担当者が「大型バスの不具合を運輸省に届け出ず、回収・修理した」と答えたのだ。この事実は河添には報告されていなかった。」「「リコール隠しはない」と大見えを切った直後の河添は「知らなかった……」と絶句してしまう。」(三菱自動車の場合。産経新聞取材班『ブランドはなぜ墜ちたか―雪印、そごう、三菱自動車 事件の深層』p241)
事件に関わりのある極めて重要な事実であるにも関わらず、社長には知らされていなかったのである。記者会見の場で大失態が演じられ、報道機関を通じて白日の下に晒されてしまったのである。その結果、新聞報道などにおける両社の発表が二転三転する結果となり、消費者の信頼をいたく裏切ることになった。
リスク管理の一環として、日ごろから不祥事に対応した記者会見の方法を準備しておく、というのは無意味であろう。しかし、両社において、重要な事実が社長に知らされなかったということは、両社において、不祥事件に対する社内的な取決めがなされていなかった、なされていたとしても、実行されなかったことを示している。このような事項は、まさにコンプライアンスの対象事項である。不祥事件に対する報告義務・経路がはっきりしているといったコンプライアンス体制が確立されていれば、両社にとって最悪といえる事態は避けられたのではないだろうか。
3.3.2
コンプライアンスと組織
金融庁検査マニュアルの位置付けは、あくまでも検査官が金融機関を検査する際に用いる手引書であるとされており、検査マニュアルの項目を一字一句過たずに実行することが求められているわけではない。逆に、それぞれの金融機関が自己責任の原則の下、それぞれの規模・特性に応じた独自のマニュアルを作成することが求められている。検査にあたっても、検査官が検査マニュアルを機械的・画一的に適用することがないように配慮することが求められている。ただし、チェック項目の語尾が「しているか」または「なっているか」とあるのは、特にことわりのない限りすべての金融機関にミニマム・スタンダードとして求められる項目であるとされている。実際のチェックリストを一覧すれば分るとおり、実は多くの項目が上記のような語尾で終わっている。もちろん、そのような対応がなされていない場合でも、金融機関の業務の健全性や適切性確保の観点から見て、各金融機関の対応が合理的であり、その規模・特性・業務内容から見て充分に効果をあげていれば必ずしも不適切な対応として非難されるわけではないとされている。
金融検査マニュアルの位置づけが、金融機関の自己責任においてコンプライアンスの確立を求めている以上、以前の裁量行政時代に見られるように、金融機関の一挙手一投足を縛るように細かく組織のあり方を規制していないのは当然であろう。それでも、組織のあり方についても幾つかのポイントが指摘されている。
l コンプライアンス等の法務問題を一元管理する体制等について、内部規定等を整備しているか。
・ コンプライアンスに関する統括部門を設置しているか。また、統括部門の所轄事項を明確にしているか。
・ 各業務部門及び営業拠点毎に、適切にコンプライアンス担当者を配置しているか。
l 不祥事件や苦情等に対処する体制を整備しているか。
・ コンプライアンス担当部門は適切に苦情等の事後確認を実施しているか。
・ 不祥事件の事実確認、関係者の責任の有無を明確化及び責任追及、監督責任の明確化を図る体制を確立しているか。
l 特定の職員を長期間にわたり同一部署の同一業務に従事させないように、適切な人事ローテーションを実施しているか。
l 適切な保険募集管理体制を確立するために、コンプライアンス担当部門は、営業部門から独立した立場で、適切な役割を担う態勢が確保されているか。例えば、営業推進や募集に係る規定などについては、コンプライアンス担当部門が営業推進部門から独立した立場で、作成ないし検証を行う措置が講じられているか。
l 取締役会は、各種リスクを管理するリスク管理部門を整備し、その格リスク管理部門のリスクを統合し管理できる体制を整備しているか。また、上記の体制においては、例えば収益部門とリスク管理部門を分離するなど沿う相互牽制等の機能が十分発揮されるようになっているか。
l 管理者は、取締役会で定められた方針に基づき、専担者の配置等、リスク管理を行うための組織が機能を有効に発揮できるよう、適切に人員の配置を行っているか。また、人員の配置に当たっては、実務経験者等、専門性を持った人材を配置しているか。
(以上、金融庁「保険会社に係る検査マニュアル」より抜粋)などが代表的なチェック項目である。
ところで、コンプライアンス担当部門(リスク管理部門も含め)に対して、チェックリストは、一見矛盾した要求を課していることに気付く。
例えば、コンプライアンス担当部門は営業などから独立した部門であることが求められている一方、その人材にはローテーションが求められている。また、ローテーションを求めている一方で実務経験、専門性を持った人材を配備することが求められている。
しかし、コンプライアンスの確立、リスク管理の徹底を目指すのであれば、上記条件はいずれも満たされなくてはならないのである。例えば、コンプライアンス担当の部署は被監査部門との癒着を避ける意味からも、独立性が強く求められている。欧米の金融機関では、検査・監査部門の人員は、他部署とは採用形態も異なっており、公認会計士・弁護士などの有資格者も多いという。
また、コンプライアンス部門に限らず、人員の滞留はとかく組織の共同体化を招き易い。ひとつの部署に長くとどまることによる慣れ・慢心が事故に繋がり易いことは言うまでもないであろう。特に金融機関では、取引先との間に特殊な関係ができることを嫌い、定期的に担当者を入れ替えることが慣習となっている例が多い。
コンプライアンス担当者に、高い専門性が求められることは言うまでもない。営利企業における業務担当者は、流れ作業を繰り返すだけの単純労働を求められているのではない。当然業務に精通し、その改善を提言できるような能力が求められているのである。
しかし、上記3条件はいささか相反することを求めているだけでなく、単独に追求し過ぎると、本来の目的を逸脱してしまう危険性を併せ持っている。
独立性を求めれば、当然他部署とのローテーションなどは期待できない。そうすると現場における実務知識を持たぬまま監査業務のみを続けることになる。このような場合に危険なのは、コンプライアンス担当部署が独善に陥ることである。たとえば、コンプライアンス違反を根絶するには、コンプライアンス違反の可能性がある業務を排除すれば良い。危なそうなことには手を出さないのである。しかし、この判断のさじ加減は極めて難しい。結果としては、過度に慎重な政策が採用されることになる。また、コンプライアンス担当部門の目的はコンプライアンスの根絶のみにあるかの錯覚から、違反があること事態が好ましくないように思われる。そうなると、違反を隠したりするインセンティブまで働くことになってしまう。逆に、重箱の隅をつつくような監査を行う結果、営業部門と対決してしまうことも多い。その結果、営業部門はとにかく監査をやり過ごすためだけに形式を整えるようになってしまう。
人事ローテーションにしてもしかりである。人事ローテーションを行うことによって、組織の共同化は防げるかもしれない。しかし、金融機関などでしばしば問題になるのは、余りにも短期間で担当者が交替してしまうことにより、経験や知識が蓄積されず、取引先としても、一から関係を作り直さなくてはならなくなることである。それだけでなく、ある施策を実行した担当者とその結果が表れたときの担当者が異なることから、好ましくない結果が出た場合でも、責任の所在があいまいになってしまう。担当者としても、自分の責任にされることは当然好ましくないので、逃げ口上として前任者の責任を持ち出すのである。もちろん、共同体化した組織においては、実際に前任者の責任追及などは真剣には行われない。
また、コンプライアンス部門と他部門の人事交流が行えば、実務経験をもった人間が監査を行うことになるが、被監査部門との独立性がはかれず、人事ローテーションを行わなければ、頭でっかちの監査専門家が重箱の隅をつつく監査を行うことになり、内部管理態勢等の評価及び問題点の改善方法の提言などは期待できない。
高度の専門性も、行過ぎれば問題になる。コンプライアンスなどは、いわゆる倫理的な側面を含む業務であるため、必ずしも弁護士や公認会計士といった有資格者のみが適任というわけではない。「その筋のいちばんの専門家が座長になるのは、よいように見えるが、実はその座長の意のままに審議会や検討会の方向づけがなされてしまうことになりやすい。座長はむしろ素人が就くべきだ。ちなみに、アメリカの病院倫理委員会は、医師以外の看護婦とか弁護士が座長につき、メンバーに闘病経験のある市民が加わっているという例が少なくない」(柳田 邦男『この国の失敗の本質』pp299-300)という。確かに、欧米では社内弁護士の存在も珍しくないという。しかし、法曹人口そのものが少ないわが国において(現在、改革が進行中であるが)、社内弁護士などを雇うのはなかなか大変である。薬害事件でも取上げたように、権威を貴ぶことが尊重されるわが国においては、当然三顧の礼を尽してお迎えすることになるわけであるが、そのような人物が検査マニュアルに求められる実務経験や専門性を持った人間であるかどうかは分らない。むしろ、ひとたび雇ってしまえば、権威が一人歩きする危険性があるのではないだろうか。
社内において、コンプライアンス担当部門がイエスといわなければ何事も前へ進まない体制になってしまう。これでは、取締役会の責任が形骸化し、コンプライアンス部門が経営権を握ってしまうことになる。それでは、表紙の名前が変わっただけで、組織の腐敗は防ぐことはできない。
このように相矛盾し、行き過ぎれば弊害を生むという要求に対して、有効な処方箋はあるのだろうか。
4.
内部監査と外部監査
金融庁の検査マニュアルにおいて、設定当初は企業が自らに対して行う検査も、金融庁の行う検査と同じ「検査」という言葉が使われていた。しかし、2001年4月の改訂において、金融機関が行う「検査」を「内部監査」という言葉に置きかえることによって、金融庁の検査とは異なった意味合いで内部監査を実行すべきことを示した。
コンプライアンスで重視されるのは、自己規律であるから、金融機関が自主的に行う内部監査が重視されるのは当然のことである。
内部監査とは、「「内部監査」とは、各業務部門等の本部部門及び営業店等(以下、「被監査部門等」という。)から独立した内部監査部門(検査部、業務監査部等)が、被監査部門等における内部管理態勢(リスク管理態勢を含む)等の適切性、有効性を検証するプロセスである。このプロセスは、被監査部門等における内部事務処理等の問題点の発見・指摘にとどまらず、内部管理態勢等の評価及び問題点の改善方法の提言等まで行うものであり、原則として、内部管理の一環として被監査部門等が実施する検査等を含まない。」(金融庁「保険会社に係る検査マニュアル」)と規定している。
これに対して、検査マニュアルに占める割合は小さいものの、外部監査にも言及している。従来から、金融機関、あるいはより一般的に公開された会社に対しては、一定の基準を設けて会計監査を受けることが義務づけられている。具体的には、商法特例法(正確には、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」)によって、資本金5億円以上、負債総額200億円以上の株式会社、証券取引法に基づいて証券取引所に株式を上場している会社及び上場申請する会社、株主が500名以上の会社、証券業協会に株式を登録している会社及び登録申請する会社などは監査を受けなくてはならないことになっている。
会計監査制度は広く受入れられた制度である。これに対して、検査マニュアルでは、必ずしも会計監査に限らない監査を受けることについても言及している。「各保険会社が、内部管理体制の有効性等を確保するため、財務諸表監査とは別に、外部監査を受けている場合には、財務諸表監査の結果と併せて、内部管理体制の有効性等を総合的に検証することになる」(金融庁「保険会社に係る検査マニュアル」)。ただし、現状ではコンプライアンスに主眼を置いた外部監査手法を確立して行っている機関も少ないことから、「ここに言う外部監査は、会計監査人による財務諸表監査に限定するものではないが、現状では、制度上義務づけられている財務諸表監査及び同監査手続の一環として実施される内部管理体制の有効性等の検証以外の外部監査を義務づけるものでないことに留意する必要がある」(金融庁「保険会社に係る検査マニュアル」)としている。
しかしながら、会計監査が金融機関・一般企業の会計上の公正さを担保するために大変有効な方法であるのと同様に、コンプライアンスを確保するために、外部監査を活用することも、大いに考えられるのではないだろうか。
4.1外部コンプライアンス監査活用のメリット
外部コンプライアンス監査を活用することのメリットは、金融機関組織外部の人間によるコンプライアンス監査を受けることによって、金融機関の組織に対して常に新しい刺激を与え続けることができる点にあるだろう。金融機関に所属する人間との癒着の可能性を最小に押さえつつ、コンプライアンス監査を行うことができる。また、金融機関内のコンプライアンス担当部署に対するコンプライアンス監査も行うことができる。
また、経営陣にとっても、癒着を防止するために、コンプライアンス監査を行う会社・機関を定期的に入れ替えることを制度化することによって、常に異なった刺激を組織に与え続けることができる。もちろん、現状ではコンプライアンス監査を適切に行いうる機関は大変限られてしまうので簡単に入れ替えるわけにはいかないであろう。しかし、会計監査の依頼先を定期的に変更するという手法を実際に採用している会社も欧米には存在する。
それ以上に、外部コンプライアンス監査を導入する最大のメリットは、取締役の責任の所在をはっきりさせることができることであろう。金融機関が会計監査に限らず外部監査を行った場合には、「各保険会社が、内部管理態勢の有効性を確保するため、財務諸表監査とは別に外部監査を受けている場合は、財務諸表監査の結果と併せて、内部管理態勢の有効性等を総合的に検証することとなる」と同時に、「当該監査結果は、監査の内容に応じて、取締役会又は監査役会に直接、正確に報告されなければならず、また、監査役監査等の実効性の確保に資するものとなっているか。」「会計監査人等の外部監査人により指摘された問題点は、被監査部門等において一定期間内に改善しているか。また、内部監査部門は、その改善状況を適切に管理しているか。」(金融庁「保険会社に係る検査マニュアル」)といったことが問われる。
内部のみにコンプライアンス担当部門を設置した場合、ともすればコンプライアンスに関する事項は担当部門、担当役員(金融庁の検査マニュアルでは、「取締役会は、専ら内部監査部門を担当する取締役を選任していることが望ましい」(金融庁「保険会社に係る検査マニュアル」)としている)に任せきりになり、何かことが起こった場合には、担当役員をスケープゴートにして、一件落着となりかねない。しかし、コンプライアンス監査を外部に委託した場合、その結果に対して責任を持つのは、取締役会である。金融庁の検査マニュアルは、非常に厳しく取締役会の責任を追及している。
そもそも、内部監査ですら、前述のように被監査部門等における内部事務処理等の問題点の発見・指摘だけではなく、内部管理態勢等の評価及び問題点の改善方法の提言等といった、経営方針に関わる事項にまで踏み込むものとされているのである。このような事項が確実に実行されるための担保として、外部コンプライアンス監査は利用可能なのではないだろうか。
このような経営方針に係る事項に外部の評価や提言を受けなくてはいけないことに抵抗があるかもしれない。これに関しては、コンプライアンスに関する事項ではないが、会社経営の重要事項に外部からの提案を大胆に受入れている事例があるので、以下紹介する。
デンマークのハイエンド・ユーザー向けのオーディオ・メーカーにバング&オルフセン(以下B&Oと略す)という会社がある。ハイエンド・ユーザー向けであることから、その音質には定評があるが、B&Oの最大の売り物は、そのデザインである。ハイエンド・ユーザー向けのオーディオは、もともとプロユースの製品を基に発展してきた場合が多く、その製品は重厚長大なものが多い。それに対して、B&Oの製品はメタリックな輝きの金属部分と黒、あるいは透明部分との対比の美しい、大変スッキリしたデザインが特徴である。高級マンションの広告などに、インテリアの一部として写っているのをよく見かける。
ところで、B&Oは大変デザイン・コンシャスな会社であるが、そのデザインを手がけているのは、社外スタッフであるそうである(「NAVI」2001年11月号
二玄社)。普通、同社のようにデザインを重視している場合には、デザイン部門を社内に備えるだけではなく、デザイン部門の長を取締役などにしている場合が多い。むしろそれが普通であろう。しかし、同社はあえて外部デザイナーの起用を続けている。内部にデザイナーを雇い入れたほうが、デザインの一貫性を高めるためには好ましいかもしれない。しかし、それでは逆に同社を特徴付けているデザインの先進性を保ちつづけることができない。デザインの一貫性も、行き過ぎれば単に製品の陳腐化につながる。また、社内デザイナーはどうしても採算性、販売実績、はては社長が気に入るデザインか、などを気にせざるを得ない。
外部のデザイナーであれば、己の信じるベストを提供し、それを製品化するか否かの選択は会社(取締役会)に一任される。そのデザインを製品化して、例え売れなかった場合でも、取締役会は安易にデザイナーの責任にすることができない。なぜならば、そのデザインの採用に主体的に係っているからである。
4.2組織のイメージ
これまでの会社組織は、どちらかというと図1のような、“いちご大福”のようなイメージであったのではないだろうか。
図1
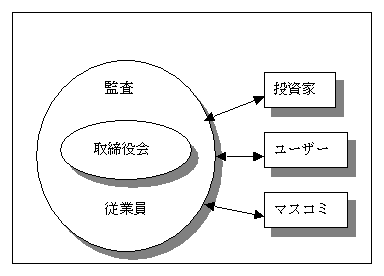
いちごに相当する取締役会は、本来会社組織の意思決定機関として従業員組織の上位に位置するのが建前であるにもかかわらず、担当部署という従業員組織に守られ、そのフィルターを通してしか外部と接触しない。従って、「知らなかった」などという事態が起きるのである。また、このような組織形態を採っていると、従業員の目が内に向いてしまい、機能体であるべき会社組織が仲間内の論理に嵌まってしまう共同体化が起こるのである。また、このいちご大福は内部にも無数のいちご大福状の構造を幾重にも持っていて、その各々が内向きの共同体になっているのである。たとえば、図1でいえば、監査部門は組織内では独立していることになっているが、会社全体として外部から見れば、監査部門も組織内組織にしか見えないのである。例えば、役所という大きな組織の中の会計検査院を思い起こせば、その位置付けが良く分るのではないだろうか。これでは、外部から機能体としての会社に要求される機能を発揮し得ない。
これに対して、現在求められている組織の形態は、図2のような“ショートケーキ”のイメージになるのではないか。取締役会を組織の外に置く形にし、同時に監査機能も敢えて外部に置くことにより、組織が内向、共同体化することを防ぐのである。また、取締役会が外部に直接露出していることにより、外部からの監査評価をどのように会社運営に生かしていくかということに関して、各々の取締役に強い自覚を促すとともに、責任体制も明確になるのである。
図2
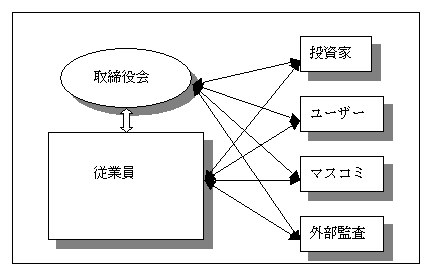
また、この図では監査機能が完全に外部に置かれているかのように描かれているが、これは会社組織において、内部監査機能を放棄してしまうことを意味していない。これは、外部会計監査を受けることが当然である会社も内部会計監査機能を当然に残していることを思い起こせば分り易いであろう。
同一の機能を会社の内外に持つことは一見無駄にも思えるが、組織が腐敗してしまった場合の決定的なダメージを思えば、そのコストも正当化されるのではないだろうか。
4.3外部監査は万能か
ただし、外部コンプライアンス監査を受入れたからといって、コンプライアンスが確立できるわけではないことは、強調しておかなくてはならない。
上記外部コンプライアンス監査と同様な趣旨で、社外取締役の選任、監査役の機能強化などが行われたが、いずれも形骸化している。また、会計監査においても、会計監査法人にとっては顧客である被監査会社との関係を壊したくないために会計監査が適正に行われなかったのではないかと疑われる事例も多い。
これは、コンプライアンスに関しては先進国であるはずのアメリカでも、実は同様であった。1990年頃S&L(Saving & Loan、貯蓄貸付組合)の破綻が問題になったとき、ちょうど現在の日本と同様、監査法人の責任が問われた。会計監査の結果適正とされた会社が、経営に大きな変化をもたらす事件もないのに半年と経たずに破綻するのは、おかしいのではないか、会計監査の時点ですでに問題があったのではないか、と監査法人の責任を問う声があがった。アメリカは訴訟大国であるから、監査法人に対する訴訟が頻発したのである。
その結果として、監査法人の姿勢が厳格になった経緯がある。
現在ちょうど10年前のアメリカが経験したような不況を経験している日本でも、監査法人の姿勢は徐々にではあるが厳格になりつつある。株式上場で大いに話題になった会社でも、監査法人が会社の混乱を理由に辞任(クレイ・フィッシュの例。Mainichi Interactive http://www.mainichi.co.jp/digital/network/archive/200104/24/2.html (10/19/2001))した例などもある。大型企業倒産が続く中、監査法人としても、従来のようなもたれ合い監査は通用しなくなりつつある。そのような環境であれば、外部コンプライアンス監査も機能を発揮できるのではないだろうか。
また、現実にはどのような団体に外部コンプライアンス監査を委託するかという問題がある。大手のコンサルティング会社、監査法人、法律事務所などがコンプライアンスに関するコンサルティングを受け付けてはいるが、現在では外部コンプライアンス監査の方法は確立されておらず、サービスの内容も一様ではない。ただし、逆の見方をすれば、異なる委託先を選ぶことにより、異なった内容の監査を受けることができる。その内容が的外れである可能性がないとはいえないが、画一的な監査を受けていることにより生ずる慣れや惰性を排除できる。異なった刺激を組織に与えることにより組織の共同化を防ぐ効果もあるのではないか。そのような効果をもたらすように監査結果を利用することも、取締役会の責任である。
5.結論
以上のように、外部監査の一環としてコンプライアンス監査を委託する方法は、コンプライアンスを確立するために、大変有効な方法であるといえるであろう。
外部コンプライアンス監査とは、単に外部の専門家にコンサルティングを依頼することをいうのではない。外部コンプライアンス監査の本当のメリットは、組織に外部からの刺激を与え続けることにより腐敗を防止すると同時に、取締役自身の責任を思い起こさせることができるなど重層的な効果が期待できる点にある。
内部のみにコンプライアンス担当部門を置いただけでは防げないコンプライアンス担当部門の聖域化を防ぎ、聖域化すると伏魔殿になりかねないコンプライアンス担当部門の監査が行えるだけではなく、取締役会の機能を際立たせることにより責任体制の明確化も図れる。
唯一の問題は、外部コンプライアンス監査は制度としては確立していないため、必ずしも外部に適切なパートナーを簡単に探し得ないことであろうか。ただし、現在でも大手のコンサルティング会社、法律事務所、監査法人などが手がけるようになっている。また、コンプライアンスの問題は、会計監査以上に会社の自己責任が問われている。制度的に要求されているわけではないのであるから、外部にコンプライアンス監査を依頼して、その内容に不満足であれば、解任すれば良いのである。そして、その責任を負わなくてはならないのはもちろん取締役会なのである。
また、外部コンプライアンス監査の結果をよりよく生かしていくためには、会社組織もそれに合わせて変わらなくてはいけない。仮にショートケーキ型などと名づけてみたが、取締役会の役割と責任がはっきりしていなくては、せっかくの監査結果を十全に生かしきることができないからである。
以上のような工夫を凝らすことによって、コンプライアンスを確保しやすい組織を実現できるのである。
<資料1>薬害エイズ厚生省判決
松村元厚生省課長に有罪 「官僚の不作為」認定
![]() ◆感染防止怠る
◆感染防止怠る
薬害エイズ事件で、血友病患者ら2人のエイズウイルス(HIV)感染、死亡について業務上過失致死罪に問われた厚生省(現厚生労働省)の元生物製剤課長・松村明仁被告(60)の判決が28日、東京地裁であった。永井敏雄裁判長は、非加熱製剤の危険を認識できた時期を1985年末と認定したうえで、安全な加熱製剤承認後にHIV感染した患者1人について「危険な非加熱製剤の販売中止・回収などの措置を取り、HIV感染、エイズ発症による死亡を防止すべき義務があった」と指摘、禁固1年、執行猶予2年(求刑・禁固3年)の有罪を言い渡した。一方、加熱製剤承認前の感染患者については、「当時、非加熱製剤投与を控えるという治療方針は提唱されていなかった」として無罪にした。
◆「帝京大ルート」は無罪
官僚が取るべき措置を取らなかった「不作為」が、初めて刑事事件として裁かれ、有罪と認定されたことは、他官庁の行政のあり方にも影響を与えそうだ。
松村被告が問われたのは、85年5―6月に帝京大病院で非加熱製剤の投与を受けた血友病患者(帝京大ルート)と、86年4月に大阪の病院で旧ミドリ十字の同製剤を投与された肝臓病患者(ミドリ十字ルート)がHIVに感染、死亡した2件。
松村被告はいずれも無罪を主張したが、判決は非加熱製剤の危険性について、加熱製剤承認前の85年5―6月にははっきりしない点が多かったが、同製剤が承認された同年末までには危険を予見でき、86年4月には「かなり明らかになっていた」と判断。この時点では、「安全な加熱製剤は必要量に達しており、松村被告もそれを認識していたのに、非加熱製剤の回収を製薬会社にゆだね、HIV感染防止の配慮に欠けていた」と認定した。
そのうえで、松村被告の職責に照らせば、ミドリ十字が加熱製剤の販売を始めた86年1月には、「自ら関係部局と協議し、製薬会社に非加熱製剤を販売中止・回収させ、医師には不要不急の投与を控えさせて、同製剤投与による感染、死亡を防止すべき義務があった」と述べた。判決はさらに、「過渡期に生じがちな混乱を避け、感染を防止するには、国の行政担当者の行動が求められており、被告が自らのイニシアチブで行動を起こすことが求められていた」と指摘した。
一方、帝京大ルートについては、松村被告に血友病治療の経験がなかったことなども挙げ、永井裁判長自らが今年3月、元帝京大副学長・安部英(たけし)被告(85)に言い渡した判決と同様に無罪とした。
判決は、執行猶予を付けた理由の1つとして、HIV問題には松村被告だけでなく上司や同僚らもかかわっており、こうした人々にも責任の一端があったと指摘した。
判決の骨子
▼帝京大の患者が感染した当時はHIVの危険性について不明点が多く、被告に注意義務違反があったとは言えない(無罪)
▼ミドリ十字ルートの患者が感染した当時は危険性も判明し安全な加熱製剤も供給可能で、非加熱製剤の販売を中止、回収させるなどの措置を取る義務が被告にあった(有罪)
(読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/yakugai/yaku0928_00.htm 2001/9/28)
<資料2>三菱自動車リコール隠し事件
「「リコール隠し」4部門幹部が決定
=三菱自動車、全社的に隠ぺい工作(8月28日配信)
三菱自動車工業(本社東京都港区)のクレーム情報、リコール(回収・無償修理)隠ぺい事件で、欠陥を運輸省に届け出ず、勝手に販売店に指示してひそかに修理する「リコール隠し」の方針が、品質保証部、サービス、設計、製造の計4部門の幹部が出席した会議で決まっていたことが、28日、警視庁交通捜査課や運輸省の調べで分った。会議で決定した方針に基づき、設計、製造部門などが「やみ修理」の実施方針を立てていた。
同課は、隠ぺい工作がクレーム情報隠ぺいの中心となった品質保証部だけでなく、全社的な規模で行われていたことを裏付けるとみて、今後、会議に出席した幹部から事情聴取する。
調べによると、同社ではユーザーからのクレーム情報は、本社の品質保証部に集められる。同部内で安全性にかかわると判断された情報は、同部長をヘッドとして、販売店との窓口となるサービス部門、設計、製造各部門の次長、課長クラスが加わった「クレーム対策会議」で議論。そこでリコールなどの対応が必要とされた案件については、部長クラスで構成する「リコール・改善対策検討会」に諮り、方針が決まる。
捜査対象となった1998年以降、乗用車「デボネア」や大型トラック、大型バス、小型バスの4件でリコール隠しが行われた。
この4件については、いずれもクレーム対策会議か、同対策会議と同じメンバーによる会議で、安全上問題があると判断された。しかし、会議ではリコールせずに、やみで修理することが決められた。
会議の決定を受けて、設計、製造部門が、やみ修理のやり方などの対応策を検討。サービス部門から販売店に回収や修理の指示を文書で伝達した。文書には「極秘扱い」「取り扱い注意」などと書かれた上、外部への情報漏れを防ぐ趣旨の注意書きが書いてあり、隠ぺいの徹底が図られた。」
(時事通信2000年8月28日配信http://www.jiji.co.jp/edit/topics/data2000/200008/0827mitsubishi/0828n4.html (09/11/2001))
<資料3>雪印乳業集団食中毒事件
「雪印乳業食中毒事件
約一万五千人が被害を訴え、戦後最大規模となった雪印乳業の集団食中毒事件。製品回収の遅れや度重なる対応の不手際で信用を失った同社は「顧客第一主義」を掲げて再出発した。しかし、事件から半年近くたった今も被害者との補償交渉は続き、売り上げも激減したままで、信頼回復への道は険しい。
▽食中毒の後遺症
「裁判しても勝てませんよ」。大阪府内の女性(30)は、雪印が提示した示談条件を拒むと交渉担当の社員にこう言われたという。「こっちが被害者なのに、まるで悪者扱いされた」。八月、慰謝料など約四十万円の支払いを求め大阪簡裁に調停を申し立てた。
女性は六月下旬、スーパーで買った雪印低脂肪乳を飲み、激しい下痢や吐き気に襲われ四日間入院した。“後遺症”で今も牛乳類は飲めないという。
雪印は事件後、約百人態勢の「お客さまケアセンター」を設置、補償交渉に当たった。広報部は「五千件あった交渉は約百件を残すだけになった」と被害者対応の順調さを強調する。
しかし、雪印の交渉態度に対する不満の声は多い。多くの被害者から話を聞いた田中厚弁護士は「統一した補償基準もなく、治療費以外は被害者の出方によって変えている」と批判。「場当たり的な対応で、事件発生当時の姿勢と変わらない」と手厳しい。
「社会とずれがあった」(西紘平新社長)との反省から、外部の有識者から提言を受けるために設けた「経営諮問委員会」も、座長に身内とも言える顧問弁護士を据えた。国民生活センターの島野康相談部長は「雪印はなにが一番の問題だったか、まだ理解していないようだ」とあきれる。
▽トップから転落
経営面でも雪印の前途は多難だ。事件の影響で売り上げが激減。九月中間決算では二百四十三億円の経常損失を出し、業界トップの座を明治乳業に明け渡した。
雪印製品はほとんどのスーパーの店頭に戻ったが、消費者は戻らない。十一月の牛乳などの売り上げも前年同月比五四%減の見通しで、安全性を軽視した代償はあまりにも大きい。
雪印乳業食中毒事件 雪印乳業大阪工場が製造した低脂肪乳などを飲んだ約一万五千人が下痢や吐き気などを訴え、飲み残しから黄色ブドウ球菌の毒素が検出された。その後、原料になった北海道・大樹工場製の脱脂粉乳の汚染が判明。大阪府警は同社幹部らを近く業務上過失致傷容廃で書類送検する方針。(共同通信)」
(京都新聞2000年12月19日 http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2000dec/19/16.html (09/11/2001))
<資料3>大和銀行 大阪地裁判決
「2000年9月20日
株主代表訴訟:大和銀旧経営陣に830億円賠償命令 大阪地裁
1995年に米司法当局に訴追された大和銀行ニューヨーク支店の元嘱託行員による債券取引を巡る巨額損失事件で、同行の個人株主2人と法人株主1社が「適切な管理、監督の措置をとらなかったため、銀行が損害をこうむった」として、85年〜95年に同行の取締役と監査役だった49人を相手取り、計14億5000万ドル(約1450億円)を同行に支払うよう求めた株主代表訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。池田光宏裁判長は「取締役の善管注意義務に違反した」などとしてニューヨーク支店長だった安井健二被告、事件発覚時の頭取だった藤田彬被告ら計11被告に計約7億7500万ドル(約830億円)を支払うよう命じた。株主代表訴訟としては、前例のない巨額の損害賠償。予期しない社員の犯罪で企業が損失を受けた場合にも、経営陣の監督責任があると判断しており、企業の経営責任を従来以上に重視した画期的な判決と言える。今後、企業経営に大きな影響を与えるのは必至だ。
事件は、同支店の元嘱託行員が84年から11年間で、米国債などの無断売買を約3万回も繰り返し、約11億ドル(約1100億円)の損失を出した。元嘱託行員は帳簿類を偽造して損失を隠していたが、95年7月に頭取に手紙で告白した。銀行側は、米国の連邦銀行法などに反して、米金融当局に2カ月間、事実を報告せず、同年9月、米司法当局に訴追された。同行は96年2月、約3億4000万ドル(約350億円)の罰金を支払った。
訴訟では、兵庫県と東京都の個人株主2人と、東京都の法人株主1社が、元嘱託行員の無断取引による損失と、同行が支払った罰金との合計額を返還するよう請求していた。「11年も不正取引を発見できず、損失を拡大させたのは、取締役と監査役の重大な職務怠慢」であり、「事実の把握後、米金融当局に速やかに報告しなかったために銀行が訴追され、多額の罰金を支払う結果を招いた」と主張した。
一方、被告側は「元嘱託行員による個人的な犯罪で、銀行は被害者。検査体制に不備はなかった。米金融当局に報告が遅れたのは、実態解明と原因究明を優先し、加えて、不確実な内容を報告すべきでないとする大蔵省の意向だった」と反論していた。 【和泉かよ子】」
(毎日新聞2000年9月20日http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200009/20/0920e051-401.html (09/13/2001))
参考文献
Bank for International Settlement (1998), Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations, http://www.bis.org/publ/bcbs40.htm (09/05/2001)
千早 正隆(1990)『日本海軍の驕り症候群』プレジデント社
勝月 裕爾(2000)『改訂 金融コンプライアンスと法令ポイント』経済法令研究会
木村 剛(2001)『新しい金融監査と内部監査』経済法令研究会
金融庁「証券会社に係る検査マニュアル」http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/shouken.pdf (08/30/2001)
金融庁「保険会社に係る検査マニュアル」http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/hoken.pdf (08/30/2001)
金融庁「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/yokin.pdf (08/30/2001)
金融庁「証券会社に係る検査マニュアルについて」金検第170号http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/shouken.pdf (08/30/2001)
高 巌編著(2001)『ECS2000 このように倫理法令遵守マネジメント・システムを構築する』日科技連出版社
高 巌・國廣 正(1999)『金融機関のコンプライアンス・プログラム』経済法令研究会
堺屋
太一(1993)『組織の盛衰―何が企業の命運を決めるのか』
PHP研究所
産経新聞取材班
(2001)『ブランドはなぜ墜ちたか―雪印、そごう、三菱自動車
事件の深層』角川書店
太平洋戦争研究会 編著(2000)『太平洋戦争』日本文芸社
戸部 良一、寺本 義也、鎌田 伸一、杉之尾 友秀、野中 郁次郎(1991)『失敗の本質』中央公論社
牛越 博文(2000)『日本版金融サービス法』日本経済新聞社
柳田 邦男(1998)『この国の失敗の本質』講談社
矢貫 隆(2001)「自動車の罪」『CAR GRAFHIC』 2001年11月号pp200-204