ファイナンス(FIN705)4クレジット
外国為替理論
Rushmore University
Global Distance Learning DBA
大國
亨
日本人を取り巻く経済環境は急速にグローバル化しつつある。そのような環境の中、日本人の金融資産もグローバル化が望まれていくのであろう。このような経済環境を背景として、外貨建て投資の重要性が高まっていくことであろう。
本年度より施行される「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて、為替相場の変動に伴い元本割れが考えられる商品については、重要事項として説明が要求されるようになる。ただし、法律上要求しているのは、元本割れがありうることに対する説明を求めているだけで、その説明内容を細かく規定しているわけではない。
外国為替を説明する場合には、相場動向と相場予想の提供を行うことが一般的であろう。相場動向と為替予想の基本的アプローチには、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析という二大潮流がある。ファンダメンタルズ分析は各国の経済状況を分析、今後の為替動向を予想するものであり、テクニカル分析は別名チャート分析とも言われるように、過去の為替動向をチャートに描き出し、将来のトレンドを予測するものである。
しかし、現在の経済学理論によれば、相場予想の可能性は否定されている。効率的市場仮説のもとでは、ファンダメンタルズはもとより、過去の値動きも現在のレートに反映されており、将来の予測には役に立たないとされている。相場予測が成り立たないのであれば、いかなる方法で外貨建て商品への投資のアドバイスをしたらよいのであろうか。
そこで、本稿においては、経済学的な為替市場の変動要因、為替相場決定理論を概説、過去のデータを用いて検証する。過去のデータを検証することにより、為替相場変動の分析の困難性と、為替相場予測の不可能性について検証する。最終的に、金融機関が外貨建て商品を個人投資家向けに販売するに際して、どのような説明が可能なのかを、投資理論としては長期国際分散投資を、投資方法としてはドル・コスト平均法取り上げ、論証する。
目次
1.
はじめに
2.外国為替の基礎知識
2.1為替レートの建て方
2.2直物相場と先物相場
2.3外国為替市場
3.為替相場の決定要因
3.1購買力平価
3.2国際収支
3.2.1経常収支
3.2.2資本収支
3.2.3貿易依存度
3.3為替相場に関する経済理論
4.効率的市場仮説と為替予測
4.1ファンダメンタルズ分析
4.2テクニカル分析
4.3効率的市場仮説
4.4為替市場は効率的か
5.外貨建て商品の勧誘方法
5.1国際長期分散投資
5.2ドル・コスト平均法
5.3情報提供をする場合の留意点
5.4インサイダー取引
6.結論
補論 実際のデータをもとにした経済理論の検証
1.はじめに
日本国内において超低金利が長続きし、国内での資金運用難が顕在化したことから、個人投資家に対しても、外貨建て投資を勧誘する動きが活発になってきた。外貨建て投資はこれまでもさまざまな形で日本国内の投資家に紹介されてきたが、残念ながら投資商品のメインストリームとはなっていないのが現状である。確かに、規制、税制、金融技術の未成熟などにより、外貨建て投資商品が必ずしも個人投資家にとって使い勝手がよくなかったことも外貨建て投資が普及しなかった一因であろう。
しかし、日本版ビッグバン以来、日本の金融市場は「フリー、フェア、グローバル」を旗印として海外に向けて開放されることになり、現在もその過程にある。当然、諸規制も規制緩和の流れに沿って自由になりつつある。個人顧客にとっても、海外の金融機関の作成した高度な金融技術を駆使した金融商品を自由に購入することが可能な時代になりつつある。
冒頭にも記したとおり、外貨建て投資の第一の魅力は、現状では高金利である。しかし、ハイリスク・ハイリターンのみをレーゾン・デートルとする外貨建て投資は、これからの個人金融資産の形成を考えていく上で好ましい姿なのであろうか。
日本人の働く企業も急速にグローバル化しつつある。これからの企業のグローバル化は、単なる海外進出にとどまらず、企業経営の急速な無国籍化・多国籍化をもたらしていくのであろう。そこで働く人間にとっても、働くフィールドが一カ国にとどまることなく、流動していくことを意味する。日本で生まれ、日本で育ち、日本で働き、日本で死んでいくという日本人の一生が繰り返されるとは限らない。そのような場合において日本人の資産形成にもこれまでとは違った投資概念があってもよいのではないだろうか。
今までは円建てであれば為替リスクがなく、外貨建てであれば為替リスクがあるという前提が何の疑いもなく受け入れられてきた。しかし、現在では老後は老人福祉環境が悪い日本を離れて海外で暮らす日本人が確実に増加しているのである。実際に、ある国に住みたいと思って投資を進めていくほどではなくても、ある程度の将来を考えれば、日本なら日本だけに投資を集中していくことは、為替リスクとは違ったリスクを負うことになるのではないだろうか。その場合に、投資先を世界的に分散する国際分散投資の考え方は大いに参考になると思われる。
国際分散投資が個人投資家にとっての投資の王道になるには、時間がかかると思われる。しかし、日本国内の低金利のみを理由としない外貨建て投資も増えていくことと思われる。外貨建て投資商品を個人顧客に販売するに際して必要とされるであろう知識をまとめるとともに、国際分散投資の背景にある考え方をまとめた。
2.外国為替の基礎知識
今日では、大新聞の一面に為替レートが登場することも珍しくはなくなってきた。経済欄には、為替に関するコメントも載っている。しかしながら、私もコラムを書いた経験があるが、はっきり言ってあれはプロ、あるいは仲間内に向けたコメントである。外国為替市場において圧倒的シェアを持っているのは銀行間取引と、大手企業・投資家と銀行の取引である。個人客などは全く眼中にないといって過言ではない。短い文章の中にプロにアピールする内容を盛り込まなくてはならないので、テクニカルにどうの、海外資本筋がどうのと仲間内の符丁の羅列に終始、一般の方には大変分かりにくい内容になってしまうのである。一般顧客の外国為替に関する知識は、かなり限られたものにとどまっているといってよいであろう。以下、本稿の議論を理解する上で欠かせない外国為替に関する基礎知識をまとめた。
2.1為替レートの建て方
銀行間市場における為替レートの建て方にはルールがある。現在、世界の金融マーケットで基軸通貨と呼べるのは米ドルである。従って、銀行間市場では1ドルがいくらになるか、といった表示がなされる。例えば、1ドル=110円といった具合である。ただし、中には歴史的経緯からか、英国ポンド、豪州ドル、ユーロなどは逆に1ポンド=1.5ドルといった表示をする。これは戦前の、あるいは第1次世界大戦前の、日の沈まぬ大英帝国の名残である。ユーロについてはユーロ成立以前のEC共通通貨のエキュ(ECU)も同じ建て方をしていた。1ユーロ=1エキュでエキュからユーロに移行することが最初から決まっていましたので、すんなりと決まったようである。ただ、ドルに並ぶ基軸通貨になる夢を持っていたのでこんな通貨の建て方になったとも言われている。神聖ローマ帝国復活を夢見ているわけでもないのであろうがヨーロッパ連盟(EECあるいはEC)発足に奔走した人間の中に、ハプスブルグ家の血統の元貴族が関わっていたのは良く知られているところである。
ところで、銀行などの店頭には、1ドル何円に続いて、1ポンド何円、1ユーロ何円と書いてある。決して1ポンド何ドルとは書いてない。これは、日本の店頭に現れる顧客のほとんどが、海外の通貨が対円でいくらになるかに興味を持っており、投資のプロでない限り、ポンドとドルとの間の為替レートに興味を持っている人はいないからである。
では、どのように対円レートを計算するのであろうか。上記の例では、1ポンド=1.5ドル、1ドル=110円であったから、1ポンドは
![]() で165円となる。
で165円となる。
ところで、日本の銀行の店頭における為替レートの建て方に触れたが、外国ではどうであろうか。外国でも、両替商や銀行の店頭ではその国から見た外国の通貨がその国の通貨でいくら、と表示してある例がほとんどである。空港などで両替をする際に、全く違う為替レートが表示してあるように感じるのは、このせいである。私の経験では(限られたものであるが)、銀行間市場のレートがでかでかと店頭に表示してあったのは、香港の銀行だけであった。さすが香港では銀行間市場のレートを知りたがる人間が多くいるのであろう。
2.2直物相場と先物市場
直物相場とは、上記銀行間市場でいわゆるスポット取引として知られているもので、約定の2営業日後に決済されるのが普通である。これに対して、顧客相場はその当日決済されるので、当日物と呼ばれる。通常、一般顧客が両替をする際に適用されるのは、この当日物相場である。
これに対して、スポット以降の日に決済されるものを先物と呼ぶ。実際の先物市場では、例えば3ヶ月先に決済される為替レートそのものが取引されているわけではなく、3ヶ月先の為替相場を約定するときに使うスワップ・スプレッド(直物レートと先物レートの差)が取引されている。また、先物市場で取引されているのはいわゆる通貨先物ではない。金融市場では、先物、スワップ、スプレッドなどは色々な場面で違った意味で使われるので、注意が必要である。
なぜ、直物と先物のレートが異なっているのであろうか。1ドル=100円なら、先物もそのままの固定レートの方が計算も簡単で助かるような気がするがいかがであろうか。実は、ドルと円の間には金利差があるので、直先のレートが同じだと、ちょっと頭のいい人は労せずして儲けられることになってしまうのである。そのようなことを許さないために、金利裁定が働いて先物レートが金利差を相殺するように決定されるのである。
例えばドル金利を6%、円金利を1%としよう。ある人が日本円、1,000,000,000円(10億円)を1年間1%の金利で借りられるとする。これをドルに交換する。1ドル=100円ですから、ちょうど10,000,000ドル(1千万ドル)になる。このとき1年後の為替レートも100円で予約できたとする。元本を6%の金利で運用すると、1年後には10,600,000ドルになります。1年後の為替レートは100円で予約しておいたので、この予約レートを用いて再び円に交換すると1,060,000,000円になる。借入金に対する利息分10,000,000円を支払っても、50,000,000円も手元に残る。円換算で元本保証5%の利回りである。そんなうまい話があるはずはない。前述のように、金利裁定が働くのである。
金利裁定は上記のような場合に、先物レートが調整されるように働く。上記の例では、ドル預金に預けておいた元利合計の10,600,000ドルと円借り入れの元本と利息の合計1,010,000,000円が等しくなるように為替レートが決定される。1,010,000,000
![]() 10,600,000=95.28となる。従って、上記の例では1年先の為替レートを予約しようとすると、100円ではなく、95.28円になってしまうのである。この場合の直物と先物の差4.72円のことをスワップ・スプレッドといい、このスプレッドが先物市場で取引されているのである。
10,600,000=95.28となる。従って、上記の例では1年先の為替レートを予約しようとすると、100円ではなく、95.28円になってしまうのである。この場合の直物と先物の差4.72円のことをスワップ・スプレッドといい、このスプレッドが先物市場で取引されているのである。
また、設定例のような場合において、外貨建て投資を実行した場合でも、為替部分のリスクヘッジのために為替先物を用いて同時にリスクヘッジを行うと、先物価格に金利裁定が働くことによって、邦貨建て投資を行った場合と同じになってしまう。外貨建て投資による高利回りを期待するためには、為替部分のリスクを取らなくてはならないことがわかる。
上記例では売り買いのレート差や、貸し出し預金レートの差(ともにビッド・オファー・スプレッドと呼ばれる)などを無視して模式的に計算してある。実際に取引をする場合には、金融機関における対顧客マージンも考慮しなくてはならない。また、金利裁定が先物レートにだけ影響を与えるように書いたが、金利が変動する事もあり得る。ただ、原理的には上記の通りである。
従って、現在のドル円相場において、先物で売り予約をしようとする場合、直物より安くなることを念頭に置いておかなくてはいけない。現状、円金利は世界中のどの通貨よりも安いはずである。2000年には、ゼロ金利解除が決定されたが、それでも歴史的超低金利は続いている。そこで、日本円は世界中のあらゆる通貨に対して上記の先物レートが直物レートより安い体系(ディスカウント体系)になっている。
ただし、未来永劫に渉って円金利が超低金利を続けるわけでもないであろう。すると、上記の関係も変わり、先物レートが直物よりも高い体系(プレミアム)になるかもしれない。そのようなときに、基本的な先物市場の原理が分かっていると、先物がプレミアムなのかディスカウントなのかすぐに分かるのである。もし、相手通貨の金利が円より高ければディスカウント、安ければプレミアムとなるのである。
2.3外国為替市場
新聞紙上などでは、「東京外国為替市場で云々」と表現されるので、株式における東京証券取引所に相当する組織が想像されがちであるが、そのような統一的組織は存在しない。しかし、いわゆるマーケットが全く存在せず、一対一の銀行間取引のみでは、現状の相場がいくらになっているのかもわからず不便であるので、実際には、外為ブローカーと呼ばれる会社が数社存在する。それらの会社が取引先である銀行からレートを預かり(売り・買いの指値注文)、そのレートをその他の取引先にも電話線を通じて配信する。もし取引先の銀行がそのレートに興味があれば、売り買いの数量などを調整して売買を成立させる。もし、より安く買いたければ、買い注文を別のレートで入れることも可能である。このようなインターバンク・マーケットにおける最低取引金額は、1百万ドルである。1百万ドルを通常1本と呼ぶ。外為ブローカー・マーケットには、日本国内に存在する銀行のみならず、海外の銀行も現地のブローカーを経由して参加している。マーケットの気配値は情報サービス会社のモニターを通して常に流されており、世界的に一物一価の原則が適用される大変自由なマーケットが形成されている。
また、最近は外為ブローカーと並んで、電子ブローキングも盛んになっている。これは、電子ブローキングのネットワークに参加している各金融機関から(現在では、金融機関、一部大手投資家などしかネットワークに参加できない)、さまざまな通貨ペアーに関して売り買いの注文を受け付け、電子ブローキング会社で整理の上、売り買いのベスト・レートを参加行に配信する。
現状では最低取引単位などは外為ブローカー市場と同じであるなど、基本的には銀行間市場である。しかし、一部の銀行はすでに顧客取引をネット上で受け付けるシステムを構築し始めている。また、外為市場においては株式市場のような統一的市場が存在しない弱点をカバーするため、何行かで共同してレートを常に提示できるシステム作りを目指すのが現在では主流である。また、現在では電子ブローキングでカバーしているのはスポット取引が中心であるが、これも先物、オプションなどスポット以外の取引を取り込む工夫もなされている。
3.為替相場の決定要因
為替相場はさまざまな要因によって変動する。代表的な為替相場決定理論を取り上げる。国際収支や金利差と実際の為替相場の関係については、補論にまとめておいたので参照されたい。
3.1購買力平価
ある国際的商品がA国では1A元、B国では10B円とすれば、1A元=10B円と為替相場は決定されるはずである。厳密には、購買力平価には絶対購買力平価と相対購買力平価が存在する。「購買力平価が、絶対、相対のいかんを問わず、長期について成立する関係であることについては、異論はないといってよい」(長谷川 聰哲、秋葉 弘哉、谷 重雄『購買力平価と為替レート』p19)。問題は、どのくらいの期間を長期というかであり、また、短期的には、どの程度の変動幅が許容されるかである。また、短期の変動を説明するのに有効であるかどうかである。長谷川 聰哲、秋葉 弘哉、谷 重雄らが1973年から1980年のデータを用いて検証したところでは、購買力平価は短期的為替レート変動の7%しか説明できない(同前p101)。ただし、その乖離は、長期均衡レートである購買力平価から発散することなく分布していることも示された。つまり、購買力平価は長期的には当てはまるのかもしれないが、短期的な為替相場の変動を説明する要因にはならないということである。
近年、最近購買力平価説が一般新聞紙上で話題になった。それは、英国の経済誌(The
Economist)が、購買力平価を計算する国際的商品に、ビッグマックを選んだからである。2000年のデータでは、米国のビッグマックは平均2.43ドルだそうである。日本のビッグマックは2001年1月現在280円である。ビッグマック仮説によれば、1ドルは115.23円である。2000年12月末のレートが114.90円であったから、かなりの妥当性を持っているようである。最近日本マクドナルドは値下げ攻勢をかけている。日本マクドナルドが経済的な妥当性をもって価格設定をしているとすれば、円には更なる円高余地があることになる。
もちろん、単一商品で購買力平価を計測することはできない。長谷川 聰哲、秋葉 弘哉、谷 重雄の研究においては、購買力平価の設定には貿易財価格より為替レートの変動への調整の制約を受けることの少ないと考えられる賃金指数を採用している。しかし、両国の経済制度や生活環境の違いなどにより、単純に比較可能なわけでもないであろう。いずれにしても、ビッグマックに限らず、競争的な市場において世界的に活動している企業が設定している価格には、企業活動の結果として当然為替レートが反映されているはずである。為替レートと商品価格のどちらが先に決定されるかといった問題はあるものの、ある程度の期間を考えれば、購買力平価を中心として為替レートが変動することは、充分に納得いくところである。
3.2国際収支
3.2.1経常収支
日本のように輸出が輸入を上回っている場合、経常収支の黒字分だけ外貨売り円買いの需要が発生する。従って、為替レートにとっては円高要因となる。円高になればそれだけ輸出競争力が低下、輸出は減少する。原理的には経常収支が均衡するまで円高になるはずである。この理論では為替相場の方向性は分かるが、適正レートは分からない。
3.2.2資本収支
資本収支とは、直接投資、借款、債券の発行などに関して、ある国から資金が出ていくか入ってくるかを示している。基本的には金利が高いほうが投資家にとって魅力がある。資本収支が黒字の国の通貨は高くなるであろうし、資本収支が赤字、つまりお金が出ていってしまうような国の通貨は弱くなるはずである。昨今の例では、米国の金利がインフレ予防を目的として引き上げつづけられた。このような場合には、基本的に米国経済の好調(あるいは過熱)を背景にしているので、金利引上げは通貨にとってはむしろ追い風となる。逆に、単に金利が高いといっても、ハイパーインフレを起こしている国の通貨では選好されるはずはない。これは、通貨防衛を目的として金利を引き上げた場合も同様である。ただし、日本と米国のような安定した国同士の為替レート分析では良く使われる手法で、金利差そのものや、金利差の動向(縮小傾向か拡大傾向か)に着目したものが多いようである。
3.2.3貿易依存度
日本は貿易(輸出)立国であるとよく言われる。統計数値は、日本の貿易依存度が必ずしも高くないことを示している(表1)。日本と米国では輸出入の割合が逆転しているものの、貿易依存度全体では、わずかながら米国の方が高い数値を示している。
欧州諸国を一国ずつに見ると、日本より貿易依存度が高いことが分かる。欧州諸国はEUを結成、現在ではイギリスなど不参加国はあるものの共通通貨のユーロを発足させるなど、歴史的、制度的に域内貿易が重視されている。日本と同じ島国といわれるイギリスですら、日本とアジア大陸の距離に比べて遥かに大陸諸国と近く、貿易依存度は高い。また、フランス、ドイツといった隣国と国境を接する大陸諸国においては、言わずもがなであろう。ただし、それらの諸国もEU域内貿易の比率が高く、EU圏内での貿易を除くと、貿易依存度は遥かに低くなり、日本と大差なくなる水準になってしまう。
逆にアジア諸国は明らかに貿易依存度が高い。中国のように大きな人口と国土を擁する国ですら日本より高い貿易依存度を示している。韓国や台湾といった明らかに貿易(輸出)に依存した経済体制を持った国は、更に高い数値を示している。
このようなことからも、円レートを動かす要因として物の貿易の占める割合が意外にも小さいことが分かるであろう。このようなことからも、日本貿易(輸出)立国論が日本の経済規模が大きくなった現状においてはあまり意味をなさなくなったことが読み取れる。そのような意味からは、日本経済に対する円高、円安の影響については、改めて検証する必要があると思われる。
表1 貿易依存度(1998年)
|
|
輸出依存度 |
輸入依存度 |
|
日本 |
9.5 |
6.9 |
|
米国 |
8.6 |
11.9 |
|
イギリス |
21.5(11.1)* |
24.8(13.9)* |
|
ドイツ |
24.9(12.3)* |
21.6(11.4)* |
|
フランス |
20.8(7.7)* |
19.6(7.4)* |
|
中国 |
19.9 |
15.2 |
|
韓国 |
33.2 |
23.4 |
|
台湾 |
42.2 |
39.9 |
*ヨーロッパ諸国カッコ内はEU地域外への貿易依存度。
輸出入依存度はGNPに対する輸出入額の割合。貿易額は国連統計月報(2000年3月号)、GNPは世界銀行“The
World Bank Atlas”による。台湾は台湾研究所「台湾総覧」による。ヨーロッパ諸国貿易相手先統計はIMF“Direction
of Trade Statistics 1999”による。EU諸国はフランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、イギリス、アイルランド、デンマーク、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランド、スウェーデンの15カ国。
出典 『世界国勢図会2000/2001』 国勢社
3.3為替相場に関する経済理論
現在のところ、為替相場に関しては決定的な理論は出現していないようである。理由の一つは、現在のような変動相場になってから高々30年ほどの歴史がないことであるが、その他の要因としては、変動相場移行後に2度に渡る石油危機、その結果として起こったスタグフレーション、アジア経済危機と今までの経済が経験したことのない変動要因が立て続けに起こったことがあげられる。それぞれの事件が為替相場に大きな影響を与えたのであるが、それらを消化した統一理論が現れるには、時間が足りなかったようである。
金利、貿易収支、為替レートの関係については、「弾力性アプローチによれば、国内物価の上昇は国際収支を悪化させ、為替レートの切り下げを招来させるし、又、所得=アブソープション・アプローチでは所得の上昇が、同様に国際収支の悪化、為替レートの切り下げへ、利子率の下落は、資本勘定を含めたマンデル=フレミング・アプローチによると、国際収支の赤字化、為替レートの切り下げを招くという結論をえる。これに対して、マネタリー・アプローチでは、これら諸変数の変化は、ことごとく、貨幣の超過需要をもたらし、国際収支を改善、為替レートを切り上げることになる。」(長谷川 聰哲、秋葉 弘哉、谷 重雄『購買力平価と為替レート』p2)と書かれている。
4.効率的市場仮説と為替予測
前述のように、為替相場に関する統一的な経済学的な見解は未だに現れていない。しかし、経済学的には為替相場の決定理論とは別に、効率的市場仮説が存在する。もし為替市場が効率的であれば、相場予測は成り立たないことをこの理論は示している。しかし、為替関連商品の販売に際して、為替動向、予測などを全く用いないことは考えられない。
代表的な為替予測の方法としては、ファンダメンタルズ分析と、チャート分析があげられる。その両者は市場では根強い支持者がおり、どちらか一方が優位に立つという状況ではない。為替レートを予測することは可能であろうか。
4.1ファンダメンタルズ分析
為替レートはよくある国の株価にたとえられる。ファンダメンタルズ分析は、株価を分析する際に頻繁に使われる手法である。ファンダメンタルズ分析では、株価とは「投資家がその株式を保有することによって、将来現金で受け取ることが期待できるすべての利益の現在価値の合計」(Malkiel,
Burton G., A Random Walk Down Wall Street,
(井出 正介訳『ウォール街のランダム・ウォーカー』p124)を発行株式数で割ったものである。この真のファンダメンタルズを決定する要因は、期待成長率、支払配当額、リスクの度合い、金利水準があげられる(同前pp124-134)。期待成長率とはその企業が将来どれだけ成長して、株式の所有者に還元してくれるかを問題にしている。期待成長率が高ければ、当然株価も高くなる。支払配当額も自明であろう。配当の高い株式ほど株価は高くなる。リスクの度合いとは、投資家は、もし配当などが同程度であれば、リスクの低い株式を選好するということである。また、投資家は金利水準にも左右される。もし金利水準が充分に高ければ、株式に替えてリターンが確実に予想できる債権投資などに資金を振り向けるであろう。
上記株価の理論に対しては、理論的な反論はないようである。問題は、いかに将来の成長率、配当額、リスクなどを予想するかである。これらの指標をいじるだけで、適正株価は大きく異なってしまう。一般的に、「強気市場に割高株はなく、弱気市場に割安株はない」(同前p146)などといわれるように、周囲の状況に大きく左右されてしまうのである。
為替におけるファンダメンタルズ分析においては、上記株式の分析はそのまま当てはめるわけにはいかないであろう。そもそも、何をもってある国の現在価値とするかは難しいところである。また、株式とは異なり、貨幣の流通量をいかにして測定するかも問題がある。一般的にはGDPやGDP成長率などを用いて分析するのであろう。実際、1999年から2000年にかけて、日本の景気が回復したか否かを計る指標として日本のGDP指標が注目され、それが短期的には為替相場に影響を与えていたことが想起される。ただし、実際にGDPの数値が発表されるのは、実際にデータが取られてから、数ヶ月たった後であることは注意を要する。
1999年から2000年にかけて日本のGDP指標が注目されたと書いた。実際には、発表されたGDP指標以上に、政府当局者の発言する将来のGDP成長率の予想に一喜一憂したものである。また、実際にそれらの発言によって為替相場も動いたものである。株式における期待成長率に政府がお墨付きを与えてくれたようなものであるから(その予想は市場関係者の予想よりかなり高いものであった)、日本円に買い手が集まったことも当然であろう。
上記のように、予想成長率の如何によって結果が大幅に異なってしまう欠点があるとはいえ、ファンダメンタルズ分析は、長期の為替動向に対して重要な示唆を与えてくれる。特に、資本収支の動向に大きな影響を与えるという意味で、その国の期待成長率は注目される。投資資金は、将来的な成長に賭けて動くものだからである。
4.2テクニカル分析
テクニカル分析とは、株価や為替レートのチャートを作り、それを“解釈する”手法である。ちょうど、星占いでチャートを作り、誰かの人生を解釈することをイメージすると分かりやすいであろう。素人目には何も物語ってくれないチャートを前に、テクニカル・アナリストは神秘的なシグナルを見出すのである。
株式相場のみならず、為替相場においてもテクニカル分析は極めてポピュラーな手法である。チャート分析の基本は経験則である。きのう起こったことは今日も起きる。前回、同じような値動きをした後、相場がひっくり返った。今日も同じことがあったから同じ事が起こるに違いない。ほとんど縁起担ぎの世界である。
チャート分析はそれだけで何冊も本が書けてしまうほどであるので、詳しい内容には触れないが、日本人には、世界最初の先物取引市場は江戸時代、大阪は堂島の米市場によって始まり、その相場分析から世界最初のチャート分析が生まれたことは記憶しておいていただきたい。株式市場などで盛んに使われているローソク足はこのとき生まれ、世界的にキャンドル・チャートとして親しまれている。日本人も金融取引においても先進性があった実例といえるであろう。
経済学においても、回帰分析といった手法が採用されることがあるが、これはテクニカル分析とは異なる。計量経済学・回帰分析を行う上で最もやってはいけないことは、経済学的に因果関係がない事象を回帰分析の結果だけで結び付けてしまうことである。例えば、戦後30年、日本の輸出は伸びてきた。同じように日本の離婚率も伸びた。この二つを回帰分析すると非常に高い相関係数が出た。だから離婚の増加が日本の輸出を支えてきた、といった経済学的ナンセンスである。
4.3効率的市場仮説
テクニカル分析とファンダメンタルズ分析は、為替市場の予測に対して全く対照的なアプローチを取っているように見える。しかしながら、経済学的な見地からは、すでに結論が出ているのである。「投資家に平均以上のリターンを提供し得るかどうかという点で、ファンダメンタルズ分析は、テクニカル分析と大して変わらないのである」(Malkiel,
Burton G., A Random Walk Down Wall Street(井出 正介訳『ウォール街のランダム・ウォーカー』p257))。現在では、為替市場はほぼ効率的市場であるとみなされており、そのような市場において、将来予測(特に近い将来)はできないとされている。「為替レートの予想を行うのは、その人が真のエコノミストでないことの証明だ」、「いまでは、計量モデルで為替レートを予測しようなどと試みる学者は、さすがにいない」(野口 悠紀雄『金融工学、こんなに面白い』pp35-36)とまで書かれている。
効率的市場仮説においては、株式など市場性商品の価格はすべての利用可能な情報を完全に反映して形成されているとしている。効率的市場は3つのタイプが規定されている。
最も厳格なタイプはストロング型と呼ばれる。ストロング型は、インサイダー情報を含むすべての公開、未公開情報が価格に反映されているとする。ストロング型の効率的市場においては、たとえインサイダー情報を用いたとしても、市場を出し抜いて高いリターンを得ることは不可能である。
次にあげられるのがセミストロング型と呼ばれるタイプである。セミストロング型においては、公開されている利用可能な情報はすぐに投資家によって使用される。そして、価格は情報を瞬間的に織り込み、市場は均衡状態に到達する。セミストロング型の効率的市場においては、価格はすでにすべての公開情報を織り込んでいるのであるから、ファンダメンタルズ分析など無意味ということになる。
最も弱いタイプがウィーク型である。ウィーク型の効率的市場においては、過去の価格変動のデータに基づいて投資したとしても、市場を出し抜けないことを主張している。テクニカル分析は、上記ストロング、セミストロング型の効率的市場はもとより、ウィーク型の効率的市場においても、その有効性を否定されることになる。
効率的市場仮説については、「この30年間、学会は経験に基づいてこれらの理論を継続的にテストしてきた。その結果、ほとんど一律にウィーク型の市場論を支持しており、概してストロング型は否定されている。セミストロング型の検証の結果については全く同意されていない」(Evansky、
Harold R., THE WEALTH MANAGEMENT,
(三原 淳雄/北山 雅一訳『ウェルス・マネジメント』p146))とされている。
4.4為替相場は効率的か
効率的市場仮説については、経済学者は概ね賛意を示しているようだが、実務家には評判が悪い。マルキールのような学者ですら(彼はプリンストン大学教授)「私は、多くの同僚たちのように、この分野すべてを否定するところまでは、心の準備が整っていない。」「市場には幾多の子鬼たちが跳梁しており、効率的市場論者を悩ませるのである」(Malkiel、
Burton G. A Random Walk Down Wall Street、
(井出 正介訳『ウォール街のランダム・ウォーカー』p261))と書いている。
効率的市場仮説への批判は大体以下の2点に絞られるようである。
第一にあげられるのは、効率的市場仮説がかなり極端な仮定に依存していることである。ストロング型はもちろん、セミストロング型でも情報は瞬時に投資家全員に共有されるとしている。そして、その情報を完全に分析して価格は決定されるとしているが、このようなことがあり得るのであろうか。
この点について、実務家の書いた文献には、「金融マーケットは思惑で動いているということを理解されたい。ある種の相場変動の発生が見込まれるとき、相場は、その予測精度(情報の確かさ)を織り込みながら動いていく。そして、その予測精度がほぼ100%になった時点で、あるいは、その予測が現実のものとなった時点で、この相場は完了するのである。」「言い換えると、ディーラーは、予測精度が6対4(ロクヨン)の時点でポジションをとらなければならない。そして、それが幸運にも、8対2、更に9対1となっていく過程で、どうにか収益をあげることができる」(田中 泰輔『相場は知的格闘技である』p41)とあるが、全く同感である。
私自身為替ディーラーとしてポジションを取った経験がある。そのとき痛感したのは、ディーラーに求められるのは判断ではなく、決断であることである。市場にある情報を100%収集、分析の後にディールを行うことはない。その時点では相場が動ききっていて、手遅れである。従って、ディーラーは情報が依然として不確実である時点においてディールを行わなくてはならない。そのとき求められるのは、判断ではなくて、決断なのである。
更に、効率的市場支持者を悩ませるのは、市場には少数とはいえアノマリー(例外)が存在することである。これは為替市場ではなく、株式市場の例であるが、1990年代半ばに人気を博したファンドに、「ダウの負け犬」戦略を採用したものがある。これは、毎年ダウ工業30種指数の採用銘柄の中から、最も配当率の高い(株価が相対的に安い)10銘柄を買うものである。この戦略はあるファンドマネージャーが考案、彼の健勝によれば1920年代以来{ダウの負け犬}がダウ平均を年2-3%上回ってきたという。当初はうまくいったようであるが、すぐに追随するファンドが続出、90年代の後半には毎年市場平均を下回る成績になってしまったという(Malkiel、
Burton G. A Random Walk Down Wall Street、
(井出 正介訳『ウォール街のランダム・ウォーカー』pp334-335))。
また、マルキール自身が以前の著書で勧めていた投資戦略(クローズド・エンド・タイプの会社型投資信託を買うこと)も、うまく行き過ぎたために、現在では魅力のない投資戦略になってしまったという(同前p454)。
為替市場における例では、私自身、ディーラーとして似た経験をしたことがある。1980年代中ごろ、米国の貿易赤字が大変問題となった(その時点では財政赤字とセットになった双子の赤字問題と言われていた)。米国の貿易統計は毎月発表されるが、発表された赤字の額を巡って、発表毎に為替市場は大きく変動したものである。赤字額が大きければ、当然ドル売り圧力がかかる。
この時点では、米国の貿易赤字額は事前にはほとんどわからず、ディーラーたちは発表を待つしかなかった。そして、発表直後、動き始めた(方向性の明らかになった)マーケットでポジションを取ることで収益をあげることができたのである。情報伝達速度に、どうしても時間がかかるからである。そして、米国商務省の発表するデータに反応してすぐポジションを取れるディーラーばかりではない。中には、翌日の新聞発表まで知らない投資家もいるのではないだろうか。もちろん、事前にポジションを取って赤字額の大小に賭けることもできる。しかし、私としては、指標発表後にポジションをとっても収益をあげられるのであるから、あえて賭けはしなかった。
ところが、このころから市場エコノミスト(FEDウォチャ―など)と呼ばれる人種が活躍するようになった。実は、米国の貿易統計は、事前に発表される各種の部分的な通関統計などから容易に推定できたのである。また、米国の貿易統計が毎月大きく振れる原因として、航空機の輸出があげられる。航空機の輸出は、金額的には大きいにもかかわらず、決して継続的に毎月計上されるものではない。しかし、航空機製造会社がたくさんあるわけでもなく、輸出のスケジュールも調べられる。
そのようなことが分かってしまうと、さまざまな金融機関が米国の貿易統計の予測を事前に発表するようになった。もし、米国の貿易統計が予想通りであり、相場が予想通りに動くのであれば、事前にポジションを取ることによって容易に収益をあげられる。もちろん前述の理由によって予測の精度はかなり高い。そこで、市場は徐々に米国の貿易統計を発表前に“織り込む“ようになっていった。そして、実際の指標が発表されても、その時点では織り込み済みであるとして、市場が反応しないようになっていった。次第に市場関係者の注目も貿易統計から離れていって、1990年代には、あまり注目されない指標になってしまった。
以上のように、アノマリーは存在する。ただし、これらアノマリーが永続しなかったことも事実である。従って、上記アノマリーの存在だけで、効率的市場仮説を否定し去ることはできない。効率的市場仮説は情報の瞬時の共有を前提としているが、瞬間的に情報が共有されるなどということは現実には期待できない。また、たとえ公表されていたとしても、投資家一般に知られていない情報は、共有された情報とはいいがたいであろう。現在の為替市場は、ウィーク型とセミストロング型の間のどこかに存在する(あるいはその間を行ったり来たりしている)のではないだろうか。
5.外貨建て商品の勧誘方法
本年度より施行される「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて、為替相場の変動に伴い元本割れが考えられる商品については、重要事項として説明が要求されるようになる(「当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがある場合」(金融商品の販売等に関する法律第3条第1項第1号))。法律上は、外貨建て商品の場合、為替相場の変動に伴い元本割れの危険性があることを指摘すれば説明義務は果たしたことになる。
しかし、為替関連商品を販売する場合に、金融機関としては、元本割れの可能性を指摘するだけで為替の仕組みや内容について触れないというわけにはいかないであろう。また、情報提供の一環として相場予測を提供することも一般的に行われている。ところが、上記のように、効率的市場において理論的には、予測は根本的に成り立たない。そもそも外貨建て商品への投資が極めてリスクに満ちたものであるとするなら、いかなる理論に基づいて外貨建て投資は正当化されるのであろうか。そして、どのような説明、予測の提示方法が好ましいのであろうか。
外貨建て投資は確かに為替リスクを負うものであるかも知れない。しかし、分散投資の観点から眺めてみると、また異なったリスク・プロファイルを持っていることが明らかになる。
昨今の日本国内における運用難から、外貨建ての投資が脚光を浴びている。実際に、その種の商品も多く目にするようになった。投資先を多様化するという意味では外貨建て投資は有効な手段である。しかし、理論的には、為替相場を確実に見通すことは不可能であることは、指摘したとおりである。現在、超低金利が続く日本円に対して外貨建て投資は表面的には高い利回りが期待されている。ところが、為替部分のリスクヘッジを行うと、金利裁定が働いて邦貨建て投資を実行した場合と変わらなくなってしまうことも、前述のとおりである。そのような場合でも、国際分散投資の観点から見れば、外貨建て投資は推奨に値する投資方法なのである。外貨建て投資は、単にリスクを取ることによって高いリターンを期待するだけの投資手段ではない。
華僑のお金持ちは、国際的な分散投資を好んで行うといわれる。彼らの場合は単に資金を国際的に分散して投資するばかりでなく、子供達の教育も、1人には英語を習わせ、もう1人には中国語に親しませるという。また、留学先も米国、英国、その他と分けるそうである。そして、もし将来一族に一朝事あれば、助けられるものが助ける、という協定を結んでいるという。
子弟の語学や留学先を分散するのは先の話であるとしても、国際分散投資の手法は注目に値する。現在、企業を取り巻く経済環境は急速に地球規模に拡大しつつあり、日本で生まれ、日本で育ち、日本で働き、日本で死んでいくという日本人の一生が繰り返されるとは限らない時代になりつつあるのである。であるとすれば、そこに働く個人のポートフォリオもグローバル化する意味があるのではないだろうか。為替リスクを避けるために一国に投資を集中することは、長期的には逆にリスクを負う事になってしまいかねないのである。分散投資が確実にリスクを軽減させる手法であることは、ファイナンス理論の常識であるといってよい(分散投資については補論2参照)。
通常、外貨建ての投資を行う場合には、為替ヘッジの有無を問題にする。しかし、長期にわたって本格的に国際分散投資を行うのであれば、ヘッジを行うことは無意味である。国際長期分散投資を行うのは、世界のある地域に対する投資のパフォーマンスが悪くても、その他の地域がよいパフォーマンスを示せば、全体のポートフォリオとしては安定したリターンが期待できるからである。ヘッジを行ってしまうと、金利裁定が働くので、事実上日本なら日本だけに投資したのと同じことになってしまう(特に固定金利商品に投資した場合)。
実際、内外機関投資家などの行う投資においては、国際分散投資の配分が、ある著名な通貨インデックス(国際的な資金配分を規定している)に基づいて行われているという。その場合、基本的にはヘッジは行わず、その通貨のままで投資評価を行う。
現在、外貨建て商品は、為替リスクのみに注目して元本割れがあり得る高リスク商品に分類されている。分散投資の考え方に従えば、円なら円だけに投資していることにも、リスクが存在するのである。そして、そのような為替リスクは投資先を分散することによって軽減できるのである。現状では、投資家に国際分散投資の前提知識も普及しているとは思われず、何よりも為替に関する知識も充分であるとは思われない。そのような状況の中ではやむをえないと思われるが、国際長期分散投資の意味を勘案すれば、金融商品の販売等に関する法律において、外貨建てであれば自動的に元本割れの危険性のある商品に該当するとして説明義務を課していることは的を射ていないように思われる。
基本的に予測不可能な為替相場において、確実にリスクを減らす投資手段が国際分散投資であることは、理論的には疑いはない。ただし、グローバルに展開した企業が投資する場合に適用できる理論やインデックスも、個人投資家が投資する場合には問題がある。個人投資家などが外貨建て投資をする場合には、情報の不備、伝達の遅れ、換金性、手数料なども問題になるであろう。特に、不慮の事故などによる換金まで考慮する場合、実際に一国をベースに生活している生活者にとっては、流動性の低い外貨建て投資は不利となるであろう。しかし、長期的な投資を考えた場合、国際長期分散投資は充分考慮に値する投資方法であると思われる。
国際長期分散の意義を充分に理解して投資する投資家に対しては、有効な投資手段であるといえるだろう。現状の投資家教育や、外貨建て商品の普及の度合いからすれば致し方ないのかもしれないが、将来的に国際長期分散投資の意味が広まるとともに、認識が変わることを望みたい。ただし、そのような場合においても、上記のようなインデックスを生活の基盤が国内にとどまる個人投資家に一律に適用することには問題がある。個人投資家あるいは小規模な投資家がどのように資金を分散するのが適当かは個別にその資質や資産内容、さらにはその人生設計を吟味して決定していく必要があるであろう。
5.2ドル・コスト平均法
投資戦略として長期国際分散投資を行うとしても、実際にどのような投資戦略が好ましいのであろうか。特に、効率的市場仮説に基づくと、最適なタイミングで投資を実行することを期待するのは不可能だということになる。
そのような不確実な状況下で長期に投資を行う際に取り得る有力な投資方法が「ドル・コスト平均法」である。ドル・コスト平均法とは一定の金額を毎月もしくは毎四半期ごとなど一定のルールに従って、長期間にわたり同じ投資対象に同じ金額を投資し続ける戦略である。同じ金額を(同じ数量ではない)投資し続けることによって、一時的な高値で投資することを防げるのである(逆に理想的な安値での購入も期待できない。ドル・コスト平均法を採用することで、リスクをなくすことはできないまでも、かなり軽減できることは証明されている(Malkiel、
Burton G. A Random Walk Down Wall Street、
(井出 正介訳『ウォール街のランダム・ウォーカー』pp389-394))。
特に個人向けの外貨建て商品を販売する場合に、資産に占める外貨建て商品の目標金額を設定して、その金額に達するまで一定金額を投資しつづけるといったアドバイスは、リスク回避の観点から推奨できる方法である。また、一般的顧客というものは、投資をした場合には、一時的な相場変動に一喜一憂しがちなものである。ドル・コスト平均法は、顧客にとっても、一時的な為替動向に煩わされることなく長期投資を実現できる、大変好ましい投資手法であるといえるだろう。
5.3情報提供をする場合の留意点
為替相場の決定理論に統一的な見解が見られないことは前述のとおりである。また、効率的市場仮説に基づけば、相場予想が成り立たないことは前述のとおりである。しかし、個人顧客に対して外貨建て商品を販売するにあたって、経済情報や相場予想を全く示さないということは考えられない。また、経済学理論上否定されているとはいえ、株式市場などでアナリスト予想が広く一般的に受け入れられている現状では、そのような相場予想を提供することが近い将来、否定されるとは思えない。個人顧客に対して外貨建て商品を勧誘する場合には、以下のような点に留意することが必要であろう。
まず、一般的な説明として為替動向や予測を記したレポートを交付する場合には、予測についてはその内容があくまでも予想であり、外れる場合もあり得ることを明示しなくてはならないであろう。実際に為替相場予想などを作成する場合には、
「本レポート記載のデータは各種の情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。本レポートは情報提供を目的としており、記載されている意見や予想は外国為替、証券、オプション、先物等の売買を勧誘するものではありません。将来的に予想通りの結果とならない可能性があります。投資の決定は投資家自身でなさるようお願いします。」
といった文言をフットノートなどの形で記しておく必要がある。
また、このようなレポートを作成する人間と実際に販売にあたる人間は異なるのが普通である。為替予測レポートなどは通常為替のトレーダーもしくはエコノミストなどが作成する。一般的には専門化が作成したものとして大変権威があると思われ、セールストークとして、「当行のエコノミストの予想によれば」などいかにも確定的な情報であるかのように説明される場合がある。ある程度のセールストークは許容されるであろうが(セールストークについては、変額保険に関する訴訟において許容例がある。東京地裁平成7・9・25民事第30部判決『金融法務事情』No.1465
p155)、過度のものは断定的判断の提供として違法性を問われることも考えられる。
国際分散投資の観点からは、為替ヘッジを行わないと前述したが、特に意図的にそのような投資方法を採用している投資家でない限り、個別商品の説明に際しては、シミュレーション表やグラフなどの形で、為替相場がいくらになったら実際のリターンがどのようになるかを示すことは必要であろう。外貨建て投資商品においては、返済金額を確定する為替相場がどの時点のものが適用されるのか、相場がいくらになったら円価に引き直した利回りがいくらになるのか、その相場がいくらになったら元本割れを起こすのかといった点を明示することが好ましい。
また、為替組み込み商品の中には、オプション、しかもノックアウト(ノックイン)・オプションなどを組み込んだものも数多い。この種の商品の場合には、投資期間内における為替相場の変動の履歴によって、最終的に適用される相場が異なってしまう(Path
Dependent Optionなどとも呼ばれる)。この種の商品の場合には、条件が満たされたかどうかのシナリオ別にシミュレーション表を作成するなどの配慮が望まれる。一般に、このような商品を説明する場合には、グラフは適さない。金融機関がプレゼンテーション資料を作成する場合、作り手側としてビジュアルな情報が好まれる。しかし、グラフを読み取るには特定の知識が要求される上、ノックアウト(ノックイン)・オプションなどを表示する場合にはグラフ自体が複雑になるため好ましくない。
以上のような諸点に留意した為替関連金融商品の販売が望まれる。
5.4インサイダー取引
効率的市場仮説のうち、ストロング型においては、インサイダー取引を含むすべての情報は市場に反映されており、たとえインサイダー情報を用いたところで市場を出し抜くことはできないとしている。しかし、ストロング型仮説は概して否定されている。特に株式市場などにおいて、インサイダー情報を用いて取引をすることで確実な収益をあげうることは、数々の摘発事例が証明している。従って、株式市場などにおいては、インサイダー取引は法的にも明確に禁止されている。
しかし、外国為替取引においては、明確にインサイダー情報に基づく取引を禁止した法律はない。これは、日本のみならず、先進諸国も同様である。従って、介入の情報や、大手投資家、ヘッジファンドなどの取引動向を入手、取引することも制度上は可能である(違法ではない)。ただし、そのような情報が公開情報となった時点で取引することは、上記効率的市場仮説のもとではほとんど無意味であろう。特に、中長期的な相場動向を問題にする場合には、意味をなさないといってよいと思われる。為替市場は株式、債券市場などと比べても経済学的に効率的な市場であり、公開情報はすでに市場に織り込まれてしまっているからである。そのような情報を反映した上で現在の相場が形成されているのであって、そのような取引が今後の相場を形成するわけではない。例外があるとすれば、大口取引が超短期的に市場に与えるインパクトを利用する取引である。つまり、大口の取引が持ち込まれたときに、同時、もしくは先回りして同方向のポジションを造ることができれば、確実な収益が見込める。実際に、為替ディーラーはこのようなチャンスがある場合には、最大限に利用しようとするものである。
確かに、セールストークとして、内外の著名な投資家の動向を話題にすることも多い。また、以前はそのような投資家も、市場が提灯をつけてくれることを期待して、取引手口を公開することもあったようである。しかし、昨今、為替市場の参加者は大体においてその取引手口が公にされることを嫌うようである。ヘッジファンドなどはあまりにも有名になりすぎた結果、投資効率が下がったり、無用の批判を浴びたりするようになったからである。もし実際にその金融機関がその投資家と取引をしているのであれば、顧客の意思に反して顧客取引情報を公開することになり、コンプライアンスの見地からは大変好ましくないことになる。逆に、その金融機関がその投資家と取引をしていないのであれば、顧客にとって情報としての価値はない。
実際には、まともな金融機関であれば顧客取引を利用して収益をあげることを否定しないものの、顧客に損失を与える、あるいは不利になるような取引を許容してはいない。また、コンプライアンスの観点から顧客の取引情報を外部に漏らすことも禁止されているのが通例である。介入の場合などでは、介入の事実をマーケットに知らしめるアナウンスメント効果を重視する場合もあるが、例外である。金融機関にとって大口の優良顧客である大手投資家やヘッジファンドの動向をリークすることは、金融機関の利害を考えれば、ありえない。少なくとも、取引に利用できるような極超短期に時間内にそのような情報を入手することは一般顧客には不可能である。
金融機関側としては、コンプライアンス上好ましくないと判断される情報の提供はするべきではない。顧客の側も、金融機関が大口取引を失うリスクを犯して情報を提供してくれるのでなければ無意味である以上、このような情報を期待するのは無駄であるといえるであろう。
6.結論
為替市場が効率的市場であり、相場展開を確実に見通すことがほぼ不可能なことは上記のとおりである。また、外貨建て商品に投資した場合に、為替リスク回避のために同時に為替ヘッジを行うと、金利裁定が働くため、邦貨で投資したのと同じ結果になってしまうことも前述のとおりである。リスクを取らなくてはリターンが得られないのである。
リスクを取ればリターンが得られるという平凡な理由以外に、外貨建て投資を正当化する理論があるとすれば、分散投資の理論である。現在、企業活動はグローバル化しており、それに伴って個人の活動もグローバル化しつつある。その中で、個人のポートフォリオの見直しも必要になっていくことであろう。そのような環境の中で国際分散投資を行うことは、ひとつの通貨のみに投資することのリスクを軽減し得る有効な手段である。
リスクを避け、相場変動の波を避けて投資を行う方法として、ドル・コスト平均法が有効な手法である。ドル・コスト平均法は相場変動リスクを避けるという意味ばかりではなく、投資家にとっても長期投資に対する心構えを自動的に提供してくれるという点でも、優れた手法と言えるだろう。
ただし、外貨建て商品と一言でいっても、通貨も異なれば、投資対象商品も債権、株式、不動産、その他と多岐に渡りうる。外貨建て商品のリスクの計測方法を統一化、明確化し、リスク分類を公表することで個人投資家向けの投資指針を作成することも必要であろう。また、そのような投資指針を前提として、どの程度の金額を外貨建て商品に投資すべきかといった問題を、個人の資質、資産内容に応じて判断していくことが必要になるであろう。
<補論1>実際のデータをもとにした経済理論の検証
国際収支と為替レート
本論においては、総合収支データと為替レートの相関関係についての計量分析は取り扱わない。また、資本収支を長期と短期に分類していないなど、かなりラフな分析である。ただし、以下の点はグラフからも読み取れるものとして、指摘しておく。
表補1-1及び1-2において、ドル円のヒストリカルデータと、実質実効為替レートの推移及び、日本の経常収支、資本収支のデータを示した。日本の経常収支は上記データ期間では一貫して黒字を示している一方、資本収支は経常収支を上回るボラティリティーを示している。これは、経常収支が産業活動の結果であるのに対して、資本収支は投資などより足の速い資金の移動を反映しているからだと思われる。
ここ15年で最も資本収支の赤字幅の大きかった1998年度において、実質実効為替レートが低下していること、逆に資本収支が黒字化した1999年から2000年にかけては実質実効為替レートが上昇していることは、注目に値する。逆に、歴史的円高(1ドル79.75円、1995年4月19日)を記録した後に(1月-2607、2月3873、3月1179、4月6092、5月2896、6月-265、7月7233、8月14897、9月9650、10月-3623、11月1015、12月768(億円))資本収支のピークが来ていることも、注目しなくてはならない。
いずれにしても、過去のデータからは、物やサービスの輸出入に関わる経常収支より、投資資金の動きに関わる資本収支の方が為替レートの動向に関係が強いことが読み取れる。貿易黒字は円高をもたらす、といった議論がよく聞かれるが、実際のデータが支持しているとは思えない。また、日本は貿易立国であるから円安が好ましい、といった議論も、本論中の貿易依存度のところで指摘したとおり、再検討が必要なようである。
表補1-1 ドル円及び実質実効レート推移
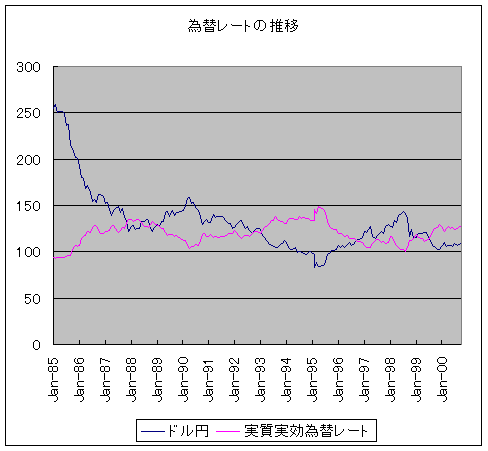
実質実効為替レートは日本銀行試算値。主要輸出相手国通貨に対する為替相場(月中平均)を、当該国の物価指数で実質化したうえ、通関輸出金額ウェイトで加重平均したもの。
出典 日本銀行http://www.boj.or.net.jp/dlong_f.htm(2001/01/09)
表補1-2 経常収支と資本収支(億円)
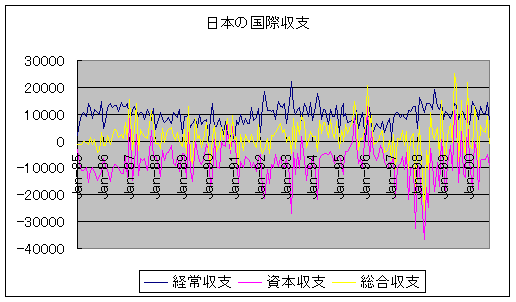
総合収支は経常収支と資本収支の合計
出典 日本銀行http://www.boj.or.net.jp/dlong_f.htm(2001/01/09)
日米金利差と為替レート
表補2-1及び2-2において、為替レートと日米のオーバーナイト金利推移を掲載した。
1995年以降、日米金利差は約5%程度で安定しているにもかかわらず、為替レートは80円割れから150円近く上昇、その後再び100円近くまで下落している。ドル円相場については、金利差に着目した分析にはあまり意味がないようである。
表補2-1
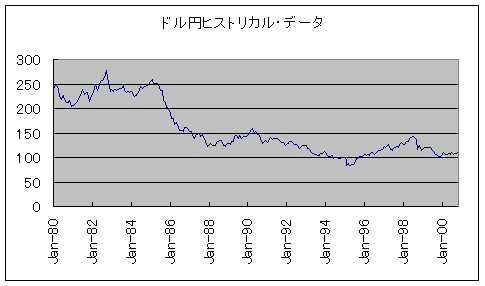
出典 日本銀行http://www.boj.or.net.jp/dlong_f.htm(2001/01/09)
表補2-2 日米金利差
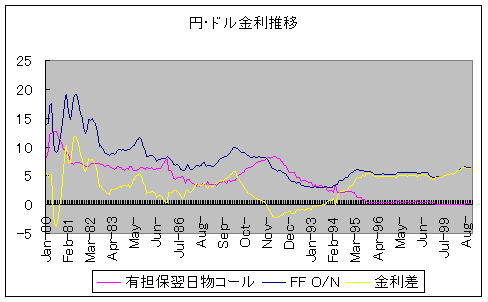
出典 日本銀行http://www.boj.or.net.jp/dlong_f.htm(2001/01/09)
FRB http://www.federalreserve.gov/release/H15/data/m/fedfund.txt
(2000/01/09)
<補論2>分散投資の理論
投資にリスクはつき物である。しかし、投資家はリスクを求めて投資をするわけではなく、リターンを求めて投資するのである。同じリターンを期待できるのであれば、リスクが小さい投資が選好されることは、当然であろう。
分散投資をすることによってリスクを減らしつつ高いリターンを実現できることを証明したのが、1990年度のノーベル経済学賞を受賞したハリー・マーコビッツである。
分散投資の効果を示すために、2つしか会社がない離れ小島の例を考えてみる。(Malkiel,
Burton G. , A Random Walk Down Wall Street,(井出 正介訳『ウォール街のランダム・ウォーカー』p277))第1の企業は、ビーチ、テニスコート、ゴルフコースなどを経営するリゾート企業である。第2の企業は傘のメーカーである。両社とも企業業績は天候に左右される。表1にそれぞれの季節に期待される業績が示されている。雨の季節には傘メーカーが繁盛し、晴れの季節にはリゾート企業が繁盛する。
表1
|
|
傘メーカー |
リゾート企業 |
|
雨の季節 |
50% |
−25% |
|
晴れの季節 |
−25% |
50% |
また、この島では晴れと雨の確率がそれぞれ2分の1であるとする。
これから晴れるか雨が降るか予想がつかないとした場合、投資家がこの2つの企業のいずれを選択しても、期待されるリターンは12.5%である。しかし、実現する天候によって、投資結果は大きく異なる。天候の予想が当たれば高い収益を実現できる一方、外れる場合は元本を割り込んでしまう。
それぞれの企業に投資するのではなく、投資金額を半分にして、傘メーカーとリゾート企業に投資するとどうなるであろうか。この場合、期待収益は12.5%で全く変わらないものの、晴れても降っても一定のリターンを実現するポートフォリオを構成できるのである。
上記の例は、離れ小島に企業が2つしかなく、雨と晴れという2つの天気しかない、極端な仮定を置いている。また、その企業業績も完全な逆相関を描いている(数学的には相関係数が−1)。実際には完全な逆相関をしている投資対象を見つけることは不可能であろう。しかし、マーコビッツは、完全に同じ動きをする投資対象(相関係数が1)でない限り、分散投資をすることによってリスクを減らせる(分散を小さくする)ことを示した。
ただし、分散投資によっても、投資のリスクを完全に取り除くことはできない。上記の例でいえば、天候に対するリスクは分散投資を行うことによって確かに減少させることができた。しかし、島の経済が不況に陥り、雨が降っても傘を買わず、晴れても遊ばなくなった場合には、いかに分散投資を行ったとしても、対処不可能である。通常、分散投資によって排除することができるリスクを非市場リスク、排除できないリスクを市場リスクと呼んでいる。
また、ドル・コスト平均法に代表される、投資を一時に行うのではなく、小額に分けて投資していく方法も、有効にリスクを減少させることが知られている。時間的に購入時期を分散させることができるため、一時的な高値のときに金融商品を取得してしまうことを防いでくれるのである。特に、長期的に投資することが予定されている資金を運用する際には、有効な方法といえるであろう。
参考文献
Evansky、
Harold R. (1997)、 THE WEALTH MANAGEMENT、
McGraw-Hill Companies、 Inc. (三原 淳雄/北山 雅一訳(1999)『ウェルス・マネジメント』ダイヤモンド社)
長谷川 聰哲、秋葉 弘哉、谷 重雄(1984)『購買力平価と為替レート』文眞堂
神谷 一郎(1999)『大蔵省財務官榊原英資氏の大罪―円安誘導政策は誤りだ―』アスペクト
加藤 隆俊(2000)『為替を動かすのは誰か』
金融財政事情研究会編(1984)『先物為替取引と財務戦略』金融財政
Krugman,
Paul(1998), THE ACCIDENTAL THEORIST, W. W. Norton & Company
(三上 義一訳(1999)『グローバル経済を動かす愚かな人々』早川書房)
Malkiel、
Burton G. (1999)、 A Random Walk Down Wall Street、 W. W. Norton & Company、 Inc.(井出 正介訳(1999)『ウォール街のランダム・ウォーカー』日本経済新聞社)
Mundell,
Robert A. (1971) , MONETARY THEORY:INFLATION, INTEREST, AND GROWTH IN THE
WORLD ECONOMY, Goodyear Publishing Company, (柴田 裕訳(2000)『新版 マンデル貨幣理論』ダイヤモンド社)
野口 悠紀雄、藤井 眞理子(2000)『金融工学』ダイヤモンド社
野口 悠紀雄(2000)『金融工学、こんなに面白い』文芸春秋
須田 美矢子(1996)『ゼミナール国際金融入門』日本経済新聞社
田中 泰輔(1991)『相場は知的格闘技である』講談社
田中 泰輔(1992)『基本ゼミナール 金融マーケット予想入門』東洋経済新報社