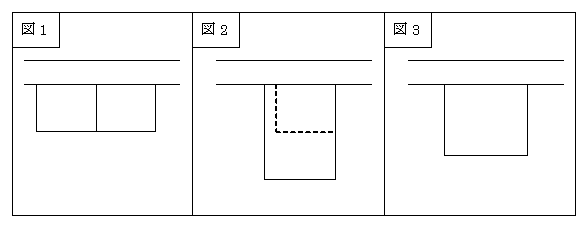 �}1�C2�C3�̓y�n�͂�������ʐ�200�������[�g���Ƃ���B�}1�̓y�n�͓��H�ɂ����Ē��������`�A�}2�̓y�n�͓��H���猩�čג����y�n�A�}3�̓y�n�͕W���n�̂悤�Ȑ^�l�p�ł���B
�}1�C2�C3�̓y�n�͂�������ʐ�200�������[�g���Ƃ���B�}1�̓y�n�͓��H�ɂ����Ē��������`�A�}2�̓y�n�͓��H���猩�čג����y�n�A�}3�̓y�n�͕W���n�̂悤�Ȑ^�l�p�ł���B�t�@�C�i���X�iFIN701�j10�N���W�b�g
�s���Y�،���
���̖��_�Ə�����
Rushmore University
Global Distance Learning DBA
�嚠
��
�{�_���̖ړI
��،��̎��s�ɒ��肽���{�s��ɂ����Ă��A�C�O�s��ł̕s���Y�،����̗�����čĂѕs���Y�̏،����Ɏ��g�ݎn�߂��B�،����ɂ�藬���������߂邱�Ƃɂ���āA�Ăѕs���Y�s��Ɏ����������A�o�u������ɂ���ď��s��̕��������҂��Ă�������������B
�{�_���ɂ����ẮA�s���Y�s��͏،����ɂ���ĕ�������̂��ǂ����A�܂��A�s���Y�،��̏��i���ɂ͖�肪�Ȃ��̂��ǂ������ȉ��̎菇�Ō�������B
�s���Y�����̊�{�͓y�n�ł���B�y�n�̒l�i�͍��E����v���Ƃ��āA
l
�y�n�̌`���L��
l
���z��@�̂܂����
��������B
���ɁA�y�n�̗��p�@�̖��Ƃ��āA
l
���L�y�ы敪���L
l
�ؒn���A����ؒn���A����؉ƌ�
�Ɍ�����������B���ɁA����ؒn���A����؉ƌ��͐V�����y�n���L�E���݂̕����Ƃ��āA�s���Y�،����ɂ��傢�Ɋ֘A������Ǝv���Ă���B
���ɁA�s���Y�،�����������Ƃ��āA
l
�s���Y�،����̎�@
l
�s���Y�Ӓ�]��
��ʓI�ȓy�n�̊Ӓ���@
���������A��������r�����A���v�Ҍ�����
�������A�ŏI�I�ɕs���Y�،����̖��y�я������ɂ��Č��_�Â���B
�ڎ�
1.
�y�n�̒l�i
1.1.1�y�n�̌������i
1.1.2�y�n�̌`��
1.1.3�ʑ�n
1.1.4���ĕt���n
1.1.5�n�グ
1.2���z��@
1.2.1�ړ��`���̊�{
1.2.2 4���[�g�����H
1.2.3 �ړ��`���ᔽ�̓y�n
1.2.4 �ړ��`�����̑��̖��
1.3
�y�n�̒l�i�Ɋւ�����
2.
�y�n�̗��p���@
2.1
���L
2.1.1
���@��̋��L�̒�`
2.1.2 �s���Y�̋��L
2.1.3���L���܂Ƃ�
2.2
�敪���L�@
2.2.1
�敪���L�@�̖��
2.2.2 �敪���L�@�܂Ƃ�
2.3
�s���Y�̒��ݎ�
2.3.1
�ؒn��
2.3.2 �ؒn�̖��_
2.3.3 �ؒn�̉����@
2.4
����ؒn��
2.4.1
����ؒn���̓��e
2.4.2 ������
2.4.3 ����ؒn���̗��p�Ɩ��_
2.5
����؉ƌ�
2.5.1
����؉ƌ��̓��e
2.5.2 ����؉ƌ��Ɋ��҂����o�ό���
2.5.3 �����I�v�V����
3.
�s���Y�،���
3.1.
�č��̕s���Y�Ƃ̓���
3.1.1
���ݎ�
3.1.2 �m�����R�[�X�E���[��
3.1.3 �č��ɂ�����s���Y�،�
3.2
�h�C�c�ɂ�����s���Y�،�
3.3
���{�ɂ�����s���Y�،���
3.3.1
SPC�@
3.3.2 �s���Y���M
3.3.3 �s���Y�،����̃����b�g�ƃf�����b�g
3.4
�s���Y�Ӓ�]��
3.4.1
�s���Y�̊Ӓ�]��
3.4.2 ��ʓI�ȓy�n�̊Ӓ���@
3.4.3 ���v�Ҍ��@�̎���
3.4.4 �s���Y�Ɋւ���f�[�^
4.
�s���Y�،��ƃR���v���C�A���X
4.1���p�����҂���鎑�Y�@
4.1.1�ƌv�̎��Y�\��
4.1.2�ƌv�̋��Z���Y�\��
4.2
����ҕی쐭��
4.2.1
���Z���i�̔��@�A����Ҍ_��@�Ɋ�Â������`��
4.2.2 ��Ɩ@�ɂ�����d�v�����̐����`��
4.3
�s���Y�،��� ���_�ƍ���̓W�]
5. ���_
�Q�l����
1.�y�n�̒l�i
�����ł́A�X�̕s���Y�̒l�i�ł͂Ȃ��A��ʓI�ɓy�n�̉��l�A�l�i���ǂ̂悤�ȗv���ɂ���Ăǂ̂悤�ɉe�����A���肳��邩�ɂ��Ăɂ��Ę_����B
�s���Y�̒l�i�͂��܂��܂ȃt�@�N�^�[�����ݍ����Č`������Ă���B�܂��A�y�n�͔��Ɍ��������A�����y�n��2�Ƃ��đ��݂��Ȃ��B�������A��q����悤�ɁA�����y�n�ł�����������A�t�ɕ��������肵�Ă��l�i�͕ς���Ă��܂��B
���ۂɕs���Y������ꍇ�Ɏ��n���������Ȃ����Ƃ͍l�����Ȃ��B�������A�s���Y�،����ɌW��s���Y�̂悤�ɁA���Z���i�ɑg�ݍ��܂ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����ƂɂƂ��āA�����ƕs���Y�̊ւ�肪�ɂȂ�댯��������B�s���Y�����ɍۂ��āA�ǂ̂悤�Ȗ��ɒ��ӂ���悢�̂ł��낤���B
1.1.1�y�n�̌������i
�y�n�̌������i�́A�s���Y�̎���ɍۂ��Ĉ�ʓI�Ȏw�W��^������̂Ƃ��čL���g���Ă���B�{�N���������i�����\����A�n�����オ�������������ƕ��ꂽ���A�����n���Ƃ͂����Ȃ���̂ł��邩�Ɋւ����{�I�ȏ�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�{���A�y�n�̔������i�͖��@��̌_�R�̌������猩�Ă��A����̓����҂����߂�ׂ����Ƃł���B�������A��ʏ���҂ɂ͓y�n�̓K���Ȓl�i�͂��ɂ����B�܂��A�y�n������삯�������ߏ�ȓ������ĂсA�n���o�u���������N���������Ƃ͋L���ɐV�����Ƃ���ł���B
�������i�Ƃ́A�y�n�Ӓ�ψ���n�������@�Ɋ�Â��A��ʂ̓y�n�̎�����i�Ɏw�W��^����Ƌ��ɁA�����p�n���̎擾���i�̎Z���Ƃ��ĎZ�o�������̂ł���B�n�������́A�����{�߂Œ�߂�s�s�v����̒�����y�n�Ӓ�ψ���I�肷��u�W���n�v�̒P�ʖʐς�����̉��i���߂�ꂽ��ʼn��i�肷�邱�Ƃɂ���čs����B
�����Œ��ӂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂́A�u�W���n�v�̐��i�ł���B�u�W���n�v�́A���������ۂɐF�X�ɗ��p����Ă���y�n���Q�l�ɑI�肳��邪�A����Ήˋ�̓y�n�ł���B�u�W���n�v�̉��i�́A�y�n�I��ψ���I�肵���u�W���n�v�̏ꏊ�ɁA�P5�O�������[�g�����x�̌`�̗ǂ��X�n�����݂��A���̓y�n���ŗL���g�p���ꂽ�ꍇ��z�肵�Č��肳���B
�]���āA���������݂��Ă����������݂��Ȃ����̂Ƃ��āA�܂��y�n�̌`��ɂ��Ă��A���ۂɂ��̏ꏊ�ɑ��݂��Ă���y�n�ł͂Ȃ��A�ł����p���Ղ��A���z�I�Ȍ`�����Ă�����̂Ƃ��ĎZ�肳���B�]���āA�����n�����L�ۂ݂ɂ��ĕs���Y���������ƁA�ȉ��q�ׂ�悤�ȕs�s�����l������B
1.1.2
�y�n�̌`��
�ی^��O�p�A�s��`�̓y�n�����Ƃ��ʐς������`�̓y�n�Ɠ������Ƃ��Ă��A�g���Â炭�A�]���ĉ��i�������Ȃ�ł��낤���Ƃ͗e�Ղɑz�������B�t�ɂ����A�ςȊi�D�̓y�n�ł����܂��g����Z�i����ʂȖړI������ꍇ�́A�ʐςɔ�ׂĊ����ȓy�n����ɓ��邱�ƂɂȂ�B�y�n�̎g�����ɉ�������̖ړI������ꍇ�ɂ́A��_�̂���y�n��T���Ă݂邱�Ƃ��A�y�n��������ɓ������@�ł���B
��ʓI�ɂ́A�����l�p���y�n�ł����}�Ɏ�����̂悤�ɁA�F�X�ƍ����o�Ă���B
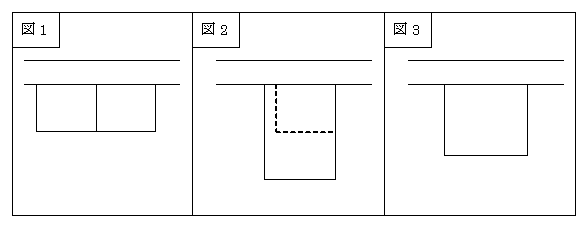 �}1�C2�C3�̓y�n�͂�������ʐ�200�������[�g���Ƃ���B�}1�̓y�n�͓��H�ɂ����Ē��������`�A�}2�̓y�n�͓��H���猩�čג����y�n�A�}3�̓y�n�͕W���n�̂悤�Ȑ^�l�p�ł���B
�}1�C2�C3�̓y�n�͂�������ʐ�200�������[�g���Ƃ���B�}1�̓y�n�͓��H�ɂ����Ē��������`�A�}2�̓y�n�͓��H���猩�čג����y�n�A�}3�̓y�n�͕W���n�̂悤�Ȑ^�l�p�ł���B
�}1�̏ꍇ�A�^�����番����Η��z�I�Ȏl�p���W���n�̂悤�ȓy�n���ł���̂ŁA�������e�ՂŁA�������i�Ȃǎw�W���i�ɋ߂����i�Ŕ����ł��낤�B�i����ł��A������k�ǂ̕��p�Ɍ����Ă��邩�A����ł��鏇�Ԃ͂ǂ����ō������܂�邱�Ƃ����邪�A�����ł͐G��Ȃ��j�B
�}2�͂ǂ��ł��낤���B�_���ŋ�����悤�ȓy�n���������A100�������[�g���̓y�n��2����B�����s���̕����Z��ł͗ǂ��������邪�A��둤�̓y�n�͍ď�������ۂɂ͂��Ȃ�����������Ȃ�͂��ł���A�D�܂����Ȃ��y�n�����Ƃ����邾�낤�B���R�A��̂̂��̂Ƃ��Đ}2�̓y�n����������ꍇ�ɂ��A�������i�ɖʐς��悶�������̒l�i�ł͏������ł��Ȃ��B��ʓI�ɁA���s���̐[���y�n�͒P�ʉ��i�������Ȃ�B
����ł͐}3�͂ǂ��ł��낤���B�W���n�̂悤�Ȑ����`�ł��邵�A�ꌩ���Ȃ������ł���B�������A���������ɂ͐}2�ȏ�ɖ����ȕ��������Ȃ���Ȃ炸�A��������Ƃ��Ȃ艜�s���̋����y�n��2�M�A�������͊Ԍ����������s���̐[��2�M���ł��邱�ƂɂȂ�B�ł́A�ꊇ���ď�������ꍇ�ɂ͂ǂ��ł��낤���B
���́A�ʐς̍L���y�n�̒l�i�́A�ʐς��L���Ȃ�̂ɔ���Ⴕ�ĒP�ʂ�����̉��i�͉������Ă����B��L�̗�ł́A200�������[�g���̓y�n�ł���B���������s���ɂ���Ƃ�����A���Ȃ�̍��z�����Ƃ����邾�낤�B�������A���̂悤�ȍ��z�����͂ǂ����Ă��̘H�����܂邵�A����Ȃ�̍����Z��X�ɂȂ��Ɣ���Ȃ��ł��낤�B���ӂ̏Z��݂�100�������[�g�����x�̏ꍇ�ɂ́A�K�v���Ȃ��̂ɍL���y�n��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B�y�n�͍L���Ƃ��������Ŗ��ɂȂ�ꍇ������̂ł���B
�����ł͈���100�������[�g���ɕ������ĕ������邱�Ƃ�O��Ƃ��ĐݗႵ�����A�ŋ߉��l�s�ł�100�������[�g���ȏ�̌��������z�ł���悤�ɂ����A�y�n�̋�抄���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ⴊ���邻���ł���i�q�����s�w�v����������A�b�Ƌ����s���Y�����@�x��70�j�B�e�ϗ�80���Ƃ���Ɩ�124�������[�g���ȏ�̓y�n���Ȃ��Ă͂����Ȃ����ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A��L�}1�A�}2�A�}3�̂悤��200�������[�g���̓y�n�͋�抄���ł����A��̂̂��̂Ƃ��Ĕ��邵���Ȃ��B���R�̘H�͋��܂�A�P���������Ȃ�ł��낤�B���r���[�ȍL���̓y�n��������������B
1.1.3�ʑ�n
����ɍL��ȓy�n�i�ʑ�n�j�̏ꍇ�͂ǂ��ł��낤���B
�L���y�n�ɑ��āA�Ⴆ�r�������Ă����̂őS���̓y�n����̂Ŕ��������Ƃ������v������ꍇ�͖��Ȃ��B�w�O�ōL���y�n�i���Ɨp�n�j�A�ȂǂƂ����ꍇ�ɂ͑S�����Ȃ������n���ɋ߂��l�i�i����ꍇ������ł��낤�j�Ŕ����ł��낤�B
�Ƃ��낪�A�Z��n�̏ꍇ�ɂ͎���قȂ�B�}���V�����p�n�Ɏg����ꍇ�͉��Ƃ��Ȃ邩������Ȃ����A����A�����w�Z����p�n��ȂǗp�r�K���ɂ�����ꍇ�̓}���V���������Ă��Ȃ��B�]���āA�������ď���������ق��ɕ��@�͂Ȃ��B
�}4�͕����Z��Ȃǂŗǂ����������ł���B�y�n��4���ɕ����A�ړ��`���i�ړ��`���ɂ��Ă͌��z��@�̍��ŏڏq�j�������߂Ɉʒu�w�蓹�H����������ł���B�}�͐��m�ȏk�ڂ������Ă͂��Ȃ����A�Ⴆ�ΑS�̂�400�������[�g���̓y�n���Ƃ���B���傤��20���[�g���l���ɂȂ�B�ʒu�w�蓹�H�͕����Œ�4���[�g���K�v�ɂȂ�A������10���[�g���ɂȂ�̂ŁA���H�p�n�Ƃ��āA4��10��40�������[�g���K�v�ɂȂ�B�܂��A���ۂɂ͐}�Ɏ������Ƃ�����肪�K�v�ɂȂ�̂ŁA����ɍL���Ȃ�B��������ƁA400�������[�g���̓y�n�Ɉ������ݓ��H������������ŁA���ۂɎg����y�n�ʐς�1���ȏ�������Ă��܂����ƂɂȂ�B�������A�y�n�̕]��������ꍇ�ɂ́A���H�̕]�����i�̓[���Ƃ��ĎZ�肳���B
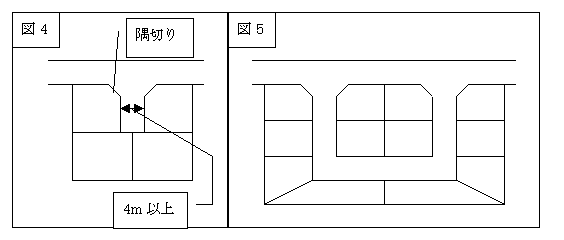
�}5�̏ꍇ�́A12���ɕ��������ꍇ�ł���B�P���100�������[�g���Ƃ��āA�����ł���y�n���S����1,200�������[�g���A���m�Ȍv�Z�ł͂Ȃ����A���H��4���[�g�����ʼn�����60���[�g����240�������[�g���ɂȂ�̂ŁA�S�̂̓y�n�ʐ�1,440�������[�g���̂����Ȃ��18�������H�Ő�߂��Ă��܂����ƂɂȂ�B
���̂悤�ȓy�n���������ꍇ�ɂ́A���R�����Ȃ�B�����H�����抄�̔�p�����Ă���ƁA2���ȏ�����Ȃ�Ǝv����B
�܂��A��ς悭����P�[�X�Ƃ��āA�����̈ʒu���s�K���ȏꍇ������B��L4�}�̂悤�ȓy�n�́A���傤�Ljʒu�w�蓹�H�̏�ɂł�ƕꉮ�������Ă���ꍇ�ł���B�m����1���̉Ƃ����Ă�ɂ͍œK�ȏꏊ�ł��낤�B�Ƃ��낪�A�y�n������K�v���ł����ꍇ�ɂ́A�Ɖ������Ȃ��Ă͕����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���̊ȒP�Ȍ����ł���Ύ��Q�͏��Ȃ����낤���A�}���V�����Ȃnj��łȌ��������ĂĂ��܂����ꍇ�ɂ͖��ƂȂ�B
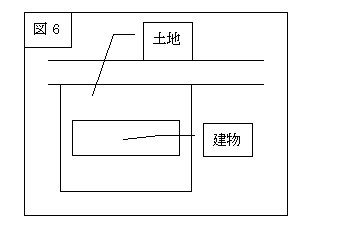
�}6�̂悤�ȏꏊ�Ƀ}���V�����Ȃǂ����Ă��ꍇ�A�����̌�둤�̓y�n�͐ړ��`�����ʂ����Ȃ��̂œy�n���ł��Ȃ��B�����̑O�̓y�n���A�ړ��`���Ȃnj��z��@��̐����͎Ȃ��ꍇ�ł��A�ג����A��ʓI�ɍD�܂����Ȃ��`��̓y�n�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���z�ς݂̃}���V�����̖ʑO�Ɍ��������Ă邱�Ƃ́A�}���V�����̏Z�l�ɂƂ��Ă��A�̌��E���]�Ȃǂ̖ʂ���D�܂����Ȃ��B���̂悤�ȏꍇ�A�}���V�������͓̂y�n�ɑ��ėe�ϗ���t�Ɍ����Ă���킯�ł��Ȃ��̂ɑ��̌��������Ă��Ȃ��A�ŗL�����p�Ƃ͒�������ԂɂȂ��Ă��܂��B
1.1.4���ĕt���n
���ĕt���n�Ƃ́A���Ɍ����������Ă���y�n�ł���B
�s���Y�̍L���Ȃǂ�����ƁA�X�n�̒l�i�Ɠy�n�t�����ÏZ��̒l�i�����܂���Ȃ����ƂɋC�t�����Ǝv���B���́A�s���Y�ɐ�߂�Z��̒l�i�́A���ɒႭ�A�ꍇ�ɂ���Ă̓}�C�i�X�ɂȂ��Ă��܂��B���{�ł͏Z��̑ϗp�N���͓�\���N�Ƃ����Ă���A���Ăɔ�ׂ�Ɣ��ɒZ���A���ÏZ��̃}�[�P�b�g��������Ƒ��݂��Ă��Ȃ��B�]���āA�Z��̔��ɂ����āA���ĕt���n����������Z��͎��Č��Ă����邱�Ƃ��O��ɂȂ��Ă���A�y�n�Ɍ����Ă��錚���͒P�Ȃ�e��S�~�̈������Ă���B���݂ł͔p���������̑���K�����������A�Z���������Ƃ������[�g�Ŕp�i��������ƁA���ʂ̉Ɖ��������ꍇ�ł����S���~�����邱�Ƃ��������Ȃ��B�]���āA���ĕt���n�̉��i�́A�Z��̂͐V�����Ă��A�ǂ��]�������Ȃ��Ȃ�B�������ĕt���n�ł��A�ؒn�������Ă���ꍇ�A���͂���ɕ��G�ɂȂ�B����ɂ��Ă͕ʍ��ŏڂ����G���B
1.1.5
�n�グ
�o�u�����O��̒n�グ�ɂ܂��s�K�ȏo�������_�@�Ƃ��āA�n�グ�ɂ͈����C���[�W���t���܂Ƃ��Ă���B�{���̒n�グ�Ƃ́A���݉�X�������Ă���C���[�W�Ƃ͈قȂ�A�ނ���y�n�ɕt�����l�������炷�J���s�ׂȂ̂ł���B
�}7�̂悤�ɁA���ƒn�ł���Ȃ���2�K���Ă̏��X��������ׂ��悪�������Ƃ���B�\�̓��H��12���[�g�����邪�A���ʂ�̓�����4���[�g���ł���Ƃ���B
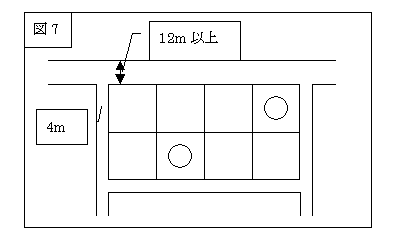
���ƒn��ɂ�����e�ϗ��̏����10����100�i�ȒP�Ɍ����A�~�n�ڈ�t��10�K���Ẵr�������Ă���j�ł���B�������A�O�ʓ��H�̕�����12���[�g�������̏ꍇ�ɂ́A�O�ʓ��H�̕�����10����6���悶�����́A�܂��͎w��e�ϗ��̂������������̂��K�p�����B�]���āA��L�̗�ł͗��ʂ݂̂ɖʂ���4���̗e�ϗ���10����24�ɐ��������B�܂�A���ʂ�ɖʂ������ɂ�2�K���Ă̌����������Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B
�Ƃ��낪�A�}7�̓y�n���ꊇ���Ēn�グ���āA�ЂƂ̓y�n�Ƃ��ăr�������݂���ꍇ�ɂ́A���S����12���[�g���ȏ�̑O�ʓ��H�ɖʂ��邱�ƂɂȂ�B�]���āA�S���̏��10�K���Ẵr�������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�}7�̈���̖ʐς�200�������[�g���Ƃ���ƁA�n�グ�O��8��捇�킹��9,920�������[�g���i
![]() �j�̏��ʐς������������Ă��邱�ƂɂȂ邪�A�n�グ���16,000�������[�g���i
�j�̏��ʐς������������Ă��邱�ƂɂȂ邪�A�n�グ���16,000�������[�g���i
![]() �j�̏��ʐς�����̃r�������Ă���B�������̃r������݂���Ƃ���A���ʐς̑����͒��ݎ����̑�����Ӗ�����B�������A�����t���A�[����̏��ʐς��L���A�㎿�ȃr�������Ă���B
�j�̏��ʐς�����̃r�������Ă���B�������̃r������݂���Ƃ���A���ʐς̑����͒��ݎ����̑�����Ӗ�����B�������A�����t���A�[����̏��ʐς��L���A�㎿�ȃr�������Ă���B
�n�グ�O�͗��ʂ�ɖʂ���2�K���Ă̌����������Ă��Ȃ������y�n��10�K���Ẵr�������Ă���悤�ɂȂ�B5�{�̎��v��O��Ƃ���A�y�n������ꍇ�ɂ��A�\�ʂ�ɖʂ��Ă��Ȃ���Ԃł͍l�����Ȃ����z����邱�Ƃ��\�ɂȂ�B���ꂪ�n�グ�̂��炭��ł���B
�������n�グ�ɂ����X�N�͂���A�Ⴆ�Ώ�L�}7�̗�ŁA����̕t�������̒n�グ���Ɏ��s�����Ƃ���B���̏ꍇ�A�Ⴆ���ʂ�ɖʂ����y�n�̗e�ϗ��A�b�v�ɐ��������Ƃ��Ă��A�����̃t���A�[�����тȌ`�ɂȂ��Ă��܂��B���ۂɂ��̂悤�ȗ�����邪�A���̏ꍇ�ɂ͒P�ʏ��ʐϓ���̒������ቺ������A���ݏ�̐�������L�����ʐς������Ȃ�����i�ǂ������Ȃ�j�A�L���t���A�[���ꊇ���Ē��݂ł��Ȃ��Ȃǂ̕��Q���o�Ă���B�܂��A�t�Ɂ���̕t������悵���n�グ�ł��Ȃ������ꍇ�ɂ́A�r�����̂��̂����Ă��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
���s��͂Ƃ������Ƃ��āA�n�グ�O�̓y�n�P���ƒn�グ��̓y�n�P���ɂ͑啝�ȍ����o��͓̂��R�ł��낤�B�ʑ�n�̍��ł͍L���y�n����抄�肷�邱�Ƃɂ���ēy�n�P����������Ə��������A���ƒn�Ȃǂł͓y�n�����邱�Ƃɂ���ĕt�����l�����߂邱�Ƃ��ł���̂ł���B
1.2���z��@
���ɁA�y�n�̒l�i�ɉe����^����v���Ƃ��āA�s���Y�ƌ��z��@�̊W�ɂ��Ď��グ��B
���z��@�ƌ����Ă��A���͈͍̔͂L���A�W�c�K��Ƃ����ēs�s�v������ł̂ݓK�p�������̂ƁA�P�̋K��Ƃ����ē��{�S���̌����ɂ��ēK�p�������̂�����B�����ł́A�W�c�K��̒�����A��\�I�Ȃ��̂Ƃ��Đړ��`�������グ��B
1.2.1�ړ��`���̊�{
���z��@�ł́A�s�s�v������ɂ����Ă͌����̕~�n�͐}8�̂悤�ɓ��H�ɂQ���[�g���ȏ�ڂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƋK�肳��Ă���B�t�ɂ����A���H�ɂQ���[�g���ȏ�ڂ��Ă��Ȃ��y�n�ɂ͌��������ĂĂ͂����Ȃ����ƂɂȂ�B�Ƃ���ŁA�S���[�g�����̓��H�Ƃ͋�̓I�ɂ͂ǂꂭ�炢�̍L���ł��낤���B���{�̎Ԃ̑�\�Ƃ��ă^�N�V�[�����グ�邪�A�w�ǂ̒��^�^�N�V�[�i�N���E���Ƃ��Z�h���b�N�N���X�j�͕���1.7���[�g���ł���B�S���[�g���̓��H�Ƃ����A���肬��^�N�V�[���Q�䂷��Ⴆ��L���ɂȂ�B
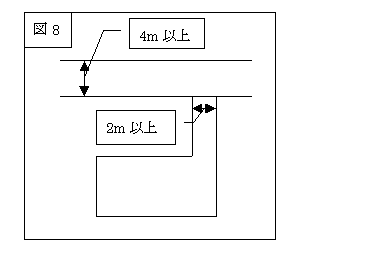
�܂��A2���[�g���̓�����́A���肬��Ԃ�1������i�h�A�͊J���Ȃ���������Ȃ����j�L���ɂȂ�B���͂��̋K��͐�Ў��ɏ��h�����Ԃ������ł����A��Q���L���������Ƃ��琧�肳�ꂽ�o�܂�����B�Ƃ���ŁA�����ɏZ��ł�������́A����̎�����v���o���Ă݂Ă������������B�Ԃ�����Ⴆ�Ȃ����H�Ȃǂ���ɑ��݂��邱�ƂɎv��������ł��낤�B�܂��A������ƒ��Ӑ[����������Ă݂�A���H����ׂ��ׂ��ʘH������Ă����Ƃ��ĊO�ȒP�Ɍ�����Ǝv���B����炷�ׂĂ����z��@�ᔽ�Ȃ̂��낤���B
1.2.2
4���[�g�����H
�y�n�͂��ׂ�4���[�g���ȏ�̓��H�ɐڂ��Ă��Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƋK�肳��Ă��邪�A��L�̂悤�ɁA4���[�g�������̋������H�ȂǁA�����ɂ͂���ɑ��݂���B�����ŁA����4���[�g�������̓��ł����Ă��A���z��@�̏W�c�K�肪�K�p�����Ɏ������ہA���ɑ��݂��A���łɌ��z������������ł�����̂̂����A����s�����̎w�肪������̂́A���z��@��̓��H�Ƃ݂Ȃ����A�Ƃ����K��i���z��@42��2���j�����ꂽ�B����ŋ������H�ɐڂ��Ă��錚���ɂ��Ă��@�I�ȗ��Â����ł����킯�ł���B
�������A�ړ��`���́A�����̐����̈��S�������コ���邽�߂ɐݒ肳�ꂽ���̂ł���A4���[�g�������̓��H�͂ł��邾�������L����������ō��Ȃ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����ŁA���̂悤�ȓy�n�͏����̓��H�g���ɔ����ēy�n�̈ꕔ�����H�Ƃ݂Ȃ���āA�������Ă�����Ƃ��͓��H�Ƃ݂Ȃ���镔���i�Z�b�g�o�b�N�j�Ɍ��z���ł��Ȃ��Ȃ�i�}9�Q�Ɓj�B��̓I�ɂ́A���H�̒��S�����琅�������Q���[�g����ނ������i����ɂ����␅�H�����藼���ɂƂ�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����␅�H�Ɠ��H�Ƃ̋��E�����瓹�H���ɐ�������4���[�g���Ƃ������j�����H�Ƃ̋��E���Ƃ݂Ȃ���A���̋��E���������ɂ͌����Ƃ��Č��z�������z������A�~�n�����邽�߂̗i�ǂ����������肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��ƋK�肳��Ă���B
������Z�b�g�o�b�N�Ƃ����B�s���Y�̍L�����ŁA�v�Z�b�g�o�b�N�Ƃ����Ɍ����������Ă���ꍇ�ɂ̓Z�b�g�o�b�N�܂ނȂǂƏ����Ă�����̂�����ɂ�����B�V���Ȃǂ̐܂荞�ݍL���ł͂��̋K��Ɉᔽ����悤�ȕ����͂܂��Ȃ��̂ŁA�Z�b�g�o�b�N�̋L�ژR����܂��Ȃ��Ǝv���Ă��������Ȃ��i�s���i�i�ދy�ѕs���\���h�~�@�̋K���ΏۂɂȂ�B�ᔽ�����ꍇ�ɂ͑�Ɩ@�ᔽ�ƂȂ�A�Ɩ���~�A�Ƌ�������̑ΏۂƂȂ�j�B
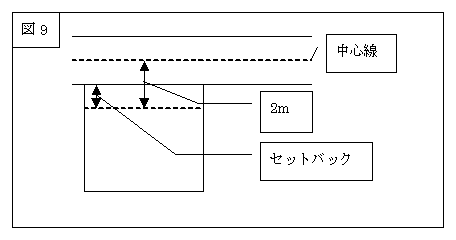
�������́A���ۂɂ͂��̂悤�ȓy�n�͂��������ɑ��݂��邱�Ƃł���B�܂��A���ۂɌ����������Ă��镨���̏ꍇ�A�Č��z�̍ۂɂ̓Z�b�g�o�b�N���K�v�ł��Ƃ����Ă��A��ʂ̕��ɂ̓s���Ƃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�����������ɏ����Ƃ𗧂đւ��悤�Ƃ����ꍇ�A�y�n�ʐς��s�����āA�v�����悤�Ȍ��������Ă��Ȃ��A�Ƃ������ԂɂȂ��Ă��܂�ʂ悤���ӂ��K�v�ł���B�܂��A�Z�b�g�o�b�N���܂ޓy�n�́A���̕��l�i�������Ȃ�B��ʓI�ɓ��H�͒l�i���Ȃ����́i�]���z�[���j�ƕ]�������̂ŁA�L���̊��Ɉ����y�n���Ɗ��Ⴂ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
1.2.3
�ړ��`���ᔽ�̓y�n
�}9�̂悤�ɁA�s�s�v������̌����̕~�n�͓��H��2���[�g���ȏ�ڂ��Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A������Ȃ��ʘH�œ��H�Ɛڂ��Ă���y�n��������������B�܂��A�߂���n�A�ӂ���n�ƌĂ�閳���H�n�����݂���B���������X�ƌ����������Ă���ꍇ������B���z��@�����O�K��͂����āA���̕~�n�̎��͂ɍL���n��L���錚�z���ȂǁA����s��������ʏ�A���S��A�h�Ώエ��щq����x�Ⴊ�Ȃ��ƔF�߂Č��z�R����̓��ӂċ������ꍇ�ɂ́A��O�I�ɐړ��`���ɏ]��Ȃ��Ă��悢���̂Ƃ���Ă���i���z��@43��1���A�������j�B�������A����ȓy�n�͗�O���̗�O�ł��낤�B�ł́A�ړ��`���ᔽ�̓y�n�͂ǂ̂悤�ȕ]������̂��낤���B
�ړ��`���ᔽ�̓y�n�E����������ɏo���ꂽ�ꍇ�͌����ɂ��čČ��z�s�Ƃ̒A������������̂����ʂł���B�y�n�E�����̔����ɑ��Ă͑�Ɩ@��s���i�i�ދy�ѕs���\���h�~�@���̑����Ȃ苭���K�����������Ă���A���ɑ�s�s�̏Z��n�ɂ��Ă͐ړ��`���ᔽ���������ɔ̔����鎖�͂قƂ�Ǎl�����Ȃ��B�]���āA�ړ��`���ᔽ�̈Ӗ����[���킩���Ă��̓y�n���w������Ȃ�A��ϊ����ȓy�n�����Ƃ��ł���B����ȓy�n�̐������̒l�i���t���Ă���͂��ł���B
1.2.4 �ړ��`�����̑��̖��
�ʑ�n�̍��ł�����������n�̕����ɂ��čēx�G���B���̂悤�ȓy�n�����́A���Ƃ��ƍL������̓y�n���Z��݂ɂӂ��킵���傫���ɕ�������ꍇ�ɂ悭�Ƃ����i�ł��邱�Ƃ͑O�q�̒ʂ�ł���B
��n�����ĕ�������ꍇ�ɂ͕K���v���̎肪����̂ŁA�i��n�̕s���葽���ւ̕����͑�n�����������ƖƋ����K�v�j�ړ��`����������͂��Ȃ��ł��낤���A�̂Ȃ���̒n�傳���������Ăđ݂��Ă���ꍇ�Ȃǂɖ�肪�N���₷���B����y�n�S�̂���l�̏��L�ɌW����̂ł���A�S�̂Ƃ��Đړ��`���A�e�ϗ��A���������ɖ�肪�Ȃ���Ό��z���͉����B
�悭���ɂȂ�̂́A�}10�ɂ���悤�ɁA���̋n�ɃA�p�[�g�����Ă��ꍇ�Ȃǂł���B���̃A�p�[�g�ɍs���ɂ͕ꉮ�̌����̋����ʘH��ʂ��ďo���肷��ȂǂƂ����P�[�X�͌��\����Ǝv���邪�A�ړ��`�������Ă���Ƃ͓���l�����Ȃ��B���Ă������͖��Ȃ����낤���A�����������N���ēy�n�̕������g�p�Ƃ���ꍇ�ɁA���ɂȂ�B
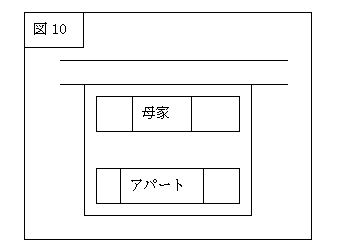
�ړ��`���������߂ɂ͕ꉮ�̈ꕔ�����ēy�n�M���Ȃ��ƌ�둤�̃A�p�[�g�̕~�n�͖����H�n�ɂȂ��Ă��܂��B�m���ɖ��@��͂��̂悤�ɓy�n�̕����ɂ���Ė����H�n�����������ꍇ�A�ʍs���������H�n�̏��L�҂ɔ�������ƋK�肳��Ă���B���̏ꍇ�ł��A�ʍs�����m�ۂ��ꂽ�����ŁA�����I�ȍČ��z���ł��Ȃ��A�]���ď������i���Ⴍ�Ȃ�ȂǁA�����H�n�̖��̖{���I�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�܂��āA�ꉮ���؉ƂŎ؉Ɛl���Z��ł���ꍇ�A�؉Ɛl�ɂ͋��Z������������̂ŁA�����e�Ղł͂Ȃ��A���͈�i�ƕ��G�ɂȂ��Ă��܂��B�]���āA�������̖����l����ƁA�ŏ����珫���̋�抄�Ȃǂ��l���ēy�n�̗��p�@�����߂Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ��킩��B
1.3
�y�n�̒l�i�Ɋւ���܂Ƃ�
��L�ݗ�͎�Ƃ��Čl���Z������݂���ꍇ��O���ɂ����ĉ���������̂ł���̂ŁA�K�������s���Y�،���s���Y�M�����ΏۂƂ��Ă���I�t�B�X�r���Ȃǂɓ��Ă͂܂�킯�ł͂Ȃ��B�������A����s���Y�،�����ʉ�����ɏ]���āA�r�����݂̂��߂ɏ����̒��ݎ������،�������i�]���ď،��̕�W���_�Ńr���͑��݂��Ȃ��j�Ƃ������P�[�X���o�Ă�����̂Ǝv���B��q���邪�A���{�ɂ�����s���Y�،����ɔ����f���[�E�f�B���W�F���X�͊m�����Ă���Ƃ͌�����B����ł́A�����Ǝ��g���s���Y�ɐ��ʂ�����ق��ɓ����̈��S�����m���߂邷�ׂ͂Ȃ��̂ł���B
�s���Y�͒l�i�������A�ϗp�N�����������Y�ł���B�܂��A�s���Y�͋ɂ߂Č��������A���ɍ��ׂȂ��Ƃő傫�����i���قȂ��Ă���B��������Ƃ��ɂ͉��������Ǝv����悤�Ȗ����܂ŏ\���C��z��K�v������B�s���Y�ɂ��������������ꍇ�́A�����Č������i�Ȃǂ��L�ۂ݂ɂ��Ȃ��ŁA�K�����ۂɓy�n�̌����ɏo�����邱�Ƃ��K�v�ł���B�Ⴆ�،�������Ă��镨���ł����Ă��A����̋�_�ŕs���Y�Ɋւ�邱�Ƃ������Ɋ댯�ł��邩�́A�ȏ�̗Ⴉ���������Ǝv���B
2.
�y�n�̗��p�@
2.1
���L
���L�Ƃ͂ЂƂ̂��̂𐔐l�ŏ��L���Ă����Ԃ������B�����ł͕s���Y�̋��L�Ƃ���ɔ������_�����グ��B�܂��A���L�͋敪���L�i��̓I�ɂ̓}���V�����̏��L�`�ԁj�̊�b�ɂȂ��Ă���T�O�Ȃ̂ŁA�敪���L�𗝉������Ō������Ȃ��T�O�ł���B
�敪���L�@�i�������́u�����敪���L���Ɋւ���@���v�j�Ƃ́A�ʖ��}���V�����@�ƌĂ�A�}���V�����u�[����w�i�ɏ��a59�N�ɉ����A�{�s���ꂽ�B�������A�W�H��k�Ќ�A�_�˂̃}���V�����̌��đւ����O���ɏ��Ȃ��悤�ɁA�}���V�����ɂ��F�X�Ȗ�肪�w�E����n�߂��B�}���V��������N�����o���A�}���V�����̘V���������ɂȂ�̂��A���������Ƃ͌����Ȃ��Ȃ��Ă���B���̒n��ł����đւ���肪�Љ���ɂȂ�̂́A���Ԃ̖��Ƃ����悤�B
�s���Y�̋��L�`�Ԃ́A�]��������Ƃ���Ă����B���ꂾ���ł͂Ȃ��A����ؒn���̑n�݂ɔ����V�����s���Y���L�`�Ԃ�A�،����ɔ������L���̕ώ��Ȃǂ���A�s���Y�̏��L�`�Ԃ����G�ɂȂ邱�Ƃ��\�z�����B�s���Y�̏��L����������ȉ��Ō�������B
2.1.1
���@��̋��L�̒�`
�s���Y�Ɋւ�鋤�L���ɓ���O�ɁA���@�ɋK�肷�鋤�L�̊T�O���Љ��B
��Ƃ��āA�ʑ���ABC3�l�ŋ��L���Ă���Ƃ���B���@�ł́A���Ɏ����Ɋւ����茈�߂����Ă��Ȃ��ꍇ�́A�����͕����Ɛ��肷��i���@��250���j�B�]���āA���̏ꍇ�͊e�l�̎�����3����1�ƂȂ�B
�ʑ��̋��L��ԂƂ́A�q���̐w���Q�[���̂悤�Ɍ�����y�n�ɐ���������3����1���g���킯�ł͂Ȃ��B�e�l���ʑ��S���ɂ��Ďg�����Ƃ��ł���Ɩ��@�͋K�肵�Ă���i���@��249���j�B�����A�e�l�̎����ɉ����Ďg������x���قȂ��Ă���B���̏ꍇ�͕����Ƃ������ƂɂȂ�B
�܂��A���L�҂̂P�l�������l�Ȃ����Ď��S���A���ʉ��̎҂ɑ�����Y���^���Ȃ���Ȃ��ꍇ�A�܂��́A���L�҂̂P�l����������������ꍇ�ɂ́A���̎����͑��̋��L�҂ɋA�����邱�ƂɂȂ�i���@��255���j�B
�e���L�҂͊e���̎��������R�ɏ������邱�Ƃ��ł�B�܂��A���L��Ԃ�E���邽�߁A���ł��i������5�N���z���Ȃ��͈͂ŋ��L�������Ȃ�����͉\�j���L���̕����𑼂̋��L�҂ɐ����ł���B�܂��A�����ҊԂŋ��c���܂Ƃ܂�Ȃ��ꍇ�ɂ͍ٔ����ɕ����̐������ł��邱�ƂɂȂ��Ă���(���@��256��)�B
�e���L�҂�1�l�ŁA���L���̕ۑ��s�ׂ��ł���B�ۑ��s�ׂƂ́A���L���̌�����ێ�����s�ׂŁA�Ⴆ�Εʑ��̒ʏ�̈ێ��Ǘ��ɕK�v�Ȏ����Ȃǂ�����ɓ�����i���@��252��A���j�B
�e���L�҂̎����̉ߔ����̎^���ĊǗ��s�ׂ��s�����Ƃ��ł���i���@��252���j�B��L�ʑ��̗�ł�2�l�̎^�����K�v�ƂȂ�B�Ǘ��s�ׂƂ͕ۑ��s�ׂ��ċ��L���𗘗p�E���ǂ���s�ׂŁA��O�҂ɑ���ʑ��̒��ݎ̌_������������A���������肷��s�ׂ�������B����ʓI�ȍs�ׂƂ��ẮA�ʑ��̗��p�҂����߂邱�Ƃ��܂܂��B
���L�҂̑S���̓��ӂ��K�v�ɂȂ�̂��ύX�s�ׂł���i���@��251���j�B�ύX�s�ׂƂ͋��L���̌`����ɕύX��������s�ׂ������A��̓I�ɂ͕ʑ����O�҂ɔ��p������A�ʑ����̂̌��đւ����肷��ꍇ��������B
2.1.2�s���Y�̋��L
���@�ɋK�肳��鋤�L�̊T���͏�L�̂Ƃ���ł���B�ꌩ���Ȃ�ׂ����K�肳��Ă���悤�ł��邪�A�c�O�Ȃ���u���L�͕����̕�v�Ƃ܂Ō�����قǖ��Ȗ��������N�����Ƃ����Ă���B
��L��̂`�a�b�𒇂̗ǂ��Z��Ƃł����悤�B���ہA���L�W�ɓ����Ă��܂��̂͋��L�҂����e�W�̏ꍇ�������悤�ł���B�ŏ��̂�����3�l�Œ��ǂ��ʑ����g���Ă����Ƃ���B
�Ƃ��낪�A�L�菟���Ȃ��Ƃ����A�ʑ��̎g�������߂����đ������������Ƃ���B�Ⴆ�AAB���������Ă��݂��ɓ���ւ��ɏI�����g�����Ƃɂ���C��r�����Ă��܂����Ƃ���BC�͕s���ł��邪�A�Ǘ��s�ׂ͊e���L�҂̎����̉ߔ������^������Ζ@�I�ɂ͗L���Ɍ��肳��Ă��܂��B
�s����C�͎������Ă��܂����Ƃ���B�����̏����͖@�I�ɂ��e���L�҂̎��R�ł���B�������A���L��Ԃ̓y�n�E�����p���悤�Ƃ��Ă��A���͔����肪���Ȃ��B����́A�l�i�̖��ł͂Ȃ��A���L��Ԃ̕s���Y�ɂ͂قƂ�ǎs�ꉿ�l���Ȃ�����ł���B�܂��A�ʑ��S�̂��������悤�ɂ��A�ύX�s�ׂɂ͑S���̎^�����K�v�ƂȂ邪�A�����Ȃ��Ƃ͖��炩�ł���B
�����ŁAC�͋��L���̕����𐿋�����B�������A��������͕̂ʑ��ł���B1���̕ʑ����ǂ������3��������̂ł��낤���B�y�n�ɂ��Ă��A�[���ȍL��������Ƃ������A��ʓI�ȓy�n�ł͖����ɕ�������ƕ��p��n�`�A�ړ��̊W����s���������܂ꂪ���ł���B
�����������Ă��邤����C���S���Ȃ����Ƃ���BC�ɂ�c1��c2�Ƃ����q���������Ƃ���BC�̎�����c1��c2�ɑ�������邱�ƂɂȂ�BAB�̌�����a1�Ca2�Cb1�Cb2�Ƃ����q���B�ɑ������ꂽ�Ƃ���B
�����Ȃ�ƁA���L�҂�6�l�ɂȂ�A�e�l�̎�����6����1���ɂȂ�B�オ�ւ��A�ʑ������ŏ��̂�������������Ȃ��Ȃ�ł��낤���A�e���L�҂̊W���a���ɂȂ�B�e���L�҂������ł�����A�@����̋��L�҂̐��͕ς��Ȃ��Ƃ͂����A���Q�������Ă���l�Ԃ̐����ꋓ�ɑ�����̂ŁA���łɏ[�����G�ɂȂ��Ă������Q�W���D����ԂɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�Ȏ��Ԃɂ�����ň����Ȑl�Ԃ����L�҂̈�l�ɂȂ�Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B������ABC�̈ꑰ�Y�}���S������ł��܂��A�ʑ���1�l�̂��̂ɂȂ�̂ł��邩��B���̂悤�Ȏ��Ԃ͋ɒ[�Ƃ��Ă��A����o�邲�Ƃɋ��L�҂������Ă��܂��������ɂ͕s���Y�Ǝ҂�����o���Ȃ��B���ہA�c�ɂ̓y�n�Ȃǂŋ��L��Ԃ̂܂��L��������X�ړ]���Ă���Ⴊ����B�܂Ƃ��Ȏs�ꉿ�l�̓[���ł��낤�B
��L�̗�ł́A���L�҂͌Z��ł��������A���Ƃ��e�F�Ƃ����ǂ����b�g�⎩���ԂƂ��������Y�͂Ƃ������A�s���Y�����L�����͑����Ȃ��悤�ł���B��͂���{�l�ɂ͕s���Y�M������̂ł��낤���B�������A�Z���e�q�Ԃł́A�ӊO�ƈ��Ղɋ��L�W�ɓ����Ă��܂��Ⴊ�����B
�y�n�Ɖ���v�w�ŋ��L�ɂ���̂͗ǂ������ł��邪�A���̏ꍇ�͂���قǖ��Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�v�w���L����������ꍇ�͗������قƂ�ǂł��낤���A���̏ꍇ�͗��Q�W�l���Q�l�������Ȃ����A���Y���^�̈�Ƃ��Ę_������̂ŁA���̂܂܋��L��Ԃ������ȂǂƂ������Ƃ͍l�����Ȃ��B
�܂��A���e�Ƃ����Ă��e�q�ŋ��L�W�ɓ���ꍇ�����͏��Ȃ��Ƃ�����B�ʏ�e�̎��S����ɂȂ�B���̏ꍇ�A�����l����q���e�̎����𑊑����ĒP�L��ԂɂȂ�̂ŁA���͎����I�ɉ��������i���S�̏������t�ł��P�L��ԂɂȂ�͓̂����j�B
���͌Z��ł���B��L�ʑ��̏ꍇ�͈ӎ��I�ɋ��L��Ԃɓ����Ă��܂����킯�ł��邩�玩�Ǝ����Ƃ������邪�A�ӊO�ɑ����̂����������������ɋ��L��Ԃɓ����Ă��܂��ꍇ�ł���B���@��́A�������Y�͍��Y�������c�������܂ł͑����l�̋��L��ԂɂȂ�Ƃ���Ă���i���@��898���j�B����͕ʂɖ��@�����L��ԂɂȂ�悤�Ɏw�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A���L�҂̂͂����肵�Ȃ����Ԃ�������ׂ��K�肳��Ă���B�Ƃ��낪�A������z�ʂǂ������āA�������c������Ȃ������ɑ��X�ɓy�n�������L�̓o�L�����Ă��܂��i��Y�������c����������ɒP�L�̓o�L�ɍX������̂́A�葱����͊ȒP�ł���j�A��Y�����ł��߂Ă��邤���ɑ����ł̐\�����������Ă��܂��A���Nj��L��Ԃ͂��̂܂܂ɂȂ��Ă��܂��A�Ƃ������ꍇ������B���ۂɂ͋��L��ԂŐ\�����Ă����ΏC���\���͉\�ł��邪�A�������ł��߂Ă���ꍇ�ɂ͂Ȃ��Ȃ����ӂ��������Ȃ��B�����Ď��Ԃ����Ă��قǖ��͂����ꂵ�܂��̂ł���B
2.1.3���L���܂Ƃ�
�ŗǂ̃A�h�o�C�X�́A�ŏ����狤�L��Ԃɓ���Ȃ��悤�ɂ���Ƃ��������悤���Ȃ��B���Y���c���e�Ƃ��ẮA���炩���ߕ������@���l���āA�q���B�����L���ŋꂵ�߂Ȃ��悤�ɂ��炩���߃v�����j���O���Ă������Ƃ��K�v�ł��낤�B
2.2�敪���L�@
�u�����̋敪���L���Ɋւ���@���v�i�ȉ��u�敪���L�@�v�Ƃ����j����i���a37�N�j�ȑO�̓}���V�����Ȃǂ̌����W�͖��@�̋��L�T�O�����߂��邱�ƂŌ��肳��Ă����B�Ƃ��낪�}���V�����̏ꍇ�A1�l�ʼn������������Ă�����A�����ɂ��L����������������Ƌ敪���L�҂̐��Ǝ����i�e�敪���L�҂����L�����L�����̏��ʐς̊����B�敪���L�@�ł͋c�����Ƃ����j�̊���������Ă��邱�Ƃ�����ȂǁA���܂��܂Ȗ�肪���������B�����ŋ��������̃��[���Ƃ��ċ敪���L�@�����肳�ꂽ�B
�敪���L�@�͑�܂��ɁA������~�n�ȂǕ��Ɋւ��郋�[���ƏZ���̎����Ɋւ��郋�[���̂Q�̕������琬�藧���Ă���B�����ł͋敪���L�@�̊T�v�ɂ��ĉӏ������ŊȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă����B
·
�}���V�����͋��L�����Ɛ�L�����ɕ������B�L����G���x�[�^�[�Ƃ������@�苤�L�����ƃ}���V�����̈ꎺ���W���Ǘ��l���ɂ���K�L����������B�i�敪���L�@4���j
·
�ۑ��s�ׂ͊e�敪���L�҂��P�ƂŎ��R�ɍs�����Ƃ��ł���B�i�敪���L�@18���j
·
�Ǘ��s�ׂ͋敪���L�ҋy�ыc�����̉ߔ����̎^�����K�v�ł���B�i�敪���L�@18���A39���j
·
�ύX�s�ׁi���������z�̔�p��v���Ȃ��ύX�s�ׁj�͋敪���L�ҋy�ыc�����̉ߔ����̎^�����K�v�B(�敪���L�@17���A39��)
·
�ύX�s�ׁi���������z�̔�p��v����ύX�s�ׁj�͋敪���L�ҋy�ыc�����̊e4����3�ȏ�̎^�����K�v�i�y����������j�B(�敪���L�@17��)
·
�e�敪���L�҂͂��̗L�����L�����̏��ʐς̊����ɉ����ĕ~�n���p���̋��L������L����B�i�敪���L�@22���j
·
�����Ƃ��Đ�L�����ƕ~�n���p�������ď������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�i�敪���L�@22���j
·
�Ǘ��͑S���Q���̒c�̂Ƃ��ē��R�ɐ�������Ǘ��g���ɂ���ĂȂ����B�i�敪���L�@3���j
·
�Ǘ��g���͈��̏��������Ζ@�l�i����B�i�敪���L�@47���j
·
�敪���L�҂܂��͊Ǘ��g���@�l�͈��̎葱�����o�邱�Ƃɂ���āA���Y�敪���L�҂ɑ��čs�ׂ̒�~�A�g�p�֎~�A�敪���L���̋����𐿋��ł���B�敪���L�����̐�L�҂ɑ��Ă��s�ׂ̒�~�A�����̈��n���𐿋��ł���B�i�敪���L�@57���A58���A59���A60���j
·
�����̉��i��2����1�ȉ��ɑ������镔�����Ŏ������ꍇ�A�W��̋敪���L�ҋy�ыc�����̉ߔ����̂�錈�c�ŕ����v����߂�܂ł͊e�敪���L�҂������ł���B�i�敪���L�@61���j
·
�����̉��i��2����1���z���镔�����Ŏ������ꍇ�͋敪���L�ҋy�ыc�����̊e4����3�ȏ�̎^���ŕ����̌��c���s���B�������l�͂��̏��L����敪���L���y�ѕ~�n���p���������Ŕ�����邱�Ƃ��^�������敪���L�҂ɐ����ł���B�i�敪���L�@61���j
·
�����̘V���A�����A�ꕔ�Ŏ����̂��߁A���̌��p���ێ������͉���̂ɉߕ��̔�p��������ꍇ�͋敪���L�ҋy�ыc�����̊e5����4�ȏ�̎^���Ō��đւ��̌��c���s�����Ƃ��ł���B���̋敪���L�҂ɑ��ẮA�^���̋敪���L�҂Ȃǂ�����n���𐿋��ł���B�i�敪���L�@62���A63���j
2.1.3�敪���L�@�̖��
�敪���L�@�̊T���͑�̏�L�̂悤�ɂȂ�B���������_���w�E����Ă���A�����ɕ����ɂȂ��Ă���ꍇ������B��ʂ���ƁA
·
���L�����Ɛ�L�����̋�ʁA�~�n���p���̏����ȂǁA���L���Ɋւ����
·
�K��̐���A�Z���ƊǗ��g���̊W�ȂǁA�Ǘ��Ɋւ�����
·
�����̕����A���ւ��Ɋւ�����
��3�_�ɂȂ�B
�����L���̖�聄
��L�����ɂ��Ă͓��R�ɓo�L�ɔ��f����邪�A�L���A�G���x�[�^�[�Ƃ��������R�ɋ��L�����Ƃ���镔���ɂ��Ă͖��m�ɓo�L��ɔ��f����Ȃ��B�܂��A�Ǘ��l���≮�����ԏ�Ƃ������K�L�������A�ʓr�o�L�����Ȃ��Ă͑�O�҂ɑR�ł��Ȃ��B���̋K������p���āA�u���ԏ��g�����N���[���Ȃǂ͖ܘ_�A�s���e�B�[��������A���ԏ��X�܂ɉ������ĕ����Ǝ҂����v���c����������A���R�ɋ��L�����Ɖ������ׂ��L���ł���B�����ɐ�L�����Ƃ��ēo�L�������v�i���{�ٌ�m�A����u�敪���L�ӌ����vp3�j�Ƃ�������܂ł���Ƃ����B
��L�����Ƌ��L�����A�����ċK�L����������ꍇ�͂��̋K�L�����ɂ��Ă���n��������Ɩ@�i�ȉ��u��Ɩ@�v�Ƃ����j��35���ɂ���āA�d�v�����Ƃ��Č_��̐\�����݂���O�ɔ���ɑ��Đ������Ȃ��Ă͂����Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B���ۂɌo�����ꂽ���͕�����Ǝv�����A���̏d�v�����̐����Ƃ������̂͌��\�����A�����I�Ȃ��̂ł���B
��Ɩ@��35���́A�d�v�����̐����͏��ʂ���t������ŁA���C�҂����Đ��������Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƋK�肳��Ă���B�K��ʂ�ɐ������s��ꂽ�ꍇ�A�d�v�����̐����������_�Ŕ��呤�������w�E���Ȃ��ƁA���Ƃ�����Ҍ_��@��K�p�����Ƃ��Ă��A����呤�ɂ͐����`�����ʂ������Ǝ咣����邱�ƂɂȂ�B���ۂɕs���Y���ꍇ�ɂ́A���������������������������炸�ɂ�����ƕ����Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ�������B
���Ǘ��̖�聄
�敪���L�@�͒c�n�`���̒c�n�S�̂��敪���L�҂̋��L�ɂȂ��Ă���`�Ԃ�z�肵�Ă��邪�A���݂ł̓}���V�����̏��L�`�Ԃ��A�X�ܕ��p�^�A��ɓ����̑ΏۂƂ��Ĕ����郏�����[���}���V�����i���ۂ̋��Z�҂͒��ؐl����j�A�s�敪���L�҂���̃��]�[�g�}���V�����Ƒ���ɓn���Ă���B
���Z�҂���������O�ɁA�Ǘ���Ђ�������Ђ̎q��ЂȂǂɌ��܂��Ă���A�ȂǂƂ����̂͗ǂ�����P�[�X�ł���B�Z�����M�S�ŊǗ��g����������ƌ������Č�����Εʂł��낤���A�敪���L�҂������Z��ł��Ȃ��}���V�����Ȃǂł͊Ǘ��g���̌������܂܂Ȃ�Ȃ��ꍇ������悤�ł���B
�܂��A�Ǘ���Ђɂ͕�����ЂƂ͈قȂ�A����̖@�I�K�����Ȃ��i������Ђ͑�Ǝ҂ł��邱�Ƃ��`���Â����Ă���A���̋��z�̋����`���Ȃǂ�����j�B�Ǘ��g������̗a����𒅕�������A�ň��̃P�[�X�ł́A�a����̖��`���Ǘ��g�����`�ɂȂ��Ă��炸�A�Ǘ���Ђ̓|�Y�ƂƂ��ɍ������������Ă��܂����A�ȂǂƂ�������������Ƃ����i���{�ٌ�m�A����u�敪���L�ӌ����vp2�j�B
�Ǘ��Ǝ҂ɑ���@�I�K�����]�܂�邱�Ƃ͂������ł��邪�A���Z�҂͎��ȍ��Y�̎��q�̂��߂ɂ��A����Ǘ��g���̉�ɂ��o�Ȃ���ׂ��ł��낤�B
�������E���đւ��̖�聄
��_�E�W�H��k�Ђʼn�ꂽ�}���V�����ŁA�����⌚�đւ��̌��c�����܂��܂Ƃ܂�Ȃ��P�[�X�����Ȃ葽���ƕ����B�܂��A��ʂ̃}���V�����ł��A���đւ������܂��������̂́A���Ƃ��Ɨe�ϗ��ɗ]�T������A���傫�ȃ}���V�����Ɍ��đւ����A���X�̋敪���L�҂̋��Z�������m�ۂ��������ŁA�c����ł���ȂǁA���Ȃ�b�܂ꂽ�����̂Ƃ���Ɍ����Ă���B1960�N����ґ�Ɍ��Ă�ꂽ�}���V�����͂����m�炸�A���x�������ɗe�ϗ������ς��Ɍ��Ă�ꂽ�}���V�����ȂǁA���������ƂɂȂ肻���ł���B
�܂��A����͏��L���̖��̂Ƃ���ł��G�ꂽ���ł��邪�A�~�n���s���N�Ȍ`���ŕ����O�ɕ��M����Ă��܂����ꍇ�A���Ƃ��Ƃ̕~�n�ɑ��Č������E�e�ϗ������ς��ɗ��Ă��Ă����Ƃ���ƁA���ւ���̌����͓��R���Ƃ̌�����菬�������̂������Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B
2.2�敪���L�@�܂Ƃ�
�}���V�����͓����ϗp�N����60�N���炢�Ƃ������Ă����B�������A���̌�̌o�߂�����ƁA��������30�N���炢�̂悤�ł���B21���I�ɓ���ƁA���x�������Ȍ�ɑe���������ꂽ�}���V���������X�Ƒϗp�N������N�����Ă����Ǝv����B���̍ۂɁA�O�q�̗��ւ����Ȃǂ��傫���N���[�Y�A�b�v����邱�Ƃł��낤�B
�}���V�������ꍇ�ɂ́A���Y�Ƃ��Ăł͂Ȃ��Z�ނ��߂̋@�B�Ɗ�����āA������ƍ��z�̑ϋv������i�Ԃ�①�ɂȂǂł���j������ōw�������ق����ǂ��悤�ł���B�����v���A�Ԃɒ���_�����t�����ł���悤�ɁA�܂��A�C���_���͈����낤�����낤�ȂǂƂ����Ǝ҂ɂ͗��܂Ȃ��悤�ɁA�}���V�����ɂ��A�t�^�[�P�A�Ƃ��̋ƎґI�т��d�v���������ł��邱�Ƃł��낤�B
�܂��A����s���Y�̏،����ɂ���āA�s���Y�̏��L�`�Ԃ��傫���ς���Ă������Ƃ��\�z�����B���ۂɕs���Y�̏��L�����擾���Ȃ��ꍇ�ł��A�،��⊔���̎擾��ʂ��ĊԐړI�ɕs���Y�̉^�c�Ɋւ�邱�ƂɂȂ�B
�s���Y�،��⊔���̎擾��ʂ��ĊԐړI�ɕs���Y�̏��L�ɂ������ꍇ�ł��A���Y���l���ێ����邽�߂ɂ́A���Y�̐����͂������A�����I�ȃ��C���e�i���X���K�v�Ȃ��Ƃ����炩�ł��낤�B
2.3
�s���Y�̒��ݎ�
���ݎ،_��ɂ��ẮA���@�Ɉ�ʓI�ȋK�肪����B�������A�y�n�����̒��ݎ،_��ɂ͎ؒn�؉Ɩ@�Ƃ����@�����ʂɐ݂����Ă���B����́A���@�ɂ�������ݎ��Γ��Ȍl�ԂŌ����_���O���ɂ����Ă���̂ɑ��A�ؒn�؉Ƃł͒��ݐl�i��Ɓj�ƒ��ؐl�i�X�q�j���Γ��ȊW�Ƃ͂����������A���ؐl��ی삷��K�肪�K�v�Ƃ���A���ɐ풆���A�R�l�̈⑰��D�����邽�߂ɐ��肳�ꂽ�Ƃ����Ă���i���ؒn�@�A���؉Ɩ@�A�����ی�@�j�B
���ؒn�@�A���؉Ɩ@�A�����ی�@�����܂�ɂ����ؐl�ɗL�����Ƃ������Ƃŕ��Q���ڗ����Ă����̂ŁA����4�N8��1����苌�ؒn�@�Ȃ�3�@��p�~����ƂƂ��Ɏؒn�؉Ɩ@�ɓ����A�{�s���ꂽ�B����ɁA����11�N12��15���A�u�ǎ��Ȓ��ݏZ��̋����̑��i�Ɋւ�����ʑ[�u�@�v����t�A�ؒn�؉Ɩ@������؉Ƃ�F�߂邩�����ňꕔ��������A����12�N3��1�����{�s���ꂽ�B�������A�ˑR�@�����ς���Ă��܂����̂ł͎ؒn�l�A�؉Ɛl�ɕs���ƂȂ�̂ŁA�V��{�s�ȑO�̌_��ɂ��Ă͐V��{�s��ɍX�V�����ꍇ�ɂ����@�ɂ��X�V����邱�ƂƂ����B�܂��A����؉Ƃɂ��ẮA�V�@�{�s����]���^�̎؉ƌ_������Ԃ��Ƃ��\�ł���B
�V�@�����ƂɐV�����ؒn�_��̌`�Ƃ��Ē���ؒn���A����؉ƌ������܂�A�s���Y����̂ЂƂ̒����ƂȂ����B�����ł͎ؒn���y�ђ���ؒn���̒��ł����Ε����ƈ�ʂɂ����Ă�������ɂ��ĉ������ƂƂ��ɂ��̖��_��o���B�����āA�s���Y�،����̗���ƂƂ��ɐ��肳�ꂽ����؉ƌ��̍���̓W�J��\������B
2.3.1�ؒn��
�ؒn�؉Ɩ@�ł͎ؒn�����A�������L��ړI�Ƃ���n�㌠�܂��͓y�n�̒��،��ł���ƋK�肵�Ă���i�ؒn�؉Ɩ@2���j�B�]���āA�_�n�̏ꍇ�Ȃǂɂ͓K�p����Ȃ����A�X�܂��Z����X�܂��̂��̂Ȃǎ��Ɨp�̌��������L����ꍇ�ɂ��ؒn�؉Ɩ@�͓K�p�����B
�ؒn���͌����̏��L��ړI�Ƃ��Ă���B�����͖ؑ��̂��̂ł����Ă�30�N���x�͏[���ɑ������邵�A���܂�Z�����Ԃ��߂邱�Ƃ͎ؒn�l����ɍX�V����邩�ǂ����s���̕s���ȏ�Ԃɒu�����ƂɂȂ�B�����ŁA�ؒn���̑������Ԃ͍Œ�30�N�Ƃ��A���@�ɂ�������ݎ̍Œ�����20�N�͓K�p����Ȃ����ƂƂ����B
�ؒn�����I�������ꍇ�A�ؒn���҂Ǝؒn���ݒ�ҁi�ؒn�l�ƒn��j�̍��ӂ�������X�V�����i���ӂɂ��X�V�ؒn�؉Ɩ@4���j�B�܂��A�n��̍��ӂ������Ȃ��ꍇ�ł��A���������L����ؒn�l���_��̍X�V�𐿋������ꍇ�́A�����Ƃ��đO�̌_��Ɠ��������ōX�V����邱�Ƃɂ����i�ؒn�؉Ɩ@5���j�B�������A�n�傪��������R�����Ӌ`���������ɏq�ׂ�A�X�V����������ł���i�ؒn�؉Ɩ@5���A6���j�B����ɁA�ؒn�l���ؒn���̍X�V�𐿋����Ȃ��ꍇ�ł��A���Ԗ�������y�n�̎g�p���p�����Ă���A���������݂��Ă���ɂ�������炸�A�n�傪�x�Ȃ��u�������R�v����Ӌ`���q�ׂȂ��ꍇ���ؒn�_�����Ƃ��čX�V���ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ����i�@��X�V�@�ؒn�؉Ɩ@5���j�B�X�V��̊��Ԃ́A�ŏ��̍X�V�ɂ����Ă�20�N�ȏ�A2�x�ڈȍ~�̍X�V�ł�10�N�ȏ�łȂ���Ȃ�Ȃ��ƒ�߂��Ă���i�ؒn�؉Ɩ@9���j�B
�ؒn���̑������Ԃ̖����O�Ɍ������Ŏ����Ă��A�ؒn���͓��R�ɂ͏��ł��Ȃ��B���̏ꍇ�A�ؒn�l���������Ԃ��đ������錚�����Ēz�����Ƃ��́A�n�傪�Ēz�����������ꍇ�Ɍ����āA�ؒn���̊��Ԃ���������邱�ƂƂ����B�����Ƃ��A�ؒn�l����Ēz����|��ʒm���������́A���ꂩ��2�����ȓ��ɒn�傪�ًc���q�ׂȂ���A���̏��������������̂Ƃ݂Ȃ����B�n��̏������������ꍇ�̉������Ԃ͏��������������A�������͌����Ēz�̓��̂����ꂩ����������20�N�ԂɂȂ�܂��i�ؒn�؉Ɩ@7���j�B�n�傪�������Ȃ������ꍇ�͎c�����Ԃ̖����ɔ����ؒn���͏I�����܂��B���̎ؒn���I����ɍX�V���s���邩�ǂ����́A�O�q�̐����ɂ��X�V��@��X�V���s���邩�ǂ����ɂ������Ă���B
���@�ɂ��A�]�݂���،��̏��n�ɂ͒��ݐl�̏������K�v�ł����A�ؒn�؉Ɩ@�ł͈��̏ꍇ�ɂ͍ٔ������ؒn�l�̐\�����Ăɂ��n��̏����ɕς�鋖��^���邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���B�����̓]�݁A�ؒn���̏��n�ɂ͒n��̏����͕K�v�Ȃ����̂Ƃ����i�ؒn�؉Ɩ@19���j�B�����z�𐧌�����ؒn����������ꍇ�ɂ����āA�y�n�̗��p�㑊���ȑ����z�ɂ��ẮA�ٔ����͎ؒn�l�̐\�����Ăɂ��n��̏����ɑ��鋖��^���邱�Ƃ��ł�i�ؒn�؉Ɩ@17���j�B
2.3.2�ؒn�̖��_
�ȏ�̂悤�ɁA���݂̎ؒn�؉Ɩ@�ł��[���Ɏؒn�l�͕ی삳��Ă��邪�A�t�ɒn�呤���猩��A��������y�n��݂��Ă��܂����炢�Ԃ��Ă���邩�s���ł���A�_��̍X�V���������ꍇ�̐������R�ɂ��Ă��A���g�œy�n���g�p����K�v������A��������������A���ނ������x���������Ȃǂ������������𑍍����Ĕ��f�����̂ŁA�ȒP�ɗ����ނ���v�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�܂��A�����ɂ��Ă��A�ؒn�̏ꍇ�A�Œ莑�Y�ł��킸���ɏ�����x�̒ᐅ���Ɍ��߂��Ă���ꍇ�������悤�ł���B���݂̌Œ莑�Y�ł̕W���ŗ���1.4���i�v���X�s�s�v���0.3���j�ł��邪�A���K�͏Z��p�n�̏ꍇ�͉ېŕW����6����1�A��ʏZ��p�n�̏ꍇ�͉ېŕW����3����1�Ɍy�������̂ŁA�����炭�����ŗ���1���ȉ��ł��낤�B�]���Ďؒn�̓����������ǂ���1�����x�Ȃ悤�ł���B�ؒn�̐ݒ莞��X�V���ɑ��z�̐ݒ藿�E�X�V�����x�����鎖��������Ǝv���܂邪�A�����Ƃ��Ă͏[���ȃ��^�[���Ă���Ƃ͂����Ȃ��B
�Q�l�����ɋ������Ă����ł́A���ݗ��́u60��ؓ�����500�~�̒n��Ŏ�Ă���Ɩ����̎��オ3���~�A�N��36���~�v�ł���A�u�Œ莑�Y�ł�20���~�Ƃ���v�ƁA�u6000���~�̓y�n�ɑ��Ď��v��16���~�A����������0.26���v�ɂ����Ȃ�Ȃ��B�u�ؒn��������6���Ƃ��Ă��A��n��6000���~��4����2400���~�A���̋��z����ɂ��Ă�0.66���v�ł���i�q���@���s�w�v����������A�b�Ƌ����s���Y�����@�xpp153-154�j�B�t�ɂ����A�ؒn�̕]���͎��ۂ̎�����i���͂��Ȃ芄���ɂȂ��Ă���Ƃ�������B
�Ⴆ�A�������N�����ꍇ�A���������ؒn�ɂ��ẮA�ؒn������������������]�����K�p����邪�A�i30����90���A�ؒn�������͘H�����}�Ɏ�����Ă���j�A����ł���n�̎s�ꉿ�i�ɔ�ׂ�Ɗ����ȕ]�����邱�ƂɂȂ�B���̑������͋ߔN�s���Y�H�������������Ɉ����グ�����Ƃ����C�ɃN���[�Y�A�b�v���ꂽ�B���́A�ȑO����n�������s�ꉿ�i�ƃ}�b�`���Ă��Ȃ����͂��������̂́A�H�������̂��̂����������̂Ŗ��ɂȂ�Ȃ����������Ȃ̂ł���i�X�c�`�j�w�V�E�{��̘H��������x��138�j�B
2.3.3�ؒn���̉����@
�ؒn���i���ؒn�@�Ɋ�Â����̂��܂ށj�̕t�����y�n�͌��݂ł�������������B�n��̒��ɂ͂Ƃɂ����y�n�������������Ȃ��l������邪�A��L�̂悤�Ɏؒn���o�ϓI�ɂ͂قƂ�Nj@�\���Ă��Ȃ��ȏ�A�ؒn���͐��������ق����]�܂����ŁB�ł́A�ؒn�������̕��@�ɂ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂�����̂��낤���B
�������@�Ƃ��ẮA
1�D
�n�傪�ؒn�������B
2�D
�ؒn�l�ɒ�n������Ă��炤�B
3�D
1��2�̒��ԂƂ��āA�y�n���A��n�Ǝؒn������������B
4�D
���ҋ����ŁA�������͒�n�����ő�O�҂ɔ��p����B
�Ƃ��������@���l������B�������A4�ł������A��n�����p������@�͌o�ϓI�ɂ͂��܂芩�߂��Ȃ��B��n�Ǝ҂Ƃ�����n���������Ǝ҂�����Ƃ����邪�A������艿�i�͍X�n���i��1���ƌ����Ă���i�t�ɂ������ꂵ���o�ϓI���l���Ȃ��j�i�X�c�`�j�w�ԈႢ���炯�̓y�n�]���x��106�j�B���p����̂ł���A�ؒn�l�Ƌ��͂��Ĉ�̂̓y�n�E�����Ƃ��Ĕ��p�̏�����ܔ�����ق����D�܂����ł��낤�B
�������A������̕��@���Ƃ�ɂ��Ă��A�n��Ǝؒn�l�̗��Q�͑Η����Ă���A���͊ȒP�ɂ܂Ƃ܂�Ȃ��̂������ł���B�������A��������X�̖����l����ƁA�S�苭�������d�˂邵���Ȃ��ł��낤�B
2.4����ؒn��
���ʎؒn���ɂ͍X�V�̐��x���F�߂��Ă��邽�߁A�n��ɂƂ��Ă͂ЂƂ��юؒn��F�߂Ă��܂��ƁA���y�n���A���Ă��邩������Ȃ��Ƃ����s��������A�y�n�����̖W���ɂȂ��Ă���Ƃ����ᔻ���������B���̂悤�Ȓn����A�����Ԃ�݂��A�m���Ɏ茳�ɋA���Ă���̂ł���A�y�n�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������҂��琧�肳�ꂽ�B
2.4.1����ؒn���̓��e
��̓I�ɂ́A�����̒���ؒn���i��ʒ���ؒn���j�A�������n����t���ؒn���A���Ɨp�ؒn����3��ނ�����B
�������̒���ؒn����
���ʎؒn���̏ꍇ�A�ؒn�l�ɂ͍X�V���������F�߂��Ă��܂����A��������50�N�ȏ�ɓn�钷���̎ؒn���ݒ�̏ꍇ�ɂ́A�X�V�����Ȃ��Ƃ��������t���邱�Ƃ�F�߂��B���̓���͌����؏��Ȃǂ̏��ʂɂ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƒ�߂��Ă���i�ؒn�؉Ɩ@22���j�B�܂��A�ؒn��̌����̗p�r�͐�������Ă��Ȃ��B
���������n����t���ؒn����
�ؒn���ݒ��30�N�ȏオ�o�߂������ɁA�ؒn��̌�����n��ɑ����̑Ή��ŏ��n��������t���邱�Ƃ�F�߂��i�ؒn�؉Ɩ@23���j�B�Ȃ��A�������n����̌`���́A�����\�������t�����_���l�ł��邽�߁A���̒���ؒn���̂悤�ɏ��ʂɂ�邱�Ƃ͕K�v�Ƃ���Ă��Ȃ��B�n��͌����̓o�L��ɉ��o�L���邱�Ƃɂ�茚��������錠����S�ۂł���B
���L�����ړ]���A�ؒn�������ł��Ă��ؒn�l�������g�p���p�����Ă���ꍇ�ɂ́A�ؒn�l����������Ί��Ԃ̒�߂̂Ȃ��؉ƌ_����������̂Ƃ����i�ؒn�؉Ɩ@23���j�B�܂��A�ؒn��̌����̗p�r�͐�������Ă��Ȃ��B
�����Ɨp�ؒn����
��L����ؒn���͂�����ɂ��Ă������ɂ킽��_��ł���B�����ŁA���Z��ړI�Ƃ��Ȃ�10�N�ȏ�20�N�ȉ��̎��Ɨp�ؒn����F�߂邱�Ƃɂ����B���Ɨp�ؒn���ł́A���Ԗ�����̍X�V�⌚�����搿����F�߂Ă��Ȃ��B���Ɨp�ؒn���̐ݒ�͌����؏��ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂Ƃ���Ă���i�ؒn�؉Ɩ@24���j�B
2.4.2������
����ؒn�������܂����p�����u���Ε����v�ƌĂ��}���V�������ݕ����́A���Ίw���s�s�ɂ��錚�ݏȌ��z���������ŊJ������A���Ύs���ő�P�������Ɖ����ꂽ���Ƃ��疼�Â���ꂽ�B���݁A�S����10�����x�����Ɖ�����Ă���B
���Ε����̊�{�I�ȓ����́A�}���V�������u�X�P���g���v�Ƃ����\�������Ɓu�C���t�B���v�Ƃ����Ԏ�蕔�����錚�z����������Ă��邱�Ƃł���B�܂��A�X�P���g���Ƃ����\���͓̂S�R���N���[�g�Ŋ�{�I�ɂ�100�N�ȏ�̑ϗp�N����z�肵�č���Ă���B�ʏ�̃}���V�����ł́A�\���Ɠ����͈�̐v�ł���̂ŁA�ꕔ���z�͓���A�S�ʓI�ȗ��ւ����K�v�ƂȂ邵�A���100�N���̑ϗp�N���͂Ȃ��B���Ε����ł́A�C���t�B���̕����ɂ��Ă̓��C�t�X�e�[�W�ɍ������������ȒP�Ɏ����ł���悤�ɂȂ��Ă���B�܂��A�Z������������l���W�܂��āA�������ă}���V���������z�A���z�i�K�ŋ��Z�҂̗v�]�����炩���ߎ����ꂽ�Ԏ�����������R�[�|���e�B�u�Z��ƌĂ�����������B
���Ε����ł́A����30�N�Ԃ͎ؒn�_��Ɋ�Â��ؒn�オ�i�����̌������ƂƂ��Ɂj�x������B30�N�o�ߌ�A�X�P���g�����������炩���ߒ�߂�ꂽ���i�i�X�P���g���Č��z���4���j�A�C���t�B���͉��i�[���Œn��ɏ��n����邪�A�Z�l�͈Ȍ�30�N�Ԓ��ؐl�Ƃ��Ĉ����������Z�ł���i���Ε����ł͑S�̂̎ؒn���Ԃ�60�N�Ƃ��Ă���B50�N�ȏ�ł�����Ε����͓K�p�ł���j�B�܂��A���ؐl�ƒn��͏��n���z�Ɖƒ��Ƃ̑��E�_������сA�����I�ɂ͎ؒn���Ԃƕς��ʎؒ��ŋ��Z���Â�����悤�v����Ă���B
�܂��A�n��ɂƂ��Ă�30�N��ɂ͒��ݐl�̂�����ݏZ����ؓ������̑��̎��ȕ��S�Ȃ��Ɏ擾�ł��郁���b�g������B�܂��A�����̌��������ɂ�莩�Ȏؒn��ݒ�A���Ȃ̏Z���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��邵�A���w�K�̃e�i���g���������������Ɋ����Ď擾���邱�Ƃɂ��ƒ������������ނȂǁA���܂��܂ȉ\�����l������B
�ґ�ȃX�P���g�������̌��z���A�������ݑ���̎x�������A����ؒn���̊��p�ɂ���ĉ������邱�ƂŎ������Ă���B����ł͗D�ꂽ�����ł���Ƃ̕]���������悤�ł���B
2.4.3����ؒn���̗��p�Ɩ��_
����5�N�̐���ȗ��̒���ؒn���𗘗p�����Z��̋����͕\1�̂Ƃ���ł���B����9�N�x�̐V�ݏZ��H�ː���1,387,014�ˁi���ݏȕ����X�N�̐V�ݏZ��H�ː��i�T�v�j�j�ł��邩��A�S�̂̏Z����ɐ�߂����ؒn���t�Z��̋����͂킸��0.26���Ƃ����ᗦ�ɂƂǂ܂��Ă��邱�Ƃ�������B
�܂��A��ˌ��ďZ��ɂ����Ē���ؒn���𗘗p�����������ӊO�Ƒ����B����́A�}���V�����Ȃǂ��A���i�ʂł̃����b�g���������₷���A�ڋq�A�s�[���̓x�����������Ƃ����Ǝґ��̘_�����琶�܂ꂽ���̂��낤�B�������A����ؒn���̊T�O�́A���݂�z�肵�đn�݂��ꂽ�Ƃ����Ă���i�i���j�o�[�h���Y�R���T���^���c�u�u����ؒn���v�͂�������Ȃ��\�\�\�u����؉ƌ��v�̈З́v
�w�o�[�h���|�[�g�x194��1998�N2��2���j�B�}���V������r���͑ϗp�N�������\�N���x�Ƃ����̂ŁA50�N�̒���ؒn�������قǖ����Ȃ��K�p�ł���ł��낤�B�Ƃ��낪�A��ˌ��ďZ��̏ꍇ�ɂ́A���ւ�������A�ȒP�ɓy�n�𖾂��n������̂ł͂Ȃ����낤�B50�N��A����40�̗��e��10�̎q�����A50�N��ɂ͊��ɗ��e�͖S���A�q����60�ɂȂ�B��N�Ɠ����ɓˑR�������Ƃ�����Z��ł����Ƃ���o�čs���Ƃ����邱�ƂɂȂ�B50�N�O�̌_������₷�����s�ł���̂��낤���B
�܂��A����ؒn���̐ݒ�ɂ́A�y�n���w������������Ƃ͂����A���Ȃ葽�z�̋��z���K�v�ɂȂ�B�Ƃ��낪�A����ؒn���͈�؎��Y�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����ɁA����ؒn���ɂ͊���������B�������n����t���ؒn���̏ꍇ�A����������A�Ⴆ��30�N�o������A���̌����p����K�v�����邪�A���̂Ƃ��Ɏs�ꉿ�l�����݂��Ă��邩�A�K���Ȏ���������ł��邩�ǂ�����ω��������̂�����B�܂��āA����̓��{�ł́A�O�q�̂悤�ɒ��ÏZ��̗��ʎs�ꂪ���݂����A���ĕt�������܂Ő����Ă��܂��B�܂��A��ʒ���ؒn���̏ꍇ�ł͊��������ƂƂ��ɖⓚ���p�œy�n��ԋp���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����̎��������傤��50�N�ł���Ζ��͂Ȃ����낤���A�r���ʼn��z�����ꍇ�ȂǁA��Ŗ��ƂȂ邱�Ƃ͕K��ł͂Ȃ��̂��낤���B
���Ε����ɂ��Ă��A���炩�̗��R�ŗ��ւ����K�v�ɂȂ����ꍇ�A�X�P���g���ƃC���t�B�����L�ҊԂł̔�p���S�̖��͎c��B�܂��A���Z�҂ɂƂ��āA�C���t�B��������S�ۂ̖ړI�ɂł��邩�Ƃ����������w�E�ł���B
���{�ł͒���ؒn���̊������}�������Ƃ��Ȃ��̂ł��邩��A����ł͊m��I�Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��B�������A�p���ł͓��l�̋K�肪���ł�17���I�ɂ͑��݂��A�u17���I�ɂ�20�N�ȉ������F�߂��Ă��Ȃ������ؒn���Ԃ��A��Ɏؒn��n��ɕԊ҂ł��Ȃ��l�B���}�����Đ������ɂȂ�A�M���̎��@����Ƃ����`��41�N����51�N�ɒ���������A18���I��61�N�A81�N�Ƃ�������Ȃ鉄���ɑ����āA����1882�N�̏��p���Y�ݒ�n�@�ɂ���āA99�N�Ƃ����������̎ؒn���Ԃ̉������F�m���ꂽ�v�i��o�@�ەv�w�s���Y�͋��Z�r�W�l�X���xp94�j�o�܂����邻���ł���B���Ȃ݂Ɍ��݂̉p���ł�999�N�ȂǂƂ������j�I�ȃ��[�X���Ԃ�ݒ肵�Ă��錚��������B
�c�O�Ȃ������ؒn�����Љ�ɔF�m����蒅����ɂ́A�܂������ォ������̂ł͂Ȃ����낤���B
�\1
�N�ʒ���ؒn���t�Z��̋�����
|
�N |
��ˌ��� |
�}���V���� |
�v |
|
����5�N |
102 |
159 |
261 |
|
6�N |
1,370 |
536 |
1,906 |
|
7�N |
2,570 |
1,246 |
3,816 |
|
8�N |
3,097 |
1,661 |
4,758 |
|
9�N |
2,576 |
1,007 |
3,583 |
|
���������s�� |
117 |
0 |
117 |
|
���v |
9,832 |
4,609 |
14,411 |
�i�o�W�@����11�N�œy�n�����@���y�����j
2.5����؉ƌ�
�]���̎ؒn�؉Ɩ@�ɂ�����؉ƌ��͒��ؐl�ɑ�ϗL���ɂł��Ă����B���ؐl����̉��́A���Ԃ̒�߂̂Ȃ��؉ƂɊւ��Ă͉��\�����ꂩ��3�����ŔF�߂���B1�N�ȏ�̊��Ԃ̒�߂�����؉ƂɊւ��ẮA�@�I�ɂ͒��ؐl����̉��\������͔F�߂��Ă��Ȃ����A���ؐl������\�����ꂪ�������ꍇ�A�����ɔF�߂�̂��ʗ�ł���B����A���ݐl����̉��\������ɂ͎ؒn���̏ꍇ�Ɠ��l�̐������R���K�v�Ƃ��ꂽ�B
�]���āA���ݐl�Ƃ��ẮA�A�p�[�g��傫�ȃr���ɗ��đւ��Ē��ݎ����𑝂₵�����Ǝv���Ă��A�؉ƌ�������ȏ�A�S�Ă̎؉Ɛl���o�čs���̂��Ђ�����҂��A���z�ȗ��ނ������x�����K�v���������B�܂��A���̗ǎ��Ȓ��ؐl���o�Ă����Ă��܂������ƂȂ鈫���Ȓ��ؐl�ɂ͌_��I���Ɠ����ɏo�Ă����Ă��炢�ꍇ�ł��A�؉ƌ������Ăɋ�������ƁA���ݐl����͌��ʓI�Ȏ�i����������B
���l�ȋK��͎ؒn�@�ɂ����݂��邱�Ƃ͑O�q�̒ʂ�ł���B���̂悤�ȋK�����n������ēy�n�A�����̋��������߂�킹�錴���ɂȂ��Ă����Ǝw�E����Ă����B���̂悤�ȏ�Ŕj���ׂ��A����ؒn���ɑ����Ē���������ݎi����؉ƌ��j�����肳�ꂽ�̂ł���B
2.5.1����؉Ɩ@�̓��e
l
���Ԃ̒�߂̂�����ݎ،_��ł���B
�]���̎؉ƌ���1�N�ȏ�20�N�ȉ��Ƃ������������������A1�N�ȉ��A20�N�ȏ�̌_����F�߂���B
l
�����̎g�p�ړI�͖��Ȃ��B
���Ɨp�A���Z�p�Ƃ��ɉ\�B
l
�����؏������ʂ������Č_�邱�ƁB
l
���ؐl�ɑ��Ă��炩���߁A�_����e���L�ڂ������ʂ���t���������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���̋`����ӂ����ꍇ�ɂ́A�]���̒��ݎ،_��Ƃ��Ď�舵����B
l
���r���͌����F�߂��Ȃ��B
�������A�����ʐ�200�������[�g�������̋��Z�p�����ŁA�]�A�×{�A�e���̉��Ȃǂ�ނȂ�����Ŏ��Ȃ̐����̖{���Ƃ��Ďg�p����ȏꍇ�́A���r��ł��A���\�����ꂩ��1�����o�߂��邱�Ƃɂ����ݎ͏I������B
l
�_��̍X�V�͂Ȃ��B
���ׂčČ_��ƂȂ�B
l
���ނ������͕K�v�Ȃ��A�_����Ԃ̏I���������ē��R�Ɍ_��͏I������B
2.5.2����؉ƌ��Ɋ��҂����o�ό���
����؉ƌ��͌��s�@�̒��ؐl�̌����𐧌���������Ő��肳��邽�߁A��Ґ�̂ĂɂȂ�Ƃ̔ᔻ�����������B�������A���ւ����e�ՂɂȂ邱�Ƃ���D�ǒ��ݏZ��s��ɋ�������邱�Ƃ����҂ł���Ȃǂ��܂��܂ȃ����b�g�����邱�Ƃ��琧�肳�ꂽ�B
��L����ؒn���Ōl�Z������݂���ꍇ�ɂ́A50�N�Ƃ����������Ԃ����ɂȂ�\�������邱�Ƃ��w�E�������A����؉ƌ��ł͊��Ԃ̐ݒ�͓����ҊԂŎ��R�Ɍ��߂���B�܂��A����ؒn���̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�A���������ؐl�̏��L�ɂȂ�B�]���āA��������ؒn���̏ꍇ�̂悤��50�N��ɍX�n�ŕԋp����K�v��A�������n����t���ؒn���̏ꍇ�̂悤��30�N��Ɍ��������K�v�Ȃǂ͂Ȃ��A�����W���������肵�Ă���B�܂��A���ݐl�ɂƂ��ẮA���݊��Ԃ��͂����肵�Ă���̂ŁA���ւ��Ȃǂ��v��I�Ɏ��s�ł��郁���b�g������B
����؉ƌ��̎{�s�ł����Ƃ������b�g������ł���̂́A�I�t�B�X�r���Ȃǂ́A���Ɨp�s���Y�̒��݂ɂ����Ă��Ǝv����B�O�q�̂悤�ɁA���{�ł͎��Ɨp�s���Y�ɂ����Ă����ؐl�̌��������������Ă������ʁA���ݐl�ɂƂ��Ă͕s�ǃe�i���g��ǂ��o�����Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�ł������B�܂��A���ؐl����͂��ł����ݎ،_���ł��邱�Ƃ��ł���̂ŁA��ɋ��X�N������Ă����B���̂��߁A���X�N�v���~�A���Ƃ��ĕ~���A����A�X�V���Ƃ��������ڂŒ��ݗ��ȊO�̋��K������K�v���������̂ł���B����؉ƌ��̕��y�ɔ����A���ݗ��ȊO�̋��K�̎���͌����Ă������̂Ǝv����B
�܂��A����؉ƌ��ɂ���Ē��݊W�����肷��̂ŁA�s���Y�̏،������s���ꍇ�ɑ���ȃ����b�g������B�Ⴆ�A����r����10�N�̒���؉ƌ_��Ńe�i���g�ɑ݂��B���̃r���ɂ��Ă�10�N�Ԃ̎��x�����O�ɔc���ł���̂ł��邩��A�����̊m���ȓ������i�ɂȂ�B
2.5.3�����I�v�V����
�܂��A����؉ƌ��ɕt�������ϋ����[���V�X�e���ɁA�����I�v�V����������i�R��
�����w�s���Y�������_����xpp182-183�j�B�����I�v�V�����Ƃ́A����e�i���g���A���݂͂�����̃X�y�[�X�����K�v�Ƃ��Ă��Ȃ����A�������Ƃ̊g��ƂƂ��ɂ���ɃX�y�[�X��K�v�Ƃ���\��������Ƃ���B���̏ꍇ�A�]���@�̉��ł́A�����̃X�y�[�X���̂܂܂ɂ��Ēu���ȊO�A�m���ɗv���ɓ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�������A����؉ƌ����g���A��L���Ɋ��p�ł���B����͕č��Ŋ��ɕ��y���Ă���V�X�e���ł���B
�t�ɁA����؉ƌ_��ł͒��r��ł��Ȃ����߁A�����ɂ킽���čL���X�y�[�X����邱�Ƃɕs�������e�i���g������Ǝv����B���̂悤�ȃe�i���g�ɑ��ẮA�����I�v�V��������邱�Ƃ��l������B�����I�v�V������t�^���邱�Ƃɂ���āA���ݐl���{���K�v�Ƃ��钷���̒���؉ƌ_����������U���Ƃ���̂ł���B
3.
�s���Y�،���
��،��̎��s�ɒ��肽���{�s��ɂ����铊���Ƃ������A�C�O�s��ł̕s���Y�،����̗�����čĂѕs���Y�̏،����Ɏ��g�ݎn�߂��B�܂��A�،����ɂ�藬���������߂邱�Ƃɂ���āA�Ăѕs���Y�s��Ɏ����������A�o�u������ɂ���ď��s��̕��������҂��Ă������������B
�O���[�o���X�^���_�[�h������Ă��邪�A�s���Y�s��͍����Ƃɂ��Ȃ��������x�A�����������Ă���B�č��ƃh�C�c�̏،������Љ��ƂƂ��ɁA���݂̓��{�̕s���Y�،��A�s���Y���M�Ȃǂ̏��i������������B
3.1�č��̕s���Y�Ƃ̓���
�ǂ����������A���E�̋��Z�s������[�h���Ă���͕̂č��ł���B�������{����������Ȃ킯�ł͂Ȃ��A�č��̕s���Y�s��ɂ��Ɠ��̎s�ꊵ�s������B
3.1.1���ݎ�
�č��̒��ݎ،_��́A���{��蒷���A���Ɨp�s���Y�ł�10�N���W���I�ł���B�܂��A�r�����ɂ͂ق��̃e�i���g�������Ă��邩�A�c�������ݎ،_����Ԃ̒����̌��݉��l���x����Ȃ��Ă͂����Ȃ��_��ɂȂ��Ă���B2000�N���{�ł��@�������ꂽ����؉ƂƓ������x����ʓI�Ȃ̂ł���B�����������s�ꊵ�s���A�s���Y�،����Ƀt�B�b�g���Ă���悤�ł���B�������A�č��ł����Z�p�s���Y�i�A�p�[�g�j�ɂ͌����������g�R���g���[��������A��������Z�l���Z��ł��܂��ƁA���ʂ܂ŏo�Ă����Ă���Ƃ͌����Ȃ����x������B�������{�̋��؉Ɩ@�̂悤�ł��邪�A��������{�Ɠ������펞���@�����������ł���B�j���[���[�N�̒��S�X�Ƃ�����悤�ȂƂ���ɂ������̈������E�ݔ��̈����r�����c���Ă���̂͂��̖@���������ł���B
3.1.2�m�����R�[�X�E���[��
�č��ł͕s���Y�S�ۂƂ����A�m�����R�[�X�����ʂł���B�m�����R�[�X�Ƃ́A�Ⴆ�Z���Č������s���Ă��A�Z���������Z�@�ւ͕s���Y�����グ�邾���ŁA���҂̑��̍��Y�ɂ͑k�y���Ȃ��Ƃ��������ł���B���{�ł́A�s���Y�S�ۂ̏ꍇ�ł��E�B�Y���R�[�X����{�I�ł���B���̏ꍇ�A�s���Y���Ƃ����s���ĒS�ەs���Y��v������Ă��A�؋���S�z�ԍς��Ȃ����蕉�͎c��B�č������̂ق����A���e�Ղɕs���Y���������₷�����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��ł��낤�B���������R���X�N�v���~�A���͍����Ȃ�B�y�n���w�����ăr�������Ă�J�����ƂɎ��s�����ꍇ�A���Z�@�ւɂ͎��s���Ƃ̓y�n����������ɓ���Ȃ��̂ł��邩��A���R�Ƃ�����ł��낤�B�]���āA��ʂ̕s���Y�،��̊i�t�����Ⴂ���Ƃ������悤�ł���B
3.1.3�č��ɂ�����s���Y�،�
�č��ɂ����Ă��A�s���Y�̏،����͕K�������������j�������Ă���킯�ł͂Ȃ����A���̒��łP�Ԓ������j�������Ă���̂�MBS�i�Z��[���S�ۏ،��j�ł���BMBS�ɂ�GNMA�i�W�j�[���C�A���{����ɍj�AFNMA�i�t�@�j�[���C�A�A�M����ɍj�AFHLMC�i�t���f�B�[�}�b�N�A�A�M�Z����Z����ɍj�Ȃǂ�����B�[�I�Ɍ����A���{�̏Z����Z���ɂ����̏Z��[�����،��������悤�Ȃ��̂ł���B���{�n�̋��Z�@�ւł��邪�A�����ɂ͍��Ƃ͈قȂ�A���{���ۏ��Ă���킯�ł͂Ȃ����A����ɏ�������̂Ƃ��đ�ύ����M�p�͂������Ă���B�]���āA���̗��������v���X�E�A���t�@�[���x�ł���B
���Ɨp�s���Y�ɑ���O�q�m�����R�[�X�E���[�����،����������̂�CMBS�i���Ɨp�s���Y�S�ۃ��[���،��j�ł���B1980�N��㔼�AS&L�i���~�ݕt�g���j�̔j�]�ɒ[�����s�Ǎ������̂��߁ARTC�i�����M�����Ёj��������s�Ǎ����ʂɏ،������Ĕ���o�����B�@�I�����������܂��Ĉ�C�ɗ��ʎs����g�債���B1990�N��ɓ����Ă������Ɋg��𑱂���CMBS�s��ł��邪�A1998�N�̃��V�A��@���_�@�Ɉ�C�ɃN���b�V�����Ă��܂����B���V�A��@���������ƂȂ��āA�����Ƃ̎����I�D������u�������߁ACMBS�ɑ��郊�X�N�v���~�A������C�Ɋg��ACMBS���i�͖\���A���s�s��͎������~�A�s�ꂩ��P�ނ�����Z�@�ւ��������B���̌㔭�s�s��͉������ACMBS�ɂ����̃��X�N������Ƃ������P���c�����B
��L�Q�̃^�C�v�̏،����s���Y��S�ۂɂ������[�����𗠂Â��ɂ����f�b�g�iDept�j�^�̏،������i�ł���̂ɑ��āAREIT�i�s���Y�����M���j�͕s���Y���̂��̂𗠂Â��ɂ����G�N�C�e�B�iEquity�j�^�̏،������i�ł���B�������AREIT�̒��ɂ�CMBS��s���Y�S�ۃ��[����g�ݍ��f�b�g�^�A���邢�̓n�C�u���b�h�^�̂��̂�����B���x���̂��̂�1960�N��ɊJ�����ꂽ���A��d�ېʼn���Ȃǂ̖@�������i�݁A���Ƀ|�s�����[�ɂȂ����̂�1990�N��ł���B
REIT�̓����́A�����Ƃ������I�ɕs���Y�̏��L���邱�Ƃ��ł��A�]���ĕs���Y�̒l�オ��v����邱�Ƃ��o����_�ɂ���BMBS��CMBS�Ȃǂł͂����ɕs���Y���瓾��������i�C���J���E�Q�C���j���،����������̂ɑ��AREIT�̓C���J���E�Q�C���ɉ����ăL���s�^���E�Q�C���܂ł��،����������̂Ƃ�����B
�Ƃ���ŁA�L���s�^���E�Q�C���Ƃ������t���g�������A�č��ɂ�����L���s�^���E�Q�C���̊T�O�͓��{�Ƃ͂��قȂ�̂Œ��ӂ��K�v�ł���B���{�ɂ����ĕs���Y�����ɂ�����L���s�^���E�Q�C���Ƃ́A�s���Y�A���ɓy�n���̂��̂̒l�オ��v���Ӗ�����B�č��ł́A���Ɨp�s���Y�������z�̓����{�Ƃ͂��Ȃ�قȂ�A�������z�ɐ�߂�y�n�̊�����2�����x�������ł���i��o�@�ەv�w�s���Y�͋��Z�r�W�l�X���xp138�j�B�]���āA�c��8���͌����ɑ��铊���ƂȂ�i���{�ł́A���Ɨp�s���Y�ł��A5���ȏ��y�n����߂�͂��ł���j�B�����͕s���Y�ł���Ƃ͂����A���ݎ����邽�߂̕��䑕�u�A�@�B�Ƃ������ʒu�t���ɂȂ�B�����͂���������p����̂ŁA���̂܂܂ł̓L���s�^�����X�ɂȂ��Ă��܂��B�����ŁAREIT�Ȃǂ̓��������ɑ��ẮA�f�B�x���b�p�[�i���{�̃[�l�R���^�f�B�x���b�p�[�Ƃ͈قȂ�A�s���Y�͏��L�����A�R�[�f�B�l�[�g�����ăt�B�[��Ǝҁj�Ȃǂ��r���Ȃ���ĊJ���E�������ĕt�����l�����߁A���v�͂����߂邱�Ƃɂ���ăL���s�^���E�Q�C����_���̂ł���B
�܂��AREIT�Ɠ����悤�ȃG�N�C�e�B�^�����Ƀ��~�e�b�h�E�p�[�g�i�[�V�b�v�𗘗p�������̂�����B���~�e�b�h�E�p�[�g�i�[�V�b�v�͂��Ƃ��ƐΖ���K�X�T���Ƃ������v���W�F�N�g�̎����W�߂̂��߂ɐ��܂ꂽ���̂ŁA�����،����������Ƃ����_��REIT�ɑ��āA�����P�ʂ͑傫���A��K�͂ȃV���b�s���O���[�������ȂǑ�^�v���W�F�N�g�Ɏg����悤���邪�A����Ȃǐ�������Γ��R�D�ǎ��v�����ƂȂ�A���̃��^�[���͋��z�Ȃ��̂ɂȂ�B
���Ȃ݂ɁA�ς����REIT�Ƃ��ẮA�Y�����ɓ�������REIT�����邻���ł���B�Â��Ď��v�͂̂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����r���������������A�Y�����ɉ������Ē��݂���̂ł���B�u�R���N�V�����E�R�[�|���[�V�����E�I�u�E�A�����J�Ƃ�������REIT�́A�S�Ă�59�̌Y������45000�̃x�b�h��������REIT�ŁA�N�ԑ�������肪50������60���܂�鍂���vREIT�Ƃ��Đl�C������܂��B���Ђ̖ژ_�����ɂ��A�Y�����͘A�M���{���B�֒��݂��邱�Ƃŋ��X�N�����Ȃ��A�R���N���[�g�ƓS�������̍\���ŊǗ����₷���A�������Ƃ��Ƀ��t�H�[������K�v���Ȃ��_�ƁA������A�����J�̔ƍߔ������͏㏸�𑱂��A�S�Ă̎��l���͌��݂�170���l����2004�N�ɂ�350���l�ɑ�������Ƃ����\����REIT�̗��_�Ƃ��Ă����Ă��܂��v�i��o�@�ەv�w�s���Y�͋��Z�r�W�l�X���xpp155-156�j�B���j�[�N�ȂƂ���ɖڂ������s���Y�J���@�Ƃ����邾�낤�B
3.2�h�C�c�ɂ�����s���Y�،�
�h�C�c�̑�\�I�ȕs���Y�������i�̃I�[�v���E�G���h�E�t�@���h�́A��{�I�ɂ�REIT�Ɠ����d�g�݂ŁA�����Ƃ͎��{������Ђ��玝���،����w�����Ď��v��B���{������Ђ̓h�C�c3���s�̊֘A��ЂŁA���ȐM�p�͂��ւ��Ă���B�Ƃ���ŁA�h�C�c�ɂ�����s���Y�̕]���́A�뉿�ɂ�邻���ł���B�]���āA�h�C�c�̕s���Y�،��̓L���s�^���E�Q�C�������҂��Ă��Ȃ��B�]���āA���O�̓t�@���h�ł��邪�A�����I�ɂ͔��Ό��{�ۏ̒���a�����o�ł���B���傤�Ǔ��{�ɏ]���������i�j�]���o�Ō��݂͔p��Ă��܂����j�A��،��ɋɂ߂Ď��Ă���B������������s�a���v���X�E�A���t�@�[�ł���B�܂��A�����闬�ʎs��͂Ȃ����A�،��̔��s��Ђ���ъ����s������I�ɔ���������i�����\�A���ł���������Ă����V�X�e���ɂȂ��Ă���i��o�@�ەv�w�s���Y�͋��Z�r�W�l�X���xpp40-43�j�B�č��̎���Ƃ͂��Ȃ�قȂ�����ŁA���ʐ�����v�����m�ۂ��Ă���̂������ł���B
3.3���{�ɂ�����s���Y�،���
3.3.1
SPC�@
�䂪���ł��s���Y�̏،����ɂ�闬�����̑��i�̂��߂̖@�������s���A������SPC�@�i�����ɂ́u����ړI��Ђɂ����莑�Y�̗������Ɋւ���@���v�Ƃ��̐����@�j������10�N9��1���{�s���ꂽ�B
SPC�Ƃ�Special
Purpose Company�̗��ŁA����ړI��Ђ������͓��ʖړI��ЂƖ��BSPC�͍��̏،����ȂǁA����̖ړI�̂��߂ɐݗ�������Ђł���BSPC�͊�ƂȂǂ����L���郍�[������s���Y�Ȃǂ��擾���ASPC���،��s�A�����Ƃɔ̔����邱�ƂŎ������B������B
�]���āASPC�͂���߂Č��肳�ꂽ�ړI�̂��߂ɐݗ�������Ђł���̂ŁA�]���̏��@�ŋK�肷���Бg�D�����K�v���Ȃ��B�@�I�ɂ�SPC��SPC�@�Ɋ�Â����ʂȎВc�@�l�ŁA���莑�Y�̏�����A���U�������Ƃ��Ă���B���̐ݗ��͊�����Ђ�L����ЂƔ�ׂĂ͂邩�Ɋȗ�������Ă���B�܂��A���{��������300���~�K�v�ł��邪�A����12�N11��30�����10���~�Ɉ�������������@�Ă�������Ă���B
�܂��A�����̂��߂̓��ʉ�Ђł���̂ŁA���v��90���ȏ��z������Α����Z������A�@�l�ł��y�����Ă���B�܂��A�ݗ��o�L���̓o�^�Ƌ��ŁA�s���Y�����ł̌y���A�擾�����y�n�ɌW����ʓy�n�ۗL�ł̖Ə��ȂǁA�����̗D���u�����Ă���B
�������A�{�s��2�N���o�����A���͂r�o�b�𗘗p�����s���Y�،����͊��҂��ꂽ�قǑ����͂Ȃ��B�s��W�҂̊Ԃł́A�]���̃P�C�}���������SPC�����̂ɔ�ׂĎ��Ԃ�������Ȃǂ̖��_���w�E����Ă���B����Ɋւ��Ă͎��{���̂Ƃ���ł��G�ꂽ�Ƃ���A����12�N5��23����SPC�@�̈ꕔ����������ASPC�����葱���̊ȗ����A�����Ώێ��Y�̊g��A���莑�Y�擾�̂��߂̎������\�ɂ��邱�ƂȂǂ����荞�܂ꂽ�i����12�N11��30���{�s�j�B
3.3.2�s���Y���M
����10�N�Ɂu�،������M���@�v���u�،������M���y�я،������@�l�Ɋւ���@���v�i���M�E�����@�l�@�j�ɉ������ꂽ���A�����SPC�@�Ɠ��l�A����12�N5��23���ɉ����Ă�������A�@�������u�����M���y�ѓ����@�l�Ɋւ���@���v�ɕς��i����12�N11��30���{�s�j�B�@��������،������Ƃ��ꂽ���Ƃ����������Ƃ���A����܂Ŏ�Ƃ��ėL���،��Ɍ��肳��Ă��������Ώۂ��A���Y���S�ʂ֊g�傳���B�]���āA�s���Y�̌�����SPC�ɂ��D��o���،��A�s���Y�M����v���ւ̓������\�ɂȂ�̂ŁA�s���Y�̏،����ɂ��傫�ȉe��������Ƃ�������B
�܂��A�����M���̎���҂ł���M����s���炪�^�p�������҉^�p�^���M���V�݂���A�s���Y���^�p�ΏۂɊ܂܂��B�������Z�ƕs���Y���Ƃ��Ɏ�舵���Ă����M����s�������M���ɏ��o�������b�g�́A�s���Y���M�̈琬�̏ォ����傫���Ǝv����B
3.3.3�s���Y�،����̃����b�g�ƃf�����b�g
�ȏ�s���Y�،����̃X�L�[���ɂ��ďq�ׂĂ������A�،������ꂽ�s���Y�ɂ̓����b�g������f�����b�g������B
�����b�g�Ƃ��ẮA�Ȃ�ƌ����Ă����������̏�������}��邱�Ƃł���B�܂��A�s���Y�Ǘ��̃v�������Ă��Ă���̂ŁA�s���Y�Ǘ��\�͂��l�Ƃ��Ă̓����Ƃ�����邱�Ƃ͂Ȃ��B���̑��A���Ƃ����������������ł��A���U�����̌��ʂ�����̂ŁA�Ⴆ���X�N�͌l�œ����z�𓊎������ꍇ��菭�Ȃ��Ă��ށB
�t�Ƀf�����b�g�Ƃ��ẮA�����Ƃ����ڕ������m���߂ē�������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�ǂ����Ă����d�����̏��i���w�����邱�ƂɂȂ�A�����ɑ���ő�̃��^�[�������҂���킯�ɂ͂����Ȃ��B���Ƃ��A���Ã������[���}���V�������l���ꂵ�Ă��錻��A���������ɂ�薣�͂���������������Ƃ�������B
�܂��A���{�ł͓s�ꂪ�����n�Ȃ̂Œ��r����������̂��Ƃ����ł���B�s�ꂪ�����n�Ƃ������Ƃ́A���i��]�����邽�߂̃x���`�}�[�N����������Ă��炸�A�����]�����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�]���āA�ЂƂ��ѕs���Y�،���ۗL����������܂Ŏ�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�،����̃����b�g�͏������ƂƂ��ɁA�����Ɣ�ׂ��ꍇ�̗������̌���ɂ���͂��ł��邪�A����ł̓����b�g�͊������Ȃ��B�č��ł͊m���ɂ���10�N�ŕs���Y�،��s��͋}�g�債�Ă����B���̗��ɂ́A�č��i�C������10�N�D�������Ă������ƂƂƂ��ɁA���ʎs�ꂪ�������ꂽ���炱���s���Y�،��s�ꂪ�g�債�����Ƃ��������킯�ɂ͂����Ȃ��B
3.4�s���Y�Ӓ�]��
���ʎs����m�����邽�߂ɂ́A�s���Y�ɌW��x���`�}�[�N�̐������d�v�ł��邱�Ƃ͑O�q�̒ʂ�ł���B�x���`�}�[�N�����肷��ۂɁA�s���Y���i�������ɕ]���A�Ӓ肷�邩�Ƃ�����肪����B�ȉ��A�s���Y���i�̕]�����@�ɂ��ĉ������B
3.4.1�s���Y�̕]�����i
�ڂ����]�����@�̐����ɓ���O�ɁA�s���Y�̕]�����i�Ƃ͉�����������Ă����B�s���Y�ɂƂ��āA���i�Ƃ͎�����i�����ł͂Ȃ��B���������]�����i�͂��ꂩ���������邱�Ƃ�z�肵�Č��߂���̂ł���B�܂��A�]�����i�Ƃ����Ă��A�������蔃�����肷��l�̗���ɂ���ĉ��i�������傫���ς��ꍇ������B�����ŁA���{�̕s���Y�Ӓ�]���ɂ����Ă͉��i�ɂ��Ĉȉ��̂悤��3��ނ�z�肵�Ă���B
�����퉿�i��
�s�ꐫ�̂���s���Y�ɂ��āA�������̓���ȏ����̂Ȃ����J�s��ɂ����āA���������҂��A����̔���}���A����̓��@�Ƃ��������ʂ̓��@�ɂ�炸�o�ύ������Ɋ�Â��čs�������ꍇ�Ɍ`�������ł��낤�s�ꉿ�l��\�����鉿�i�𐳏퉿�i�Ƃ����B
�����Ƃ���ʓI�ȉ��i�Ƃ����Ă悢�ł��낤�B
�����艿�i��
�s�ꐫ�̂���s���Y�ɂ��āA���������҂����̕s���Y�Ƃ̕����A���邢�͕s���Y�̕����ɂ��ꕔ���擾����ꍇ�ɍ����I�Ȏs�ꉿ�l�Ƙ������邱�Ƃɂ��s�ꂪ���ΓI�Ɍ��肳���ꍇ�Ɍ`����������s�ꉿ�i�������B
�Ⴆ�A�ؒn���҂���n�̕�����ړI�Ƃ��锄�����s���ꍇ�A���̓y�n���ă����b�g������l�͎ؒn�l�������Ȃ��̂ŁA��ʂɒ�n���i�͐��퉿�i���������肳���B�܂��A�O�q�̂悤�ɁA�n�グ�Ǝ҂����̓y�n�̕�����ړI�Ƃ��čו������ꂽ�y�n�������ꍇ�A������̂��傫�Ȏs�ꉿ�l����ɉ��i��ݒ肷��̂ŁA��ʂɐ��퉿�i���͍����Ȃ�B�܂��A�_�n�Ȃǂ��_�n�@�ɂ���Ď擾�҂����肳��Ă���̂Łi���O�ɔ_�n�@�̋����Ƃ�Ȃ������_��͖����ɂȂ�A�܂���O�͂�����̂̔_�Ə]���҈ȊO�͂���߂Ď擾������j�A��ʓI�Ȑ��퉿�i�̎Z��͓���ł��낤�B
�����艿�i��
�@���I���z�����n�̊Ӓ�ȂǁA��ʓI�Ȏs�ꐫ���l�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��s���Y�̌o�ω��l��\�����鉿�i����艿�i�Ƃ����B
3.4.2��ʓI�ȓy�n�̊Ӓ���@
�`���̌������i�̍��Ō������i�̎Z����@�ɂ��ĊȒP�ɐG�ꂽ���A���ۂ͂ǂ̂悤�Ɍv�Z����̂ł��낤���B
�]���s���Y�̉��i�͉E���オ��̏㏸�����邱�Ƃ����R�́i�������Öق́j�����Ƃ��Ċ��҂���Ă����B�]���āA�s���Y����������ꍇ�ɉ��i�f����ޗ��Ƃ��Ď�������r�@�ŏ\���ɖ��ɗ������B������A������y�n���i���㏸����̂ł��邩��A�L���s�^���E�Q�C�������Ă���A���^�[���͏\���Ɍ����߂邩��ł���B�������A�o�u���̕���͂��̂ʂ�ܓ���Ԃ���ς������B��ςǂ��납�A������̂��̂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A��������r�@���g���Ȃ��Ȃ�ƁA�K���Ȏ��~�߂��Ȃ��܂ܓy�n���i�͓ޗ��̒�ւƗ�������ł��܂����B
���Ɨp�̕s���Y��]������ꍇ�ɂ����v�Ҍ��@�͗L�͂ȕ���ƂȂ�B�܂��A����������Ⴊ�Ȃ��ꍇ�ł��\���Ɋ��p���ł���B�ŋ߂̕s���Y�s�������v�Ҍ��@�̊ϓ_���璭�߂Ă݂�ƁA�o�u�����̎��v���ɔ�ׂ�Ɩ��̂悤�ȁA�N�ԉƒ����������i��10�����z������̂܂ŐV������Ɍ���Ă���B���v�Ҍ��@���L�͂ȕs���Y���i�]���c�[���Ƃ��Ĉ�ʂɔF�m�����A���݂̕s���Y���i�͖��炩�ɒ�ɋߕt���Ă��邱�Ƃ��F�������ł��낤���A�����Ȃ�Εs���Y�s���̉����҂ł���B
�܂��A�ŋߘb��ɂȂ��Ă���،������ꂽ�s���Y�i���邢�͕s���Y���M�j��]������ꍇ�ɂ����v�Ҍ��@�͑傫�ȈӖ��������Ă���B���v�Ҍ��@�Ȃǂ̈��̕]���@�Ŏ�����������Ɣc������Ă��Ȃ��Ɠ����̕]�����ł��Ȃ��B
�N�ԉƒ����������i��10�����z����������Ə��������A���̒P���ȔN�Ԏ��v/���i�������Ď��v�Ҍ��@�Ƃ����Ă��܂��Ă悢�̂ł��낤���B�ˑR���̒��x�̈Ӗ��Ŏ��v�Ҍ��@�Ƃ����Ă���ꍇ�������Ǝv���邪�A���݂ł͂���ɐ������ꂽ���v�Ҍ��@�����������܂�Ă���B
�ȉ��A��ʓI�ȊӒ�]���@�Ƃ��āA�����@�A��������r�@�ɂ��ĐG���ƂƂ��ɁA���v�Ҍ��@�ɂ��ďڐ�����B
�������@��
�����@�Ƃ́A���鑢�����ꂽ�����n�Ȃǂ�]������ۂɁA���l�̓y�n�����������ē������x�̑�n������̂ɂ����炩���邩�i�Ē��B�����j���v�Z����B�܂��A�����͎��Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɓ��R�Ɍ������邵�A�y�n�ɂ��Ă��i�ǂ̑����Ȃǂ��l������̂ŁA�����C�����K�v�ɂȂ�B�����Ō����@�͉��i���_�ɂ�����Ώەs���Y�̍Ē��B���������߁A�K�v�Ȍ����C�����s���ĎZ�o�����B�]���āA�Ӓ肳���Ώۂ̓y�n������̂Ɏ��ۂɂ����炩�����������v�Z����̂ł͂Ȃ��B��ʓI�ɁA�ΏۂƂȂ镨���̎��͂��J������s������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ͗L���ȊӒ���@�ƂȂ邪�A�J������Ă���N���̌o���Ă��܂����s�X�n�Ȃǂ̊Ӓ�ɂ͌����Ȃ��Ƃ����B
����������r�@��
�Ⴆ�A����n��ɂ�����s���Y�̎��������W�߂ĕ��ׂĂ݂�A�����ɂ͓��R�ЂƂ́g����h���`������Ă���͂�����B�����ŁA�Ώەs���Y�̕]���z�𐄌v����ꍇ�ɁA���ӂ̗ގ��s���Y�̔��������T���A��������ƂɑΏەs���Y����������Ƃ����炢����ɂȂ邩�𐄌v���@�ł���B�]���āA��������r�@���L���ɋ@�\���邽�߂ɂ́A�ߗׂ܂��͓�����������̗ގ��n��ɂ����Đ���Ȏ�����s���Ă��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�܂��A�s���Y�͗ގ��n��Ƃ����ǂ��ʐ����������߁A�K���ȕ���s���K�v������B
�������̎��W�ɍۂ��ẮA���@�I�v��������ł��Ȃ����A����ȗv�����e�����Ă��Ȃ����Ȃǂ��`�F�b�N���č̗p���邱�ƂƂ���Ă���B�������A�s���Y�͈�ʓI�ɂ͗��������Ⴍ�A�܂���L�̂悤�ȓ��ꎖ����܂Ȃ������Ƃ��Ă��A�ʐ��������B���̂悤�ȏ̒��Ŏ�������I������ꍇ�ɁA�ǂ����Ă����@�I�Ȕ���������܂܂�Ă��܂��A���@�I�����̖ړI�ƂȂ镨���̒n���̍����ɑS�̂����������Ă��܂����炢���������B�t�ɁA�o�u�������A������Ꭹ�̂��ɒ[�Ɍ������Ă��܂��ƁA�K���Ȓn�����Z�o�ł����A�n�������Ɏ��~�߂�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�o�u�������o�āA���ł��ᔻ����Ă���Ӓ�]�������Ƃ����Ă悢�ł��낤�B
�����v�Ҍ��@��
�t�Ɏ��v�Ҍ��@�͍��ł����Ă͂₳��Ă���Ӓ���@�ł���B�Ⴆ�A����s���Y����݂��Ă���ƁA�������������邪�A�Œ莑�Y�ŁA�s�s�v��łƂ������ŋ���A�����̈ێ��Ǘ���A�C�U��A�Еی����Ȃǂ��K�v�o��Ƃ��Ďx�o�����B�܂��A�����̑ϗp�N�����N���̌o�߂ƂƂ��Ɍ����Ă����̂ŁA���ւ���p���Ƃ��Ă̌������p���o��Ɋ܂܂��B���v���炱���̕K�v�o����������������̂������v�ƌĂԁB���̂悤�ȕs���Y�̌o�ϓI���l�́A���N���ݏo����鏃���v�̌��݉��l�̑��a�Ƃ��ċ��߂���B
�ƒ������A�d�Ō��ہA�ی����A�Ǘ��ێ���Ȃǂ͐����Ƃ��Ĕc�����₷���A�Z�茋�ʂ������Ƃ��ĊȒP�ɏo���邵�A���Ă̕s���Y���i�͂��ׂĂ���Ō��܂��Ă���A�ȂǂƂ�����ƁA�ȒP�ɔ[�����Ă��܂������ł���B�������A�s���Y�̒��݂͑�̂ɂ����Ē����ɂ킽��B��������ƁA�ƒ��͌������ڂ낭�Ȃ��Ă������i���ɓ����Ȃ̂��A�͏o�Ȃ��̂��A�ɒ[�Ȃ��Ƃ������ƑJ�s�������Ă������̉ƒ��͓������A�Ȃǖ�肪����B�\1�A2�̂悤�ɁA���͂��Ȃ�ω�����B���̑z�肪5���قȂ�A���R�r���̉��i����5���ς�邱�Ƃ͗e�Ղɑz�������B�܂��A�̐S�v�̊Ҍ�������������ɐݒ肷�邩���傫�Ȗ��ł���B���̑��̎����A�o��͌��݂̐�������r�I�ȒP�Ɏ�ɓ���̂Ŗ��͂Ȃ����A�Ҍ������ɂ���ĎZ�茋�ʂ���ς��Ă��܂��B�Z�����̂͌�q�̂悤�ɊȒP�ł��邪�A���g���悭�m���߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���ۂ̕s���Y�Ӓ�ɂ����ẮA��L3���@�p���A3���@�̓����A�Ώەs���Y�̐��i�����Ă̏㌈�肷�邱�Ƃ��D�܂����Ƃ���Ă���B���ہA���ꂼ��̕]�����@�ɂ��꒷��Z�������āA�K���������v�Ҍ��@���D��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�������A���㐷��ɂȂ�ł��낤���v�����̏،����Ȃǂɂ����āA���v�Ҍ��@�͍ł��K�������@�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��낤�B
3.4.3���v�Ҍ��@�̎���
�����ڊҌ��@��
��L�̊ȒP�Ȏ��v�Ҍ��@�͒��ڊҌ��@�ƌĂ�܂��B�Ⴆ�A�����ɔN��C�~�̎��v���グ�Ă��镨��������Ƃ���B���̏ꍇ�A���̕s���Y�̌��݉��l�iPV�j�͏����̃L���b�V���t���[�̌��݉��l�̑��a�Ƃ��ċ��߂���B
�����Ƃ��Ď����A
![]()
![]()
![]()
![]()
�Ƃ��ĕ\�����B�s���Y����オ�鏃���v��500���~�A�Ҍ�������5���Ƃ���ƁA5,000,000/0.05��100,000,000�i�P���~�j�ƂȂ�B
�������A�����Œ��ӂ��K�v�Ȃ̂́A��L�ݒ��ł́A���v�͉i���ɕs�ρA�����̘V�����ɂ�闧�ւ��Ȃǂ���؍l�����Ă��Ȃ����Ƃł���B�܂��A�Ҍ�������5���ɐݒ肵�����A�P���ɊҌ�������10���ɂ��������ŕ]���z��2����1�ɂȂ��Ă��܂��B���݂̓��{�̋�����Ԃ���ɒ�������2�����̗p����A���R�s���Y���i�͒��ˏオ��B�������������炪�K���Ȃ̂ł��낤���B�č��ł͎������������A�K���ȕs���Y�C���f�b�N�X���ꂪ�`������Ă���悤�����A���{�ł͂��܂����n���Ă��炸�A�s���Y���ƁA�����Ƃ̑��l�I�ȃm�E�n�E�ɗ����Ă��镔�����傫���悤�Ɏv����B
�����A����ł���ʓI�ȌX���Ƃ��ẮA�P����̌㔼�A�����6�|10���i���j���炢�ɐݒ肵�Ă�����������悤�Ɏv����B���̊Ҍ����[�g�͒����̎��x�͂���Ƃ��Ɏg���̂ŁA�ȒP�ɂ͕ϓ����Ȃ��B�]���āA�s���Y�̓K�����i�͑�̏�������10����16�N���A�ƍl���Ă����ƈ�̎w�W�ɂȂ�ł��낤�B
�i���j�@����12�N8���A���y���y�n�ǒn�������ۂ��u�����p�s���Y�̎��v���i�̎Z��̎��s�ɂ��āv�Ƃ������̒��ŁA60���̒��ݗp�s���Y�̏��L�҂ւ̃A���P�[�g�Ɋ�Â����v���i�y�ъ������̒������s�����B���̌��ʁA�e���x�[�X�łW〜11���A�o���������̑����Ҍ�������4.8〜7.7���i���f�l6.0���j�Ƃ������ʂĂ���̂͒��ڂ����B
�������A���̎w������ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�i���j���{�s���Y��������2000�N�V���Ɍ��\�������l�ł́u�����Ҍ������v�̕���5.8���ADCF�@�i��q�j�ɂ��ꍇ�́A���Ȏ����ւ̊��Ҏ��v���̕��ς�8.2���A�ؓ����̕��ϋ�����3.1���A�������Ԓ��ɑz�肷��u�ŏI�Ҍ������v��5.6���i�i���j���{�s���Y�������i2000�j�u�s���Y�����ƒ����i��Q��j�̌��ʊT�v�vhttp://www.reinet.or.jp/jp/10-toukei/10D-tohshi2.htm
�i2000/09/12�jp1�j�A�O�H�M����s�̌��\���Ă���s���Y�C���f�b�N�X�́u�P�N�x�C���J�����v�v��1997�N�ɂ����ẮA�S�����ςŖ�4���A�ۂ̓��E��蒬�E�L�y���n���5����Ɓi�O�H�M����s�i2000�j�u�P�N�x�C���J�����v���vhttp://www.mitsuibishi-trust.co.jp/houjin/fdsnidx/fdid09.html
�i2000/09/12�j�j�X���Ƃ��Ă͎��Ă�����̂̈�v���Ă���Ƃ͌����������B
���̌����Ƃ��ẮA�A���P�[�g�������s���Ă��鍑�y���̏ꍇ�ő��@�֓�����170�В����̂�55�ЁA���{�s���Y��������128�В�40�Ђ̉����ƂɎ��v�����v�Z���Ă���̂ɑ��āA�O�H�M����s�̏ꍇ�͒n�������̕W���l�ɗe�ϗ����x�����ς��̌�����z�肵�A���Y�z�茚���̎��v�����Z�o������@�����ȂǁA�Z�o���@�̊�b���傫���قȂ��Ă��邱�Ƃ���������B
������ɂ��Ă��A���݂̓��{�ɂ͕s���Y�����ɂ������W���I�C���f�b�N�X�͑��݂��Ȃ��ƌ����Ă悢�Ǝv����B
��DCF�@��
���ڊҌ��@�͑O�q�̂悤�ɁA�L���b�V���t���[�͉i���ɕs�ςƂ����O��Ɋ�Â��ĕs���Y�̉��l���v�Z���Ă���B�]���āA�C���J���E�Q�C���݂̂ɒ��ڂ��ăL���s�^���E�Q�C���͍l������Ă��Ȃ��B����͕s���Y�̏،����̍��ŏڏq���邪�A�č��Ȃǂɂ�����s���Y�����ł́A������Ԃ�������l�������قƂ�ǂł���B���������s���Y���،�������ꍇ�A�،��̊����ɍ��킹�ē��Y�s���Y�����������ꍇ�̉��l�𐳊m�ɗ\�����Ȃ��Ă͏،��Ƃ��Đ��藧���Ȃ��i�s���Y�̐��i��A�i�v�͂Ȃ��܂Ȃ��j�B�܂��A�L���b�V���t���[�ɂ��Ă��A�����̏㏸�A���X�N�Ȃǂ̕��͂��s������ŁA�K�v�o��̏㏸�A�C�U�v��Ɋ�Â��o������āA���Ԓ��̃L���b�V���t���[���Z�肵�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A�������ԏI�����̕s���Y�̏������l���Z�肵�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����͓��R�������邪�A�������Ԓ��Ɍ����̕�C�A�����Ȃǂɂ����v�͌���ɂ��L���s�^���E�Q�C���������܂��ꍇ������B�t�ɁA�ĊJ���̏ꍇ�Ȃǂ́A���̃L���s�^���E�Q�C���ɏd�������������͂ɂȂ�B
��������10�N�Ƃ��Đ����ɕ\���ƁA
![]() �@�������A
�@�������A
![]()
�o�u�͌��݉��l�A
![]() �͊e�N�x�̃L���b�V���t���[�A���͊Ҍ������A�q�u�͓]�����l�A�����͓]�����Ҍ�������\���B
�͊e�N�x�̃L���b�V���t���[�A���͊Ҍ������A�q�u�͓]�����l�A�����͓]�����Ҍ�������\���B
�ʏ�A�q�u��11�N�x�̃L���b�V���t���[�������Œ��ڊҌ����邱�Ƃɂ���ċ��߂�̂����ʂł���B10�N��̓]�����l��ʏ�̊Ҍ������ƈقȂ郌�[�g�ŊҌ�����̂́A11�N��̃L���b�V���t���[��\������ꍇ�̕s�m�����Ȃǂ���A�ʏ�̊Ҍ������i��L�ł����j��荂���ݒ肳�ꂽ���[�g�Ō��݉��l���v�Z���邽�߂ł���B
��ύ����I�Ɍ��߂��Ă���悤�Ɏv����DCF�@�ł��邪�A����̓��{�ł͂�͂蕁�y�ɂ͎��Ԃ������肻���ł���B���Ă͂߂鐔�l�����������ɁA�s��̃R���Z���T�X�⑽���̎������̔�r���Ȃ��Ɯ��ӓI�ɓ�������肪���E���ꂩ�˂Ȃ��ȂǁA��肪����B
3.4.4�s���Y�Ɋւ���̃f�[�^
DCF�@�Ȃǂɂ��n�����Z�o����ꍇ�A�����Ȃ鐔�l���̗p���邩�Ō��ʂ��S���قȂ�ł��낤���Ƃ͗e�Ղɑz�������B�ł́A���ۂ̃f�[�^�͂ǂ̂悤�ȕϓ��������Ă���̂��낤���B
�\2�y�ѕ\3�͓���23����ɂ������K�̓r���̋��̐��ڂ������Ă���B�O���t�͉ߋ�4�N�Ԃ̃f�[�^�������Ă���B�f�[�^�̎����͈قȂ���̂́A������А���f�[�^�T�[�r�X�V�X�e���̃��|�[�g�ł́A�ߋ�10�N�Ԃɂ����̂ڂ�ƁA1990�N���̋���0.5�����Œ�ɁA1994�N�ɂ͋���9.5�����L�^���Ă���B�܂��A����������1991�N�ɖ�36,000�~/�ł��������̂�1997�N�ɂ�17,500�~/���x���܂Œቺ���Ă���i������А���f�[�^�T�[�r�X�V�X�e���i2000�j�u�O��s�s���ɂ�����I�t�B�X�s���̒����\���vhttp://www.ikoma-cbrichardellis.co.jp/j/jouhou/6-9-yosoku.pdf
�i2000/11/08�j�j�B
�\2����23��
��K�̓r���̋��̐���
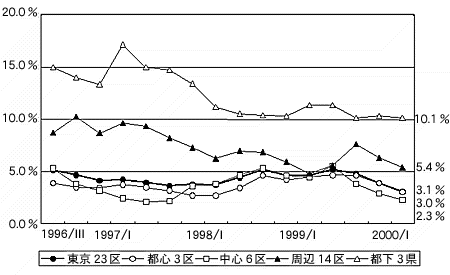
�\3
��K�̓r�����\����̐���
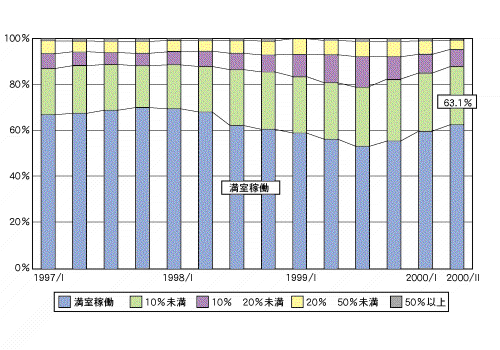
�i�o�T
�I�t�B�X�r������������ http://www.officesouken.com/market/market_03.html
�j
����ɁA�o�u������𗠕t����f�[�^�Ƃ��āA�������s�X�n�ɂ�����n�����i�w����\4�ɕt�������Ă����B���ƒn�̒n���w���́A1991�N���ɖ�105�̃s�[�N���L�^������A�n���͑����A2000�N���_�ł͖�30�ɂ܂Œቺ���Ă���B
�\4
�������s�X�n�n���w��
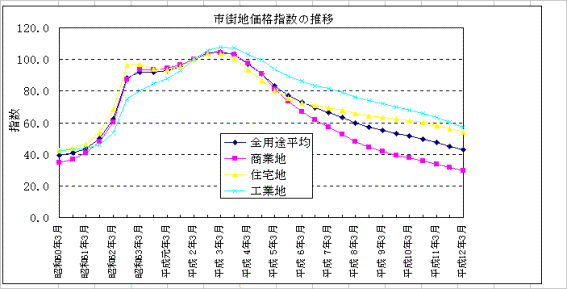
�i�o�T
���c�@�l���{�s���Y�������i2000
�j�u�s���Y���v�vhttp://www.reinet.or.jp/jp/10-toukei/10A-sigaichi/10A-tokyoj.htm
�i2000/11/08�j�j
��L�̎����́A�o�u������̐[���x�������Ă���B�o�u�����̂́A���{�o�ςɂƂ��Ė��o���ł��������߁A�\���ł��Ȃ������Ƃ��Ă���ނȂ������͂���B�������Ȃ���A�s���Y�s��̃{���e�B���e�B�[�̍����ɂ́A�[���Ȓ��ӂ��K�v�ł��낤�B
�܂��A�ʏ�A�،������ꂽ�s���Y���w�����郁���b�g�Ƃ��āA���U������}��邱�Ƃ��グ����B�Ƃ��낪�A�o�u���̕���́A�����畡���̕s���Y�����Y�Ɋ܂ނ��Ƃɂ���ă��X�N���U��}�낤�Ƃ��Ă��A�n���̉����ɍ��킹�Ē�����������A���܂��ɋ����オ�鎖�Ԃ������N���������Ƃ���L��������ǂݎ���B����̃o�u������̉ߒ��ŁA�s���Y�s���Ɠ����ɋN����Y�ƑS�ʂ̕s�����A�n���A�����̓��������������炵�A���܂ň����グ�Ă��܂����̂ł���B�s���Y�����ɂ����ĕ��U�����ɂ��w�b�W������߂ē����ɂ������Ƃ������Ă���Ƃ����邾�낤�B
4.
�s���Y�،��ƃR���v���C�A���X
�t���[�A�t�F�A�A�O���[�o��������Ƃ��Ďn�܂������{�ŋ��Z�r�b�O�o���́A�]���^�̍s���A�@�̌n�ɂ��傫�ȉe���������炵���B�]���̏c����s���A����ɔ����ĕ������Ă����@�̌n�̂��Ƃł́A�����I�i�t���[�j�œ������̂���i�t�F�A�j���Z�s���͊��҂ł��Ȃ������B�܂��A�]���̊Ԑڋ��Z���嗬�Ƃ������Z�V�X�e���́A���Đ�i�����i�O���[�o���j�Ƃ̋��Z���������������Ă�����ł��łɎ���x��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł������B�����ŁA�]�����Z�i��s�j�A�ی��A�،��A����ɂ��̑����i�s��ȂǏ��i�ʁi�g�����Ȓ��ʁh�Ƃ̕\���̂ق����I�m�ł���Ƃ����邩������Ȃ��j�ɕ�����Đ��肳��Ă����Ɩ@������@���̐��肪�]�܂ꂽ�B��������{�ŋ��Z�T�[�r�X�@�ł���B�S�̂�������{�ŋ��Z�T�[�r�X�@���̂��̂́A�܂����肳��Ă��炸�A�]���̋Ɩ@�Ƃ̌��ˍ���������A�ߓ����ɐ��肳��錩���݂͗����Ă��Ȃ��B�����A�����I�ɓ��{�ŋ��Z�T�[�r�X�@�̈ꕔ�ƂȂ�@����g�D�͂ł�����A���Z���i�̔̔����Ɋւ���@���i����13�N4��1���{�s�\��A�ȉ��A���Z���i�̔��@�Ɨ����j�����̈ꕔ�ł���B
4.1���p�����҂���鎑�Y
�o�u������ɂ���ċ@�\�s�S�Ɋׂ������{�̋��Z�V�X�e�����~�ς��邽�߂ɓ��Ăɂ���Ă���̂��A1999�N�����_�ɂ�����1,390���~�ɒB����ƌv����ɒ~�ς��ꂽ���Z���Y�ł���B���̖c��ȋ��Z���Y��L�����p���邱�Ƃɂ���āA�����o�ς̌��S�Ȕ��W��}��ƂƂ��ɁA�傫�����������E���Z�s��ɂ�������{�̈АM�����߂����Ƃ�����̂ł���B
4.1.1�ƌv�̎��Y�\��
�\5�Ɍ�����悤�ɁA�䂪���̉ƌv����̋��Z���Y�ɂ����āA�����E�a���������ȏ�̔䗦���߂Ă���i1999�N53.8���j�B����́A�č��̗�Ɣ�ׂ�ƁA�ۗ������Ⴂ�������Ă���B�č��ɂ����ẮA�����E�o�����i1999�N36.9���j�Ɠ����M���i12.8���j�łقڔ������߂邱�Ƃ��番����Ƃ���A���X�N���Y�̐�߂銄���������B�č��̗�́A��i�����ł��ł������䗦�������Ă���B��r�N�����K��������肵�Ă��Ȃ����A���B�e���ɂ�������S���Y�ƃ��X�N���Y�̊����͎��̂Ƃ���ł���B�p��1998�N���S���Y20���A���X�N���Y20���A�t�����X1997�N���S���Y33���A���X�N���Y40���A�h�C�c1998�N���S���Y40���A���X�N���Y18���i����
�E�A�Ћ�
�q�q�u���{�̉ƌv�̋��Z���Y�I���s���v�w���⒲������x1999�N11����
���{��s�@�}�\6�j�B�č��̗�́A���B�����Ɣ�ׂĂ����X�N���Y�̊������������Ƃ�������B�t�ɁA���{�̗�́A��i�������ŁA���S���Y�̐�߂銄�����ۗ����č������Ƃ�������B
���ꂾ���łȂ��A1989�N��1999�N�̔�r�ɂ����āA���{�̉ƌv�ɐ�߂銔���E�o�����i13.3������8.4���j�A�����M���i3.9������2.5���j�̊�������������ቺ���Ă���̂ɑ��āA�����E�a���̐�߂銄���͂킸���Ȃ���Ƃ͂����������Ă���i48.5������53.8���j�B
��ʓI�ɂ̓o�u������̉e���Ƃ������Ƃ��ł���ł��낤�B�����̉����Ȃǂɂ�薣�͓I�ȓ����Ώۂ��������A��������Ɣj�]�͓����s���̈�w�̕ێ牻�������炵�A���������Ƃ͌�������X�N���Y�̔䗦����w�ቺ�������B
�m���Ɉ�l�̓����s���Ƃ��ẮA�s�����ȓ_�͂Ȃ����A�ꍑ�̌o�ϊ������l�����ł́A�D�܂����Ƃ͌����Ȃ��ʂ�����B�m���ɁA���̕������ɂ����āA�ƌv����̒��~�����Z�@�ւɈ�U�~�ς���A���̎�������Ƃ֑݂��o�����Ԑڋ��Z�ɂ���ē��{�o�ς��x���Ă����B�������A�o�u������ɂ���ċ��Z�@�ւ̗^�M�n���\�͂͑啝�ɂ����Ȃ��Ă��܂����B���Z�@�ւ̓o�u������ɂ�鎑�Y�f�t����BIS��ɂ�鎩�Ȏ��{�䗦�K���������߂̃o�����X�E�V�[�g�E�X�������v���������܂��āA�݂��o����啝�ɗ}�������B���ꂪ������g�݂��a��h�ł���B�݂��a��ɂ���Ċ�Ɗ������傫��������A10�N�Ԃɓn��o�ς̒���������̂ł���B
���̈���ŁA���ۋ��Z�s��͂�����O���[�o�����̖��̂��Ƃɓ��������߁A���݂��ɉe���������悤�ɂȂ��Ă��Ă���B�䂪�����������Z�s�������Â��邱�Ƃ͕s�\�ɂȂ����̂ł���B�܂��A���Z�C�m�x�[�V�����ɂ���āA�V�������Z���i�����X�ɐ��܂�A�K���ɘa�ɔ����ĉ䂪���̎s��ɂ����X�ƎQ�����Ă���悤�ɂȂ����B�䂪���ɂ����Ă��A���Z�r�b�O�E�o�����i�W�A�ƌv���ۗL������Z���Y�����X�N�E�L���s�^���Ƃ��Ē��ڎ��{�s��ɓ�������邱�Ƃ����҂���Ă���B
�\5
�ƌv����̋��Z���Y�\���̕ω�
���{
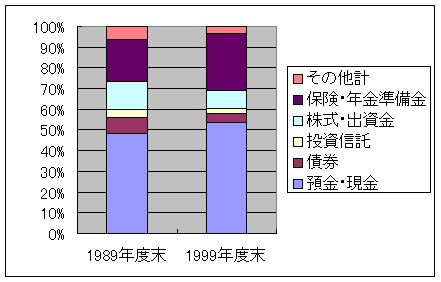
1989�N�x�����Z���Y926���~�@GDP��2.3�{
1999�N�x�����Z���Y1,390���~�@GDP��2.8�{
�č�
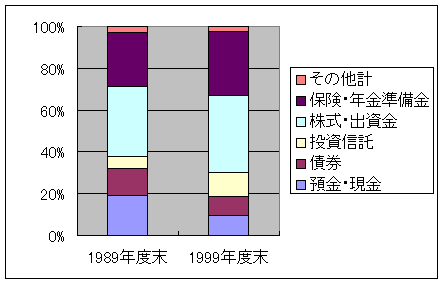
1989�N�x�����Z���Y15.0���h���@GDP��2.6�{
1999�N�x�����Z���Y36.2���h���@GDP��3.9�{
�o�T
���{��s�u�����z���v����݂��䂪���̋��Z�\���v
4.1.2�ƌv�̋��Z���Y�I���s��
���{�̉ƌv�̋��Z���Y�I���s���ɂ�����ێ琫�����Ȃ荂�����Ƃ́A��L������������炩�ł��낤�B���̂��Ƃ́A���c�@�l�،��L��Z���^�[�̍s��������������f����i�\6�j�B���~�I���s���ōł��d�������̂͌����̈��S���Ƃ��ł��o�����ꂪ�ł��邱�Ƃł���A������l�オ������҂���䗦�͂��Ȃ藎����B
�\6�@���~�I���
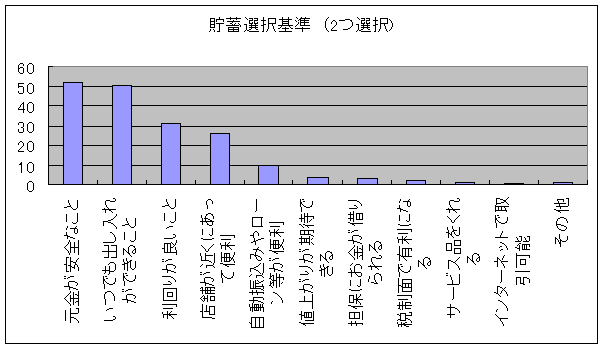
�o�W�@���c�@�l�،��L��Z���^�[�u����12�N�x�u�،������Ɋւ���S�������v���ʂ̊T�v�v��蔲��
���̒����́A10,000���т̃T���v�����A�L�������6,331���т�Ώۂɍs��ꂽ�B���̂������������L���Ă��鐢�т�20.8���A���ď��L�����o�������鐢�т��܂߂Ă�31.0���ł���B�����M���̍w������8.8���A�����M�������ĕۗL�����o�����܂߂Ă�16.9���ɂƂǂ܂�B
�\7�͏��a54�N����̒��~�̐��ڂ����߂��Ă��邪�A�e�폤�i�ۗ̕L�䗦�̓o�u�����̉e���͑傫���͎Ă��炸�A���Ȃ���肵�Ă��邱�Ƃ�������B�킸���ɁA�����M�����\7�ɂ����ď��a63�N�i�قڃo�u���̃s�[�N�ɏd�Ȃ�B��ꎟ���M�̃u�[���Ƃ���ꂽ�j��16.7������8.8���ւƔ������Ă��邱�Ƃ��ڂɕt�����x�ł���B�t�ɁA�����ۗL���т�20���O��ň��肵�Ă���A�o�u���̉e�������Ă��Ȃ����Ƃ͋����[���B
�\7�@���~�̐��ځi�����A���j
|
|
��s���̕��ʗa�� |
�X�ǂ̒ʏ풙�� |
��s���̒���a�� |
�X�ǂ̒�z |
���K�M���E�ݕt�M�� |
���a�� |
���`���~ |
���� |
�����M�� |
���Ѝ� |
�O���Ŕ��s���ꂽ�،� |
��s���̑������a�� |
�X�ǂ̑��̒�������� |
���C�h |
|
���a54 |
87.9 |
51.6 |
68.4 |
42.5 |
11.2 |
18.6 |
18.0 |
16.0 |
6.4 |
7.2 |
0.3 |
* |
* |
* |
|
57 |
87.7 |
48.3 |
83.8 |
52.1 |
12.1 |
20.1 |
20.5 |
18.0 |
8.2 |
10.9 |
0.3 |
* |
* |
* |
|
60 |
86.8 |
44.8 |
80.1 |
48.9 |
13.7 |
18.2 |
20.0 |
15.8 |
12.8 |
10.5 |
0.6 |
* |
* |
* |
|
63 |
87.4 |
47.0 |
73.0 |
49.2 |
12.7 |
17.7 |
21.3 |
18.5 |
16.7 |
10.8 |
1.0 |
* |
* |
* |
|
����3 |
88.4 |
47.1 |
71.9 |
51.0 |
13.0 |
15.8 |
21.3 |
19.6 |
15.1 |
9.5 |
1.4 |
- |
8.7 |
3.0 |
|
6 |
87.0 |
51.5 |
68.0 |
51.0 |
11.1 |
15.2 |
20.5 |
20.5 |
12.1 |
7.9 |
1.3 |
6.8 |
12.1 |
2.2 |
|
9 |
86.3 |
55.6 |
61.6 |
49.3 |
7.4 |
9.8 |
14.8 |
19.2 |
8.8 |
6.7 |
2.1 |
5.3 |
9.4 |
1.2 |
|
12 |
87.6 |
58.7 |
61.5 |
48.9 |
5.9 |
8.6 |
14.9 |
20.8 |
8.8 |
6.8 |
2.5 |
5.1 |
10.5 |
0.8 |
���̒����ł́A�����Ⓤ���M�����Ȃ��ۗL���Ă��Ȃ����ɂ��Ă��������s���Ă���i�\8�A9�j�B�����ɂ��ẮA�����ۗL�̌o���̂Ȃ�4,368���т̎���4����3�ȏオ�����ɊW�Ȃ��w�����Ȃ��Ɖ��Ă���B�����M���ɂ��Ă��A�����M���w���̌o���̂Ȃ�5,260���т̂���3����2�߂��������M���ɊS���Ȃ��Ɖ��Ă���B���{�̉ƌv�̋��Z�ɑ���ێ琫���悭����������B
�\8�@�����w������
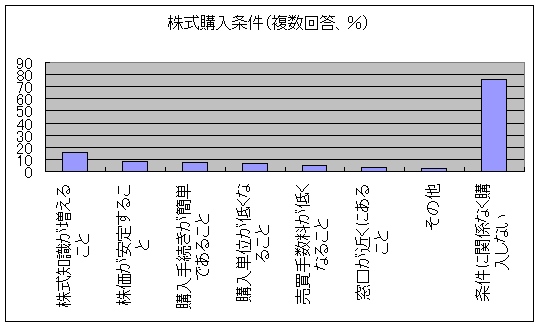
�o�W�@���c�@�l�،��L��Z���^�[�u����12�N�x�u�،������Ɋւ���S�������v���ʂ̊T�v�v
�\9�@�����M����w�����R
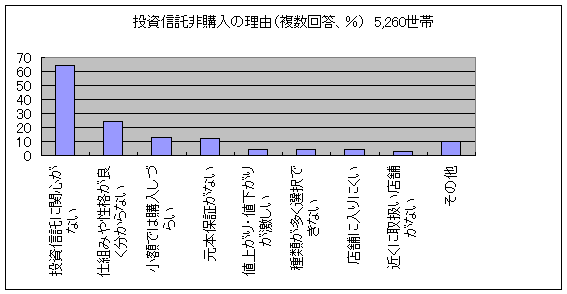
�o�W�@���c�@�l�،��L��Z���^�[�u����12�N�x�u�،������Ɋւ���S�������v���ʂ̊T�v�v
�������A�O�q�����悤�ɁA���Z�̃O���[�o�����̍L����ƂƂ��ɁA�����Ƃ̎��ȐӔC�������]�܂��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͔F�����Ă���A�،���ۗL���Ă��Ȃ����тɂ����Ă������߂����،��m�����K�����邱�Ƃ̕K�v����F�����Ă���B
�\10�@�،��ۗL��/�،��m���K���̕K�v��
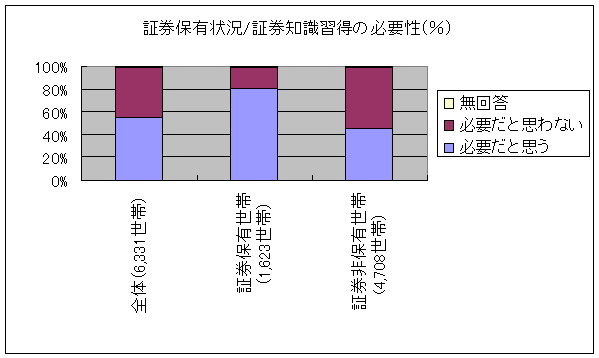
�o�W�@���c�@�l�،��L��Z���^�[�u����12�N�x�u�،������Ɋւ���S�������v���ʂ̊T�v�v
���{�l�̋��Z�I�D���Ȃ����̂悤�Ɉ��S�u���ł��邩�ɂ��ẮA�c�O�Ȃ���A����͂Ȃ��悤�ł���B�����A�u�@�����ɕK�v�ȏ���E�ʂƂ��ɕs�����Ă���A���i���e���ǂ���������Ă��Ȃ��A�A�萔���������Ă���Ώ��z�̓������s���ƂȂ�A�B�a�������Ɣ�r�����ꍇ�A�Ő��ʂł̃����b�g�����ΓI�ɗ���Ă���v�i����
�E�A�Ћ�
�q�q�u���{�̉ƌv�̋��Z���Y�I���s���v�w���⒲������x1999�N11����
���{��sp13�j�j�Ƃ������w�E�͂Ȃ���Ă���B
�܂��A���j��U��Ԃ��Ă݂�A��O�̓��{�ɂ����āA���S���Y�ƃ��X�N���Y�̊����ɂ͑傫�ȍ��͂Ȃ��A1930�N���_�ŁA���S���Y��40���A���X�N���Y��35���i����
�E�A�Ћ�
�q�q�u���{�̉ƌv�̋��Z���Y�I���s���v�w���⒲������x1999�N11����
���{��s�@�}�\14�j�ƂȂ��Ă���B�]���āA���{�l�̌��݂̃��X�N���̎��́A�����č������ł͂Ȃ����Ƃ�����������B���X�N���Y�̔䗦�́A�I������ɋ}���Ɍ������Ă������B�w�i�Ƃ��ẮA���̋}���ȃC���t����A�}���D���x�̑n�݂ɂ���ėa���������コ�ꂽ���Ƃ��傫���e�����Ă��邾�낤�B���̎��������ƂɁA�X�Δz�����x�Ƃ����قƂ�ǎЉ��`�I�Ȍo�ϐ���ɂ���Đ��̕�����}���Ă����킯�ł���B���̐��̂��̂́A���̌�̗��j���ؖ����Ă���Ƃ���A���{���Ăѐ��E�̈ꗬ���Ɉ����グ�邱�Ƃɐ��������B�Ƃ��낪�A��x�ɂ킽��I�C���V���b�N�A�o�u���̕�����o�����A����Ɍo�ς̃O���[�o�����A�T�[�r�X�����i�W�A�]���^�̊Ԑڋ��Z�V�X�e���̌��E��I��A���50�N�i���ۂɂ͐푈���Ɍ��݂̓����V�X�e���͊��������j�̐��Z�ƂƂ��ɁA�V�����V�X�e�����͍����ꂽ�B���̌��ʂƂ��ċ��Z�r�b�O�o�����J�n����A���܂��܂Ȗ@�������肳��A�s���V�X�e���ɂ��ύX��������ꂽ���Ƃ́A�O�q�̂Ƃ���ł���B
4.2����ҕی쐭��
�r�b�O�o���ɔ����ϊv�̈�Ƃ��āA�V�������Z���i�̊J���̎��R�y�ѐv�������m�ۂ��邽�߂̖@�������s��ꂽ�BSPC�@�ȂǁA��A�̕s���Y�،����ȂǂɊւ���@�����܂ޏW�c�����X�L�[���́A���Z�R�c��ŋc�_����Ă����B���̈���ŁA�O�q�̂悤�ȕێ�I�ȓ��{�l���Ăы��Z�s��ɂ�����v���C���[�Ƃ��ČĂі߂����߂̖@�����������ɋ��Z�R�c��ŋc�_����A�@�������ꂽ�̂����Z���i�̔��@�ł���B
�r�b�O�o���ȍ~�̋��Z���i�̑��l���܂��āA����ҕی쐭��Ƃ��ċ��Z���i�̔��@���A�s�ꐮ���A�V���i�J���̃v���b�g�t�H�[���Ƃ���SPC�@�ȉ����Ԃ̗��ւƂ��Đ������ꂽ�̂ł���B�]���āA�s���Y�،��Ȃǂ͂��ׂċ��Z���i�̔��@�̋K����������B�܂��A���Z���i�̔��@�Ɠ����Ɏ{�s��������Ҍ_��@���A�s���Y�،��̔̔����K������B����҂ɂƂ��ẮA���Z���i�̔��@�Ə���Ҍ_��@�́A����ɍ��킹�Ď����ɗL���Ȗ@����I��K�p�ł���B
4.2.1
���Z���i�̔��@�A����Ҍ_��@�Ɋ�Â������`��
���Z���i�̔��@�ɂ����ẮA���Z���i�̔��Ǝғ��ɏd�v�����̐����`�����ۂ���Ă���i���Z���i�̔��@��3���j����A����Ҍ_��@�ɂ����ẮA���Ǝ҂̓w�͋`���ɂƂǂ܂��Ă���i����Ҍ_��@��3���1���j�B
���Z���i�̔��@��3���ɂ����āA�d�v�����Ƃ��Đ������Ȃ��Ă͂����Ȃ������Ƃ��āA���{�����������邨���ꂪ����ꍇ�ɂ́A���̎|�y�їL���،��s��ɂ����铖�Y�w�W�A�����āA���̋��Z���i�̔̔��Ɋւ��Čڋq�̔��f�ɉe�����y�ڂ����ƂƂȂ鎖���ɂ��Đ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă���B
����Ҍ_��@�ɂ����ẮA��S���S���ŁA�d�v�����Ƃ͏���Ҍ_��̖ړI�ƂȂ���̂̎��A�p�r�Ȃǂ̓��e�A�������͑Ή��Ȃǂ̎�������ɌW����̂ŁA�u����҂̓��Y����Ҍ_���������邩�ۂ��ɂ��Ă̔��f�ɒʏ�e�����y�ڂ��ׂ����̂������v�Ƃ����������R�ƋK�肵�Ă���B�u�ʏ�v�̔��f��Ƃ��āA��ʕ��ϓI�ȏ���҂���Ƃ��Ĕ��f���s���Ƃ��Ă��邪�i�o�ϊ�撡�u����Ҍ_��@�̉���vp19�j�A�K�����������猩�Ă��A���Y����҂̗�����o�����l�������Ɍ^�ɂ͂܂�������������Ώd�v����������������ƂɂȂ�Ƃ��Ă���͖̂�肪����Ǝv����B
����10�N�̒i�K�ł͍��������R�c��̋c�_�ɂ����āA���Ǝ҂ɏ��`��������Ҍ_��@�̂Ȃ��Ŗ��m�Ɉʒu�t����K�v������������Ă���i�o�ϊ�撡�u����Ҍ_��@�i���́j�̋�̓I���e�ɂ��āvp14�j�B����ɁA�u����ɑ��ẮA���Ǝ҂ɐV���ȋ`�����ۂ����ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ������������A�]���A����ɂ����郁���b�g������\�ɑ傫���o���āA����҂����Ȍ�����s����Ń����b�g�Ɠ��l�ɕK�v�ȃf�����b�g�ɂ��Ă͏o���Ȃ������Ȏ��Ǝ҂����X�ɂ��Č����邽�߁A�d�v�����Ɋւ�����̊J�����`���Â���K�v������̂ł���A����܂œK�Ȏ��Ɗ������s���Ă��Ă���A����҂ɖ����������Ă��鎖�Ǝ҂ɂƂ��ẮA�V���ȋ`�����ۂ�����Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ƍl����v�i�o�ϊ�撡�u����Ҍ_��@�i���́j�̋�̓I���e�ɂ��āvp14�j�Ɩ��m�ɒf�肵�Ă���B����ɂ�����炸�A���ۂɌ��z���ꂽ����Ҍ_��@��3���1���ɂ����Ď��Ǝ҂̓w�͋`���ɂƂǂ܂��Ă���̂́A����ҕی삪�啝�Ɍ�ނ����Ƃ̈�ۂ���������Ȃ��B
�܂��A������̖@���ɂ����Ă��A���Z���i�̔��Ǝғ��^���Ǝ҂ɑ��ď[���Ȑ��������邱�Ƃ����߂Ă�����̂́A�ڋq�^����҂̗������m���߂邱�Ƃ�S���v�����Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ́A�u���Ԑ����i��ꎟ�j�v�ɂ����āA�u��������[���Ƃ��Đ����`�����l����ꍇ�ɂ́A�u����������X�N�͈ړ]����v�A�u�������Ȃ���Έړ]���Ȃ��v����{�Ƃ��āv�i���Z�R�c��u���Ԑ����i��ꎟ�j�vp15�j���邱�ƁA�u���p�҂����Z���i�̓��e���ׂĂɂ��Ēm�邱�Ƃ�z�肷��͔̂��I�ł���v�i���Z�R�c��u���Ԑ����i��ꎟ�j�vp15�j�ƒf���Ă��邱�Ƃ�������炩�ł��낤�B����Ҍ_��@�ɂ����Ă͂���ɁA�u����҂́A����Ҍ_����������ɍۂ��ẮA���Ǝ҂�����ꂽ�������p���A����҂̌����`�����̑��̏���Ҍ_��̓��e�ɂ��ė�������悤�ɓw�߂���̂Ƃ���v�i����Ҍ_��@��3���2��
�j�ƁA����҂̓w�͋K��܂Œu���Ă���B�������{�����͓w�͋K��ł���A�u����҂��{���2���ɋK�肳�ꂽ�w�͂����ɉʂ����Ȃ������Ƃ��Ă��A�{���Ɋ�Â��Č_��̎��������F�߂��Ȃ��Ȃ�����A���Q�����ӔC������������A�ߎ����E�̔��f�ɂ����Ė@�I�ɉe�����y�肷�邱�Ƃ͂Ȃ��v�i�o�ϊ�撡�u����Ҍ_��@�̉���vp6�j�B
�����`���ɂ��ẮA�u���Ԑ����i��ꎟ�j�v�ɂ����ēK���������ɂ��ĐG��Ă���̂��Q�l�ɂȂ�ł��낤�B�K���������Ƃ́u���`�ɂ́A���̗��p�҂ɑ��ẮA�@���ɐ�����s�����Ă����̋��Z���i�̔̔��E���U���s���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������[���ł���A�L�`�ɂ́A���p�҂̒m���E�o���A���Y�́A�����ړI���ɏƂ炵�ēK���������i�E�T�[�r�X�̔̔��E���U���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������[�����Ӗ�����v�i���Z�R�c��u���Ԑ����i��ꎟ�j�vp38�j�B�܂��ɃR���v���C�A���X�̐��_���̂��̂ł���A���ꂩ��̋��Z���i�̔̔��ɍۂ��ċ��߂��Ă��郋�[���ł���Ǝv����B�������A�Ⴆ�Εs�K���Ƃ���闘�p�҂��Ȃ��������]����ꍇ�Ȃǂɂ����ẮA�_��ɂ����鎄�I�����̌������܂���A�u�ꗥ�ɖ����Ƃ����舵����@�߂Ŗ����I�ɋK�肷�邱�Ɓv�͓���i���Z�R�c��u���Ԑ����i��ꎟ�j�vp17�j�Ƃ��ċ��Z���i�̔��@�ɔ��f����Ȃ������̂͑�ώc�O�Ȃ��Ƃł���B
����ɁA���Z���i�̔��@��3���4����2���ł́A�ڋq����d�v�����̐����͗v���Ȃ��Ƃ̈ӎv�̕\�����������ꍇ�ɂ́A�d�v�����̐������ȗ����ėǂ��|�K�肳��Ă���B�m���ɁA������A���̋��Z��������čs���Ă���ڋq�ɑ��ẮA���Z���i�̔��Ǝғ��A�ڋq�Ƃ��ɏd�v�����̐������ȗ����Ă��܂��v���������ē��R�ł��낤�B�������A�ڋq�ɋ}���ł��邩��Ƃ��A�ʓ|�����������₱���������͎~�߂Ă���A�Ƃ���ꂽ�ꍇ�ɂ��F�߂Ă��܂��̂͂������Ȃ��̂ł��낤���B
����Ҍ_��@�ɂ����Ă��u���Y���Ǝ҂����Y����҂ɑ����Y�����������悤�Ƃ����ɂ�������炸�A���Y����҂���������Ƃ��́A���̌���ł͂Ȃ��v�i����Ҍ_��@��4���2���j�Ɠ��l�ȋK�肪����B���̋K��Ɋւ��ẮA����҂����������ۂ������R���u�������鎞�Ԃ��Ȃ��A�������邱�Ƃ��ʓ|�ł���v�Ƃ������ꍇ�ł��K�p�����Ƃ��Ă���i�o�ϊ�撡�u����Ҍ_��@�̉���vp15�j�B����10�N�ɂ����鍑�������R�c��ɂ����ẮA���`����Ə������̂́A�u�P�ɏ���҂��������ۂ����Ƃ����̂ł͏\���ł͂Ȃ��A����҂������I���\���ɗ���������ŏ������ۂ����ꍇ�Ɍ���ׂ��ł���v�i�o�ϊ�撡�u����Ҍ_��@�i���́j�̋�̓I���e�ɂ��āvp14�j�ƋL����Ă���̂Ɣ�ׂ�ƁA�啝�Ȍ�ނ���������B
�܂��A����������ꍇ�̕��@�ɂ��Ă͈�ؐG��Ă��Ȃ��B�Ⴆ�A���݂̏����ł͓d�b��ʂ��Đ����������邱�Ƃ��ܘ_�F�߂���ł��낤���A���ʂ���t������@���F�߂���ł��낤�B���ʂ���t����ꍇ�ɂ́A��t������Ő����������Ȃ��Ă͈�ʓI�ɂ͐������������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���邪�A���@�̏�����͔F�߂��Ă���Ɨ��������B
�_��E�������ʂ̌�t�͗��@�ɂ����ċ`���Â����Ă͂��Ȃ����A���Z���i����@�ɂ����Ă͋`���Â��Ă�����ׂ��������Ǝv����B���Ȃ��Ƃ��A����I�Ɍ_����e�ɂ��ď��ʂŌ��z���邱�Ƃ͋`���Â���ׂ����Ǝv����B���Z���i�̎���Ɋւ��ẮA��������R���t�@���[�V�����i����m�F���j�̌�t�Ƃ��Ċ��ɑ�T�̋��Z�@�ւŎ��s����Ă���Ǝv����B
4.2.2��Ɩ@�ɂ�����d�v�����̐����`��
�s���Y�̌������������ꍇ�ɂ͑�Ɩ@���K�p�����B��n�E�������������ꍇ�ɂ́A��Ɩ@��35���ɂ����āA������������܂łɈ��̏d�v�������L�ڂ������ʂ���t������ő�n���������C�҂����Đ��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƋK�肵�Ă���B
��Ɩ@�ɂ����āA�d�v�����Ƃ��Đ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ڂ͉��L�̂悤�ɑ�ϑ���ɓn��B��\�I�Ȃ��̂��ӏ������ɂ���ƁA
���ׂĂ̌_��ԗl�ɑ���
l
�{�݂̐�����
l
�����Ɋւ��镉�S
l
���L���A�n�㌠�A�����B����A���،����œo�L���ꂽ���̂�����ꍇ�ɂ́A���̎�ށA�o�L���`�l
l
�s�s�v��@�A���z��@�A���̑��̖@�߂Ɋ�Â����������̊T�v
l
���̏ꍇ�ɂ͗p�r���̑��̗��p�Ɋւ��鐧��������ꍇ�͂��̎���
�����������̏ꍇ�ɂ͂���ɁA
l
�H���������̐ړ��A�����̎�v�\���A�ݔ��̐ݒu�Ȃǂɂ��Ă̐����i�K�v�ȏꍇ�ɂ͐}�ʂ�Y�t�j
�������敪���L�ł���ꍇ�ɂ͂����
l
��̌����̕~�n�Ɋւ��錠���̎�ށA���e
l
��L�����̗p�r���̑��̗��p�̐����Ɋւ���K��̒�߁i�Ă��܂ށj������Ƃ��͂��̓��e
l
���L�����Ɋւ���K��̒�߁i�Ă��܂ށj������Ƃ��͂��̓��e
l
��̌����܂��͕~�n�̈ꕔ�����̂��݂̂̂Ɏg�p�������|�̋K��̒�߁i�Ă��܂ށj������Ƃ��͂��̓��e
l
��̌����A�~�n�̊Ǘ����ϑ�����Ă���ꍇ�ɂ́A�ϑ����Ă�����̂̎����ƏZ��
l
��̌����̌v��I�Ȉێ��C�U�̂��߂̔�p�̐ςݗ��Ă��s���|�̋K��̒�߁i�Ă��܂ށj������Ƃ��͂��̓��e�Ƃ��łɐςݗ��Ă�ꂽ���z
l
�����̏��L�҂����S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ʏ�̊Ǘ���p�̊z
��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B�{�_����1.�y��2.�Ŗ��Ƃ��Ďw�E���������̑啔�����A���͏d�v�����Ƃ��Đ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������Ɋ܂܂�Ă��邱�Ƃ��������肢��������Ǝv���B
�������A�s���Y�،��ȂNj��Z���i�����ꂽ���̂ɂ��ẮA��Ɩ@�͓K�p����Ȃ��B�]���āA�s���Y�،����������ꍇ�ɂ́A�������������ꍇ�ɔ�ׂĕs���Y�ɑ����\���ɓ`���Ȃ����ꂪ����Ǝv���邪�A�������ł��낤���B
���̓_�ɂ��ẮA���Z�R�c��̋c�_�ɂ����Ă��A�u�W�c�����X�L�[������g�����ꂽ���Z���i�́A�䂪���ł͊�����ЍƂ������`���I�ȋ��Z���i�Ɣ�ׂĂ܂����j���A����݂����������Z���i�ł��邱�Ƃ������Ƃ������_�ɗ��ӂ���K�v������v�i���Z�R�c��i1999�j�u���Ԑ����i��ꎟ�j�v�W�c�����X�L�[���Ɋւ��郏�[�L���O�O���[�v
���|�[�gp30�j�Ɠ��ʂȒ��ӂ�v�����Ă���B
�O�q�̂悤�ɁA�s���Y�͓����ΏۂƂ��āA�ۂ߂ĕ�����ɂ������i�������Ă���B���ꂾ���łȂ��A���Z���i�Ƃ��Ă̕s���Y�،���̔����邱�ƂɂȂ���Z�@�ւ��K�������s���Y�����ɐ[���m���ƒ����o���������Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃ́A�o�u������̗��j�������ʂ�ł���B
4.3
�s���Y�،��� ���_�ƍ���̓W�]
���{�ɂ����ĕs���Y�،��s�ꂪ���W���邩�ǂ����́A�s���Y�،��s�ꂪ�g�債�Ă����ߒ��ɂ����āA�����ɓ����Ƃɑ��Č����Ő��m�ȓ�������ł��邩�A�܂�������r�����ł��闬�ʎs����ł��邩�ɂ������Ă���Ƃ����邾�낤�B
���݁A���܂��܂ȕs���Y�C���f�b�N�X���l�Ă���Ă���B�������A���y���ɂ�钲���̂Ƃ���ł��G�ꂽ���A����̓��{�ɂ͈ˑR�[���ȗ��Â��ƐM�p�͂�������s���Y�C���f�b�N�X�͑��݂��Ȃ��B�܂��A�\�z�̂��ƂɂȂ�f�[�^�����Ȃ�̕ϓ���������Ă��邱�Ƃ̓f�[�^������ǂݎ���B����ł͎c�O�Ȃ���A���{�ɂ�����s���Y�����ɂ�����鎑���E���̕s���͔ے�ł��Ȃ��B���̂悤�Ȋϓ_���猾���A���v�Ҍ��@�����ǂ���Ƃ��Ă���s���Y�،��Ȃǂ͈�ʌl�����Ƃ���������͕̂s���ł���A���������ł���ƌ��킴��Ȃ��B
���{�Ńr�b�O�o�������ԕ���ɒ~�ς��ꂽ���Z���Y�̊��p��ʂ��ē��{�o�ς̕�����}�낤�Ƃ������̂ł��邱�Ƃ́A�O�q�̂Ƃ���ł���B���ꂾ���ł͂Ȃ��A���{�ɂ�����s���Y�،����͍��̏،����Ƃ����{���̕s���Y�،����̖ړI�Ƃ͂��܂�W�̂Ȃ��s�Ǎ��̏��p�𑣐i����������葤�̎v�f�哱�Ői�߂��Ă��邱�Ƃ����������鑤�ɂƂ��Ă͋C�ɂȂ�Ƃ���ł���B
���{�o�ς̓o�u�������10�N�ɂ킽���Ă��̌��ǂɔY�܂���Ă����B�����āA2000�N���݂ł����̕��̈�Y�����p������Ă��Ȃ��B�������Ƀo�u�������10�N�����ĂA������x�̏��p�͐i�Ƃ͂��ł��邪�A���݂Ȃ����{�̋��Z�@�ւ̕s�Ǎ������ł�100���Ƃ�200���Ƃ������Ă���A2000�N���ɂ����Ă����Z�@�ւ̔j�]���������ł���B���̍ő�̌����́A�o�u������̒Ɏ���ł��傫�������ނ����s���Y�W�̕s�ǎ��Y�̏��p���s��Ȃ��������Ƃɂ���B
���{�ɂ����ẮA1990�N���_�ɂ����đ�GDP��Ō��Ė�10���قǂ̎����s����Ԃɂ���������Z�@�l��ƕ����1999�N���_�ł́A��5���قǂ̎����]�������邱�ƂɂȂ��Ă���B�t�ɁA1990�N���_�ł͎�̎����]���Ԃɂ�������ʐ��{���傪��8���̎����s����ԂɊׂ��Ă���i���̊ԁA�ƌv����͈�т��Ď����]��j�i���{��s�u�����z���v����݂��䂪���̋��Z�\���v�j�B���݁A���{���{�̕����镉��600���~�Ƃ����Ă��邪�A���̓��v�́A�o�u�������A���ԕ���ɑ��݂����s�Ǎ����A�P�ɐ��{����Ɉړ]���������ł��邱�Ƃ������Ă���B
�s�ǎ��Y�Ƃ́A���Y���̂��s�ǂȂ̂ł͂Ȃ��A���Y�̌��݉��l�ɔ�ׂĕ뉿���������邩��s�ǂȂ̂ł���B���Ƃ��s�ǎ��Y�Ƃ͂����A���̕]���i�l�i�j���[���ɉ�����A�ʂɕs�ǎ��Y�ł͂Ȃ��Ȃ�B�č��ɂ�����1980�N�㖖�̔j�]����S&L�i���~�M�p�g���j�̏����ɍۂ��āARTC�iResolution
Trust Corporation,
�����M�����Ёj���������@���͕̂ʂɓ��{�̏ꍇ�Ƒ傫���قȂ�Ȃ��B�ő�̈Ⴂ�́ARTC��S&L�̕s�ǎ��Y�p����ɍۂ��āA������Ɣ����l�i�ɂ܂ʼn����Ĕ��������Ƃł���B�]�O�̕뉿�ł͕s�ǎ��Y��������������Ȃ����A�[���ɒl��������A�D�ǎ��Y�ɂȂ�B�����W�̂��ꂢ�ȕs���Y���Ó��ȉ��i�i���ۂɂ͂��Ȃ���������炵���j�Ŏ�ɓ���̂ł��邩��ARTC�ɂ�鎑�Y���p�͏����ɐi�W�����B�������i�ł̕s���Y�̔��p�́A�ꎞ�I�ɕs���Y���i�̉����������炵�����A���̌�̕č��o�ς������Ɋg�債���̂͂����m�̂Ƃ���ł���B
�s���Y�،����ɓo�ꂵ�Ă���v���C���[�����߂�ƁA�c�O�Ȃ���o�u�������o���A���̕���ƂƂ��ɒɎ�������ނ����ł��낤���Z�@�ցA�s���Y�W��Ђ̖��O�������Əo�Ă���B�s�Ǎ����،�������ɍۂ��āA�]�����z���Ó��ł��邩�A�������`�F�b�N���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B
���ݓ��{�Ŋ�悳��Ă���s���Y�،��̑����͂��Ȃ���S���ɔz�����Ă���悤�ŁA�M�p�x�͍����Ǝv���邪�A�t�ɗ����̖ʂŌ��������ɔ�ׂĖ��͂̂Ȃ����i�������悤�ȋC������B�K�����݂̂Ƃ���A�ȑO�̒�،��̓�̕��ɂȂ����Č��͂Ȃ����A���Ƃ��،��Ƃ͂�������������ꍇ�ɂ́A�����̋ᖡ�ƂƂ��ɁA�G�N�C�e�B�^�̏ꍇ�ɂ͎��ۂ̓����������A�f�b�g�^�̏ꍇ�ł��i�t���ɋC������ȂǁA�\���Ɍ�������K�v�����邾�낤�B
5.
���_
���{�ɂ�����s���Y�̏،����ɂ��ẮA���̏������͔F�߂���̂́A����ł͒��r����������A�����w�W�ƂȂ�C���f�b�N�X���s���ł���ȂǁA�����ΏۂƂ��ă����b�g��葽���̃f�����b�g������Ă���悤�Ɏv����B
���ɁA�l�����ƂɂƂ��ẮA�s���Y�،��̓��e���u���b�N�{�b�N�X�ɋ߂��A�����Ώۂ̊J�����[���Ɉׂ���Ȃ��܂ܓ��������U�����˂Ȃ��ȂǁA��肪����Ǝv����B
����A�s���Y�،��݂̂Ȃ炸�A�W�c�����X�L�[���ɂ̂��Ƃ����V���i�����X�ƊJ������邱�Ƃł��낤�B�V���i�̔̔��ɍۂ��āA���Z�@�ւ͏]�����i�̔̔��ɂ������č��x�Ȑ����`�������߂��Ă���B���̂悤�ȋ��Z���i�̔��Ɋւ���R���v���C�A���X�̊m�����A��X�̕s���Y�،��ȂǐV�����X�L�[���ɂ̂��Ƃ������i�̔̔����\�ɂ���̂ł���B���Z�@�ւ̕s�f�̓w�͂��]�܂��B
�Q�l����
���{�ٌ�m�A����i2000�j�u�敪���L�@�ӌ����v
http://www.nichibenren.or.jp/sengen/iken/0006-01.htm
�i2000/08/29�j
���ݏȁi1997�j�u�����w�����Z��W���Ǘ��K��̉����̊T�v�v�@http://www.moc.go.jp/house/topics/kiyaku/gai01.html
�i2000/08/29�j
�q���@���s�i2000�j�w�v����������A�b�Ƌ����s���Y�����x�Z��V���
�u�X�P���g���^����ؒn���}���V�����\�\���Ε����\�\�v�wJournal
of Financial Planning�x August 2000 pp20-21
�X�c�`�j�i1996�j�w�ԈႢ���炯�̓y�n�]���x�T�ԏZ��V����
�X�c�`�j�i1997�j�w�V�E�{��̘H���������x�_�C�������h��
���y���i1999�j�u����11�N�œy�n�����vhttp://www2.tochi.nla.go.jp/cgi-bil/
���ݏȁi1997�j�u����9�N�x�̐V�ݏZ��H���vhttp://www.moc.go.jp/chojou/kencha97.htm
��o�@�ەv�i1998�j�w�s���Y�͋��Z�r�W�l�X���x�t�H���X�g�o��
�����O��A�Z�b�g�}�l�W�����g�Ғ��i2000�j�w�s���Y�̏،����@���̎d�g�݂Ǝ�@�x�������_��
���c�@���}�i2000�j�w�s���Y�̗�������x�Z��V���
���Z���i2000�j�u����ړI��Ђɂ����莑�Y�̗������Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���āvhttp://www.fsa.go.jp/p_mof/houan/hou10d.htm�@�i2000/08/29�j
���Z���i2000�j�u���Z���i�̔̔����Ɋւ���@���ėv�j�vhttp://www.mof.go.jp/kouan/hou11b.htm
�i2000/08/02�j
���Z���i2000�j�u���Z���i�̔̔����Ɋւ���@���{�s�߈Ă̌��\�ɂ��āvhttp://www.fsa.com.go.jp/jp/news/newsj/kinyu/f-20001006-1.html
�i2000/10/17�j
���Z���i2000�j�u���Z���i�̔̔����Ɋւ���@���{�s�߁i�āj�vhttp://www.fsa.go.jp/news/newsj/kinkyu/f-20001006-1.pdf
�i2000/10/17�j
���Z�R�c��i1999�j�u���Ԑ����i��ꎟ�j�vhttp://www.mof.go.jp/singikai/kinyusin/tosin/kin005.pdf
�i2000/08/29�j
���Z�R�c��i1999�j�u���Ԑ����i��j�vhttp://www.mof.go.jp/singikai/kinyusin/tosin/kin010d.htm
�i2000/08/29�j
�o�ϊ�撡�i2000�j
�u����Ҍ_��@�̉���v�vhttp://www.epa.gp.jp/2000/c/0605c-abridment.pdf
�i2000/09/20�j
�o�ϊ�撡�i2000�j
�u��������@����Ҍ_��@�vhttp://www.epa.gp.jp/2000/c/shouji/keiyakuhou0.pdf
�i2000/09/20�j
�o�ϊ�撡�i2000�j
�u����Ҍ_��@�y����W�z�vhttp://www.epa.gp.jp/2000/c/shouhi/keiyakuhouex.pdf
�i2000/09/20�j
���y���i2000�j�u�����p�s���Y�̎��v���i�̎Z��̎��s�ɂ��āi���v���i�����j�vhttp://www.nla.go.jp/tochi/kekka.htm
�i2000/09/07�j
(��)���{�s���Y�������i2000�j�u�s���Y�����ƒ���(��2��)�̌��ʊT�v�v
�@�@http://www.reinet.or.jp/jp/10-toukei/10-toushi2.htm
�i2000/09/12�j
(��)�O�H�M����s�uMTB-IKOMA�s���Y�����C���f�b�N�X�Ƃ́vhttp://www.mitsubishi-trust.co.jp/koujin/fdsnidx/fdid01.html
�i2000/09/17�j
���{��s�i2000�j�u�����z���v����݂��䂪���̋��Z�\���vhttp://www.boj.or.jp/ronbun_f.htm
�i2000/11/24�j
����
�E�A�Ћ� �q�q�i1999�j�u���{�̉ƌv�̋��Z���Y�I���s���v�w���⒲������x1999�N11����
���{��s
��R�@���A�g�c�@�F���Y�i1999�j�u���{�̒��~�͉ߏ�Ȃ̂��F���邢�͉��Ď�v���̒��~���ߏ��Ȃ̂��vhttp://www.boj.or.jp/ronbun/wps9905.htm
�i2000/11/24�j
���c�@�l�،��L��Z���^�[�i2000�j�u����12�N�x�u�،������Ɋւ���S�������v���ʂ̊T�v�vhttp://www.skc.or.jp/pdf/h12_1.pdf
�i2000/11/24�j